地球研・日比国際ワークショッブ(8)

▪︎総合地球環境学研究所・奥田昇さんを代表とするプロジェクトの「日比国際ワークショップ」の2日目、さらにさらに続きます。
▪︎野洲市須原の「せせらぎの郷 須原」を訪問したあとは、甲賀市の小佐治に移動しました。この小佐治は、私たちの研究ブロジェクトにとってとても重要な調査地になります。来月から、いよいよ本格的にこの小佐治集落との連携が始まります。ここはもち米の生産で有名です。そのことを活かして農村レストランの経営にも成功されています。野洲市の須原での「魚のゆりかご水田」と同様に、生物多様性に配慮した環境保全型農業と、コミュニティの活性化やこの地域のhuman well-beingとがどのような形で結びつくのか、それをどのように評価してフィードバックし、この地域を支援できるのか…その辺りのことがプロジェクトとしては重要になってきます。これまでのことは、小佐治については、以下のエントリーをご覧いただければと思います。
小佐治での生き物調査
甲賀市の小佐治を訪問
「豊かな生き物を育む水田プロジェクト」
甲賀市の農村で調査
甲賀の農村で
▪︎小佐治では、まず「もちふる里館」を訪問しました。ここは、もち米や米湖をつかった料理が楽しめる農村レストランや直売所、そして集会室や会議室等がセットになった建物です。ここで、地域の概況を伺いながら、米粉でつくったうどんをいただきました。写真はありませんが(写真を撮る前に食べてしまった…)、小麦粉のうどんとはまた違った食感の麺でした。美味しくいただきました。そのあとは、加工工場である「甲賀もち工房」を見学させていただき、そして小佐治の環境保全部会の皆様が取り組んでおられる「豊かな生きものを育む水田づくり」の現場を訪問しました。




▪︎ここの水田の特徴については、過去のエントリーに書きましたが、再度、説明します。小佐治は、古琵琶湖層群の地層が隆起した丘陵地帯にあり、水田も大変細かな重粘土からできています。そのため、大変、水はけが悪いのです。きちんと水がぬけていないと、稲刈りのときに使うコンバインのキャタピラが埋まって動かなくなります。そこで、水はけをよくするために、水田の周囲に、といっても水田の内側なのですが、水田内水路をつくっています。営農のための工夫なのですが、そこが水田の生き物の生息場所になっているのです。水田の水を引いたあとも、その水路には水が残ります。集落では、そこに塩ビのパイプ等を設置して、生き物たちのシェルターにされておられます。このような取り組みの成果が少しずつ生まれています。写真の説明も少し。上段右は、「豊かな生きものを育む水田づくり」の活動をしている圃場の前で、説明を受けているところです。下段左。水田内水路を見学しているところです。越冬したメダカ、ドジョウ、水性昆虫等が確認できました。小佐治では、「メダカが成長する水田で生産した米=生物に配慮した営農で生産した米=安心・安全の米」ということを強調して、「メダカ米」を販売されています。ただし、「豊かな生きものを育む水田づくり」の活動は、経済以外にも、もっとローカルな社会・文化の文脈に依存していて外部からは「見えにくい」効果があるのです。それについては、また別のエントリーで説明しようと思います。

▪︎小佐治での見学を終えたあとは、大原貯水池に移動しました。そこで、大原財産区の関係者に、いろいろ説明をしていただきました。ありがとうございました。大原財産区については、「甲賀市の大原財産区を訪ねる」をご覧いただければと思います。
▪︎2日間にわたって野洲川流域の各地を訪問しました。どの地域の皆さんも、大変暖かく私たちを歓迎してくださいました。非常にお世話になりました。ありがとうございました。翌日3日めは、実際に野洲川の支流で、水質観測のデモンストレーションが行われ、午後からは琵琶湖に浮かぶ沖島を訪問したようです。ようです…と書いたのも、私自身は、3日目は参加できなかったからです。平和堂財団の「夏原グラント」の審査会があったからです。「夏原グラント」は、滋賀・京都で取り組まれている環境保全活動を支援する事業です。私は、2014年度からこの「夏原グラント」の審査員をしています。これについては、別途エントリーしようと思います。
地球研・日比国際ワークショッブ(7)

▪︎総合地球環境学研究所・奥田昇さんを代表とするプロジェクトの「日比国際ワークショップ」の2日目、さらに続きます。
▪︎野洲市の幸津川の大水口神社のあとは、同じく野洲市の須原に移動しました。ここでは、「せせらぎの郷 須原」という農業団体が組織され、「魚のゆりかご水田」の取り組みが行われています。「魚のゆりかご水田」に関しては、以前のエントリー「野洲市のゆりかご水田」をご覧ください。今回、須原の「せせらぎの郷 須原」を訪問したのには理由があります。私たちのプロジェクトが、この須原での取り組みに強い関心をもっていること同時に、フィリピンの共同研究者の皆さんに、日本の環境保全型の農業とコミュニテイビジネスとの関係について知っていただきたかったからです。私たちがフィリピンで比較研究を進める予定の農村では、アグロエコツーリズムと農産物のブランド化を進めようとしておられます。この須原での取り組みが大きなヒントになればとの思いから訪問することにしたのでした。





▪︎現場では、代表の堀彰男さんが、フリップボードを使って「魚のゆりかご水田」についてご説明くださいました。また、ワークショップに参加された方達は、「せせらぎの郷 須原」で生産した「魚のゆりかご水田米」や、食米から生産した吟醸純米酒「月夜のゆりかご」を購入させていただきました。「月夜のゆりかご」については、試飲もさせていただきました。ありがとうございました。こちらの「せせらぎの郷 須原」には、じつにたくさんの人びとがやってこられます。全国的にも高く評価されている取り組みです。公式サイトをお持ちですが、そこに「台湾・フィリピンより視察」という記事をアップしてくださいました。少しだけ、写真について説明します。中断の左。白く見えるものは、魚道を設置しやすいようにつくられたコンクリートの土台です。この土台をもとに、魚道を毎年設置するのです。トップの写真は、湖西の比良山系です。この日は大変天気が良く、くっきり比良山系が確認できました。
地球研・日比国際ワークショッブ(6)



 ▪︎総合地球環境学研究所・奥田昇さんを代表とするプロジェクトの「日比国際ワークショップ」の2日目です。1日目の宿泊、守山市にあるビジネスホテルでした。前日に続きこの日の天候もよく、ホテルの部屋からは、湖西の山々が実によくみえました。左の方(南側)には比叡山が、右の方(北側)にはまだ山頂に雪を残す比良山系がはっきりと見えました。本当は、ここで琵琶湖も見えればよいのですが、このホテルの部屋の高さからでは、琵琶湖の湖面は見えません。
▪︎総合地球環境学研究所・奥田昇さんを代表とするプロジェクトの「日比国際ワークショップ」の2日目です。1日目の宿泊、守山市にあるビジネスホテルでした。前日に続きこの日の天候もよく、ホテルの部屋からは、湖西の山々が実によくみえました。左の方(南側)には比叡山が、右の方(北側)にはまだ山頂に雪を残す比良山系がはっきりと見えました。本当は、ここで琵琶湖も見えればよいのですが、このホテルの部屋の高さからでは、琵琶湖の湖面は見えません。
▪︎2日目、私たちがまず向かったのは、野洲川河口近くにある、幸津川(さずかわ)の大水口神社です。境内には、明治29年の大洪水の際に、野洲川が決壊したことを伝える「川切れ100周年」の石碑が建てられています。横を見ると1本の筋が刻まれていました。明治29年の大洪水の際には、ここまで水位があがった…ということを示しているのです。現在、琵琶湖の水位は人工的にコントロールされています。また、かつては2匹の蛇がうねるような形をしていた野洲川の河口域(南流と北流)も、直線的な放水路につけかえられています。かつてのような水害はなくなりました。大水口神社の前、以前は田舟が通るクリーク(水路)でした。この地域は、水郷地帯だったのです。もちろん、現在では、クリークも埋め立てられ、周囲の水田も圃場整備が行われ、もはやかつての風景を想像することはなかなか難しい状況です。
地球研・日比国際ワークショッブ(5)

 ▪︎総合地球環境学研究所・奥田昇さんを代表とするプロジェクトの「日比国際ワークショップ」の1日目の最後。夕食をとるために野洲市菖蒲にある「あやめ荘」に移動しました。ここで、琵琶湖の湖魚を使った様々な料理をいただきました。フィリピンの皆さんはどうかな…と思っていましたが、皆さん大喜びでした。しかも、発酵食品である「鮒寿司」をじつに美味しそうに召し上がっておられました。実際、ここでいただいた「鮒寿司」は絶品でした。すばらしい。
▪︎総合地球環境学研究所・奥田昇さんを代表とするプロジェクトの「日比国際ワークショップ」の1日目の最後。夕食をとるために野洲市菖蒲にある「あやめ荘」に移動しました。ここで、琵琶湖の湖魚を使った様々な料理をいただきました。フィリピンの皆さんはどうかな…と思っていましたが、皆さん大喜びでした。しかも、発酵食品である「鮒寿司」をじつに美味しそうに召し上がっておられました。実際、ここでいただいた「鮒寿司」は絶品でした。すばらしい。
▪︎写真は、南山大学の篭橋さん(4月からは京都大学に異動されます)と、フィリピンの「Laguna Lake Development Authority」のAdeline Santos BROJAさんです。急遽、湖魚料理を楽しみながら、プロジェクトの人間社会班の研究内容に関する議論が始まりました。英会話の不得手な私にかわって、篭橋さんが懸命に通訳をしてくださいました。ありがとうございました。今回は、人間社会班からこの国際ワークショップに参加したのは、篭橋さん(環境経済学)、金沢大学の大野さん(環境政策論)、秋田県立大学の谷口さん(社会学)、そして島根県から来られた平塚さん(フリーの環境コンサルタント)、4名方達と私です。皆さんとは、食事のとき、食事のあとの酒の時間、バスによる移動の時間…様々な空き時間に、非常に有益なディスカッションをすることができました。
地球研・日比国際ワークショッブ(4)



▪︎平湖・柳平湖の視察のあとは、近江八幡市津田町にある水草堆肥をつくっている場所です。原料は、琵琶湖の南湖に繁茂する水草です。現在、南湖の水草が大変な問題になっています。この水草を刈り取る専用船で対応しています。巨額の費用がかかります。刈り取った水草ですが、現在は、乾燥させて水草堆肥にして、無料で配布しています。この水草堆肥、大変、美味しい野菜ができるらしく大変人気があります。昔は、沿岸の農村が、琵琶湖の藻取りを行っていました。もちろん、化学肥料がない時代です。藻取りは、相論といって、隣村と争いになるぐらいでした。水草が大きな経済的価値をもっていたのです。ところが、化学肥料が簡単に入手できるようになると、水草は見向きもされなくなりました。
▪︎現在、多くの湖沼では、水質の悪化にともない水草が減少しています。琵琶湖では、逆に、以上に繁茂する状況になっています。そのことが、様々な問題(湖底の低酸素化や生態系への悪 影響)を引き起こしています。詳しくは、次の文献を読んでいただければと思います。滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員である芳賀裕樹さんが執筆されています。「南湖の水草(沈水植物)繁茂」という解説です。
▪︎写真は、その水草堆肥です。トップの写真、リーダーの奥田さんが指でつまんでいるものは、淡水の二枚貝です。下段・右側の写真は、水草にまじっている二枚貝を撮ったものです。この写真の水草は、まだ熟成させている途中段階ですので臭いがしました。しかし、最終的に水草が完全に堆肥になると、まったく無臭の状態になります。
▪︎繁茂する水草が、かつてのように経済的な価値を生み出し、琵琶湖から陸地へと再び運ばれ利用されるような「循環」の仕組みができれば良いのですが、今のところ、それはうまくできていません。社会のなかに「水草の利用」がうまく組み込まれなければならないのです。現在は、税金を買って刈り取り、県有地で堆肥にして、そのあとは無料で配布しています(一人一人への無料配布の量には上限がある)。これからの大きな課題かと思います。なにか、良い方法はないものだろうか…とても気になります。
地球研・日比国際ワークショッブ(3)



 ▪︎京都大学生態学研究センターの調査船「はす」による視察のあとは、草津市にある平湖・柳平湖に移動しました。平湖・柳平湖は琵琶湖の周辺にある内湖のひとつです。現在、淡水真珠養殖復活に向けて地元の皆さんが挑戦をされています。真珠といえば、伊勢志摩地方の海での真珠養殖を連想します。しかし、琵琶湖でも特に第二次世界対戦後、盛んにイケチョウガイによる真珠養殖が行われてきました。しかし、琵琶湖の水質悪化によりイケチョウガイが壊滅状態となり、92年にはイケチョウガイの漁獲量が統計上はなくなってしまいました。いったん壊滅状態となった淡水真珠養殖ですが、水質が改善するにしたがい、再び復活に向けての取り組みが始められたのです。
▪︎京都大学生態学研究センターの調査船「はす」による視察のあとは、草津市にある平湖・柳平湖に移動しました。平湖・柳平湖は琵琶湖の周辺にある内湖のひとつです。現在、淡水真珠養殖復活に向けて地元の皆さんが挑戦をされています。真珠といえば、伊勢志摩地方の海での真珠養殖を連想します。しかし、琵琶湖でも特に第二次世界対戦後、盛んにイケチョウガイによる真珠養殖が行われてきました。しかし、琵琶湖の水質悪化によりイケチョウガイが壊滅状態となり、92年にはイケチョウガイの漁獲量が統計上はなくなってしまいました。いったん壊滅状態となった淡水真珠養殖ですが、水質が改善するにしたがい、再び復活に向けての取り組みが始められたのです。
▪︎私たちが平湖・柳平湖を訪問すると、地元の集落の役員さんと、草津市の農林水産課の職員の方たちが待っておられました。淡水真珠復活への挑戦に関して、いろいろお話しを伺いました。お話しだけでなく、実際の淡水真珠も見せていただきました。フィリピンからの女性研究者たちは、この淡水真珠にとても関心をもったようです。どちらかというと、県境者というよりも女性として…でしょうか。それを見た、フィリピンの男性研究者は、「ガールズはすごいね!」と笑っておられました。
▪︎平湖・柳平湖で復活を目指しているのは淡水真珠だけではありません。魚の復活も目指しておられます。ここでは、放流したニゴロブナの稚魚がまたこの内湖に戻ってこれるように、魚道の設置が行われることになっています。かつては、琵琶湖と内湖とはつながっていましたが、国の巨大プロジェクトである琵琶湖総合開発等により、現在では琵琶湖と内湖とが分断され、水位にも落差が生まれています。このままでは、魚が琵琶湖から遡上してきません。そのため、いろいろな経緯のなかで魚道が設置されることになったのです。
▪︎私たちのプロジェクトによって、その二ゴロブナ等の魚類のモニタリング調査も行う予定になっています。プロジェクトとして(科学として)この地域の活性化を支えることにしています。この地域は、もともと水郷地帯でした。農作業に行くには、いつも田舟を漕いでいかねばなりませんでした。そのときは、必ず、平湖・柳平湖を通って行っていたといいます。また、集落内には、水路が流れており、家の2階の窓から釣りができたいといいます。そのような魚を食用にもされていました。この地域は、いわゆる「魚米の郷」だったのです。ところが、河川改修や圃場整備事業により、そして最後は琵琶湖総合開発により、かつての水郷地帯の風景はかんぺきなまでに消えてしまいました。「水」と「陸」が分断してしまいました。50歳以上の人たちは田舟の艪(ろ)をこぐことができますが、その年齢の以下の方たちはできないのだそうです。子どもの頃に、艪をこぐ経験ができなかったからです。
▪︎さて、ワークショップの話しに戻りましょう。平湖・柳平湖の現場では、魚が産卵に来ているところを撮った写真も見せていただきました。地元では、浅瀬に魚がやってきてバシャバシャと水しぶきを飛ばしながら産卵を行うことを、「魚がせる」といいます。内湖と切れてしまってからは、あたりまえのように見られた「魚がせる」こと地元の子どもたちは知らないといいます。現在、自体も地元の皆さんとは、魚を復活させて、小さなところから村づくりの活動を始めることができたらいいですねと話しあっています。水田と内湖と琵琶湖と魚がセットになった暮らし。村づくりの活動に参加しておられる皆さんは、そのような暮らしがこの地域の基本的な姿であり、そこにできるだけ戻っていくべきだと考えておられるのです。
【関連エントリー】
平湖柳平湖の「つながり再生構築事業」の協議会
「つながり再生モデル構築事業」第4回協議会」
魚の賑わい
琵琶湖岸の水郷地帯
地球研・日比国際ワークショッブ(2)

▪︎総合地球環境学研究所・奥田昇さんを代表とするプロジェクトの「日比国際ワークショップ」の1日目です。奥田プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」では、琵琶湖に流入する野洲川流域と、フィリピンのラグナ湖に流入するビナン川流域の2つの流域を主要なフィールドにして比較研究を進めます。また、国内の宍道湖、手賀沼、八郎湖、そして海外では台湾等の湖沼とも部分的に比較研究を進めることになっています。ということで今回のワークショップは、日本から15名、フィリピンから8名、台湾から1名の研究者が参加して開催されました。
▪︎26日の総合地球環境学研究所でのオリエンテーションを兼ねたキックオフミーティングの後、第1日目の27日には、まずは琵琶湖疎水を見学したのち、大津市の比叡山延暦寺の門前町・坂本にある「鶴喜蕎麦」で蕎麦を楽しみました。蕎麦の昼食のあと、京都大学生態学研究センターの調査船「はす」に乗せていただき、野洲川の河口や流域下水道の処理施設のある矢橋の帰帆島をめぐりました。調査船からの見学には、生態学研究センター長の中野さんも一緒に同行してくださいました。センター長としてご多忙なわけですが、調査船に乗船することについては、ご同行くださいました。ありがとうございました。



▪︎上の写真は、調査船「はす」から比良山系を写したものです。この日は暖かく、琵琶湖には何隻ものヨットが走っていました。ただし、気温自体は高くても、早いスピードで走る船上は風も強く、私は早々に運転室に入り風をよけることになりました。皆さんは、楽しそうですね。
地球研・日比国際ワークショップ(1)

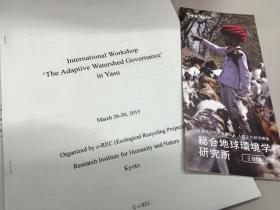

▪︎昨晩は、お世話になった方の盛大な送別会が開かれましたが、昼間は、京都の洛北にある総合地球環境学研究所にいました。昨日から日曜日まで、私がコアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の国際ワークショップが開催されます。私たちのプロジェクトでは、国際比較のフィールドとして、フィリピンのラグナ湖に流入する流域のある地域に研究調査のサイトを設定しています。今回のワークショップでは、そのフィリピン側の共同研究者の皆さんが来日されました。そして、日本のメインとなる調査値、滋賀県の野洲川流域を、我々日本側の研究者と一緒に視察しながら、ディスカッションを行う予定になっています。
組織の壁を越えて
 ▪︎ここしばらく間に、職場の組織の壁を越えて、いろんな方達と語りあうチャンスがありました(呑みとセット)。そして、いずれの方達とも、組織の壁を越えて、もっといろいろ私たちの大学について語り合おう、行動しよう…という気持ちを共有できました。「Beyond the wall of sectionalism !」です。それぞれが、心のなかで「このままではあかん…」と思っていても、それを心の外に出して、声にして、お互いにつながっていかなければ何も変わりません。ここしばらくの間で、いろんな方達と心がつながった…のではないかと思います。
▪︎ここしばらく間に、職場の組織の壁を越えて、いろんな方達と語りあうチャンスがありました(呑みとセット)。そして、いずれの方達とも、組織の壁を越えて、もっといろいろ私たちの大学について語り合おう、行動しよう…という気持ちを共有できました。「Beyond the wall of sectionalism !」です。それぞれが、心のなかで「このままではあかん…」と思っていても、それを心の外に出して、声にして、お互いにつながっていかなければ何も変わりません。ここしばらくの間で、いろんな方達と心がつながった…のではないかと思います。
▪︎昨晩は、大変お世話になった方の盛大な送別会でした。素敵な送別会になりました。送別会なのですが、自分の座った席のテーブルにいた他学部の教員の方達とも、「こんなことを一緒にやろう」 、「こんなこともできるやろ」と盛り上がりました。他のテープルからやってこられた方とも、「そういうことだと、応援しますよ」と言っていただけました。仕事は、やはり夢を語りあって、それを共有して、力をあわせて実現していくことが大事かと思います。「仕事には、ロマンが必要や!!」。これは、私が滋賀県庁(琵琶湖博物館開設準備室、琵琶湖博物館)に勤めていたときに、常々、私の上司が言っていた言葉です。それぞれの部署のルーティーンの仕事をきちんと確実にやることも、もちろん必要ですが、同時に、セクションの壁を越えて、みんなで一緒に大きな夢を実現していくことが大切だと思うのです。
▪︎送別会の帰り、坂道を歩いていると、政策学部の深尾先生と一緒になりました。深尾先生は、政策学部を代表する若手教員のお一人です。その深尾先生と歩きながら、「ほんじゃ、ちょっと呑みますか」ということになり、先斗町にある「お酒と、ときどきトルコ meme」という、ちょっと変わったお店にたどり着きました。「お酒と、ときどきトルコ meme」。先斗町の通りから路地に入り、2階にあがったところにあるのですが、深尾先生が鋭い勘で「この店や!」と決めてくれました。トルコ風の水餃子をいただきながら、いろいろ話しをさせていただきました。結論からいえば、「龍大を、もっとオモロイ大学にしよう‼︎」ということでしょうか。そういえば、不思議なことに深尾先生とはサシで呑んだことはなかったな〜。楽しい時間をいただきました。ということで、多くの職場の皆さんと壁を越えて、一緒に頑張っていこうと思います。もちろん、「仕事には、ロマンが必要や!!」が基本です。
