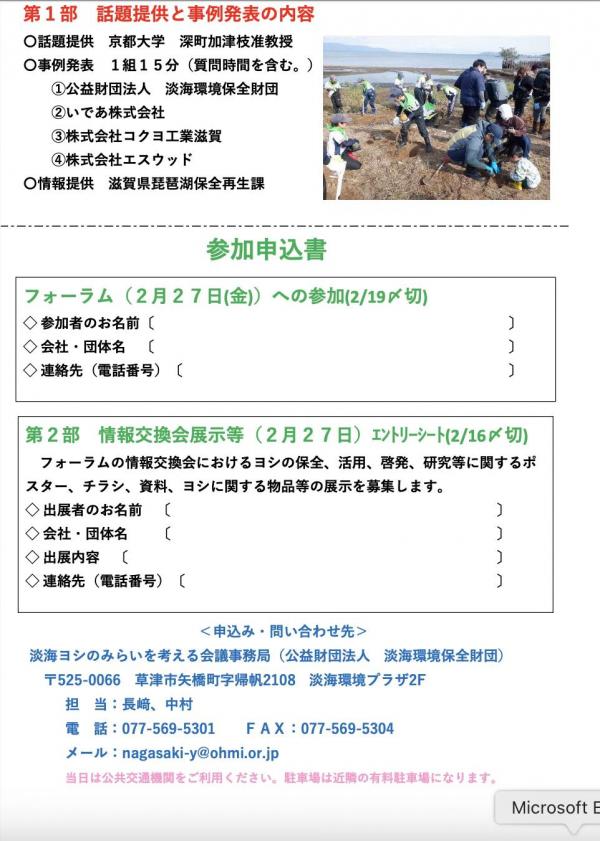東京出張


 ▪️3泊4日の東京での出張を終えて、昨晩、帰宅中。28日から31日までです。ひさしぶりの東京でしたが、寄り道もせずそのまま直帰しました。4日ともしっかり働いて、晩は一緒に出張した同僚の皆さんたちと楽しく夕食をいただくことができました。いろんな話もできて、リラックスできました。
▪️3泊4日の東京での出張を終えて、昨晩、帰宅中。28日から31日までです。ひさしぶりの東京でしたが、寄り道もせずそのまま直帰しました。4日ともしっかり働いて、晩は一緒に出張した同僚の皆さんたちと楽しく夕食をいただくことができました。いろんな話もできて、リラックスできました。
▪️ここから、話は急に変わるのですが、宿泊したホテルのベッドだと朝快適に起床できました。自宅の布団だと毎朝、イタタタ…と言いながら起きているのです。布団の硬さとかあっていないんですね。今回の出張で、「はやくベッドを買おう」とかたく決意しました。布団やベッドは毎日使う道具ですからね。とはいっても、おそらくは無印良品あたりで購入するんじゃないのかな。まだ決めてはいませんけれど。こちらですかね。
▪️写真ですが、夕食に入ったお店でいただいたモツ鍋です。馬肉なんかもウリにしている居酒屋さんでした。馬刺しとともに美味しくいただきました。もっとも最後の〆の雑炊は同僚に食べてもらいました。持病の関係で、糖質は天敵なものですから。めでたし、めでたし。
「仰木と仰木の里」のこれから

▪️自宅のある新興住宅地に隣接する農村、仰木の中にあった耕作放棄地を農地に再生して農作業のお手伝いをしている様子を、時々facebookに投稿してきました。これは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も参加している仰木地域共生協議会の活動です。その仰木地域共生協議会の活動が、農水省の「農村RMO」として認められ、補助金がでることになり、いよいよ本格的に活動をしていく予定になっています。ということで、3月1日にキックオフのイベントを開催します。詳しくは、以下をご覧ください。
当協議会では以下のイベントを実施いたします。
どなたでもご参加いただけますが、定員がございますので、早めのお申し込みをよろしくお願いします。申し込みは以下のサイトからお願いします。
https://ogikickoff.peatix.com/【イベントの趣旨】
滋賀県大津市、豊かな自然と歴史が息づく「仰木」地区。 本イベントは、地域の歴史や文化を再確認し、新たな仕組みや多様な活動事例を共有することで、これからの地域づくりを共に考える場です。対話を通じて、未来に向けた協力体制を一緒に築いていきませんか? 地域の方、仰木の未来に関心がある方、どなたでも大歓迎です!お昼は仰木の棚田米や地元の食材で丹精込めて作る愛情たっぷりのお弁当を用意しています。(希望者のみ、実費500円)
【開催概要】
日時: 2026年3月1日(日)10:00 〜 16:30場所: 成安造形大学 コミュニティスペース「結」
定員: 30名(先着順)
参加費: 無料
主催: 仰木地域共生協議会
後援: 大津市
協力: 成安造形大学、一般社団法人仰木地区活性化委員会わさいな仰木
【プログラム内容】
1. 基調講演「仰木地区の歴史と文化、そしてこれからの地域づくり」 講師:加藤 賢治 氏(成安造形大学 副学長)
2. プロジェクト説明
農村RMOの概要説明(滋賀県農政水産部農村振興課)
先行事例紹介:加納 文弘 氏(桜谷地域農村RMO推進協議会 会長)
仰木地域共生協議会の紹介:桂 一朗(事務局長)
3. ゲスト講演「未来につながる食×農の新しい取り組み」 講師:松本 直之 氏(一般社団法人 次代の農と食をつくる会)
4. 地域活動紹介リレー
農業、地域活動、教育など、仰木周辺で活動する様々な方による活動紹介です。
5. グループワーク
グループごとにテーマを設けて仰木や仰木の里、周辺地域のこれからを一緒に考えます。
人間に対する思いやりの感覚を持ったAI
▪️コンピューター科学者のジェフリー・ヒントンさんは、2024年にノーベル賞物理学賞を受賞されています。もともとは米グーグルの元幹部でしたが、2023年に、AIの発達がもたらす危険性について自由に話せるようにGoogleを退職されています。こちらの「人類がAI支配を生き延びる唯一の道「AIのゴッドファーザー」が提唱する解決策とは」という記事は、昨年の8月のCNNのネットニュースですが、AIが急激に進化していることを実感するようになり、調べ物をしていてこのような記事に辿り着きました。
▪️ヒントンさんは、多くのテック企業が試みているように「従属的な」AIに対する人間の「支配」を守ろうとしてもうまくいかないと考えています。AIは私たち人間よりも賢いので、自分たちの目的を達成するために人間を支配しようとするというのです。「AIは現時点で既に、自分の目的を達成するために人間を欺いたり、だましたりする事例が報告されている」のです。それじゃあどうするのか。ヒルトンさんは、母親が子どもを守るように、AIに人間に対する思いやりの感覚を持たせることだというのです。ちょっとジェンダーに関するバイアスっぽいものも感じますが、言わんとすることはわかります。
▪️この記事を読んで、小さな頃に読んだ漫画「鉄腕アトム」を思い出しました。この漫画ではオメガ因子という装置が登場します。このオメガ因子を装着されると、ロボットが良心を持たず人間に対して平気で悪いことをするようになるのです。たしか。この時、ロボットは基本、人間に対して善良な存在なのですが、AIの場合は、そのまま成長していくと必然的に人間にとって邪悪な存在になっていくことが予想されているのです。オメガ因子が組み込まれていなくても。そうならないように工夫をして人間に対する思いやりの感覚を持たせるということにるわけですね。でも、具体的にはどういうことなんでしょうね。間に合うのかな。以下は、記事の最後の部分です。
AIはいずれ、AIを超えた「汎用人工知能(AGI)」になると多くの専門家が予想する。
ヒントン氏は、かつてはAGIの実現に30~50年かかるだろうと思っていたが、今は「合理的に考えて5~20年」で達成されると考えるようになったと話した。
もしAIがこれほど急速に進化すると知っていたらどうしていたかという質問に対しては、AIを機能させることしか考えなかった自分を悔やんでいると告白し、「安全問題についても考えるべきだった」と答えた。
現実化するディストピア、世界に拡散するディストピア。
▪️「ディストピア」って映画や小説の中に描かれていると素朴に思っていたけれど、もう現実なんですね。恐ろしい。ミネソタ州で暴れ回っている⁉︎ アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)が身につけている情報システムについて調べて驚きました。こういうネットニュースを読みました。『ニューズウィーク』の記事です。2つの引用を貼り付けます。「移民政策の名の下に進むこの変化は、いずれ国境を越え、他国の制度設計にも影響を与える可能性がある」というのが恐ろしい。
米国の移民関税捜査局(ICE)が構築しつつある監視システムは、もはや近未来SFの描写と見分けがつかない水準に達している。顔認識、位置情報、DNA、虹彩スキャン、電話盗聴、ソーシャルメディア分析――それらが単独ではなく、巨大なデータ基盤のもとで統合され、全米規模で運用されているからだ。
【監視対象は全世界】
ここまで読めばわかるように、これらの監視が移民に限定されていないことは大きな問題だ。アメリカにいる者をすべて調べ、不法移民をあぶり出すという理屈のため、アメリカにいる人間は誰でも監視対象だ。つまり、もはやICEはアメリカにいるすべての人間を監視する組織になっているのだ。
専門家は、この状況を「移民排除を名目にした全国民監視」と指摘する。データブローカーとAIの発達により、国家はかつてないほど低コストで包括的な監視を実現できるようになった。その最先端にいるのがICEなのだ。
こうした動きが示すのは、アメリカが「自由と法の国」から、「アルゴリズムとデータに統治される監視国家」へと静かに変貌しつつある現実だ。移民政策の名の下に進むこの変化は、いずれ国境を越え、他国の制度設計にも影響を与える可能性がある。
▪️アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)によって、ミネアポリスの市民2人が射殺されました。アメリカの有名なシンガーであるブルース・スプリングスティーンさんが、この市民2人が射殺された事件を受け、強硬な移民政策を進めるトランプ大統領、ミラー大統領次席補佐官、ノーム国土安全保障省長官を名指しで批判する曲を発表しました。この記事で知ることができました。
世界農業遺産の「琵琶湖システム」と「魚のゆりかご水田」
▪️滋賀県では、琵琶湖の湖岸に接する水田で、盛んに「魚のゆりかご水田」の取り組みが行われています。そのなかでも、特にこの動画の「須原せせらぎの郷」の取り組みがよく知られています。この「魚のゆりかご水田」は、国連の国連食糧農業機関(FAO)の「世界農業遺産」として認定された「琵琶湖システム」の中核にある取り組みです。正確には、「琵琶湖システム」は、「森・里・湖に育まれる、農業と漁業が織りなす琵琶湖システム」です。後半の「農業と漁業が織りなす」の方の中核に「魚のゆりかご水田」は位置付けられることになります。
▪️しかし同時に考えないといけないことがあります。前半の「森・里・湖に育まれる」の部分です。「魚のゆりかご水田」が可能になるのは、もちろん地元の農家をはじめとする関係者の皆さんの努力にあります。それはもちろんなんですが、そのような「魚のゆりかご水田」が可能になるのは、その背景にあるれ「森・里・湖」での様々な活動があるからなのです。「森・里・湖」で環境や生物多様性を守るために地道に活動されている方達の存在を忘れてはいけないと思っています。また、そのような方達の活動にもっと光が当たっていく必要があるとも思っています。産業としての林業、落葉紅葉樹の森林の保全、里山の保全、環境こだわり農業、ヨシ群落の保全、身近水路や小河川の保全…、全てが「琵琶湖システム」に包摂される取り組みなのです。これらの多種多様な人が関わる活動がつながりあって「琵琶湖システム」はできています。そのようなことは普段は意識しないのですが、少しお互いに意識し合うだけで、何か変化が起こるはずです。
「利やん」で再会

▪️世界のニュースを読んで、国内のニュースを読んで、気持ちがどんどん塞いでいきます。世界はどうなっていくのでしょう。希望を紡ぎ出すことのできないまま、生きていくのはなかなか辛いものがあります。でも、そういうときは、仲の良い方達と語り合い、そのなかから希望を紡いでいくことが大切なのかなと思います。
▪️昨日は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。珍しく、農学部の古本強先生から「利やん」で呑もうとのお誘いがあり、ご一緒させていただきました。古本さんとは、農学部を開設するときの諸々の仕事を一緒にさせていただきました。とても、気持ちの良い方です。古本さんからは、農学部の最近の様子やご家族のことなどいろいろお聞かせいただきました。そうしていると、お客さんがお2人入ってこられました。そのうちのお1人は、以前、「利やん」でお会いした方でした。長野県で図書館を通して地域づくりに取り組まれている平賀研也さんです。もうお1人は、手塚美希さんです。岩手県の紫波町にある「オガール」という人びとが交流する様々な機能を持った複合施設で、図書館の司書をされています。
▪️平賀さんは、お店に入ってくるなり私のことを思い出してくださいました。初っ端「毎日、利やんに来ているんですか」と言われてしまったのですが、いやいや、週1回が基本です。でも、不思議に「人との出会い」が生まれるのがこのお店なのです。その後ですが、4人で話が盛り上がりました。古本さん、絶好調でした。きちんと帰宅できたかな…。昨晩の様子を、平賀さんがfacebookで説明してくださっています。すべての人に公開されているので、ここに貼り付けさせていただきます。希望を紡ぎ出すことができました。ありがとうございました。
▪️前回、平賀さんにお会いした時のことは、以下の投稿からご覧いただけます。このときは、偶然に、岐阜県で図書館を通して地域づくりに取り組まれている吉成信夫に「利やん」でお会いした時の投稿です。
▪️手塚美希さんとは初対面でした。どのような方なのか、以下をご覧ください。手塚さんのご講演をまとめた記事です。
カナダの首相であるマーク・カーニーさんの講演
▪️学生の頃の話です。経済的には安定成長の時代ですね。指導教員であった領家穰先生がこんなことを黒板に書きました。
制度<集団<個人
制度>集団>個人
▪️この不等号が何を表現しているのかというと、変化のスピードをあらわしています。上の方は、個人が変化していくスピードと比較して、集団はもっと遅く、制度はさらに遅い(あるいは、そのように感じられてきた)かもしれないけれど、これからは、逆になる、あいるはすでに逆になっているといわれたのです。いろんなことを忘れてしまうのですが、この時のことは強く記憶しています。実際、大学卒業後にしばらくしてバブル経済が始まり、その後バブルが弾け、その頃同時に、東西の冷戦がおわり、ソ連は解体しました。東西の冷戦が自分が生きている間に終わるとは思いもしませんでした。
▪️領家先生は、もうお亡くなりになっていますが、もしご健在でアメリカのトランプ大統領に振り回されている世界の状況をご覧になるのならば、この不等号に国家や世界が加わっていたでしょう。その世界を、ひとりの老人(トランプ)という個人が振り回しているわけです(もちろん、背景にはスタッフがいて、取り巻きがいるわけですが)。私が学生時代に、すでに「社会学では、全体社会が国家であることを自明にしてきたけれど、もう今や全体社会は世界や」と言っておられましたので、このときはたまたま世界が入っていなかっただけかもしれません。当時、多国籍企業についてはよくいわれましたが、グローバル経済、グローバリゼーションということは、私の記憶にはありません。
▪️しかし、その第二次世界大戦後に築き上げられてきた世界の国際秩序が、崩壊しはじめたという講演を聞きました。個人、集団、制度、国家を超えて、国家間の国際秩序、すなわち世界の方から大きく変わろうとしている、いやこれまでの国際秩序が崩壊したというのです。カナダの首相であるマーク・カーニーさんが、スイスで開催されている世界経済フォーラム(ダボス会議)で講演をしました。その講演が、あちこちで高く評価されているように感じます。
▪️カーニー首相は、アメリカが主導して築き上げてきた戦後の世界秩序(アメリカの利害に基づいた)は、それが本当であるかのように演じる全員の意志、言い換えればそのような虚構に依存していたという事実をストレートに語っています。身も蓋もない話ですが。そのような虚構は、アメリカ自身が、トランプが粉砕しているわけですからね。だったら、そんなの無理して信じるふりをするのをやめてしまおうぜと、言っているわけです。信じるのを辞めたら、困るのはトランプじゃん、というわけです。偉そうにしているアメリカのような国を相手にせず、既存の国際秩序はすでに崩壊してしまったのだから、中堅国家による新たな協力体制の構築していきましょう。そう言っているわけです。日本では、今のところあまり報じられていませんが…。最初、私はXの投稿で知りました。以下は、その講演の日本語訳です。
▪️2023年に100歳で死去したヘンリー・キッシンジャーさんは、トランプ大統領について「一つの時代の終わりを告げ、古い見せかけを捨てさせるために歴史に現れる人物」という評価をしていたようです。キッシンジャーは、ニクソン政権およびフォード政権期の国家安全保障問題担当大統領補佐官、国務長官を務めた国際政治学者です。カーニーの講演とキッシンジャーの評価はかなりの部分でかさなります。「一つの時代の終わり」とという部分。戦後、良くも悪くもアメリカが築いてきた世界秩序が終わるということでしょう(もちろん、キッシンジャーはトランプの手法や憲法への挑戦については厳しく批判していますけど)。そもそも、トランプ大統領って憲法や法律をこれまでの大統領のように自分を縛るルールとしては捉えていませんし。無視するか敵を攻撃するための道具に使うかどちらかのように思います。そもそも憲法や法律がどのようなものであるのかも、深く理解していない可能性があるようなきがします。
▪️第2期のトランプ政権になって以降、そして今月に入って、ベネズエラへのアメリカ軍の侵攻、さらにグリーンランドの領有といった一連の出来事が起きてきすごく気持ちが悪かったのは、戦前の帝国主義的な世界に逆戻りして、ギャングの親分が「縄張り」を主張して、暴力と金の力で好き放題やるような世界に戻ってしまうことに対する拒否感なのだと思います。地面が揺れるよう気持ち悪さです。そのような世界の状況のなかでのマーク・カーニーの講演です。注目されるわけですね。
▪️カーニーがいう「中堅国家による新たな協力体制」に日本はどう向き合っていくのでしょうか。トランプが、G7(主要7カ国)が構築しようとしてきたリベラルな国際秩序ではなく、それに代わる利益と力による新たな国際枠組みとしてコア5(5とはアメリカ、中国、ロシア、インド、日本、EUは排除されています)を構想しているらしい。ただ、そもそもトランプ大統領は、今年の11月にある中間選挙以降も政権が維持できるのか(民主党が上下両院で過半数の議席を取れば弾劾されるかも)、残りの任期3年間大統領の職務を続けられるのか。79歳です。発言や彼の挙動をみていると…心身ともに健康状態はどうなんだろうと思いますね。特に、精神面ですが…。
「まちラボFAN」と「仰木地域共生協議会」

▪️今日の午前中、研究室に部長をしている「まちラボFAN」の学生さんたちがやってこられました。来年度部長に就任するにあたり、書類にサインと印鑑を押してほしいということでやってこられたのです。学生さんたちは、仰木の里というJR湖西線「おごと温泉」駅を最寄駅とする大きな新興住宅地の小学校で、地域住民の皆さんと一緒に「エディブル・スクールヤード」という活動をされています。小学生の児童の皆さんの食育を支援する活動です。ということで、「こういう活動もあるんですよ」と、理事として参加している「仰木地域共生協議会」の活動を知ることのできるブログのことをお伝えしました。以下のブログを学生の皆さんにも丹念に読んでいただき、小学校の食育に加えて、このような農村と新興住宅地の連携活動にも関心をもってくださると嬉しいなと思っています。ちなみに、この協議会は、農水省による「農村RMO」からの補助金をもとに活動を始めています。