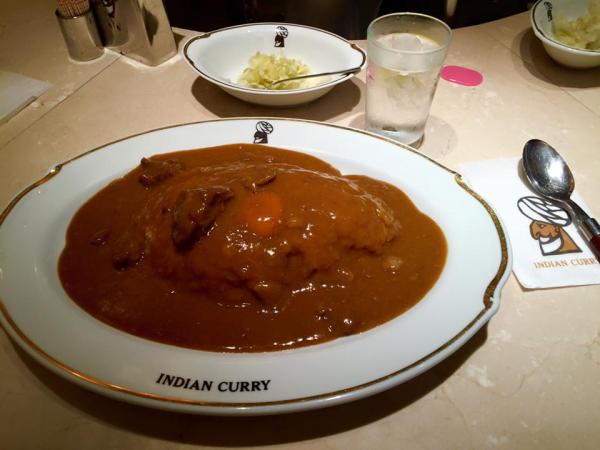NHKクローズアップ現代「“穏やかな死”を迎えたい~医療と宗教 新たな試み~」
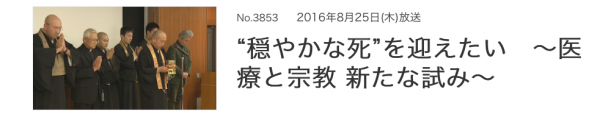
■細かな議論は別にして、とても大切なことだと思います。なおかつ、とても関心があることでもあります。
NHKクローズアップ現代「“穏やかな死”を迎えたい~医療と宗教 新たな試み~」
facebook「滋賀県農政課世界農業遺産推進係」のページ
NHKクローズアップ現代「小さな島の大きな決断~地方創生の現場から~」

■NHKの「クローズアップ現代」、新年度から新しい番組に変わるようですね。新しい番組がどのような内容なのか私は知りませんが、1993年から続いてきた国谷裕子キャスターの番組がNHKから消えてしまうことに、非常にがっかりしています。もったいない…。私は、勤務時間の関係で、なかなか放送を拝見することはできませんが、公式サイトにある「放送まるごとチェック!」は頻繁に拝見してきました。放送が一部動画で観ることができますし、放送内容が全てテキスト化されています。学生を指導する際にも、活用させてもらいました。国谷裕子キャスターが降板することで、この公式サイトも消えてしまうのでしょうね。もったいない…、非常にもったいないと思います。
■今日は、会議と会議の間の時間で、来年度の授業の内容を考えていました。その際にヒントにさせてもらったのが、クローズアップ現代の今年の1月13日に放送された「小さな島の大きな決断~地方創生の現場から~」です。こんな内容です。アンダーラインは、私が注目したところです。ぜひ「放送まるごとチェック!」でご覧いただきたいと思います。番組に登場された、青柳花子さん、その後も頑張っておられますかね〜。
“消滅”を回避し、自ら地域振興アイデアを絞り出せ-いま全国の自治体に、年度内を期限に総合戦略の策定が求められている。データに基づく人口ビジョンや具体的な雇用創出戦略が国に承認されれば、地方創生予算から助成を受けられる仕組みだ。現実には特効薬はなく「コンサルタント丸投げ案」も存在すると言われる中、新潟沖にある人口365人の孤島の挑戦が注目されている。新潟県粟島浦村(あわしまうら)は、衰退する漁業と観光民宿業を抱え、25年後には人口が180人まで減ると予測される典型的な消滅危惧自治体だ。いま、残った若者たちが島外協力者と10年先を見据えた「基幹産業の再生プロジェクト」に取り組む。横ならびの基準料金を定めた民宿ではない新しい宿の設立などを含む「若者提言書」の策定を進め、変化に前向きになれない村を粘り強く動かし始めた。総合戦略の提出期限が迫り、島民らが迎えた決断の日。地に足をつけた創生とはどうあるべきか、ある地域の奮闘を通じて考える。
■「放送まるごとチェック!」では、キャンスターの国谷さんが、コメンテータの山崎亮さんに以下の質問をされています。質問に対する山崎さんの答えが面白いですね〜。
●人口減少・将来の予測が厳しい島ならば、外から来た方のアイデアを歓迎するかと思いきや抵抗感が強かった その姿をどう見た?
「こういう強いつながりの中で、何かを動かしていこうと思う時には家族のような関係の中からどういうふうに、それを新しい方向へつむぎ直していくのかという事が大切になると思いますね。」●外から来た変化をもたらしてくれそうな人に対する不信感や本気度を問う気持ち 島の人々のその気持ちの背景にあるのは何か?
「その本気度を確かめたくなるという気持ちが湧いてしまうんだと思いますね。」●外から来た人が特別扱いされる事で、まなざしが厳しくなる そういう例もあった?
「我々が関わった当初はやはり、役場の人たちが外から入ってくる移住者ばっかりに優遇策を出しているんじゃないかという話をとてもよく聞きました。」●人間関係が濃密でいろいろな古いルールがある地域で理解を進め、本当の変化をもたらしていくには、どういうプロセスを踏んでいけばよい?
「誰かが持ってきたものをやろうという事ではない事。」「本人たちがこれをやるというふうに言い出したかどうかという事と、この人たちと一緒にやりたいと思えるような仲間を、ちょっと時間はかかるけれどもつくる事ができたかどうか。」●コンサルタントの阿部さんは40代までの移住者を中心に話し合いを重ねた その中での気づきや理解はどういうふうに生まれてくるもの?
「情報を知らないと、なかなか新しい発想が出てきませんので、これから島の人口はどれぐらいになるのか、それから、もし人口が減ってしまうんだったらどんなやり方があるのか、全国や世界の事例をみんなに知って頂く。」「要望や陳情型の意見ではなくて、提案・実行型の意見ですね。」●提案されたものが実行できるかは人間関係が大事だとおっしゃったが、どこを見ている?どういう人を見ている?
「人と人のつながりをどういうふうに作っていくのか、最初にそれを見て、そのあとつながった人たちが地域資源とどういうふうにつながると新しい事業が生みだされるのか?人と物の関係を見るのは、その次ぐらいかもしれないですね。」
■いろいろ指摘をされていますが、共感するところが多々ありました。地域づくりや地域活性化だけの問題ではなく、現在、自分が関わっている超学際的・実践的な研究プロジェクトと照らし合わせても、とても参考になります。
1人への支援が、社会のためになる・山仲善彰市長インタビュー
 ▪︎「滞納取り立てよりも支援」という山仲善彰・野洲市長のインタビュー記事(朝日)を読みました。野洲市は、全国に先駆け、「生活困窮者自立促進支援モデル事業」に取り組んきたました。山仲さんのインタビュー記事は、そのような取り組みの成果や実績に基づくものです。
▪︎「滞納取り立てよりも支援」という山仲善彰・野洲市長のインタビュー記事(朝日)を読みました。野洲市は、全国に先駆け、「生活困窮者自立促進支援モデル事業」に取り組んきたました。山仲さんのインタビュー記事は、そのような取り組みの成果や実績に基づくものです。
▪︎山仲さんとは、滋賀県庁におられる時から少しお付き合いがあります。琵琶湖環境部長をされていた時に、琵琶湖の環境問題関連の仕事では、いろいろお世話になりました。今も、滋賀県の「ヨシ群落保全審議会」ではご一緒させていただいています。しかし、よくよく考えてみれば、山仲さんと環境以外のことでお話しをさせていただいたことはなかったように思います。私は、右の朝日の記事を読んで、多くの点でなるほどと納得しました。
▪︎この記事に刺激を受けて、さらに野洲市の政策に関してネットで関連記事を探してみました。すると、『日経ビジネス』の記事がみつかりました。『日経ビジネス』の「2000万人の貧困』というシリーズ記事の中のひとつのようです。「1人への支援が、社会のためになる『困窮者自立支援法』モデル都市の市長の提言」(2015年9月1日(火))というタイトルが付いていました。貧困に苦しむ人びと、高齢者、障害者といった社会的弱者を、行政としてどのように包摂していくのか、また、そのためにはどのような行政組織の経営が必要なのか…といった内容でした。以下は、インタビューの冒頭に山仲さんが語っていることです。基本的な考え方が示されています。続きについては、ぜひ直接お読みいただければと思います。

行政の基本は、市民の方がそれぞれ健康で幸せで自己実現でき、人生を楽しめるための公共サービスを提供することだと思っています。
伸びようとする人がより伸びられるように、困難な状況にある人はきちっと自立できるようにということです。困窮者や弱者から発想が始まっているのではありません。弱者も、そうでない人も、それぞれの人生がいいものになることが大事だと思います。
ただ、伸びる人の場合はある程度、自分で資源調達ができたり、支援が見つけられます。けれど弱者の場合、そうはいかないことがある。ですから、どちらかと言えばそこを手厚くすることによって、全体が良くなるという視点に立っています。
もう一つは、やっぱり「1人を救えない制度は制度じゃない」ということです。役所へ行くと「この制度はあなたのためではないのでお引き取りください」とか、「いや、うまく合わないんですよ」と言われて追い返される。生活保護のいわゆる「水際作戦」(注:生活保護の受給申請者に対して、費用を抑えるなどの目的で、自治体ができるだけ受給できない理由を見つけようとすること)なんていい例ですよね。
制度というのはそれではいけません。そこにニーズがあるのだから、何とか解決するための手段でなくてはいけない。公序良俗に反することはいけませんが、その人の人生にかかわることや地域のためにというニーズなのであれば、課題を最終的にクリアできるようにするのが務めです。
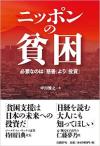 ▪︎なお、この山仲さんのインタビューは、日経BP社から発行されている『ニッポンの貧困 必要なのは「慈善」より「投 資」』の中にも収録されているようです。以下は、amazonに掲載された内容紹介です。
▪︎なお、この山仲さんのインタビューは、日経BP社から発行されている『ニッポンの貧困 必要なのは「慈善」より「投 資」』の中にも収録されているようです。以下は、amazonに掲載された内容紹介です。
日本の相対的貧困は、およそ2000万人――。75歳以上の後期高齢者よりも多いこの国の貧困層は、この先3000万人まで増えるとも言われています。そしてこの病巣は静かに、けれども急速に、日本に暮らすあらゆる人々の生活を蝕み始めています。
ひとり親、女性、子供…。これまで貧困は、社会的弱者の課題として語られることが多かったはずです。
けれど貧困は今や「一部の弱者の問題」として片付けられる存在ではなくなっています。困窮者の増加が消費を減退させ、人材不足を進め、ひいては国力を衰退させる――。
経済記者が正面から取り組んで見えてきたのは、貧困問題が日本経済や日本社会に及ぼす影響の大きさでした。
「かわいそう論」はもう通用しません。求められるのは、貧困を「慈善」でなく「投資」ととらえ直す視点の転換です。企業やビジネスパーソンにできることは何か。
貧困を巡る日本の現状と課題、そして解決の糸口を「経済的観点」から分析した初のルポルタージュ。
▪︎この本の紹介にある「貧困は今や「一部の弱者の問題」として片付けられる存在ではなくなっています」や、「貧困問題が日本経済や日本社会に及ぼす影響の大きさでした」という指摘は、山仲さんの「1人への支援が、社会のためになる」という考え方と、どこかで繋がり合うような気がします。現在、貧困ではない人でも(貧困は自分には関係ないと思っている人でも)、より大きな視点に立てば、貧困問題は自分自身の問題でもあるわけです。自己責任という言葉は、時として、このような現実を隠蔽することになります。また、社会が成立するために必要な共同性をも蝕んでしまうことになります。
「“移住1%戦略”は地方を救えるか」(NHKクローズアップ現代)

■昨日のNHKの「クローズアップ現代」は、「“移住1%戦略”は地方を救えるか」でした。非常に興味深い内容です。私は、教授会と研究科委員会、そのあとは専攻委員会と会議が夜まで続き、この番組を視ることができませんでした。ということで、クローズアップ現代のサイトを確認してみました。以下は、この番組の内容を紹介したものです。
「もし毎年1%の人を呼び込めれば、町の人口減や高齢化は食い止められる」とする“理論”が注目を集めている。典型的な中山間地である島根県邑南(おおなん)町などで実践が始まっている「1%戦略」だ。年に数世帯ずつ家族が定住してくれれば、大規模な産業誘致や開発などしなくとも、数百人規模のコミュニティは存続可能という。実際、移住は地方衰退の救済策としてどこまで有効なのか?NHKでは明治大学と共同で全国の自治体に移住に関する最新状況を調査した。昨年度、県外流入者は1万人超、この5年で4倍近くに増えたことがわかった。さらに、移住支援を行うNPOの調査でも移住者の半数を40代までが占めるなど、現役世代の増加が顕著だ。地方を選択する理由は“暮らしやすさ”という。大抵、表面上は収入減となる地方移住だが、生活上の様々な要素を貨幣価値に換算し具体的に分析してみると、東京生活より「豊か」にすることも可能なことが見えてきた。田園回帰と呼ばれる最近のムーブメント、地方消滅対策としての可能性とヒントを、データジャーナリズムのアプローチから探る。
■解説は、一橋大学の小田切徳美さん。番組では、東京から鳥取県に移住した若いご夫婦の紹介からはじまります。鳥取での生活の豊かさを経済的価値に置き換えると、「利便性については東京に劣るものの、総合評価で比べると鳥取のほうが3万円以上価値が高くなりました。 鳥取の暮らしやすさは全国でもトップクラスという結果がはじき出されています」というのです。最近、よく知られるようになった徳島県の神山町も紹介されます。このような最近の地方での動きを、移住支援を行うNPOグリーンバレーの理事・大南信也さんは、「今までなかったような機能が少しずつそこに集まってきて回り始めるということですよね、地域内でいろんな(ことが)。ある面、経済が循環し始める、小さいながらも」と説明されています。小さな経済の循環。そして、そこに人のつながりが生まれてくる。興味深いですね~。
■島根県の山あいにある,自治体、邑南町も紹介されています。人口は11,000人の邑南町では、定住促進策を進め、人口減少を食い止めようとしています。この町では、「移住1%戦略」に取り組んでいます。地元のシンクタンクのシミュレーションで、 地区の人口の1%ほどの移住者を呼び込めば、企業誘致や特産品の開発に頼る必要はないということがわかってきたのです。地元の自治会の副会長さんは、「私たちが不安に感じていたことが、7人という数値を与えてもらったことで、頑張る努力目標が見えた」と述べています。ということで、就農を希望する移住者には、後継者がいない農地を提供するなど、移住してきた若者たちに地域をあげて支援をされています。番組では、小田切徳美さんが、次のように解説されています。
●移住者は、何が移住の決め手になったと語っている?
実は、移住者の方々が異口同音に、「人」だというふうに言うんですね。この「人」っていう意味は多様です。例えばお世話をしてくれた地域コーディネーターの方とか、あるいは移住者の先輩だったり、あるいは見守ってくれた集落のご老人だったり、いずれにしても、ああいう人がいるからこの地域に行くんだということで引き寄せられていく、そういうパターンがあるようですね。
●自治体は何を大事にして総合戦略を作るべき?
総合戦略は現在、市町村単位で作られています。しかし、もっと重要なのは、コミュニティー単位でのビジョン作りです。このコミュニティー単位でのビジョンを作って地域をみがいていく、そのことによって、そこに移住者が入って、そして移住者と共に地域を作り上げることが可能になると思いますね。 (地元の人たちも意識は変わっていく?)そうだと思いますね。
■私自身、実際に番組を視ることはできませんでしたが、ぜひ「NHKオンデマンド」で見てみようと思います。「幸せ」とはいったい何なのか、「豊かさ」とはどういうことなのか、人とのつながり、身近な環境とのかかわりのなかでゆっくり・じっくり、それらの「幸せ」や「豊かさ」を実感することの大切さを、若い年代の人たちも感じ始めているのです。
西粟倉村のこと

▪︎つい先日、知り合いの新聞記者から問い合わせがありました。仕事上の問い合わせというよりも、個人的に意見を聞かせてほしい…という感じでしょうか。このような質問です。「日本創成会議が提唱している東京圏から地方への移住呼びかけについてはどう思うか?」。この「移住の呼びかけ」については、以下の日本経済新聞の記事をご覧ください。
民間有識者でつくる日本創成会議(座長・増田寛也元総務相)は4日、東京など1都3県で高齢化が進行し、介護施設が2025年に13万人分不足するとの推計結果をまとめた。施設や人材面で医療や介護の受け入れ機能が整っている全国41地域を移住先の候補地として示した。
創成会議は「東京圏高齢化危機回避戦略」と題する提言をまとめた。全国896の市区町村が人口減少によって出産年齢人口の女性が激減する「消滅可能性都市」であるとした昨年のリポートに次ぐ第2弾。
東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県では、今後10年間で75歳以上の後期高齢者が175万人増える。この結果、医療や介護に対応できなくなり、高齢者が病院や施設を奪い合う構図になると予測した。解決策として移住のほか、外国人介護士の受け入れ、大規模団地の再生、空き家の活用などを提案した。
移住候補地は函館、青森、富山、福井、岡山、松山、北九州など一定以上の生活機能を満たした都市部が中心。過疎地域は生活の利便性を考え、移住先候補から除いたという。観光地としても有名な別府や宮古島なども入っている。
高齢者移住の候補地域は以下の通り(地名は地域の中心都市。かっこ内は介護施設の追加整備で受け入れ可能になる準候補地域)。
【北海道】室蘭市、函館市、旭川市、帯広市、釧路市、(北見市)
【東北】青森市、弘前市、秋田市、山形市、(盛岡市)
【中部】上越市、富山市、高岡市、福井市、(金沢市)
【近畿】福知山市、和歌山市
【中国】岡山市、鳥取市、米子市、松江市、宇部市、(山口市、下関市)
【四国】高松市、坂出市、三豊市、徳島市、新居浜市、松山市、高知市
【九州・沖縄】北九州市、大牟田市、鳥栖市、別府市、八代市、宮古島市、(熊本市、長崎市、鹿児島市)
▪︎いかがでしょうか。なるほどと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、私は、この提案内容に納得がいきませんでした。一極集中している東京の視点から語られているからです。乱暴にいえば、東京=大都市の論理に地方を従属させて消費しようとしているかのようです。移住とは、そんなに簡単なものでしょうか。高齢者の移住に関していえば、身体の弱ってきた人たちほど、移住は難しいと思います。移住してそこに根を生やして、その土地の人たちといろんな関係を作り、その地域になんらかの貢献をして…そういうプロセスを経ることが移住には必要だと思っているからです。このよう提案は、「物価の安い海外で優雅に暮らそう」という発想と、ほとんどかわりはありません。知人の新聞記者に教えていただきましたが、かつて「シルバーコロンビア計画」というものがあったそうですね。wikipediaで申し訳ありませんが、以下のように説明されています。「1986年に通商産業省のサービス産業室が提唱した、リタイア層の第二の人生を海外で送るプログラムを指す。正式名称『シルバーコロンビア計画”92”-豊かな第二の人生を海外で過ごすための海外居住支援事業』。『92』が付いているのは、目標年次を1992年としていたため。結局は、『計画』どまり、『構想』レベルに終わった」。また、もっと以前に遡れば、「南米への移住」等の政策についても、同様の考え方のように思います。
▪︎そのようなやり取りを、知人の新聞記者としたあと、facebookでひとつの記事をみつけました。岡山県にある西粟倉村に関する記事です。西粟倉村は、岡山県の最北東端に位置し、兵庫県・鳥取県と境を接する村です。記事は、「ニシアワー」という名前がついたサイトです。西粟倉村の挑戦者たちの活動を伝えるサイトです。こう紹介されています。
ぐるぐる、めぐる。生態系の循環に寄り添う地域作り
ニシアワーは、岡山県西粟倉村の挑戦者たち活動をお伝えするメディアです。2008年、西粟倉村で50年後(2058年)を目指す「百年の森林構想」が掲げられました。50年後を目指す冒険の物語は、ローカルベンチャーと呼ばれる挑戦者たちが村に眠っている可能性を発掘していくこと、そして挑戦者たちを見守ってくださる応援者を増やして行くことによって成立し、前進していきます。
■「なんだか、おもしろいぞ!!」と思わせる力のようなものを感じました。西粟倉村の主産業は林業てす。しかし、多くの国内の地域と同じく林業になかなか展望を見いだせない状況にありました。そのような厳しい状況にありながらも、西粟倉村は2004年に合併を阻み、独自の道を歩み始めます。2008年には「百年の森林構想」を打ち出し林業と地域と人の再生をはかっていきます。この「百年の森林構想」の経緯にいて説明した文書を引用してみます。
西粟倉村は、2004年に合併を拒み、村として自立していく道を選択しました。スケールメリットよりもスモールメリット。小さな村だからこそ実現できる未来があるはずだ。大都市、大企業の下請けにはならない、自立した循環型の地域経済を目指すべきだ。2004年以降、議論を積み重ねるなかで、目指すべき方向が徐々に言語化されていきました。
2005年には「心産業(しんさんぎょう)」というコンセプトが打ち出されます。心の生態系の豊かな村へ。心のつながりを大切にしながら、価値の創出と交換が行われる地域経済へ。(中略)仕事がないから過疎化する。だったら仕事を生み出そう。地域資源から仕事を生み出していける起業家型人材の発掘・育成を進めることになりました。 そして2008年、「百年の森林構想」という旗が掲げられました。「百年の森林構想」というビジョン、「心産業」というコンセプト、「雇用対策協議会」という推進組織によって、移住・起業の連鎖反応が広がっていくことになります。
■非常に建設的で前向きな地域経営に対する意志のようなものを感じます。地域の主体性です。そのような主体性が、移住・起業の連鎖を生み出したというのです。このあたりについては、「挑戦者たち」というページにいろんな方たちが登場します。たとえば、酒屋と日本酒バーを開業した女性、「地域の中のローカルベンチャーの支援をする。それのなにが悪いんですか」と主張する役場職員、地域商社、西粟倉・森の学校の若き経営者…。非常に気になる方たちばかりです。こういう方たちがいる地域って、魅力的ですよね。その魅力に挽きつけられるように多くの方たちが、この西粟倉村にやってこられるようです。そして、西粟倉村で生まれて育っている子供たちが増えているというのです。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
他人はどうあれ力

▪︎ヒビノケイコさんという方がおられます。「日々の稽古」というふうに聞こえます。ペンネームでしょうか。それとも、本名で、漢字は日比野恵子さん…だったりして。どうなんでしょう。それはともかく、ヒビノさんが出版された本をamazonで調べたところ、以下のようなプロフィールの方でした。
1982年大阪生まれ。京都精華大学芸術学部卒。山カフェ・自然派菓子工房ぽっちり堂オーナー。 四コマエッセイストとして執筆。
移住支援活動をする夫と全国での講座や田舎ツアーを行う。21歳の時、地に足がついた暮らしとそこから湧き出す表現を求め、京都郊外のお寺を借りて自給的な暮らしをスタート。
2006年出産を機に、さらに腰を据えて生きようと高知県の山奥へ移住し「自然派菓子工房ぽっちり堂ネット店」をopen。 「家庭×仕事×地域」のバランスを大切にアートを生かした経営を目指す。
山奥ながらも「わざわざ行きたいカフェ」として人気店に。50件以上のメディアや書籍で紹介される。コミュニティデザイナー山崎亮氏との出会いを機に講演活動をスタート。
2014年~作家活動を中心にすえ、新しい時代に必要な視点を地域から発信している。
▪︎とてもユニークのプロフィールの方ですね。すごく行動力もある方のように思います。ヒビノさんの『山カフェ日記~30代、移住8年。人生は自分でデザインする』を、一度読んでみようと思います。
▪︎今日は、そのヒビノさんのブログの記事を紹介しようと思います。学生の皆さんにとって、とても大切な指摘をされているからです。「ヒビノケイコの日々。人生は自分でデザインする。」というブログの「大学生は「他人はどうあれ力」を身に付けよう。ポーズをとらず、素直にガンガン物事に向かう子を育てたい」というエントリーです。冒頭には、こう書かれています。「最近、色々な大学での講座や、大学生に関わることが多くて、その中で感じることがあります。とにかく学生さんの差が激しいってこと。やる気があり一生懸命物事にむきあって突き進んでいく子と、なんとなく周りに流されて、ポーズをとってるうちに卒業しそうな子」。多くの大学教員の皆さんが感じていることかもしれません。
▪︎ポーズをとる…とは、どういうことなのてしょうか。このような例でヒビノさんは説明しています。
例えば、発表のプレゼンを見ていても、意識一つで全くありようが違う。自分にしか意識がいっていない子は、リサーチも考察も行動も深くやっていない時点で発表の舞台にたっちゃう。そして、ダルそう、テキトウ、まとまってない話をきかせる、かっこつけてる、なめてる・・・というような態度をとってしまう。聴いている方にとっても結構大変だし、先生も「ちゃんと話なさい」と小学生に言うようなことしかアドバイスできなくなります。
反対に、ちゃんとリサーチ、考察、行動、思索をし、発表も工夫して話す子もいます。ちょっと何かが抜けてても、下手でも、やっぱり熱量をかけてきている子は一目でわかるもの。背筋を正して話をききたくなるし、先生も掘り下げたアドバイスをどんどんしたくなる。だからどんどん伸びていく。
両者の違いは、
・主観だけで自分のことにしか意識が向いていない
・客観性も持ち合わせていて相手のことも考えてる、の差。
そして、「相手は、時間とエネルギーをかけて聴いてくれている」という意識があるかないか。
「他人の目を気にしない力」ってすごく大事なんじゃないかな。これも多くの学生さんをみていて思うこと。
「他人がどうしてるか?どんな姿勢で態度でやってるか?」を気にして合わせてると、実は学外に出たとき、自分までレベルの低い状態に染まっていたことに気がつきます。
▪︎プレゼンがうまくいかなかったときのことを恐れる。自分だけが頑張っていると周りから見られるのは嫌だ。だから「ポーズ」をとって、あるいは周りの「ポーズ」と同調することで、なんとか自分を守ろうとする…ということなのでしょうね。「ポーズ」を取り続けることで、その場その場の自分はなんとか守れるけれど、結局、自分を成長させていくチャンスを失ってしまのではないか、それでよいのか…というわけですね。以下は、ヒビノさんがまとめたポイントです。
■大学生。これがぎりぎりのチャンスと思って姿勢を変えよう
1、自分のちっちゃいプライドにこもらず、相手のこともみえる客観性を持つ
2、ちょっと下手でもいいから、とにかく熱量をかけてやりきる
3、かけた熱量に対応して、アドバイスの質はかわる
4、姿勢のいい子と悪い子の差が大きい。だから逆に、いい子は今めっちゃ得で引き上げられます。
▪︎このヒビノさんのエントリーでは書かれていませんが、私が気になっていいることがあります。それは、関心があるわけでもないのに、「なくとなく」「とりあえず…」と、様々な資格取得の講座やインターンシップに参加して、疲れて果てている学生の皆さんのことです。いろいろ経験することは大切ですが、ただ将来に対する不安を少しでも減らすためだけに参加しているのであれば、時間がもったいないような気がします。エネルギーが分散して、けっきょく、どれも中途半端になっていないか、とても気がかりです。「周りが参加しているので…自分も参加しないと…」といった不安に襲われる。そういう気持ちを聞かせてもらったこともあります。このような場合にも、「他人の目を気にしない力」が必要になるのかもしれません。
島田叡さんのこと
 ▪︎私は神戸市の出身です。高校は、神戸市長田区にある兵庫県立兵庫高等学校を卒業しました。神戸新聞に、母校と関係の深い方の記事が掲載されました。島田叡(あきら)さんです。兵庫高校の前身は旧制の神戸二中になりますが、島田さんはこの二中の卒業生です。以下は、新聞記事からの引用です。
▪︎私は神戸市の出身です。高校は、神戸市長田区にある兵庫県立兵庫高等学校を卒業しました。神戸新聞に、母校と関係の深い方の記事が掲載されました。島田叡(あきら)さんです。兵庫高校の前身は旧制の神戸二中になりますが、島田さんはこの二中の卒業生です。以下は、新聞記事からの引用です。
神戸市出身で、沖縄県最後の官選知事として沖縄戦に散った島田叡(あきら)氏(1901~1945年)の顕彰碑が沖縄県民の募金で建立され、命日とされる6月26日、那覇市の奥武山(おうのやま)公園内で除幕される。除幕式には、井戸敏三知事ら兵庫県代表団も出席し、いまも沖縄県民に慕われる「島守」の事跡をしのぶ。
島田氏は旧制神戸二中(現兵庫高)、東京帝国大をへて旧内務省に入った。45年1月に沖縄県知事として赴任し、米軍上陸を前に県民の疎開や食糧確保に奔走。米軍の砲撃の下でも壕(ごう)を転々として執務を続け、本島南部で消息を絶った。
没後70年を前に、慰霊碑は沖縄県民の有志が期成会を設立し、募金を呼び掛けたところ、主に県内から600万円近くが集まった。顕彰碑は高さ3メートルで、「琉球」を象徴する石灰岩の台座に、「希望」をイメージしたステンレスの球体を組み合わせる。
期成会会長で元沖縄県副知事の嘉数昇明(かかずのりあき)さん(73)は「碑に沖縄県民の『島田さんを忘れない』という思いが結集された。島田さんからもらった兵庫との交流の新たなスタートにしたい」と話す。
除幕式には、兵庫県から井戸知事や久元喜造・神戸市長、沖縄県人会兵庫県本部や兵庫高同窓会「武陽会」関係者ら計50人の代表団が参加し、沖縄県関係者らとの交流会も開かれる。
▪︎現在の兵庫高校の校舎は、私たちの頃とは違っています。建て替えられています。私たちが学んだ校舎は、戦前、旧制神戸二中の時代からの建物でした。いろいろ思い出すのですが、学校の敷地の西側、野球のバックネットの裏側にあった斜面に、島田叡さんの慰霊碑が建てられていました。「合掌の碑」と呼ばれています。両手を合わせて合掌したようなデザインの慰霊碑です。現在、この慰霊碑は、沖縄に向かって建てられています。私たちの時はどうだったのか…記憶が定かではありません。慰霊碑には、こう書かれています。神戸二中の後輩である、竹中郁さんの詩だそうです。
「このグラウンド
このユーカリプタス
みな目の底に収めて
島田叡は沖縄へ赴いた
一九四五年六月下浣
摩文仁岳の近くで
かれもこれも砕け散った」
▪︎現在、この「合掌の碑」の横には、島田さんの座右の銘であった「断而敢行、鬼神避之」 の碑が建てられています。「断じて敢行すれば、鬼神もこれを避く」。私たちのときは、どうだったのか…情けないことに、このことも記憶がありません。兵庫高校に在学していたとき、島田叡さんがどういう方なのか、詳しくは知りませんでした。授業のさいにも、ほとんど説明がなかったように思います。
▪︎wikipediaには、こうありますね。「沖縄への米軍上陸は必至と見られていたため、後任者の人選は難航していた。沖縄に米軍が上陸すれば、知事の身にも危険が及ぶため、周囲の者はみな止めたが、島田は『誰かが、どうしても行かなならんとあれば、言われた俺が断るわけにはいかんやないか。俺は死にたくないから、誰か代わりに行って死んでくれ、とは言えん。』として、日本刀と青酸カリを懐中に忍ばせながら、死を覚悟して沖縄へ飛んだ」。「北部への県民疎開や、食料の分散確保など、喫緊の問題を迅速に処理していった」。死を覚悟して沖縄に赴き、沖縄県民の皆さんのために尽力された島田さん。享年、43歳でした。新聞記事には、いまも沖縄県民の皆さんに「島守」として慕われていると書かれています。夏の高校野球の沖縄県大会で優勝した高校には、「島田杯」が贈られています。
インデアンカレーのレシピ
NHKエコチャンネルのブログ「昔の人は、なぜ不便な山村に暮らしていたのか?」
 ▪︎一つ前のエントリーに引き続き、これもfacebookでみつけた興味深いブログ記事です。NHKの「エコチャンネル」という環境情報専門の動画サイトにあるブログです。このようなサイトがあることを知りませんでした。いろいろ、興味深い情報があるので、これからは時々チェックしてみようと思います。で、どういうタイトルのブログ記事なのかといえば、「昔の人は、なぜ不便な山村に暮らしていたのか?」…です。NHK甲府放送局、山岳カメラマンの米山悟さんの記事です。面白いです。一部を引用しておきます。
▪︎一つ前のエントリーに引き続き、これもfacebookでみつけた興味深いブログ記事です。NHKの「エコチャンネル」という環境情報専門の動画サイトにあるブログです。このようなサイトがあることを知りませんでした。いろいろ、興味深い情報があるので、これからは時々チェックしてみようと思います。で、どういうタイトルのブログ記事なのかといえば、「昔の人は、なぜ不便な山村に暮らしていたのか?」…です。NHK甲府放送局、山岳カメラマンの米山悟さんの記事です。面白いです。一部を引用しておきます。
なぜお婆さんたちのご先祖は、代々ここで暮らていたのか? それは戦乱で日本が貧しく、インフラが未熟だった時代(間近では昭和20年代)には、都市に住んでいるよりも、山あいに住んだ方が、清潔な水、食べ物、燃料、建材が、お金ではなく労働と協調によって手に入り、生きやすかったからです。こうした集落の多くは平家の落人、戦国時代起源の伝説を持ち、新しいところでは敗戦直後の満洲帰還者の戦後開拓として始まった所が多いのです。先のお婆さんも、戦後の飢餓の時代も麦があったから食べ物には困らなかったと言っていました。彼らは自分の事は自分で出来る、お金に頼らず生きて行ける力を持つ、逞しい知恵と力の持ち主です。食べ物を収穫し、うまく保存し、炭を作り、製材をする。先行きの見えない今の時代、人が最も必要とする確かなものではないかな、と思うのです。
現代人は山里を不便なところと思いこんでいますが、身一つで住み着いて生き延びられる所は、本来平野部や盆地の中央ではなく、山裾だったのだと思います。平野部の江戸、名古屋、大阪の都市は、治水と流通が整備された太平の17世紀以降に初めて都市化が可能になった場所です。山歩きを通してそんなことに気が付きました。
▪︎「お金ではなく労働と協調によって手に入り、生きやすかったからです」、「食べ物を収穫し、うまく保存し、炭を作り、製材をする。先行きの見えない今の時代、人が最も必要とする確かなものではないかな」。両方とも大切な指摘だと思います。