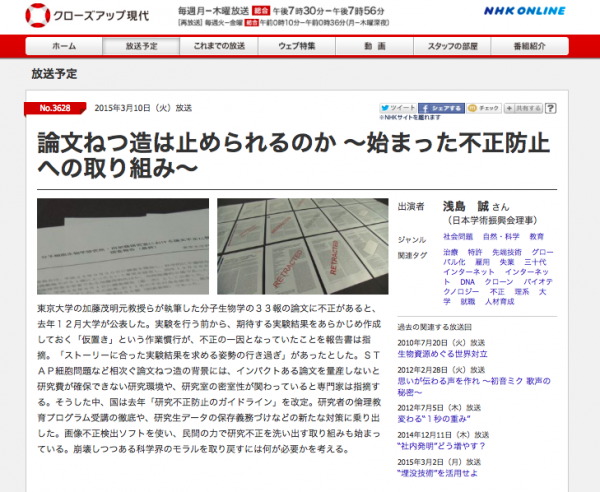東京・丸の内の「インデアンカレー」

 ▪︎昨日は東京に日帰り出張だったので、昼食は東京で、しかも丸の内にある「インデアンカレー」に行ってきました。いつもは、大阪梅田の阪急三番街のお店ですが、チャンスがあれば、すべての店舗でカレーを食べたいと思っています。「インデアンカレー」は、9店舗あります。大阪に7店舗。あとは、芦屋市と東京・丸の内です。今日、丸の内店にいったので、9店舗のうちう店舗「制覇」したことになります。
▪︎昨日は東京に日帰り出張だったので、昼食は東京で、しかも丸の内にある「インデアンカレー」に行ってきました。いつもは、大阪梅田の阪急三番街のお店ですが、チャンスがあれば、すべての店舗でカレーを食べたいと思っています。「インデアンカレー」は、9店舗あります。大阪に7店舗。あとは、芦屋市と東京・丸の内です。今日、丸の内店にいったので、9店舗のうちう店舗「制覇」したことになります。
▪︎阪急三番街では、いつも「ルー大盛り&卵」を注文しますが、昨日は「ルーダブル&卵」にしてみました。写真がルーダブルです。しかし、個人的な印象なのですが、「これが本当にルーダブルなのだろうか…」と、少し疑問に思っています。「ルーダブル」だったら、「カレールーの海に島が浮いている」であってほしいなあと思います。ひょとして、「ルートリプル」って頼めるのだろうか。メニューにはありませんが。
▪︎味ですが、確かに「インデアンカレー」の味です。間違いありません。しかし、付け合せのキャベツのピクルス、ちょっと見た目の感じが微妙に違います。ピクルスにするまえに塩で揉んで水分を出すのでしょうが、なんだかちょっと揉みすぎ…って感じもします。とはいえ、こちらも美味しくいただきました。
CITI Japan プロジェクト

▪︎東京の四谷にある上智大学に日帰りで出張してきました。昨日、「CITI Japan プロジェクト」(Collaborative Institutional Training Initiative Japan Project) による「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議『研究倫理教育の現場と課題』」が開催されました。600名以上の方たちが、全国の大学から集まりました。「CITI Japan プロジェクト」の事務局でも予想外の参加者だったらしく、会場は受付だけでかなり混乱をしており、予定かよりも15分ほど遅れて始まりました。
▪︎いろいろ勉強になりました。まずは、医学・薬学・生命科学の事例をもとに取り組みの報告がなされました。自然科学系の研究倫理の問題ではありますが、いろいろ考えさせられるところがありました。その後は、グループに分かれてのグループディスカッションになりました。全国の大学から集まられた関係者の皆さんが、非常にシビアな危機意識とともに、研究倫理教育の問題に取り組んでおられることがヒシヒシと伝わってきました。もちろん文科省が言うから仕方なく…というのではありません。自分たちが「生き残っていくために」、「きちんとした人材を養成していくために」必死になっておられるのてす。「それは、自然科学系のことであって、人文社会科学には関係ない…」という意見もあろうかと思いますが、それは的外れだろうと思います。具体的な問題や取り組み事例の紹介があればよかったんでしょうが、そのあたりは取り組みが遅れているように思います。個別の学会的にはどうなんでしょうか…。たとえば、社会調査のデータに関して…。いろいろよくわからないところがあります。
▪︎帰りの新幹線では、本学の職員の方と目の前の仕事のことだけでなく、仕事のビジョンのようなことについても、じっくり話しをすることができた。それは非常によかったと思います。
【追記】▪︎本日の「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」の様子は、3月10日のNHK「クローズアップ現代」で取り上げられる予定だそうです。
東京大学の加藤茂明元教授らが執筆した分子生物学の33報の論文に不正があると、去年12月大学が公表した。実験を行う前から、期待する実験結果をあらかじめ作成しておく「仮置き」という作業慣行が、不正の一因となっていたことを報告書は指摘。「ストーリーに合った実験結果を求める姿勢の行き過ぎ」があったとした。STAP細胞問題など相次ぐ論文ねつ造の背景には、インパクトある論文を量産しないと研究費が確保できない研究環境や、研究室の密室性が関わっていると専門家は指摘する。そうした中、国は去年「研究不正防止のガイドライン」を改定。研究者の倫理教育プログラム受講の徹底や、研究生データの保存義務づけなどの新たな対策に乗り出した。画像不正検出ソフトを使い、民間の力で研究不正を洗い出す取り組みも始まっている。崩壊しつつある科学界のモラルを取り戻すには何が必要かを考える。
武蔵野美術大学生による黒板ジャック
研究倫理教育の現状と課題
▪︎明日、上智大学で「CITI Japan プロジェクト 研究倫理教育責任者・関係者連絡会議『研究倫理教育の現状と課題:これからの日本のあり方を考える』」が開催されます。この会議の開催趣旨は以下の通りです。明日、この会議に、研究部の職員の方たちと一緒に出席します。4月からの仕事を少し前倒しで取り組ませていただく…ような感じでしょうか。
2014年8月,「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(新ガイドライン)」(文部科学省)が発表されました.その中でとりわけ重要な役割を担うのが「研究倫理教育 責任者(RIO)」です.新ガイドラインでは,大学を含む各研究機関の部局毎にRIOの設置, そして組織を挙げた定期的な研究倫理教育を義務づけています.
研究活動とは,「人類が未踏の領域に果敢に挑戦して新たな知識を生み出す行為」によって生み出さ れる,「人類が共有するかけがえのない資産」です(日本学術会議「科学者の行動規範」より).新ガ イドラインによれば,責任ある研究活動とは,ひとりひとりの研究者,研究者コミュニティ,そして それらを支える研究機関によって成立するものであり,RIOの活動は,それらすべてに大きく影響 することが想定されます.ただし日本では,RIOに関する取組の歴史が浅いため,RIOにどのよ うな役割が求められ,またどのような取組を進めていくことが望ましいのかという点には不明な点が 多く,大きな課題となっています.
「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」では,文部科学省,新ガイドラインの実装において重要 な役割を担う機関(日本学術振興会,科学技術振興機構),現場で研究倫理教育を担うRIO関係者の 皆様,また研究倫理教材を作成している皆様の間の情報共有,交換を通じて,日本の研究倫理教育の 活性化を目指します.
▪︎理化学研究所の例の問題もあってか、社会一般にも研究者倫理の問題が広く知られるようになりました。勤務する龍谷大学でも、すでに「「研究活動における不正行為の防止及び対応に関する規程」を制定しています。今回の連絡会議では、そのような規定だけではなく、規定にもとづき大学教員や研究者がきちんと研究活動をしていくために置かれる「研究倫理教育 責任者(RIO)」がテーマになります。3つの大学、東京医科歯科大学、筑波大学、京都大学の「研究倫理教育の取組例」について講演がおこなわれます。また、韓国での取り組みについても講演が行われます。そのあとは、「研究倫理コミュニティの創成に向けて」というテーマでグループディスカッションになります。明日は、全国から600人を超える大学関係者が参加されます。各大学から数名ずつでしょうから、この問題に対する全国の大学の関心の強さを窺い知ることができますね。おそらく会場はかなり混乱するでしょう。はたして、グループディスカッションが可能なのかな…若干の不安がありますが、勉強してまいります。
▪︎今回の連絡会議を主催するのは、「CITI Japan プロジェクト」です。「CITI」とは、「Collaborative Institutional Training Initiative」のことです。詳しくは、こちらのサイトをご覧いただきたいと思います。このサイトのなかで、「CITI」に関する動画がアップされていましたので、貼り付けておくことにします。
「近江会」

▪︎昨日は、教授会のあと、学部懇親会「近江会」が開催されました。「近江会」は、5月・12月・3月の年3回開催されます。今回の会場は、京都にある「フォーチュンガーデン」でした。大変雰囲気のある建物でした。というのも、このビルは、もともと、「関西建築界の父」と呼ばれた武田五一の設計による島津製作所のビルだったからです。しかも、雰囲気に加えて、お料理も美味しくいただくことができました。幹事の皆さんに感謝したいと思います。
 ▪︎昨日は、定年退職される3人の先生方(コミュニティマネジメント学科)の送別会でもありました。3人の先生方には、お一人お一人にご挨拶をさせていただきました。学部の運営にいろいろご尽力いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。お3人の先生方は、ご退職後もそれぞれに素敵な目標をお持ちです。前向きに、楽しみながら、目標をもって…素敵なことですね。
▪︎昨日は、定年退職される3人の先生方(コミュニティマネジメント学科)の送別会でもありました。3人の先生方には、お一人お一人にご挨拶をさせていただきました。学部の運営にいろいろご尽力いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。お3人の先生方は、ご退職後もそれぞれに素敵な目標をお持ちです。前向きに、楽しみながら、目標をもって…素敵なことですね。
▪︎ところで、研究科長をしているため、「近江会」では最後の挨拶をすることになっています。宴会の開始時には、学部長が素面できちんと真面目に挨拶をされるのですが、最後の私の挨拶はすでに宴会のアルコールで出来上がった状態ですので、毎回、かなり「くだけた感じ」の挨拶で許していただいています(これは仕方がありません…)。昨晩は、鶴田浩二さんの「傷だらけの人生」の歌謡曲の話しから挨拶を始めました。
▪︎1970年の昭和の歌謡曲に「傷だらけの人生」があります。俳優である鶴田浩二さんがリリースしたシングルです。1970年といっても、お若い方たちはわかりませんね。大阪万国博覧会が開催された年です。万国博覧会以外にも、いろんな出来事がありました。 日本航空機よど号ハイジャック事件がおきました。第64回臨時国会(公害国会)が招集され、 初の公害メーデーも実施されました。大学のなかでは学生運動が停滞し、いわゆる内ゲバを繰り広げるような状況になっていました。まあ、そのような時代に、鶴田浩二さんの「傷だらけの人生」はリリースされたのです。「傷だらけの人生」の冒頭、鶴田さんは歌うまえに台詞を語ります。大変有名ですが、1番の台詞の最後は「今の世の中、右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」です。
 ▪︎鶴田さんの「傷だらけの人生」は大ヒットしました。その歌詞は、当時の世相といいますか、人ひどの気持ちを反映していたのかもしれません。とはいえ、1970年を過ぎても日本の社会はそれなりに安定していました。その1970年から45年が過ぎました。現在、超高齢社会、人口減少社会、自治体の消滅…明るい未来が語られることはありません。18歳人口も、2018年から急減します。18歳人口は、戦後2回目のピークだった1992年の60%までに減少しているそうです。しかも、大学の数は増えています。全体の入学定員は増加が続いています。大学は厳しい大学間競争のなかでもがき苦しんでいます。18歳人口が減少することはわかっていたことではありますが、いよいよ本当に「右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」のなかでの生き残りをかけて闘う時代に突入してしまいました。私が勤務する社会学部でも学部改組を行いますが、これは学部改革の第一歩でしかありません。また、学部単体の改革だけで、これからの競争を生き残れるとも思えません。「この大学での学ぶことの魅力はここだ!!」ということを、大学全体としてアピールできなければ生き残れないと思います。もちろん、こういうことはこれまでも繰り返し言われてきました。しかし、大学という組織は大変保守的な組織です。なかなか社会の環境の変化に適応できません。環境の変化に適応できない組織は滅んでいきます。しかし、教職員が死に物狂いの努力をしたときに、「右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」状態のなかでも、「前方」には小さいけれども確かな灯りが見えてくるのではないかと思うのです。そして、「うちが潰れることはないやろう」、「自分が退職するまでは大丈夫やろう」という考え方がもしあるとすれば、それはかなり困ったことだなと思うのです。
▪︎鶴田さんの「傷だらけの人生」は大ヒットしました。その歌詞は、当時の世相といいますか、人ひどの気持ちを反映していたのかもしれません。とはいえ、1970年を過ぎても日本の社会はそれなりに安定していました。その1970年から45年が過ぎました。現在、超高齢社会、人口減少社会、自治体の消滅…明るい未来が語られることはありません。18歳人口も、2018年から急減します。18歳人口は、戦後2回目のピークだった1992年の60%までに減少しているそうです。しかも、大学の数は増えています。全体の入学定員は増加が続いています。大学は厳しい大学間競争のなかでもがき苦しんでいます。18歳人口が減少することはわかっていたことではありますが、いよいよ本当に「右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」のなかでの生き残りをかけて闘う時代に突入してしまいました。私が勤務する社会学部でも学部改組を行いますが、これは学部改革の第一歩でしかありません。また、学部単体の改革だけで、これからの競争を生き残れるとも思えません。「この大学での学ぶことの魅力はここだ!!」ということを、大学全体としてアピールできなければ生き残れないと思います。もちろん、こういうことはこれまでも繰り返し言われてきました。しかし、大学という組織は大変保守的な組織です。なかなか社会の環境の変化に適応できません。環境の変化に適応できない組織は滅んでいきます。しかし、教職員が死に物狂いの努力をしたときに、「右も左も真っ暗闇じゃござんせんか」状態のなかでも、「前方」には小さいけれども確かな灯りが見えてくるのではないかと思うのです。そして、「うちが潰れることはないやろう」、「自分が退職するまでは大丈夫やろう」という考え方がもしあるとすれば、それはかなり困ったことだなと思うのです。
“Collaborative Governance of Forests Towards Sustainable Forest Resource Utilization”
 ▪︎Facebookで、知人の井上真さんが、ご自身の研究チームの成果をまとめられました。“Collaborative Governance of Forests Towards Sustainable Forest Resource Utilization”です。ちょっと高目の値段の専門書ですが、さっそく予約しました。東京大学出版会から出ます。この本の出版に関しては、Columbia University Press と Singapore University Press も協力しているとのことです。私たちの総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」は、生物多様性・栄養循環と流域の環境ガバナンスのあたりをテーマにしており、森林の井上さんたちの研究とは異なる部分があるとは思いますが、基本的な考え方のところでいろいろ学ばせていただけるのではないかと思っています。
▪︎Facebookで、知人の井上真さんが、ご自身の研究チームの成果をまとめられました。“Collaborative Governance of Forests Towards Sustainable Forest Resource Utilization”です。ちょっと高目の値段の専門書ですが、さっそく予約しました。東京大学出版会から出ます。この本の出版に関しては、Columbia University Press と Singapore University Press も協力しているとのことです。私たちの総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」は、生物多様性・栄養循環と流域の環境ガバナンスのあたりをテーマにしており、森林の井上さんたちの研究とは異なる部分があるとは思いますが、基本的な考え方のところでいろいろ学ばせていただけるのではないかと思っています。
▪︎以下は、東京大学出版会での紹介文と目次です。
在地と外来の利害がせめぎ合う熱帯社会において,自然資源と社会の持続的発展を支える森林ガバナンスのために必要な条件とは何か.資源や権利を共に活用し,多様な利害を分かち合うことで,複数のアクターを取り込む包摂的アプローチとしての「協治」の可能性を探る.
主要目次
Introduction (Motomu Tanaka)Part I: Policies, Institutions and Rights to Share:Prerequisites for Collaborative Governance
Chapter 1 Historical Typology of Collaborative Governance: Modern Forest Policy in Japan (Hiroaki Kakizawa)
Chapter 2 Endogenous Development and Collaborative Governance in Japanese Mountain Villages (Hironori Okuda/Makoto Inoue)
Chapter 3 Collaborative Forest Governance in Mass Private Tree Plantation Management: Company-Community Forestry Partnership System in Java, Indonesia (PHBM) (Yasuhiro Yokota/Kazuhiro Harada/ Rohman/Oktalina Nur Silvi/Wiyono)
Chapter 4 Legitimacy for “Great Happiness”: The Communal Resource Utilization in Biche Village, Marovo Lagoon in the Solomon Islands (Motomu Tanaka)Part II: Sharing Interests, Roles and Risks: The Process of Collaborative Governance
Chapter 5 Task-sharing, to the Degree Possible: Collaboration between Out-migrants and Remaining Residents of a Mountain Community Experiencing Rural depopulation (Mika Okubo)
Chapter 6 Collaborative Governance for Planted Forest Resources: Japanese Experiences (Noriko Sato/Takahiro Fujiwara/Vinh Quang Nguyen)
Chapter 7 Forest Resources and Actor Relationships: A Study of Changes Caused by Plantations in Lao PDR (Kimihiko Hyakumura)
Chapter 8 Whom to Share With? Dynamics of the Food Sharing System of the Shipibo in Peruvian Amazon (Mariko Ohashi)Part III: Sharing Information: Extending Collaborative Governance
Chapter 9 Providing Regional Information for Collaborative Governance: Case Study regarding Green Tourism at Kaneyama Town, Yamagata, Japan (Nobuhiko Tanaka)
Chapter 10 Simulating Future Land-cover Change (Arief Darmawan/Satoshi Tsuyuki)
Chapter 11 Potential of the Effective Utilization of New Woody Biomass Resources in the Melak City area of West Kutai Regency in the Province of East Kalimantan (Masatoshi Sato)Final Chapter (Makoto Inoue)
▪︎編者は井上真さん東京大学農学部に勤務されていますが、もうお一人は田中求さんで、ご所属は九州大学の「持続可能な社会のための決断科学センター」です。このような研究機関が九州大学に設置されているとは知りませんでした。様々な学問分野を統合する形で組織されています。メンバーのなかには知っている方もおられますね。詳しくは、こちらをご覧ください。少し公式サイトから引用します。
「決断科学」とは,さまざまな不確実性の下で,価値観の多様性を考慮しながら最善の決断を行い,その決断を成功に導く方法論に関する科学である. この新たな科学は,複合的で不確実性を持つ現象についての洞察と俯瞰的理解,不合理性を伴う人間行動・心理の体系的理解, および地球環境と人類社会が直面する諸課題についての統域的理解によって成り立つ. 科学を基盤としてこれからの時代を牽引するグローバルリーダーには,専門分野における世界でトップレベルの研究業績に加え, 自然科学・社会科学を統合した問題解決型の新しい科学(統域科学 Trans-disciplinary Science)を開拓し, 適確な決断を通じて人類社会の持続可能性達成に大きく貢献する能力が求められる. 「持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム」ではこの要請に応えるために,地球環境と人類社会の持続可能性に向けてのオールラウンド型科学として, 「決断科学」(Decision Science)を開拓するとともにその人材を育てることを本プログラムの目標とする.
▪︎これを読んだだけでは、具体的な内容についてはわかりませんが、新しい学問地の形成を目指していることは間違いありません。このような言い方をすると叱られるかもしれませんが、欲張った内容になっていますね。私が共同研究員をしている総合地球環境学研究所もそうですが、多くの大学や研究機関で、実際の複雑な問題をどのように解決していくのか、多くのステークホルダーとともに問題をどのように解決していくのかという課題に取り組んでいます。超領域、あるいは超学際的と呼ばれる新たな学問の構築が目指されているのです。単なる「理念」や「はったり」ではなく、実質的に成果を生み出していくために、多くの人びとが懸命になって研究に取り組んでいます。しかし、そのような新たなパラダイムにもとづく学問の構築には、まだ時間と努力が必要だと思います。
小澤征爾のアルバム
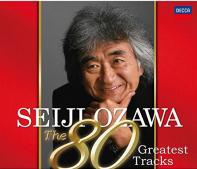
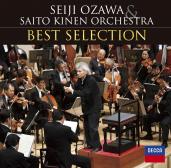
▪︎最近、音楽・アートのマイブームは、レディ・ガガと小沢征爾。小澤さんについては、調子に乗って、iTuneでアルバムを購入してしまいました。一番左のアルバムは、小澤さんが80歳なられたことを記念しているものかと思います。amazonの解説は、左から順番に以下の通りです。
小澤征爾の80歳(2015年時)を記念したベスト・アルバム。1973年から2013年にかけて、サイトウ・キネン・オーケストラ、ボストン響、ウィーン・フィル、ベルリン・フィルら関係の深いオーケストラと録音した数々の名演奏から80トラックを厳選、CD5枚組にまとめた決定盤。“世界のオザワ”の集大成的な作品。
1992年に産声をあげたサイトウ・キネン・フェスティバル松本。彼らが録音してきた名演から選りすぐりの音源を収録。小澤征爾総監督復帰演奏となった2010年の「7分間の弦楽セレナード」、2001年9月13日に`米同時多発テロ`犠牲者追悼のために演奏された「G線上のアリア」を初収録!フェスティバル20回目の節目を祝うに相応しいベスト盤となっている。
▪︎「小澤征爾の80曲。」は、小澤さん自身が指揮した名曲集、「美味しいところ」を集めたものです。言い方をかえれば、つまみ食い的な感じになってしまうのだけれど、様々な曲を聞き比べできるます。「ベストコレクション」の写真をご覧ください。食道癌から復帰した小澤さんが指揮をされています。冒頭が、amazonの解説にもある「2010年の『7分間の弦楽セレナード』」なのだと思います。ご体調もまだ完全ではなかったのでしょうし、このときは持病の腰痛もひどい状態だったといいます。だから、椅子も用意されているのかもしれません。しかし、サイトウ・キネン・オーケストラにとって特別のこの「弦楽セレナード」の指揮を始めるといつもの小澤さんに戻っておられました。入魂の指揮のでしょうか。たまたま、テレビで放映されたときのものをアップされている方がおられました。
大津魚忠で「みずとりの会」

▪︎話しが前後しますが、土曜日の「北船路野菜市」の後、中心市街地の京町通りにある「魚忠」さんに行きました。「魚忠」さんの建物は、国の「登録有形文化財」に認定されています。明治38年(1905年)に、呉服商の店舗兼住宅の町家として建てられたものなのだそうです。また、庭は、近代日本庭園の先駆者とされる作庭家である7代目・小川治兵衛(屋号:植治)の作庭なのだそうです。無鄰庵・平安神宮・円山公園等の国定名勝指定庭園を作庭されたことで名高い方なのだそうです。「…なのだそうです」と続きますが、小川治兵衛さんのお名前程度しか存じあげなかったものですから。教養がまったく足りませんね。
▪︎話しを元にもどします。なぜ、「魚忠」さんにお邪魔したかというと、瀬田キャンパスにある「放送大学」の卒業生の皆さんの親睦の集まりが開かれたからです。「みずとりの会」といいます。最高齢は85歳、一番お若い方は55歳だったかと思います。様々な年代の方たちが放送大学を卒業されたあとも、集まって親睦を深めておられるのです。なぜ「みずとりの会」なのかというと、「酒」とい感じを部首と旁(つくり)にわけると、「さんずい」と「酉」になります。「さんずい」は水の意味、「酉」は「とり」です。ということで、「みずとりの会」なのです。お酒の好きな方たちが集まっておられるのですね。
▪︎私は、こちらの会の冒頭で簡単に「北船路米づくり研究会」のお話しをさせていただきました。素朴な学生の活動から始まった研究会が、いろいろんなご縁をいただくことなので、純米吟醸無ろ過生原酒/純米吟醸酒「北船路」をプロデュースするに至ったことをお話しさせていただきました。皆さん、大変真剣にお話しをお聞きいただきました。私の話しはさておき、その後は、参加された皆さんとともに「魚忠」さんの美味しいお料理と「北船路」をいただきました。会が終わったあとは、「北船路」を醸造されている平井商店さんにご案内して、皆さんにお買い求めいただきました。販売促進活動です。
小澤征爾・ベルリンフィルの「悲愴」と湯浅卓雄先生のインタビュー
▪︎先日、facebookで知りました。NHKの「あさイチ」という番組に、指揮者の小沢征爾さんが、なぜ指揮をするときに指揮棒を使わないのか…その理由について説明されているというのです。現在、小澤さんは指揮棒を使っておられません。ずいぶん前からのような気もします。しかし、指揮棒を使わない理由ですが、ちょっと拍子抜けするようなものなんです。一番上の動画が、それです。たぶん著作権の問題をクリアしていないので、もうじきカットされると思いますが、もしよろしければご覧ください。
▪︎今日は、大切な昼食会が奈良のとある料亭でありました。お酒も少しはいった昼食会だったので、自宅に戻ると、これまでに溜まった疲れもあり、2時間ばかり昼寝ならぬ夕寝をしてしまいました。そして困ったことに、そのさいに金縛りになってしまいました。どんな感じかというと、横に人がいる気配が濃厚にするのですが、体は動かない…そんな感じです。昨晩は、寝ているあいだにこむら返りを起こしてしまうし。おそらくは疲れが溜まっているので、こうなるのでしょうね。心身ともにもう少し休めてリフレッシュしないといけないですね。もう、若くないしね…。
▪︎ということで、夕食後YouTubeで、小澤征爾さんが指揮をされている動画をじっくり観て・聴いて、心に栄養を与えることにしました。冒頭に書いた「あさイチ」のこととで、にわかに小澤征爾さんのことが気になり始め、iTuneでサイトウ・キネン・オーケストラ、小沢征爾指揮「BEST SELECTION」も調子に乗って購入してしまいました(通勤時に楽しもうと思います…)。2番目の動画は、小沢征爾さんが2008年にベルリンフィルハーモニーを指揮したときのリハーサル風景です。曲は、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」です。冒頭、小澤さんは、ボストンにある野球チーム「レッド・ソックス」のウインドブレーカーを着て練習に到着されます。小澤さんは、ボストン交響楽団の音楽監督でした(1973-2002)。それはともかく、リハーサル風景を、私は何度も見直しました。ゾクゾクっとするものがありました。当時のコンサートマスターである安永徹さんとの、ボーイング(運弓の仕方)に関するやり取りにも注目しました。
▪︎小澤さんのイメージの音楽にするためには、このようなボーイングはどうだろうかと安永さんは提案します。おそらくは、このようなボーイングの方が弾いていると結果として小澤さんのイメージに近づく…という提案なのかなと思います。もちろん、私の推測、邪推にしかすぎまんせんが…。しかし小澤さんはオリジナルなボーイング(チャイコフスキーが指定したてボーイング)に戻してほしいと言います。小澤さんは、インタビューにもこたえています。いいオーケストラというのは、室内楽のように、お互いの音を聴いて反応しあっている…と。また、(体や心の)中で感じたものが音になればよい…ともこたえておられました。このあたり、コンーサトマスターの安永さんとのボーイングのやり取りとも関係しているように思います。音楽を自分の内側から感じること…それを形にしていくのは難しいのです。3番目の動画は、本番の演奏です。
▪︎また、ふと思い立つことがあり、いろいろ調べてみました。YouTubeで学生オケ時代にお世話になった湯浅卓雄先生のインタビュー動画をみつけることができました。湯浅先生とは9歳違い。学生時代に指揮をしていただいたときは、まだ30過ぎのアニキという感じでした。この動画を視ると、髪が白くなっておられることをのぞいて、若いときの雰囲気と基本的には同じよに思います。お若い。先生と最後にお会いしたのは、大阪の天王寺動物園でした。私は結婚して子供がおり、家族3人で動物園に遊びに来ていたのですが、湯浅先生も家族連れで遊びに来られていたのでした。お互いに笑ってすれ違いました。なんだか、思い出すとおかしいですね。ちょっと立ち止まってお話しをさせてもらうとよかったのに…。関西のプロのオケや市民オケの指揮も時々されているということなので、できれば先生にお会いしたものです。