Korea AG-BMP Forum The 4th International Conferenceでの報告(1)

■先月末、9月27日に、韓国の全州市で開催された「Korea AG-BMP Forum The 4th International Conference」に参加し、第1セッション「流域管理のパラダイムシフト」においてキーノートスピーチを行いました。今回は、総合地球環境学研究所で取り組んだプロジェクトの成果(『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』京都大学学術出版会)をもとに、琵琶湖の農業濁水問題を事例とした「階層化された流域管理」についてお話しをさせていただきました。私がなぜ、この国際会議に呼ばれたのか。遠回りになりますが、以下で説明させてください。
■全州市に隣接するセマングムには広大な干潟がひろがっていました。錦江と東津江という2つの大きな河川の河口一帯に広がる広大な干潟です。様々な環境団体の反対、漁民の反対がありましたが、韓国政府は、1991年から大規模な干拓事業を開始ししました。そして、2006年に防潮堤が完成し、現在は陸化が進んでいるのです。
■当初、ここから生まれる新しい土地は農業用地だったのですが、現在の韓国社会はそのような農地を必要としなくなっています。ちょうど、戦後の滋賀県で、食料増産のために、琵琶湖の周囲の内湖が干拓されていったのと似ています。干拓事業が終了したときは、すでに米があまり減反政策が始まったからです。現在、このセマングムの干拓地では、農地のかわりに、工業団地の建設やリゾート観光地を建設することが計画されています。ところが、ある問題が危惧されています。後背地域から流入する農業関連の排水が、陸化された干拓地とともに生み出される人工湖の水質を悪化させるというのです。
■大きな2つの河川から干潟に流入する河川水には、自然由来に加えて農業排水も含まれていたと考えられます。そこには広大な干潟に生息する多様な生物の生存にとって必要な栄養が含まれていたのではないかと思います。2つの河川と海が育む豊かな干潟が広がっていたのです。しかし、干拓により干潟が消滅し、生物もいなくなってしまうと、こんどはその栄養塩が水質を悪化させると問題視されるようになってきたのです。もちろん、かつての農業(稲作、畑作、畜産)とは異なり、農業の近代化ととも環境に負荷を与える農業(土地改良、化学肥料、畜産廃棄物…)に変化していることも無視できませんが、日本の諫早湾干拓事業などと同様の環境破壊を招くものだと非難されているのです(この干拓事業に対しては工事差止請求を行われましたが、韓国の最高裁では退けられています)。
■Korea AG-BMP Forumでは、韓国の様々な大学の研究者、韓国の関係省庁や関係機関が参加し、このようなセマングムが抱える問題に取り組んでいます。もちろん、この干拓事業の「そもそも論」的な根本のところで、大きな矛盾を抱えていることは間違いありません。しかし、すでに防潮堤が完成してしまった状況において、「現実問題」としてどうすれば水質悪化を防ぐことができるのか。その点について、たくさんの農業土木や工学の研究者、そして農業政策の研究者が、様々な研究や事業に取り組んでおられるのです。皆さんの報告を聞かせていただきましたが、それらの学問分野からのアプローチは、どちらかといえば、トップダウン的なものになります。農家による農業排水の負荷を低減させる技術を開発する、環境負荷削減に農家の営農を誘導していく…そのようなアプローチです。しかし、そのようなアプローチでは、限界があります。農家自身が、流域管理のステークホルダーとして参加・参画するなかで、自分たちのコミュニティの「幸せ」と流域の環境改善とを両立させていく必要があるのです。
■今回のKorea AG-BMP Forumのタイトルは、「Local community development through agricultural NPS pollution control」です。非点源(農地のような広がりをもち、特定の点に還元できない汚濁減)汚染のコントロールを通した地域農業コミュニティの発展なのです。水質改善をすること、そのものが目的ではなく、水質改善を通して農村を発展させていこう、それも内発的な発展を支援していこうというのが、今回のフォーラムの目的となっているのです。私が参加したのは第1セッション「流域管理のパラダイムシフト」ですが、このパラダイムシフトとは、従来のトップダウン的な流域管理のアプローチを大きく転換し、もっとボトムアップのアプローチを展開していく必要があるとの問題意識にもとづいています。このような問題意識が存在したからこそ、日本やアイルランド、そしてアメリカからゲストスピーカーが招かれたのです。(続きます)




【上段左】「階層化された流域管理」について報告する私です。【上段右】フォーラム開催前の記念写真。
【下団左】フォーラム終了後には、韓国MBCテレビの取材を受けました。夕方のニュースで放映されました。【下団右】フォーラムの前日には、セマングム地域を視察しました。視察のさいに、地元ローカルテレビ局の取材を受けました。
マザーレイクフォーラム・びわコミ会議(第3回)
 ■今日は午前中大学にいってちょっとした用事をすませて、昼からは滋賀県庁にいきました。琵琶湖環境部琵琶湖政策課が所管している「マザーレイク21計画」(琵琶湖総合保全整備計画)の第2期に関連する「第2回マザーレイク21計画学術フォーラム」が開催されたからです。
■今日は午前中大学にいってちょっとした用事をすませて、昼からは滋賀県庁にいきました。琵琶湖環境部琵琶湖政策課が所管している「マザーレイク21計画」(琵琶湖総合保全整備計画)の第2期に関連する「第2回マザーレイク21計画学術フォーラム」が開催されたからです。
■国の6つの省庁(当時の国土庁・環境庁・厚生省・農林水産省・林野庁・建設省)が1997年度から2カ年にわたり共同で実施した「琵琶湖の総合的な保全のための計画調査」をふまえて、滋賀県では、琵琶湖を健全な姿で次世代に引き継ぐための指針として、2000年3月に、琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク21計画)を策定しました。1999年度から2010年度までが第1期になります。私は、国土交通省の琵琶湖総合保全計画検討調査委員や、滋賀県の琵琶湖総合保全学術委員会委員としてこの「マザーレイク21計画」の第2期、2011年度から2020年度までの計画策定にかかわってきました。
■今日、開催された「マザーレイク21計画学術フォーラム」は、この「マザーレイク21計画」(2期)の進行管理(PDCAサイクル)の中で、施策の評価を、学術的な見地から琵琶湖と流域の状況について指標などを用いて整理・解析する役割を担っています。今日は、半年前に開催された第1回での議論や注目を、事務局が積極的に受け止めて、新しい方向性が示されました。もちろん、今日は基本的な方向性であり、この先、まだまだ難関が続々と続くわけですが、こういうのは気持ちがよいですね。困難なのはわかっているけれど、未来に「希望」がみてくるから。仕事は、こうでななくてはいけません。仕事は、前向きでないといけません。
 ■ところで、この「マザーレイク21計画学術フォーラム」とも関係しますが、市民参加による施策の評価を行う会議も開催されます。8月31日に「コラポしが21」で開催される、「第3回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」です。詳しくは、以下をご覧ください。
■ところで、この「マザーレイク21計画学術フォーラム」とも関係しますが、市民参加による施策の評価を行う会議も開催されます。8月31日に「コラポしが21」で開催される、「第3回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」です。詳しくは、以下をご覧ください。
第4回KAB国際会議
■韓国から国際会議のプログラムが届きました。
こんな内容の国際会議です。
The 4th International Conference
AG-BMP Development for Reservoir Water Quality Improvement
Korea AG-BMP Forum (KAB-4)
September 26-27, 2013, Jeonju, Korea韓国では、これまで中央政府主導による点源汚染と処理施設中心の水質管理政策を行ってきました。しかしながら、近年、その限界が徐々に理解されるようになり、面源汚染、特に農業面源汚染削減の努力がなされています。韓国の農業は、小規模農業であり、水質管理への農家個々人の参加が不可欠です。
このような背景のもと、第4回・韓国農業ベスト・マネージメント・プラクティスに関する国際会議(Korea AG-BMP)では、テーマを「農業面汚染源の管理と地域共同体の発展」とし、地域共同体の視点から、統合化されたセマングム流域管理のために、制度、技術、そして地域の人々の参加をどのように促進していくのかという点に光をあてていきます。
この国際会議では、農業面汚染源を管理するための諸政策や技術を適切に指揮し、流域の利害関係者間で考え方や見方を共有し、さらには地方政府によって運営される持続可能な流域管理へのパラダイムシフトを探求する予定です。
■私は、第一セッション「流域管理のパラダイムシフト」で、お話しをさせていただきます。さて、これからサマリー、原稿、パワーポイントの準備と続きます…。こういう国際会議は全く不慣れなもので、かなりプレッシャーです〜。研究仲間からのサポートももらい、なんとかきちんと報告を終えたいと思います。
■フルマラソンに加えて国際会議…。頑張ります。
韓国の国際シンポで基調講演をします。
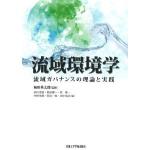 ■9月末、韓国の国際シンポジウムで基調講演をすることが本決まりになりました。
■9月末、韓国の国際シンポジウムで基調講演をすることが本決まりになりました。
■韓国では、韓国農村公社の農漁村研究院、建国大学、ソウル大学など10の専門機関と自治体、NPOなどが2010年から研究協力体系を構築して、セマングム流域を中心に「農業面汚染源の低減のための制度改善、技術開発、住民参加およびインセンティブなど」に関する研究プロジェクトを進めておられます。この研究プロジェクトの一環として、毎年、国際シンポを開催されています。シンポジウムでは、「農業面汚染源の管理と地域共同体の活性化」というテーマをもとに共同体的な観点からアプローチし、住民参加の活性化のための制度改善および住民支援インセンティブに対する国内外の事例と経験を共有することを目指しておられるようです。
■今回は第4回目のようですが、これまでの「政府主導の点汚染源の管理」から「地域共同体中心の面汚染源の管理」への流域管理のパラダイムシフトのターンポイントになることを強く期待されています。ということで基調講演のテーマは、「(仮)流域の水質汚染源管理のパラダイム転換」ということになっています。
■私は、過去に、総合地球環境学研究所( 大学共同利用機関法人・人間文化研究機構)のプロジェクトで琵琶湖淀川水系の流域管理に関する研究を行いました。そのさい、階層化された流域管理というアイデアを提案し、そのアイデアを骨格にしてプロジェクトを進めてきました。その成果は、『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(和田英太郎 監修/谷内茂雄・脇田健一・原雄一・中野孝教・陀安一郎・田中拓弥 編、京都大学学術出版会)として出版されています。今回の国際シンポジウムでの基調講演は、このプロジェクトの成果をもとにお話しをさせていただこうと思っています。
甲賀の農村で

■過去のエントリーで、総合地球環境学研究所の文理連携(協働)の研究プロジェクトのことをアップしました。先週の25日(土)、このプロジェクトのコアメンバーの皆さんと、野洲川流域の視察と簡単な聞取り調査にでかけました。この日は朝8時半にJR瀬田駅に集合したあと、リーダーの奥田さんが所属する京都大学生態学研究センターの車2台に分乗して、第二名神高速道路を使い野洲川の上流部まで一気にさかのぼり、上流かから琵琶湖の湖岸まで、一日かけて野洲川を少しずつ下っていきました。
■ちょうど昼頃になりますが、甲賀市にある小佐治という集落を訪問しました。小佐治は、137世帯の農村です。JRの最寄りの駅は、草津線の寺庄。滋賀県の内陸部とはいえ、兼業可能な地域です。近くには、工業団地も多数あります(滋賀県は、湖東に工場群が集積する内陸工業県です)。もちろん、専業や兼業の農家以外にも、非農家の皆さんもお住まいです。そして、他の農村地域と同じように、少子高齢化や農業の後継者の問題をかかえています。
■この辺りは、古琵琶湖層が隆起した丘陵地帯です。古琵琶湖というと、聞き慣れない人がいるかもしれませんね。琵琶湖はもともと現在の三重県の伊賀上野で、400万年前に誕生しました。地殻変動によってできた「大山田湖」です。湖とは、おおきな水たまり。地殻変動で大地生じた凸凹に応じて移動します。琵琶湖が、およそ現在の位置に到着したのは、40万年〜100万年前の間といわれています。私たちが訪問した甲賀市は、その琵琶湖の移動の通り道に位置しているのです。現在の甲賀市の位置には、約270年前から「甲賀湖」という深い湖が形成されました。この「甲賀湖」は約20万年間続きました。古い時代の琵琶湖、古琵琶湖のなかでは一番安定していた湖といわれています。
■小佐治は、甲賀市の丘陵地帯にあります。古琵琶湖の泥がたまった湖底の粘土が隆起してできた丘陵地帯です。そのため、関東地方でいうところの「谷津田」がたくさんみられます。トップの写真をご覧ください。まるで、人間や動物の肺の気道と肺胞のようでしょう。古琵琶湖の湖底が隆起してできた丘陵は、細かな粘土からできていますから、雨水を簡単には透しません。あふれた雨水は、低いところに流れていき、大地を削り、写真のような谷を形成していったのです。人間は、この谷筋に流れる雨水を頼りに水田をつくっていきました。もちろん、丘陵の森に降った雨水をためておく溜池もつくました。溜池に溜めた水を谷につくった水田にひいていったのです。大きな溜池は5つですが、小さいものは100はあったとのことです。
■もっとも、1962年に、少し離れたところに灌漑用の大原ダムが建設されたあとは、このダムの水を水路により溜池までひっぱってきました。いったん溜池に貯水して使用しているとのことです。ですから、かつて存在した小さな溜池は現在では、使われず、堤もこわれているのではないかとのことでした。ちなみに、こちらの小佐治のばあいは、丘陵の森は、ほとんど民有林でした。だいたいどの農家も1町歩ほどの山林地をもっているといいます。また、村の共有林もありました。ですから、かつては、冬になるとどの農家も山で山仕事をするのが普通だったといいます。もっとも、高度経済成長期の燃料革命で、これらの山はほとんど利用されなくなりました。
 ■村人のお話しによれば、古琵琶湖の細かな粘土でできている水田は、米や餅米の生産に大変適しているのだそうです。特に、小佐治の餅はこの村の名物になっており、皇室にも献上されてきたようです。左の写真は、ドブガイの化石と粘土の固まりです。古琵琶湖の時代の化石がこうやって地中から出てくるんですね。ご覧いただけばわかると思いますが、粘土は乾燥すると大変固くなります。この地域では、以前は、稲刈りの終った後でも、冬場に水田を湛水状態にしておいていたとのことでした。来年の春に農作業を始めるとき、鍬などの農具が入りやすいようにするためです。古琵琶湖の贈り物である粘土の土が、この地域の農業に特色を与えているように思います。
■村人のお話しによれば、古琵琶湖の細かな粘土でできている水田は、米や餅米の生産に大変適しているのだそうです。特に、小佐治の餅はこの村の名物になっており、皇室にも献上されてきたようです。左の写真は、ドブガイの化石と粘土の固まりです。古琵琶湖の時代の化石がこうやって地中から出てくるんですね。ご覧いただけばわかると思いますが、粘土は乾燥すると大変固くなります。この地域では、以前は、稲刈りの終った後でも、冬場に水田を湛水状態にしておいていたとのことでした。来年の春に農作業を始めるとき、鍬などの農具が入りやすいようにするためです。古琵琶湖の贈り物である粘土の土が、この地域の農業に特色を与えているように思います。
■ところで、最近では、この特産品を使った、米粉の麺料理や餅料理を食べさせる農村レストランもオープンしています。いわゆる、コミュニティビジネスです。大変熱心に村づくりに取り組んでおられることがわかります。もちろんハッピーな話しばかりではありません。先ほども少し触れましたが、民有林の管理ができなくなり、山は荒れ、獣害がひどくなり、田んぼにいた生物の賑わいも減ってしまったといいます。また、後継者不足や村の農地の維持についても問題になっています。現在、まだ法人化はしていないものの、「集落営農」にも取り組み始めているそうです。
■ただし、頑張って村づくりに取り組んでおられるだけのことはあります。小佐治では、水田の生きものを復活させる、生きものの賑わいを取り戻す事業にも取り組んでおられます。滋賀県庁の農村振興課の事業に応募されたのです。なぜ、応募されたのか。この辺り、「村の論理」をきちんとわかっていなければなりません。補助金というお金だけみていたのでは、「村の論理」は把握できません。問題は、農業を基盤とした村の永続生や持続性なのです。言い換えれば、「持続可能な農村コミュニティ」を目指してこの地域を再生していくためには、身近な環境保全に努めることが必要だ…と考えておられるのです。小佐治では、環境こだわり農産物の生産にも取り組んでおられます。生きものを育む水田で生産された米や餅米は、それ自体が付加価値を持つとともに、さきほどの農村レストランのようなコミュニティビジネスとともに「村のブランディング化」に寄与することでしょう。先行き不透明な、厳しい現実が存在していることは事実なのですが、小佐治のみなさんは、村づくりに大変意欲的に取り組んでおられます。そのことは、村人が話しをされている時の話しぶりや表情からも窺えました。
■興味深いことに、この村には、外部から4世帯が移り住んでこられました。子どものいる若い家族の転入を村としては大歓迎されています。また、家族の定住をサポートされてもいます。転入した家族の方でも、積極的に村の活動に参加されているようです。そのような新住民のお1人にもお話しをうかがいました。いろいろ農村地域で暮らしたいと思って移り住める家を探していたとき、この村が美しいと思ったのだそうです。そのことが、転入した一番の理由だとのことでした。山は荒れてきているとはいえ、身近な里の自然に配慮をし、村人の手が加わっているのです。村の風景は、ここに暮らす村人の心のあり様をも映し出しているはずです。そのことが、ここの村の風景を、そして村の暮らしを美しく見せたのではないでしょうか。
■今回視察したグループが取り組む研究プロジェクトは、いわゆる文理融合・文理協働の研究プロジェクトということになります。私としては、このプロジェクトの研究をとおして、ここの村づくりのお手伝いができたらと思っています。村としても、私たちの参加を歓迎してくださっています。村人の話しをうかがいながら、私の頭の中には、これからのプロジェクトが取り組むべきことがらのアイデアが、脳みそのなきら次々と湧き出してきました。経験上、こういうイメージは、とても重要なのです。これからが、楽しみです。少し先のエントリーになると思いますが、この小佐治の村づくりの取り組みを、こんどは野洲川の流域管理の問題や、生物多様性、生態系サービスの問題と結びつけながら考えてみたいと思います。
今日の来客
■今日、金融大手(メガバンク)のコンサルティング会社の方が2人研究室におこしになりました。私は、ふだん、このような業界の方たちとお付き合いすることはめったにないので、さてどんなものかなと思っていましたが、面白いディスカッションができました。来室の目的は、農業、地域と企業の連携による地域活性化に関する事業や、生物多様性保全に繋がる地域や農林水産業振興に関する事業に関して、意見交換を行うことでした。
■意見交換させてもらったテーマは、ひとつが農業のもっている多様な価値を、もうひとつが生物多様性のもたらす生態系サービスの多様な価値を、どのように可視化させ、そのための社会的な仕組みはどうしたらよいのか、ということだったように思います。私はそのような外部経済化されている価値を、一足飛びに市場の内部に引き込むことで可視化することには賛成できませんが、可視化し人びとのコミュニケーションを促進していくことのひとつの手法としては可能だと思いました。詳しいことは書けませんが、なんといいますか、面白い視点をもって仕事をなさっておられるな〜と思いましたし、私のような者でも、こういった企業の方たちと、広い意味でのコラボレーションができるのかなと思いました。
人間・社会班で研究会議

■総合地球環境学研究所の文理連携(協働)の研究プロジェクトに参加していますが、昨日は、このプロジェクトの「人間・社会班」の第1回めの会議を、龍谷大学社会学部町家キャンパス「龍龍」で開催しました。
■ご参加いただいた皆さんは、これまで、コモンズや流域の問題に取り組んでこられた方たちです。それぞれの専門領域は、経済学、政治学、地理学、社会心理学、社会統計学、生態学、そして私のような社会学と異なるわけですが、異なるからこそ、多元的な視点から、流域管理に関するこのプロジェクトの屋台骨の部分に関して、活発に議論を交わすことができました。
■文理融合(文理協働)プロジェクトのロジックをどう組み立てるのかという点については、自然科学の分野の皆さんよりも、概念操作に長けた人文・社会科学の皆さんのほうが向いているのかもしれません。このプロジェクト、FS( feasibility study)の段階にあり、十分に研究費がついているわけではありません。しかし、11月末のプロジェクトの全体会議までに、「人間・社会班」としてさらに2回ほどの研究会議をもつとともに、メーリングリスト等で、情報・意見交換やディスカッションができればと思っています。
【追記】■本日の朝、通勤途上、京都駅内のオープンカフェで、プロジェクトのサブリーダーである谷内さん(京都大学生態学研究センター)と、昨日の議論の総括とディスカッションを行いました。谷内さんとは、このプロジェクの進捗や流域管理に関する新しい論文の共同執筆に関して、毎週、勉強会をもっているのです。朝はやはり、頭がよく動きますね。
研究会

■これから取り組もうとしている文理連携(協働)の研究プロジェクトのことについては、以前に少し書きました。数日前のことになりますが、この文理連携(協働)の研究プロジェクトに関して研究会を持ちました。研究会とはいっても、このプロジェクトの「人間・社会班」の谷内さん(京大生態研)と一緒に、全体の「骨格」や「土台」を考えていくような作業を行うのが目的でした。
■現在の生物多様性をめぐる文理融合(協働)の国際状況やFuture Earth等の動向を再確認したうえで、流域における生物多様性や栄養循環の問題、その問題とクロスする人間社会の様々な空間スケールでの活動、さらには流域診断や社会実践等との関係につい、議論したものを、KJ法風にホワイトボードの上に整理してみました。
■12日には、研究プロジェクトの「人間・社会班」の様々なバックボーン(環境経済学、環境社会心理学、数理統計学、政治学…)をもったメンバーが集まり、さらに詳細な部分について議論をしていく予定になっています。ところで、iPhoneで撮った写真、ボケボケのブレブレです…すみません。


