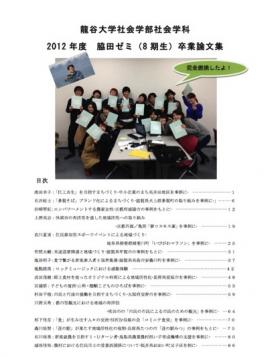新3年生ゼミ


■今日は、3年生ゼミの初回でした。今日、たまたま病欠の1人もあわせて全員で18名です。女学生が4名ですので、今年の3年ゼミは全体に男子に偏っています。初回ですので、事務的な連絡のあとは、各自で簡単な自己紹介をしてもらいました。1つめの特徴ですが、体育局所属の学生がいることです。サッカー部、少林寺拳法部、アメリカンフットボール部…。私のゼミでは珍しいことです。ぜひ部活と、卒論やゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の活動を両立させてもらいたいと思います。2つめの特徴は、滋賀県の学生が多いということです。きちんと数えませんでしたが、半分以上が滋賀県の学生でした。これも珍しいことです。
■滋賀県出身の学生のなかには、彦根市を中心として伝承されているボードゲーム「カロム」ができるという学生が2名いました。嬉しいですね〜。私は毎ボードをもっているので、せび指導してもらいたいと思います。今日は、簡単な自己紹介だけでしたが、来週は、印象に残るパフォーマンスも交えて自己紹介をしてもらうことになっています。楽しみです。
■今日は、4年生ゼミの学生が2人やってきてくれました。そして「北船路米づくり研究会」の活動の説明をしてくれました。研究会の活動は、学生の自主性にもとづいて行われているので、私から強制的に参加させることはしていません。しかし、過去3年、先輩たちが築いてきた実績をぜひとも継承していってもらいたいと思います。そのなかで、自分のもっている人間力を鍛えてほしいと思います。今年の目玉である活動は、「地酒プロジェクト」。研究会の学生たちが開催したイベントがきっかけとなり、北船路の農家が生産する酒米を原料に、大津の中心市街地の酒蔵が新しい銘柄の地酒を製造することになりました。この新しい地酒をどのようにアピールしていくのか、新3年生の活躍が期待されます。頑張ってほしいな〜。
新しいゼミ生を迎えます!

■2013年度の前期は、授業開始日が(先週の)火曜日でした。3年生のゼミは月曜日4限なので、新年度になってから、まだ新しいゼミ生たちに会っていません。月曜日が楽しみです(1月末に自主的にもったオリエンテーションでは顔合わせだけをしました)。第1回のゼミには、4年ゼミ生も2人やってきてくれます。そしてゼミ活動の一環としておこなっている「北船路米づくり研究会」に関するオリエンテーションをおこなってくれます。すでに配布資料等も準備してくれています。これまでの研究会の活動実績や新たなプロジェクトに関して説明をしてくれる予定です。
■新たなプロジェクト。「地酒プロジェクト」と私たちは呼んでいます。昨年の研究会で開催した都市・農村交流イベント「かかし祭」をきっかけに、大津市の中心市街地の酒蔵・平井商店さんと、私たちが通っている棚田の農村・北船路の営農組合とのあいだでコラボの企画が浮かび上がりました。湖西・比良山系は蓬莱山麓にある北船路の棚田で酒米を生産し、その酒米を原料に新しい銘柄の地酒を平井商店さんが生産する。そして龍大生が、そのプロデュースを行う…というものです。この「地酒プロジェクト」では、3年生の皆さんに頑張ってもらいたいと思います!!
■写真は、昨日、瀬田キャンパス1号館の6階から撮影したものです。新緑の季節まではもう少しだけ時間がかかりそうですね。でも、その雰囲気は瀬田の森のなかに少しずつ漂ってきています。
2013年度前期・4年ゼミ(社会学演習ⅡA)掲示板
5月2日
■就職活動の関係で、来週からの発表順番が変更になります。
5/9:卒論の個別相談
5/16:安平
5/23:臼杵
5/30:北川
6/6:山根
6/13:山田
6/20:井上
6/27:松見
7/4:枡田
4月11日
■新4年生のゼミ生の皆さん。前期の報告の順番が決定しました。とりあえず、6月末までは、以下の順番で進めます。就職活動等で、報告できないばあいは、誰かと交代することを原則としてください。報告しないと評価できませんので、その点をよくわかっておいてくださいね。
4/25:脇田の講義
5/2:中村
5/9:安平
5/16:臼杵
5/23:北川
5/30:山根
6/6:山田
6/13:井上
6/20:松見
6/27:枡田
■ゼミのコンパ係(飲み会世話係)は北川くんに決定。LINEで予定を調整してください。コンパの開催は、木曜日の夕方で調整してください。
2012年度卒業式








■一週間以上前、先々週の金曜日、3月15日に「2012年度 学位記、卒業証書・学位記、修了証書授与式(社会学部、社会学研究科)」=卒業式が行われました。脇田ゼミ8期生16名も無事に卒業をすることができました(卒論指導、大変やったぞ~…)。ここにアップした写真は、卒業した8期生から送ってらったものです。卒業生の皆さん、ありがとうございました。
■写真中段以下の写真は、社会学部同窓会歓迎のパーティのときのものです。龍谷大学では、いわゆる「謝恩会」ではなく、卒業したばかりの学生を新・同窓会メンバーとして同窓会が歓迎する…そのような趣旨でパーティが開催されています。そして、毎年、私たち教員もこのパーティに招待されています(同窓会の皆さん、ありがさうございます)。さて中段の写真の中央、卒業生の皆さんからとても素敵なTシャツをいただきました。私がマラソンを走っていることから、このようなTシャツをプレゼントしてくださいました。また、中段写真の右ですが、手作りの「記念アルバム」をいただき、大変感動しているところです。卒業生の皆さん、心のこもった記念品、本当にありがとうございました。
■脇田ゼミの「北船路米づくり研究会」や卒論に取り組んだ経験は、きっと社会人になってからも活きてくると思います。社会人として活躍されること期待しています。また、年に1回は同窓会を開催するようにいたしましょう。学年監事の杉下佳苗さん、よろしくお願いいたします。
北船路米づくり研究会の研修&総会

■2月3日(日)の午前中は、職場のチームで出場した「大津市民駅伝」でした。そして午後からは「北船路米づくり研究会」の活動でした。この日は、一年間の「北船路米づくり研究会」の活動の総括、そして研修と研究会の総会が開催されました。会場は、北船路に隣接する南船路にある「BSCヨットスクール」をお借りしました。トップ写真は、そのヨットスクールから琵琶湖の風景です。
■研修と書きましたが、社会人になるための個々人の能力を、「北船路米づくり研究会」の具体的な活動のなかでどのように伸ばしていくのか…といったことをテーマに、ヨットスクールの井上校長と研究会の顧問である吹野藤代次さんからご講演をいただきました。言い換えれば、社会人前教員ですね。
■研修のあとは、研究会の総会に移りました。






【上段】左:総会を終えて今年の3月に卒業する4年生たちと集合写真。中:こちらは3年生も入っての集合写真。右:かえるおんな(なっつ。)。
【下団】左:タスキをかけているのが、現在の4年生リーダー。研究会の代表が右側の3年生リーダーに移ります。中:研究会顧問に、4年生が作成した手作り感満載のアルバムが贈られました。右:4年生がもうじき卒業ということで、そのお祝いもかねて、顧問が餅をついてくださいました。
○関連エントリー:「大津市民駅伝2013」
2012年度 脇田ゼミ(8期生)卒業論文発表会

■昨日は3・4年ゼミ生が全員集まって、午前11時半から夕方17時半過ぎまで、「2012年度 脇田ゼミ(8期生)卒業論文発表会」を開催しました(2号館108)。1人15分程度の短い発表時間ですが、16名全員が、レジュメとゼミで作成した卒業論文集をもとに、卒論の概要(特に課題設定と分析、得られた結論等)の報告を行いました。また、卒論の調査や執筆に関する反省点、また3年生への卒論に関するアドバイスもしてもらいました。
■学生により取り組みの熱心さ、特に最後の「詰め」という点については差がありますが、全員、自ら行ったフィールドワークをもとづき卒業論文を執筆しました。これは、私のゼミに入るにあたっての約束事です。
——————-
池田 幸子:「「住工共生」を目指すまちづくり-中小企業のまち高井田地区を事例に-」
石井 柾士:「「多賀そば」ブランド化によるまちづくり-滋賀県犬上郡多賀町の取り組みを事例に-」
石川 祐香:「新規就農を目指すI・Uターン者-鳥取県農業農村担い手育成機構の支援を事例に-」
岩﨑 智紀:「エンパワーメントする農家女性-京都府城陽市の事例をもとに-」
上野 高志:「休耕田の再活用を通した地域活性への取り組み-京都丹波/亀岡「夢コスモス園」を事例に-」
衣川 夏実:「住民参加型スポーツイベントによる地域づくり-岐阜県揖斐郡揖斐川町「いびがわマラソン」を事例に-」
作間 大輔:「高速道路開通と地域づくり-滋賀県甲賀市の事例をもとに-」
塩谷 明子:「食で繁がる新規参入者と限界集落-滋賀県高島市安曇川町を事例に-」
城谷 佳祐:「農村における住民同士の受委託関係について-福井県おおい町父子区を例に-」
塩飽 雄馬:「ロックミュージックにおける感動体験」
武田 茂樹:「郷土食材を使ったオリジナル料理による地域活性化-長野県須坂市を事例に-」
宮越 碧:「子どもの貧困-山科・醍醐こどものひろばを事例に-」
村田 千穂:「市民と行政の協働を目指すまちづくり-大阪府交野市を事例に-」
川野 天希:「都市型観光における地域の再評価-吹田市の「市民の市民による市民のための観光」を事例に-」
杉下 佳苗:「食」が生み出す人々の交流」
森川 佑努:「道の駅」が果たす地域活性化の役割-兵庫県たつの市「道の駅みつ」の事例をもとに-兵庫県たつの市「道の駅みつ」の事例をもとに-」
——————–
・もっと早く調査に取り組めばよかった。調査や執筆に時間がかかる。さらに分析を深めようと思っても時間切れになってしまった。
・卒論執筆は長期にわたるため、自分のモーチベーションを卒論提出の段階に向けて高めていくための工夫が必要。
・自分の本当の学問的な興味関心が何なのか、よく考えるべき。
・指導教員(私のことですが…)と、もっときちんと面談をするべき。
・専攻研究をきちんと読んでおかなければ、フィールドワーク(調査)をしても、どこに学問的ポイントがあるのかよくわからない。
・卒論題目が決定した後、調査結果の分析を進めていくさいに齟齬が生じてしまった。早めに調査や分析の見通しをたてるべき。
■このような4年生の反省、今年だけのことではありません。毎年毎年、4年生は同じことを反省し言うわけです。こちらは口を酸っぱくして指導をしていますが、自分が実際に卒論に取り組まなければ、先輩たちの反省点も切実なものとして受け止められないのかもしれません。ということで、次の学年からは、卒業論文の指導をかえます。これまでは、あくまでゼミ生の自主性にまかせていましたが、卒論完成までにいくつかの段階とタスクを設けて、面談についても定期的に行っていくことにしました。なかなか難しいものですね。
ゼミの決定
 ■龍谷大学社会学部社会学科では、3年生4月からのゼミの所属を決めるにあたり、前年(2年生)12月に、学生の皆さんに「履修志望クラス申込書」を提出してもらうことになっています。この申込書には、第一志望から第七志望までの教員名を記入し、第一志望と第二志望については、その志望理由を書くことになっています。個人的には、第一次募集、第二次募集…と何回かに分けて募集をしてゼミの所属を決めたほうが良いのではと思っています。それは、最初に希望したゼミに所属できなかったばあいでも、気持ちを改めて、志望動機を考えなおすことができるからです(自分は何を学びたいのか…真剣に考える)。とはいえ、そんなことをいっても仕方がありません。現在のやり方は、一発でゼミの所属が決定するわけですから。
■龍谷大学社会学部社会学科では、3年生4月からのゼミの所属を決めるにあたり、前年(2年生)12月に、学生の皆さんに「履修志望クラス申込書」を提出してもらうことになっています。この申込書には、第一志望から第七志望までの教員名を記入し、第一志望と第二志望については、その志望理由を書くことになっています。個人的には、第一次募集、第二次募集…と何回かに分けて募集をしてゼミの所属を決めたほうが良いのではと思っています。それは、最初に希望したゼミに所属できなかったばあいでも、気持ちを改めて、志望動機を考えなおすことができるからです(自分は何を学びたいのか…真剣に考える)。とはいえ、そんなことをいっても仕方がありません。現在のやり方は、一発でゼミの所属が決定するわけですから。
■ところで、私が担当する来年度の3年生ゼミの人数は18人になりました。志望理由は、列挙してみるとおよそ以下のようなものでした。私のゼミの方針や、得意とするジャンルもよく理解して志望していることがわかります。
・農村、農業、食に関心がある。
・社会貢献活動(北船路米づくり研究会)を経験してみたい。
・地域づくりや、地域の活性化に関心がある。
・フィルードワークを通じて学ぶことに関心がある。
・自分の家が農家なので。
・スポーツと地域社会の関係について考えたい。
・地域イベントに関心がある。
・鉄道と地域社会に関心がある。
■昨年の夏からこのホームページを作り、授業でも「北船路米づくり研究会」の活動紹介をしたりと、様々な情報発信をしてきました。社会学科は、一発でゼミの所属を決定するという仕組みになっているため、できるだけ教育-学生のミスマッチを減らすためです。その効果が少しは出ているのかなと思います。
■以下は、私のゼミに関する記事です。
ゼミナール
卒業論文
2年生のゼミ選択について…
(写真は、ゼミの活動「北船路米づくり研究会」での集合写真です。投稿した記事の内容とは関係ないのですが…なんとなく…寂しいので。)
2013年度「脇田3年生ゼミ」の 皆さんへ(現2年生)
■2013年度「脇田3年生ゼミ」の 皆さんへ(現2年生)
■すでにご承知かもしれませんが、社会学科2年生の皆さんが4月からの所属するゼミが発表されました。社会学部教務課の前に掲示してあります。私の方で所属決定を確認した皆さんにメールを送りました(大学のメールアドレスです)。メールを受け取られた方は、私のゼミで間違いないか、まず掲示板で確認をしてください。よろしくお願いいたします。
■また、4月から始まるゼミに先立ち、皆さんとの「初・顔合わせ」をしたいと思います。急なことですが、1月28日(月)12時15分に2号館の110教室に来てください。時間は30分程度です。都合が悪い人は、wakita##soc.ryukoku.ac.jp までメールで連絡をしてください(このメールアドレスの「##」を抜いて、かわりに「@」を入れてください)。そのさい、メールには、必ず学籍番号と氏名を書くようにしてください。よろしくお願いいたします。
卒業論文集の作成
 ■私のゼミでは、毎年、卒業論文集を作成しています。ゼミ生全員で提出した卒業論文のA4サイズの原稿を、4枚ならべてA3サイズに縮小コピーしたものを持ち寄り、印刷して作成します。今日は、その作業の日でした。とりあえず、全員の卒業論文の印刷が終りました。あとは、これに表紙をつけて、大型のステープラーで閉じるだけです。その作業は、今日、来られなかったゼミ生たちにしてもらうことになっています。今日は、まだ授業実施日のはずなのに、欠席しているゼミ生がいます。「卒業論文を提出してゼミはもうない…」と勝手に思い込んで予定を入れてしまっている学生たちです。彼ら彼女らには、きちんと作業をやってもらいます!!
■私のゼミでは、毎年、卒業論文集を作成しています。ゼミ生全員で提出した卒業論文のA4サイズの原稿を、4枚ならべてA3サイズに縮小コピーしたものを持ち寄り、印刷して作成します。今日は、その作業の日でした。とりあえず、全員の卒業論文の印刷が終りました。あとは、これに表紙をつけて、大型のステープラーで閉じるだけです。その作業は、今日、来られなかったゼミ生たちにしてもらうことになっています。今日は、まだ授業実施日のはずなのに、欠席しているゼミ生がいます。「卒業論文を提出してゼミはもうない…」と勝手に思い込んで予定を入れてしまっている学生たちです。彼ら彼女らには、きちんと作業をやってもらいます!!
■ところで、今年のゼミ4年生は、全員で16名。縮小したものであっても、論文集は90ページになりました(全部で35部作成しました)。来月は、この論文集を使って、3・4年生全員が集まり、ゼミ全体で卒業論文発表会をおこないます。1人の発表時間は15分(発表12分、講評3分)。短い時間ですから、プレゼンテーション能力が問われることになります。自分が取り組んだ卒業論文の概要とその成果を、わかりやすく他のゼミの仲間や後輩である3年生に説明しなくてはいけません。それぞれのプレゼンテーションも、卒論の成績評価の一部になります。ですから、ナメてもらっては困るわけです。一方、3年生にとっては、これから取り組まねばならない卒業論文の、調査から提出に至るまでのプロセスをイメージするチャンスになります。特に私のゼミでは、フィールドワークにもとづく事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらうことになっています。ですから、卒業論文を仕上げるまでには、長い時間が必要になります。いわば「脳味噌の持久力」が要求されるわけです。4年生をお手本に、3年生にも頑張ってもらいたいと思います。
■4年生たちは、毎年毎年、後輩である3年生に次のようにいいます。「もっと、早くから取り組んでおけばよかった…」。今年の4年生もきっとそう言うと思いますが、その言葉の重さをどこまで3年生が理解できるのか…少し心配なところがあります。
2回生・ゼミ選択のための情報
 ■ようこそ!! 龍谷大学社会学部社会学科2回生の皆さん。ゼミ選択のための情報として、以下をお読みいただければと思います。
■ようこそ!! 龍谷大学社会学部社会学科2回生の皆さん。ゼミ選択のための情報として、以下をお読みいただければと思います。
—————————–
○脇田ゼミの基本情報です。
→ゼミナール
○ゼミ選択のためのヒントです。
→2年生のゼミ選択について…
○脇田ゼミのこれまでの卒論について。
→卒業論文
○教員としての脇田の情報。→ABOUT-A
○脇田個人の情報。→ABOUT-B
—————————–
■ゼミ選択に関して脇田に直接話しを聞きたい…というばあい、できれば以下までご連絡をください。wakita#@#soc.ryukoku.ac.jp ←@前後の「#」をとったものが私のメールアドレスです。
■ゼミ申請締め切り日の前日まで(12/20まで)、この記事をホームページのトップに掲示します。
■トップの写真は、2012年2月に開催した4回生の「追い出しコンパ」の際に撮ったものです。
【追記】■12月17日(月)、「北船路米づくり研究会」の説明会をゼミ生主催により開催します。2号館101号室で12:45〜13:20です。
■17日(月)頃から、たくさんの2回生の皆さんが研究室を訪れてくれています。できれば、事前に、このホームページをきちんと読んでおいてください。よろしくお願いいたします。夏からこのホームページを整備してきたわけですが、きちんと読んでいただいていないことが、少し…残念です(^^;;。