お礼状を書く・社会学入門演習

■木曜日の2限は、1年生の「社会学入門演習」です。社会学科固有の授業です。先日の土曜日、琵琶湖に浮かぶ沖島(滋賀県近江八幡市)を訪問し、離島の生活や離島振興について、さまざまな観点からお話しを伺いました。そこで今週は、まずは「お礼状」を書くことから始めました。学生たちに聞いてみましたが、これまで「お礼状」を書いたことがある人は、18人中2人…。まあ、そんなものでしょうかね~。「お礼状」の執筆を終えたあとは、報告書執筆の準備にとりかかります。まずは、テーマを決め、アウトラインを考えるという課題をだしました。さて、どうなるかな~…。
琵琶湖博物館

■昨日は、「社会学入門演習」・現地実習の2日目。琵琶湖博物館に行きました。私は、1991年度から95年度まで、滋賀県庁職員として琵琶湖博物館開設準備の仕事をしていました。そして開館した1996年度から98年度まで、滋賀県立琵琶湖博物館の主任学芸員として勤務していました。もう15年も前のずいぶん昔の話しです。
■私は、C展示室「湖の環境と人々のくらし」の展示担当でした。自分の専門分野の展示だけでなく、いろいろ担当をしなければなりませんでした。トップの展示などは、「担当させられた」展示でした。「 わたしたちのくらし50年」という展示です。こんな内容です。
「わたしたちのくらしは、1955(昭和30)年ごろをさかいに、大きく変化しました。 この立体年表には、1955(昭和30)年から2005(平成17)年までの50年間におきたできごとだけでなく、時代をうつしたテレビニュース、 それぞれの時代のなつかしい電化製品や食品、生活用品、おもちゃ、本、雑誌、レコードなどが展示されています。50年間のくらしの変化をふりかえることで、今の「ゆたかなくらし」のなかでわすれてしまっている、 以前のくらしのこまかな記憶が、すこしづつよみがえってきます。 そのような記憶をもとに、いまのくらしの「ゆたかさ」とは何なのか、 そしてくらしの変化が環境をどのように変えたのか、考えてみましょう。」
■博物館が開館したときは、通路の左側までしか展示はありませんでしたが、開館した年も入れれば開館後18年がたち、通路の右側までに展示が「伸びて」います。「社会学入門演習」の私のクラスを履修しているB君が、「僕は、昭和が好きなんです」と展示に見入っていました。君たちは、平成生まれですものね〜。

■博物館が開館してから長い時間が経過しているので、中には、現状にそぐわない展示内容もあります。しかし、展示を更新することは、財政的にもすごく大変なことなのです。県庁や県議会が予算を認めないといけません。かなり大きな仕事になってしまいます。そこで、全面更新とまではいかなくても、少しずつ、一部の展示は新しくなったり(トップの「わたしたちのくらし50年」のように追加される)、あるいは新しく付け加えられます。この巨大なマイマイカプリとカタツムリの模型は、親しい学芸員のYさんが担当した「オサムシ」関連の企画展で製作されたものだと思います。実物の20倍です。妙に惹かれてしまいました。
■この動画は、A展示室「琵琶湖のおいたち」という展示室の片隅にある小さな動画です。現在は、学芸員のトップにたつTさんが子ども達をつれて、古琵琶湖の化石を探しにいくという設定と撮られたものです。映っている子どもたちは、全員、学芸員の子どもたち。懐かしいですね〜。もちろん、うちの子ども2人も化石を探しています。小さい時のまま、動画のなかに子どもが「保存」されています。少し不思議な気持ちです。
沖島訪問-社会学入門演習・現地実習-

■6月8日(土)・9(日)の両日、社会学科の「社会学入門演習」の現地実習でした。担当しているクラス18名の1年生とともに、8日(土)は、滋賀県近江八幡市の沖島町を訪問しました。琵琶湖には3つ島がありますが、コミュニティがある島は、唯一、沖島町だけなのです。淡水湖の島にコミュニティがあること自体、世界的にみても大変珍しいことのようです。
■ところで、「社会学入門演習」の現地実習は、1年生の前期、必ず履修しなければならない必修課目です。私は、この課目を4年ぶりに担当することになりました。これまでは、コウノトリの保護を活かした地域づくりをしている豊岡、蛸を切り口に街おこしをしている明石市などを訪問しましたが、今回は、龍谷大学瀬田キャンパスのある地元の滋賀県をフィールドにしようと考えました。そのうえで沖島町を選択しました。私自身は、過去に何度も、沖島を訪問させていただいていること。社会学部教務課の職員Cさんのご実家がこの沖島にあり、お父様が自治会の副会長をされていること。また、離島振興法の改正で、沖島がこの法の適応を受けて、過疎対策や活性化対策に国から経済的な支援を受けることができそうなこと・・・。いくつかの理由から、「社会学入門演習」の現地実習のフィールドとして、沖島に行かせていただくことにしたのです。

■8日(土)は、JR瀬田駅に8時半に集合しました。はたして遅刻せずに全員そろうのか・・・と心配していましたが、気合いが入っていたのか全員きちんと揃ってスタートすることができました。瀬田駅からは、チャーターした大型観光バスで琵琶湖の湖周道路を走り、一路、沖島の対岸にある堀切港まで。トップの写真は、その堀切港から撮った沖島です。沖島には、沖島町自治会が経営する通船で移動しました。私自身は、滋賀県立琵琶湖博物館に勤務している時代から何度も沖島を訪れていますが、ほとんどの学生たちは初めての沖島だったと思います。そういう意味では、良い思いでにもなったのではないかと思います。
■2枚目の写真は、教務課の職員Cさんご実家です。そうなんです。西福寺という、お寺なのです。ここは、蓮如聖人の伝説のあり500年以上の歴史をもつ浄土真宗本願寺派のお寺でもありますす。午前中は、お寺の歴史や沖島の歴史について、Cさんのお父様であるご住職から御法話がありました。息子さんであるCさんも、この日は、お父様の法事のお勤めのお手伝いもあり、ご実家に帰省されており、いろいろお世話いただきました。Cさん、ありがとうございました。午後からは、お父様と、檀家である漁家のNさんから、離島である沖島の教育・漁業・文化・生活、さらには町の活性化についてお話しをいただきました。質問については、学生たちがあらかじめ授業中に一生懸命考えてきたものです。前半は、私がその質問にもとづきお話しを伺う形式にしましたが、後半は、代表の学生数人がお話しを伺うようにしました。少し心配しましたが、インタビューの初歩の初歩、半構造化されたインタビューの真似ごと程度は経験できたのではないかと思います。1時間半程、つたない質問に丁寧にお答えいただきました。本当にお世話になりました。ありがとうございました。
沖島訪問

■6月8日(土)、「社会学入門演習」の18名の新入生たちと一緒に、琵琶湖の浮かぶ離島、沖島(近江八幡市)を訪問します。沖島には、長い歴史をもつコミュニティがあります。ここの自治会長さんと副会長さんのお2人にお話しを伺う予定になっています。本当は、沖島に宿泊できればよかったのですが、諸般の事情から沖島での宿泊は難しいということがわかりました。仕方がないので、夕方、野洲市のユースホステルに移動して宿泊する予定になっています。翌6月9日(日)は、草津市の烏丸半島にある滋賀県立琵琶湖博物館で一日勉強することになっています。
■「社会学入門演習」では、1年生が必修の授業です。すべてクラスが、学外に現地実習旅行に出かけ、そこでの体験にもとづき報告書を執筆することになっています。以下は、シラバスの講義概要です。ちょっと固い説明になっていますね…。
————————————–
この科目では、大学での学修スタイルと、本学科における大学生活にいちはやく慣れる機会を提供することを目的として、クラス単位で1泊2日の現地実習旅行をおこない、現地で見たり聞いたりして得た知識をもとに、実習報告書を作成する。
高校までの「勉強」と、大学での「学修」は大きく異なる。高校までは、基本的に与えられた知識を身につければよかったのに対して、大学での「学修」の最大の特徴は、自分がおもしろい・重要だと思える知識を自分で掴み取るという点にある。そのために大学の授業では、「話し合い(議論)」が非常に重視される。そしてその基本となるのが、「異質な他者」とのコミュニケーション能力である。初めて出会うクラスメイト、教員、実習旅行先で出会う人、自分の書いた報告書を読むことになるであろう人、これらの人々は、家族や友人とは異なり、独りよがりに「気分語」「仲間語」を発するだけではわかってもらえない、自ら進んで関係を持とうとする姿勢や、お互いに理解し合えるための工夫が必要な「異質な他者」である。この実習を、そうした「異質な他者」との出会いを体験し、「話し合い」という様式のコミュニケーションに慣れる場として捉えて欲しい。それが、本学科での4年間の学修生活の基礎を培うはずである。
————————————–
■私のクラスでは、4班にわけて、このシラバスにある「話し合い(議論)」を進めてきました。そのなかで、沖島でお聞きする質問項目についても議論してきました。ネット上の情報や動画をみながら、そして以下の新聞記事などを参考にしながら、質問項目を整理してきました。今回の現地実習では、事前に、この質問項目を沖島の自治会の関係者にお渡してする予定にもなっています。
【産経新聞記事】
琵琶湖・沖島の挑戦(上) 「離島」になりたい 財政優遇に未来かける
琵琶湖・沖島の挑戦(下) 日常が「スローライフ」 観光客呼び込みに活路
■ところで、上の画像、Google Mapから取り出したものです。琵琶湖の真ん中あたりです。もう少し細かくいうと、堅田と守山の間を渡る琵琶湖大橋を超えた北湖の南部にあたります。右上のほうに、沖島が確認できるでしょうか。画像の左の方は、湖西になります。私の3・4年生ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」の活動は、ちょうこの画像では左の真ん中あたりになります。山裾に四角い圃場がひろがっているのが見えるでしょうか。ここが、北船路の棚田になります。下の写真は、北船路の棚田から沖島を撮ったものです。

入門演習・質問の作成
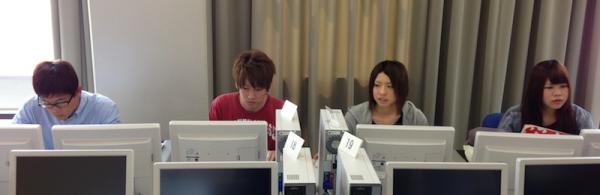
■5月9日に、「入門演習」の授業がありました。今週の宿題は、琵琶湖の離島である彦根市近江八幡市沖島町の動画やネット上にある様々な情報を参考にしながら、沖島でお聞きする質問項目を、一人5個ずつ考えてくるというものでした。この日は、パソコンのメールを使いながら、各自の5つの質問項目を4つの各班ごとに集約して、議論をおこない、整理してまとめる作業を行いました。社会調査の入門の入門のような作業と、パソコンやメールの初歩的な学習を、同時に行ったわけです。

■大学に入学したての学生たちの質問項目ですが…。たしかに、しっかり考えられた質問もありましたが、ときどき「あれっ???」と思うような質問もあったりして…。質問項目を作成すると、そこには、自分たちが自明としている事柄や考え方がそこに浮かび上がってきます。来週は、さらにこの質問項目について、学生の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。その上で、デジカメやICレコーダーの使い方について勉強します。
入門演習のこと

■この4月に社会学部社会学科に入学した学生たちは、全員「入門演習」履修することになっています。写真の学生たちは、私が担当している「入門演習」の皆さんです。6月の沖島調査旅行に向けて、今から、事前学習に取り組んでいきます。
■こんな写真を撮ったのも、顔と名前を記憶しないといけないからです。3年生のゼミ生が18人、入門演習の1年生が18人。私には、なかなか大変です…。人数を数えると19人います。1人は、2年生。このクラスにLA(ラーニング・アシスタント)をしてくれている五十嵐くんです。五十嵐君、よろしくお願いします。
【追記】■「飲食厳禁」とありますが、それはここがパソコン等を使う情報処理実習のための教室だからです。ちなみに、「飲食厳禁」の「禁」の下にいる男子学生、この表情はわざとです。もうちょっと、皆でウケてあげればよかったかな…。
2013年度前期・4年ゼミ(社会学演習ⅡA)掲示板
5月2日
■就職活動の関係で、来週からの発表順番が変更になります。
5/9:卒論の個別相談
5/16:安平
5/23:臼杵
5/30:北川
6/6:山根
6/13:山田
6/20:井上
6/27:松見
7/4:枡田
4月11日
■新4年生のゼミ生の皆さん。前期の報告の順番が決定しました。とりあえず、6月末までは、以下の順番で進めます。就職活動等で、報告できないばあいは、誰かと交代することを原則としてください。報告しないと評価できませんので、その点をよくわかっておいてくださいね。
4/25:脇田の講義
5/2:中村
5/9:安平
5/16:臼杵
5/23:北川
5/30:山根
6/6:山田
6/13:井上
6/20:松見
6/27:枡田
■ゼミのコンパ係(飲み会世話係)は北川くんに決定。LINEで予定を調整してください。コンパの開催は、木曜日の夕方で調整してください。
新しいカテゴリー
■この4月から学部新入生を対象にした「入門演習」を担当することになりました。4年ぶりでしょうか。ということで、カテゴリー「入門演習」を増やしました。
南京町「老祥記」の豚まん

■出身地は、兵庫県は神戸市。結婚で神戸を離れてはや四半世紀以上たちますが、故郷といえばやはり神戸です。先日、妻が友人と神戸に遊びにいってきました。お土産は、南京町「老祥記」の豚まん。とっても懐かしかった。現在のように南京町が整備される以前、私が高校生の頃は、狭い路地にある小さなお店でした。その頃のことを思い出しました。しばしば、買いにいきました。「老祥記」のサイトをみていただくと、トップのその頃のお店の写真が出てきます。急に思い立ちましたが、神戸出身ということで、いつか神戸マラソンに出場したいですね〜。
■写真は、そのお土産の豚まんです。ちょっと色の映りが変ですが(真ん中の豚まんが青っぽい…)、これはiPhoneでいいがげに撮ったせいです。美味しいというか、私には「懐かしい」味です。