滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの評議員会

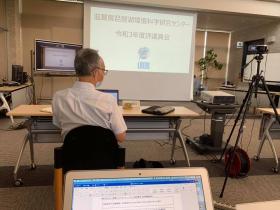
■昨日は、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの評議員会でした。毎年、夏に、この評議員会でセンターの研究プロジェクトの成果をお聞きして、評価を行います。昨日は、朝9時から始まり16時半頃まで、一日がかりの仕事でした。いずれも自然科学的な研究プロジェクトです。私自身の専門分野は環境社会学で自然科学的研究ではありませんが、同じ琵琶湖の環境問題をテーマにしていることから、非常に勉強になります。
■私は、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの評議員会を、2012年から10年間務めてきたことになります。規定では再任したとしても「8年まで」となっているようですが、どういうわけかその8年も超えて10年務めさせていただきました。評議員も昨日までとなりました。長い間ありがとうございました。もっとも、評議員会とは別に、これからも滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員の皆さんとの研究交流を続けて行ければと思います。
「第37回滋賀県ヨシ群落保全審議会」

■朝食が遅れて昼になってもお腹が減っていなかったので、昼食抜きで昼からの仕事に出かけました。仕事を終えてホッとしたら、お腹が減ってきたので、スターバックスで遅めのオヤツを。おそらく今年最初の「抹茶フラペチーノ」になります。
■今日は、「第37回滋賀県ヨシ群落保全審議会」でした。会長させていたていただいていますが、2015年9月からですから、およそ6年に渡ってこの審議会で仕事をしてきたことになります。委員の皆さんの活発な議論や、事務局の皆さんの頑張りもあって、今日は、「滋賀県ヨシ群落保全基本計画改定」の答申案をまとめることができました。皆さんのおかげです。ありがとうございました。
■思えば、審議会であるにも関わらず、それと並行して委員の皆さんとワークショップを開催したり、事務局の皆さんと一緒にヨシ刈り等の活動をされている団体にヒアリングに回ったりしました。私自身も、いろいろ勉強させていただきました。事務局の皆さんとのディスカッションも、自分の頭の中を整理するのに役立ちました。
■基本計画の改訂では、「量から質へ」、「ヨシ群落の面積を増やしていくことから、どのように健全なヨシ群落を多様な関係者と保全していくのか」という方向に大きくパラダイムシフトすることになりました。このような方向性については、すでに審議会の議事録等で公表されていますが、具体的なことは答申が出された後に、県の方から発表されることになります。ただ、計画はあくまで計画です。この計画を土台に、それぞれに個性と特徴を持ったヨシ群落を、具体的に保全していくための事業や取り組みについて検討し、取り組んでいかねばなりません。そのような取り組みにも、できることならば、微力ながら参画・参加させていただければと思います。
素敵なミーティング
■理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の活動を通して知り合った、民間企業の社員さん達と、うちの教員の皆さんとの出会いの場を設けて、昨日は、素敵なミーティングを行うことができました。農学部のT先生とは琵琶湖の水草堆肥について、先端理工学部のY先生とは環境DNAについて。とても有意義、かつ前向きな意見交換ができたと思います。私は、琵琶故知新の理事長で、大学教員としては両先生が主催する研究プロジェクトに関わっていることから、今回のミーティングが実現しました。
■うちにはREC(Ryukoku Extension Center )という社会連携の部署があるのですが、そこを通さず、個人的に民間企業と大学の研究者とをつなぐことになりました。おそらくRECだと、こういったまだ「ぼんやり」としたミーティングはできないでしょうから。委託研究など、具体的に事業を進めていくということであれば別でしょうけどね。それはともかく、これまでに頂いたいろんな「ご縁」を大切にしながらも、出会いの場を作ることで「ご縁」を社会的に活かすことができればと思っています。うまくつながって、コラボの花が開いたらいいなあ…と思っています。
■コラボの花が上手く開いたら、このブログでもご報告できるようになるかもしれません。ご期待ください。
動画「2分(とすこし)で解説 びわ湖の日とMLGs」
■本日、琵琶湖保全再生課水政策係から以下のようなメールが届きました。
石けん運動、そしてマザーレイクフォーラムが担ってきた、自分たちの環境は自分たちで守ろうとする“自治”と、県民と行政が協力しながらそれを達成しようとする“連携”の精神を受け継ぐべく、きたる令和3年7月1日「びわ湖の日」40周年に、新たな取組がはじまります。それが『マザーレイクゴールズ(MLGs)』です。
令和3年(2021年)7月1日は「びわ湖の日」40周年。
びわ湖の日と、その精神を受け継ぐ新たな取り組みマザーレイクゴールズ(MLGs)について解説します。MLGsへの賛同はこちらから簡単にできます!
https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/userLoginDispNon.action?tempSeq=9485MLGsについての詳細は、「マザーレイクゴールズ(MLGs)アジェンダ(素案)」をご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/317517.html#琵琶湖
#滋賀県
#SDGs
#MLGs
#マザーレイク
#マザーレイクゴールズ
#びわ湖の日
■ということで、私もMLGsへ賛同いたしました。
湖北のゆりかご水田
■今朝、滋賀県庁の農政水産部農政課世界農業遺産推進係の皆さんがfacebookに投稿されていました。滋賀県の湖北、長浜市延勝寺の「魚のゆりかご水田」の様子です。投稿の写真では、塩ビ管を使った魚道が設置されています。私自身は、以前、長浜市の早崎で見せていただきたましたが、おそらくそれと同じ原理の魚道だと思います。
■圃場整備等、水田の田面と排水路の水面との間に大きな落差が生まれました。かつてのように、水田に魚が遡上できなくなりました。フナやナマズなどの琵琶湖の淡水魚に配慮するため、滋賀県の湖岸のあちこちの地域で、この「魚のゆりかご水田」のプロジェクトが取り組まれています。魚が遡上するために、排水路に魚道を設置して排水路の水位自体を少しずつ高くする方法と、この投稿のように排水路から水田に魚道を設置する方法とがあります。「魚のゆりかご水田」プロジェクトに取り組むそれぞれの集落の営農やむらづくりの状況や事情に応じて、このような2魚道を柔軟に使い分けることが大切かなと個人的には思います。
■私が早崎で見学させていただいた時は、魚が遡上しやすいように塩ビのパイプの中に小さな階段をつけてみてはどうかというアイデアが出ていました。その後、どうなりましたかね。それぞれの農家の皆さんが、集落の営農の状況に合わせて工夫されています。滋賀県庁が中心となって取り組んできたプロジェクトですが、それぞれの集落の事情に応じて、技術的なことはもちろん、その他運用方法等についても、いろんな工夫をしていくことが大切かと思います。
■さて、このTwitterの投稿者は「世界農業遺産推進係」となっています。そうです。このような「魚のゆりかご水田プロジェクト」も含めて、「森・里・湖に育まれる漁業と農業が織りなす『琵琶湖システム』」は、2019年2月に「日本農業遺産」に認定され、国連食糧農業機関(FAO)が認定する「世界農業遺産」の候補としても認められました。 ところが、世界的なコロナ感染拡大(パンデミック)により、世界農業遺産の審査が進んでいません。コロナ禍が収束した段階で審査が始まるものと思っています。
『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)
 ■ずっと編集に取り組んできた例の本、出版されるのは月末だそうです。これで、気持ちがスッキリしました。次の仕事に頭と気持ちを切り替えることができます。
■ずっと編集に取り組んできた例の本、出版されるのは月末だそうです。これで、気持ちがスッキリしました。次の仕事に頭と気持ちを切り替えることができます。
■この本は、総合地球環境学研究所(大学共同利用機関法人人間文化機構)の文理融合型プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」の成果をまとめたものです。プロジェクトに参加した人たちが各自の成果を学術論文にまとめ、その論文をもとに原稿を執筆した…わけですが、そのような論文を束ねただけの本ではありません。全体を貫き通す研究プロジェクトの考え方を強く意識して編集しています。
■ですから、通常の論文集ではありません。文理融合を志向する上での困難、地域と連携していく超学際的研究を目指す上での困難、そのような困難にも愚直に取り組んだことがわかるように工夫しています。また、プロジェクトの進捗の際に何があったのかが垣間見えるような工夫もしています。個々には、素晴らしい成果が出ているわけですが、全体としての評価については、いろいろご意見をいただかねばなりません。私自身は、「どうだすごいだろ〜」と胸を張るようなつもりでこの本を編集していません(そのような本は、世の中にたくさんありますけど、少なくとも私は違います)。正直にプロジェクトのことを書いています。この本が、個別のディシプリンの壁を越えて、環境科学の新たな地平を切り開いていこうとする方たち、特に若い研究者の方たちや、地域社会で環境問題に実践的に取り組む方達にぜひ読んでいただきたいと思って編集しました。そのような願いも、本書とともに読者に届けば幸いです。
■以下は、目次です。
はじめに
序 地球環境の中の流域問題と流域ガバナンスのアポリア
序-1 流域への注目と2つの研究戦略
(1)教育映画 “Powers of Ten”
(2)空間スケール
(3)水平志向の研究戦略
(4)垂直志向の研究戦略
(5)先行するプロジェクトについて
序-2 学際研究・文理融合研究から超学際的研究へ
はじめに
(1)文理融合による2つの先行プロジェクト(1997-2006年度)
(2)超学際的アプローチによる流域ガバナンス研究の展開(2014-2019年度)第1章 流域ガバナンス研究の考え方
第1章解説
1-1 文理融合型研究プロジェクトの「残された課題」
(1)相似的関係にある2つのアポリア
(2)研究プロジェクト「地球環境情報収集の方法の確立」
(3)研究プロジェクト「琵琶湖―淀川水系における流域管理モデルの構築」
(4)残された課題
1-2 流域における生物多様性と栄養循環
(1)なぜ、生物多様性は必要か?
(2)生物多様性とは何か?
(3)流域の生物群集の固有性と階層性
(4)生物多様性の恩恵
(5)生物多様性と栄養循環
1-3 流域における地域の「しあわせ」と生物多様性
(1)「魚のゆりかご水田」プロジェクト
(2)経済的利益の向こうに見え隠れすること
(3)農家にとっての「意味」
(4)集落の「しあわせ」
1-4 「4つの歯車」仮説 垂直志向の研究戦略の展開
(1)「鳥の目」と「欠如モデル」
(2)経済的手法と人口減少社会
(3)「ブリコラージュ」と超学際
(4)「4つの歯車」仮説
(5)協働の本質
1-5 2つの流域を比較することの意味
(1)シラン・サンタローサ流域
(2)流域を比較することの意味
(3)「虫の目」による修正
(4)本書の構成◉コラム1-1 湖沼をめぐる循環とガバナンス 2つの視点はなぜ重要か?
◉コラム1-2 環境トレーサビリティと流域の環境第2章 野洲川流域における超学際的研究の展開
第2章解説
2-1 琵琶湖と野洲川流域――インフラ型流域社会の特徴
(1)琵琶湖の固有性と多様性
(2)野洲川流域の風土と文化
(3)変貌する琵琶湖と流域管理
(4)インフラ型流域社会
(5)流域の新たな課題
(6)流域管理から流域ガバナンスへ
2-2 上流の森を保全する多様な主体の「緩やかなつながり」
(1)大原の概要
(2)森林保全を担う主体の多様化
(3)上流の森林地域でのフィールドワーク
2-3 圃場整備と少子高齢化――「地域の環境ものさし」によるアクションリサーチ
(1)小佐治地区の地理的特徴
(2)圃場整備と生態系基盤の変容
(3)小佐治地区の環境保全活動
(4)アクションリサーチと「地域の環境ものさし」
(5)「地域の環境ものさし」が地域にもたらしたもの
2-4 魚と人と水田――「魚のゆりかご水田」
(1)須原地区の地理的特徴
(2)琵琶湖に生息する魚
(3)琵琶湖総合開発による人や魚の変化
(4)「魚のゆりかご水田」プロジェクト
(5)「魚のゆりかご水田」5つの恵み
(6)経験知と科学知
(7)「魚のゆりかご水田」プロジェクトの課題
(8)経験知と科学知で人と人、人と自然をつなぐ
2-5 在来魚がにぎわう内湖の再生に向けて
(1)内湖と人の関わり
(2)志那の内湖
(3)内湖を残す
(4)内湖の保全・利用をめぐる関係性と生きものへの配慮
(5)次世代に残す魅力あるまちづくりに向けて
2-6 南湖の水草問題をめぐる重層的なアプローチ
(1)水草問題の経緯と現状、滋賀県の対策
(2)水草が植物成長に及ぼす効果
(3)水草利用と環境保全
(4)水草問題の多面性
(5)水草問題から新しい環境自治へ◉コラム2-1 水田における栄養循環調査――田越し灌漑と冬季湛水は水質保全に貢献するか?
◉コラム2-2 「鮒の母田回帰」を確かめる――ストロンチウム安定同位体比による分析第3章 流域の対話を促進するために
第3章解説
3-1 流域の栄養循環と生物多様性との関係
(1)「鳥の目」から見た栄養循環の特性と流域ガバナンス
(2)野洲川流域の栄養物質の動態と人間活動
(3)安定同位体を用いたリン酸の発生源解析
(4)懸濁態リンの流出と発生源
(5)野洲川流域の栄養循環と生物多様性の関係
(6)川の中の栄養物質の動き――川の水質浄化作用
(7)生物多様性と栄養循環のかかわり
3-2 信頼関係がつむぐ主観的幸福感――野洲川流域アンケート調査に対するマルチレベル分析
(1)主観的幸福感に関するこれまでの研究成果
(2)野洲川流域アンケート調査――「幸福な個人」と「幸福な地域」
(3)信頼の二面性――「きずな」と「しがらみ」
(4)「しがらみ」を緩和する一般的信頼
(5)流域全体の「しあわせ」の醸成に向けて
3-3 流域の栄養循環と地域のしあわせを生物多様性でつなぐ
はじめに
(1)「4つの歯車」仮説
(2)「4つの歯車」仮説の実態:野洲川流域を対象として
(3)超学際的研究におけるツールとしての意義◉コラム3-1 リンはどこからやってくるのか? リン酸酸素安定同位体比による分析
◉コラム3-2 流域からの地下水経由による琵琶湖へのリン供給
◉コラム3-3 産業連関分析からひもとく経済活動が引き起こすリンの流れ第4章 シラン・サンタローサ流域における超学際的研究の展開
第4章解説
4-1 ラグナ湖流域における人口の急速な増加と開発――流域管理の課題
(1)フィリピン開発の歴史と課題
(2)シラン・サンタローサ流域における流域管理の課題
4-2 シラン・サンタローサ流域におけるコミュニティが抱える課題――カルメン村を事例として
(1)カルメン村の概要
(2)周辺開発によるカルメン村の変容
(3)開発影響下にあるカルメン村の将来
(4)マリンディッグの泉の保全に関するアクションリサーチ
4-3 シラン・サンタローサ流域における栄養負荷、栄養循環と生物多様性の現状
(1)流域の土地利用と河川の栄養バランスの不均衡の関係
(2)栄養螺旋長の計測による河川の栄養代謝機能の評価
(3)栄養負荷と大型底生無脊椎動物の多様性の関係
(4)シラン・サンタローサ流域における栄養循環と生物多様性、今後の展望
4-4 サンタローサ流域における共通の関心(Boundary Object)――地下水問題
(1)歴史的に豊富な地下水
(2)地下水に関する問題と懸念
(3)シラン・サンタローサ流域の地下水の窒素汚染の現状
(4)バウンダリーオブジェクトとしての地下水
(5)ワークショップによる調査活動のまとめ
4-5 サンタローサ流域委員会の発展と地域の福祉
(1)サンタローサ流域における流域管理に向けた協力・協働の歴史
(2)サンタローサ流域委員会(SWMC)の設立(2017年)
(3)サンタローサ流域委員会(SWMC)の制度分析
(4)サンタローサ流域における参加型ステークホルダー分析
(5)協力関係の強化にむけて――サンタローサ流域フォーラムの開催
(6)サンタローサ流域の流域ガバナンスの今後第5章 流域ガバナンス研究の超学際的発展にむけて
5-1 垂直志向の研究戦略から明らかになったこと
(1)第三のアプローチ
(2)野洲川流域とシラン・サンタローサ流域の結果の差異は何によるのか?
(3)未来の専門家の姿
5-2 多様な流域のモザイクとしての地球
(1)多様な流域のモザイクとしての地球――ユニバーサル型の地球環境問題の視点から
(2)地球環境研究の文脈の中での私たちのプロジェクト
(3)「ジャーナル共同体」からの越境謝辞
索引
執筆者一覧
『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)、責了。

■一昨日の月曜日の出来事です。総合地球環境学研究所での研究成果をもとにした、『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)、責了(責任校了)しました。出版会の編集者に「これで責了、でよろしいでしょうか?」とメールで確認されてドキドキしましたが。
■普通の論文集ではないので、本の全体に一本太い筋(文理融合型プロジェクトの論理)を通す作業に疲れました。本当に。今日は、もう1人の編者である谷内茂雄さん(京都大学生態学研究センター)と、朝から夕方まで、ずっと龍谷大学で最後の編集作業を行っていました。そして、責了です。というわけで谷内さんと、とりあえずの慰労も兼ねて、一緒に夕食を摂りました。
■おそらく、私たち2人は、もうこんなしんどいことは、二度とできないと思います。しんどいこと…とは、難しいこの手の本の編集だけでなく、文理融合型の研究プロジェクト自体もです。7年間取り組みましたが、年齢的に、体力と気力が持ちません。二度とと書きましたが、谷内さんと私は、流域環境問題に関する文理融合型の研究プロジェクトに取り組むのは、これで三度目になります。ですから、四度目はないということですね。2人とも、研究者の人生のかなりの時間を、この手の文理融合型の流域研究プロジェクトに捧げてきました。
■今回のプロジェクトの最後では、谷内さんと、毎晩のようにzoomによる編集作業を続けました。これからはこのようなことをしなくても良いわけで、少しは体調が回復してくれるのではないかと思います。谷内さんも同じ気持ちだと思います。大袈裟に言っているのではなく、ホンマの話です。2人とも、ホンマに体調を崩しました。で、この仕事が解決したら(完全に終了したら)、2人の思い出の地?!岩手に、慰安旅行に行こうといっています。まあ、コロナで実際には今のところ行けませんけど。
■でも、歳を取れば取るほど、時間の経過はスピードを増してきます。facebookで知りましたが、最善寺というお寺の伝導掲示板には、このような法語が掲示してあったようです。「三十までは各駅停車、四十までは快速列車、五十までは急行列車、六十過ぎれは超特急」。残された時間を何に優先的に使っていくのか、いろいろ考えなければばなりません。
【追記】
■聖書にこういう言葉があるそうです。「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む」(ローマの信徒への手紙5:3-4)。とても自分自身に忍耐があったとは言えないけれど、この仕事の終了までなんとか辿り着けたこと、そしてこの7年の経験が、この言葉と重なりあうものであってほしい…と思います。あと母校関学のスクールモットー、Mastery for Service (マスタリー・フォー・サービス 奉仕のための鍛錬)は、「社会学をやっている自分が、なんでこんなプロジェクトをやっているのだろう…」と迷った時に、いつも自分を励ましてくれました。
■これからは大きなプロジェクトはせずに、コツコツと楽しみながら自分の研究を続けていければ、そして流域の保全に関する実践的な取り組みに関わっていければと思います。平安時代、人々から「阿弥陀丸」と呼ばれた念仏信仰(称名念仏・専修念仏)の先駆者、教信のことをイメージしながら、自分の立っている場所から、流域ガバナンスのことについて考え・発言し・行動していければと思います。少なくとも前期高齢者を終えるまでの期間は、そのようなことができる健康と体力も維持したいと思います。もう、なんだか退職するかのようなことを書いていますが、あと6年間、定年退職まで龍谷大学に勤務するつもりです。残された大学教員の時間を大切にして頑張りたいと思います。
ご当地サーモン
近年、日本各地で「#ご当地サーモン」と呼ばれる養殖ブランドサケ・マスが数多く誕生しています。
それぞれ工夫を凝らした養殖をしており、味わいもそれぞれ。
自分の好きな酒があるように、自分の好きな「推しサケ(マス)」も探してみたらいかがでしょうか。#水産庁 pic.twitter.com/tFIas7fyo1— 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) November 11, 2020
■これは、農水省のTwitterです。この狭い日本の国土で、これだけの「ご当地サーモン」があることに驚きました。琵琶湖のビワマス、私が食べるのは天然のものですが、養殖のものもあります。しかし、全国的にはニジマスが多いですね。このニジマスについては、知り合いの外来生物の問題に詳しい専門家の方は、以下のようなメッセージをSNSを通してくださいました。
ニジマス人気、強烈! これが外来種だというと、驚かれることも多いですね。
北海道の河川はニジマスだらけで、本州も各地で定着している状況にあり、在来種に対しては競争相手として、産卵妨害者として、いろいろな影響があるので、養殖魚としての評判はよしとしても、野外ではいろいろな問題を抱えている厄介者だと思っています。人間の各種営みと同様、経済社会的な効用と自然環境面での弊害との認識をできるだけ広めて、是々非々で判断していく必要があると思います。
■農水省は産業振興のための役所なので、このようなツイートになりますが、おそらく環境省だとまた違った主張になるのではないかと思い、調べてみました。以下のようなものがありました。
underwaterのイノウエダイスケさんにお会いする。

■先週の土曜日、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、イノウエダイスケさんにインタビューさせていただきました。イノウエさんは、「underwater」というタイトルで、京都や琵琶湖の川に生息する魚たちの様子を動画作品にまとめて発表されています。イノウエさんの公式サイト(イノウエさんはポートフォリオと呼んでおられますが)のプロフィールによれは、私の子どもの世代に近い、2人の男の子のお父さんです。お若いです。お仕事では、一級建築士として設計をされています。
■私は、たまたまTwitterでイノウエさんのことを知り、作品の数々に大変感動しました。そして、とうとう実際にお会いしてお話を伺わせていただきたいと、私の方から無理にお願いをしたのです。イノウエさんのことについては、このブログでも一度ご紹介しています。「UNDER WATER」。こちらもご覧いただければと思います。
■イノウエさんへのインタビュー、大変充実したものでした。思わず、インタビューであることを忘れて、淡水魚・川談義を楽しんでいる自分にふと気がついてしまいました。楽しかったな〜。少し時間がかかるかもしれないけれど、インタビューをもとに作成した記事は、「琵琶故知新」の公式サイトに掲載させていただく予定です。インタビューをさせていただいたのは、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事で、「琵琶故知新」設立の母体となった市民グループ「水草は宝の山」代表の山田英二さんが経営される民宿「きよみ荘」の前にある真野浜です。美しい浜です。そして、背中の男性がイノウエさんです。イノウエさんへのインタビューを、山田さんにお願いをして、真野浜と琵琶湖の北湖を眺めることのできる「きよみ荘」の食堂でさせていただきました。
■イノウエさんの作品をご覧になって、生態学、生物学にとっても価値があるとお考えになる人もおられると思います。もちろん、そうなのかもしれません。しかし、私には、イノウエさんの「心象風景」であるように思えました。「心象風景」とは、「現実ではない、心の中に浮かんだ架空の風景」のことを言います。こう書いてしまうと誤解を招くかもしれません。イノウエさんの作品は、確かに現実を写したものなのですから。しかし、イノウエさんの作品からは、イノウエさんがこれまで川との関わり、淡水魚と関わってきた長い時間と、そしてそのような時間の中で醸されてきた優しい眼差しが浮かび上がってくるように思うのです。どのような作品にするのか、どのようなフレームの中で淡水魚の生き様を捉えるのか、そのような眼差しが作品のメタレベルのところにしっかりと存在しているように思うのです。
■さてさて。私はプロのライターではないので、「琵琶故知新」の公式サイトにイノウエさんへのインタビューを記事としてアップするのには少し時間がかかるかもしれませんが、どうか楽しみにしていただければと思います。
サシバを通して人がつながる。サシバを通して地域環境を捉え直す。
■サシバという渡り鳥がいます。タカ目タカ科サシバ属に分類される猛禽類です。人の手の加わった里山環境を繁殖地として、南西諸島から東南アジアにかけて越冬する渡り鳥です。サシバからすれば、農薬や化学肥料等を使わず、人の手が適度に加わることで、様々な餌になる動物がたくさん生息していることが望ましいということになります。サシバがやってくるということは、それだけ餌が豊富にあるということになるのでしょうか。サシバは、多様な生物が織りなす里山の生態系の頂点にいるのです。そのような意味で、里山の指標となる生物でもあるのです。NPO法人オオタカ保護基金では、サシバの生息環境や食性を以下のように説明されています。
サシバの生息地の多くは、丘陵地に細長い水田(谷津田)が入り込んだ里山環境である。また,樹林の点在する農耕地や草地、低山帯の伐採地を伴う森林地帯にも生息する。
主な食物は、田畑や草地、周辺の森林に生息するカエル類、ヘビ類、トカゲ類、モグラ類、昆虫類である。サシバは、見晴らしのよい場所に止まって獲物をさがし、地上や樹上に飛び降りて、それらを捕まえる。2009年に栃木県市貝・茂木地域で行った、巣に運び込まれたエサ動物に関する調査結果を左に示す。サシバは、里山に生息する様々な小動物を餌にしていることから、里山生態系の指標種と言われている。
■以下は、このサシバについての日本自然保護協会の説明です。記事のタイトルからもわかるように、絶滅危惧種でもあります。
絶滅危惧種・サシバはどんな鳥?(前編)
絶滅危惧種・サシバはどんな鳥?(後編)
■この投稿にアップした動画は、沖縄県宮古島市伊良部島で琉球泡盛泡に関するものです。普通、泡盛の原料はタイ米が用いられるのですが、この動画のメーカー「宮の花」さんは国産米を使って蒸留されました。栃木県市貝町の米です。伊良部島はサシバが越冬地に向かう際の中継地であり、そして里山と谷津田が広がる栃木県市貝町はサシバの繁殖地です。絶滅危惧種であるサシバを守っていくためには、生息地の環境を保全しなければなりません。サシバを通して、繁殖地と越冬地の人々が連携されたわけですね。「サシバが舞う自然を守りたい人々の思いが」つながったわけです。加えて、市貝町の農家も、サシバの餌となる生き物が豊富に生息できるように、里山の管理や谷津田の営農に取り組むことになります。農家の皆さんは、サシバを通して地域環境を捉え直しておられるのではないかと思います。そうすることで、谷津田で生産された米の付加価値を高めることができます。加えて、そのような付加価値が、農家の収入にも結びつくものである必要があります。最後のところ、農家を支援する制度が市貝町ではどうなっているのでしょうね。よくわかっていません。時間を見て、確認をしてみたいと思います。
■ところで、宮古島伊良部町の「宮の花」さんが蒸留された泡盛「寒露の渡利」、ネットで予約をしました。宮古島はサシバが越冬地に向かう際の中継地です。たくさんのサシバが空を舞うのだそうです。そのことを都島の皆さんは、「寒露の渡り」と呼んでいます。泡盛のネーミングはそこからきています。予約した泡盛がいつ届くのかはわかりませんが、非常に楽しみにしています。皆さんも、ぜひご予約ください。