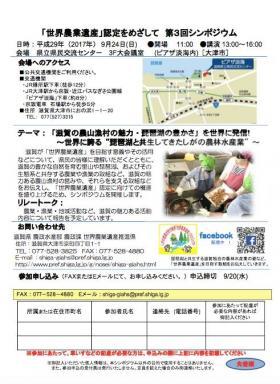「日本農業遺産」「世界農業遺産」のお祝い

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに、「日本農業遺産」に認定されたことについては、このブログでお伝えいたしました。「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の会員をはじめとする関係者の皆さん、滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんが力を合わせて取り組みが結実したこと、おめでとうございます。アドバイザーとして申請作業を支援させていただいた私も、大変幸せな気持ちになっています。ただし、まだ道半ばです。これから世界農業遺産として認定いただけるようにさらに努力を継続していかねばなりせんし、もし、仮に世界農業遺産に認定いただけたとしたら、今度はその価値を活かす様々な取り組みをさらに前進させなければなりません。世界農業遺産自体の申請は、農政水産部が所管されていますが、もし認定されたとすれば、琵琶湖環境部や商工労働部との緊密な連携、県内の諸団体との連携、そしてそれらの連携に基づいた様々な事業の展開が必要になってくるのではないかと思います。
◾️昨日は、「世界農業遺産」への認定申請承認と「日本農業遺産」認定をお祝いして、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお祝いの会が開催されました。農政水産部の職員の皆さんが中心ですが、その中には、「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」を一緒に歩いてくださった方もおられます。昨日は、嬉しすぎて皆さん相当お酒を飲まれました。その様子が写真にも出ているかな。ということで、写真はちょっとトリミング…してあります。もっとも、昨日は単に飲むだけでなく、県の職員の皆さんと、「世界農業遺産」に関連して2つの事業モデルについて相談をすることができました。実現したらいいなあと思います。多くの皆さんと楽しい夢(妄想)を語り合えば、100の夢(妄想)のうち3程度は実現するのではないだろうか…、いつもそのように思っています。


◾️この日のお祝いの会では、美味しい鮒寿司が披露されました。私も職員の皆さんと一緒にお相伴にあずかることができた。知事と技監のお手製の鮒寿司です。ありがとうございました。どちらもとても美味しい鮒寿司だったけれど、私の好みからすると、旨味が口の中によりふわっと広がった技監の鮒寿司の方にやや気持ちは傾いた。なのですが、やはり両方とも美味しかったです。
長浜市長にインタビュー
 ◾️昨日は、朝から長浜市役所に出かけました。「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の仕事でした。滋賀県の大学コンソーシアムは、「滋賀県内に立地する13大学と6つの市・県が相互に連携し、滋賀にある大学として存在感のある個性輝く大学づくりを目指すとともに、地域社会の発展に貢献」することを目的に設立されました。「大学・地域」となっているところが重要かと思いすま。
◾️昨日は、朝から長浜市役所に出かけました。「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の仕事でした。滋賀県の大学コンソーシアムは、「滋賀県内に立地する13大学と6つの市・県が相互に連携し、滋賀にある大学として存在感のある個性輝く大学づくりを目指すとともに、地域社会の発展に貢献」することを目的に設立されました。「大学・地域」となっているところが重要かと思いすま。
◾️今日の仕事も、大学と地域社会との連携に関して、長浜市長の藤井勇治さんにインタビューすることでした(ちなみに、藤井さんは、龍谷大学の卒業生です)。今日の藤井市長へのインタビューは、20年ほど前からお付き合いのあるコンソーシアム顧問の仁連孝昭先生(滋賀県立大学名誉教授、元副学長)、長浜バイオ大学の河合靖先生、そして私の3名でさせていただきました。コンーソシアムの大学連携政策研究事業 「県内高等教育振興のための政策研究事業」に関連するインタビューです。
◾️インタビューの後は、藤井市長から「せっかくですから、盆梅展もみていってください」と招待券をいただくことができました。ということで、ひさしぶりにたくさんの盆梅を鑑賞してきました。展示場である「慶雲館」には、うっすら梅の香りが漂っていました。写真は「不老」と名付けられた八重紅梅。推定樹齢は400年だそうです。長浜最大の盆梅だそうです。400年。世話をきちんとしていれば、これだけ長く花を咲かせることができるのですね。藤井市長、ありがとうございました。




◾️市役所での仕事を終えて帰宅する際、湖西線にある自宅最寄り駅まで琵琶湖の周囲を時計回りで帰るのか、それとも湖北の近江塩津経由して逆時計回りで帰るのか、ちょっと迷いました。嬉しい迷いです。せっかくですから、ちょっと「ローカル鉄道の旅」の雰囲気を味わおうと、後者の逆時計回りで帰るのことにしました。あいにくの天候でしたが、水墨画のような琵琶湖の風景を楽しみながら帰宅することができました。マキノのあたりでは、水田を横切る猿の集団を見かけたり、北小松では道路の工事が進んでいるなとか…ちょっとした変化に気がつきました。近江今津での乗り換えでは、ホームが違うということにギリギリで気がつき慌てて隣のホームに停車した電車に駆け込みましたが。
◾️昨日は長浜市長へのインタビューでしたが、来週の金曜日は草津市長へのインタビュー、そして25日は滋賀経済同友会の関係者へのインタビューになります。
世界農業遺産への認定申請が承認されました。
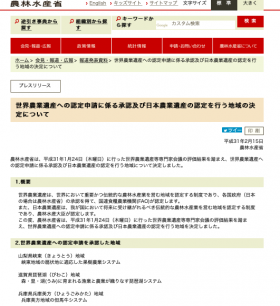 ◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。
◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。
◾️私と滋賀県の世界農業遺産への申請作業との出会いは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。そのような裏の話し横に置いておいて、正式にこの世界農業遺産に関わるようになったのは、2016年の春からです。滋賀県内で唯一、農学部を設置しおり、滋賀県と包括協定を締結している龍谷大学が関わることになり、庁内に設置された「世界農業遺産プロジェクト推進会議」の議長に農学部の竹歳一紀先生が、そして私がアドバイザーに就任し、申請作業の支援に関わってきました。現在までの約3年間に、何度も会議や打ち合わせの作業を重ねてきました。また、2016・2017・2018年と、3年連続で「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」に県庁の皆さんと一緒に出場し、チームとしての団結心を高めるとともに、取り組みの広報にも取り組んできました。そして先月は、世界農業遺産・日本農業遺産の二次審査会で農林水産省へ行ってきました。先日、その時の写真を滋賀県庁の農政課から送っていただきました。ありがとうございました。この二次審査の時のことは、ブログで「世界農業遺産・日本農業遺産二次審査」として報告させていただきましたので、お読みいただければと思います。
◾️さて、「世界農業遺産」への認定申請が承認されたからといって、ここでのんびり一息ついている時間はありません。認定取得を目指した取組をさらに力強く推し進めていかねばなりません。加えて、もしうまく世界農業遺産に認定されることができたとしても、それはゴールではなく新たにスタートになります。認定されたということをジャンピングボードとして、評価された琵琶湖システムの価値を、どのように仕組みで発展させていくのか、分野を超えた方達の協働が必要になってきます。まだまだ取り組むべき課題があります。アドバイザーという側面から支援する立場ではありますが、できるだけのことをやっていきたいと思います。

【追記】◾️このブログの右上の方で、語句検索をできるようになっています。「世界農業遺産」と入力して検索すると、40近いエントリーがヒットしました。
「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」の打ち上げ&「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業の世界農業遺産認定を目指す決起集会」

◾️先週の木曜日のことになりますが、先日開催された「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の打ち上げと、世界農業遺産認定を目指す「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業の世界農業遺産認定を目指す決起集会」が、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開催されました。滋賀県庁の農政水産部の皆さんとよく飲みました。最後、何か話したような気がするけど何を話したか忘れてしまいました。まあ、聞いた皆さんも忘れているでしょうがwww。
◾️写真は、飲んだ後の集合写真です。私は4月生まれで既に還暦になりましたが、私の左右におられるお2人も同級生です。年度内には還暦に。ちなみに向かって左は、農政水産部を率いておられる部長さんです。若い方達に囲まれて、我らアラ還は幸せです。しかし、スーツの皆さんの中で、1人私は…浮いてるような。でも、とりあえず我らはチームです!!
◾️さて、滋賀県が世界農業遺産に向けて行った申請、まずは国内の一次審査は突破しました。しかし、審査はまだまだ続きます。今回の決起集会という飲み会が、ローマでの世界農業遺産認定につながる一歩となるように、引き続きアドバイザーとして、頑張っておられる職員の皆さんのお手伝いをさせていただきます。頑張った成果が実を結び「世界農業遺産」に認定されると、来年の「びわ100」では「祝・世界農業遺産認定」を祝って100kmを歩くことになります。しかし、重要なことは、むしろ認定の後の取り組みの方ですね。ローマへ通ずる道の向こうには、まだまだ次の道が伸びています。
◾️木曜日は、この打ち上げ&決起集会、そして金曜日は昨日のエントリーにも書きましたが、鉄道ファンとの交流会。飲み会が続きました。
『滋賀の農業水利変遷史』
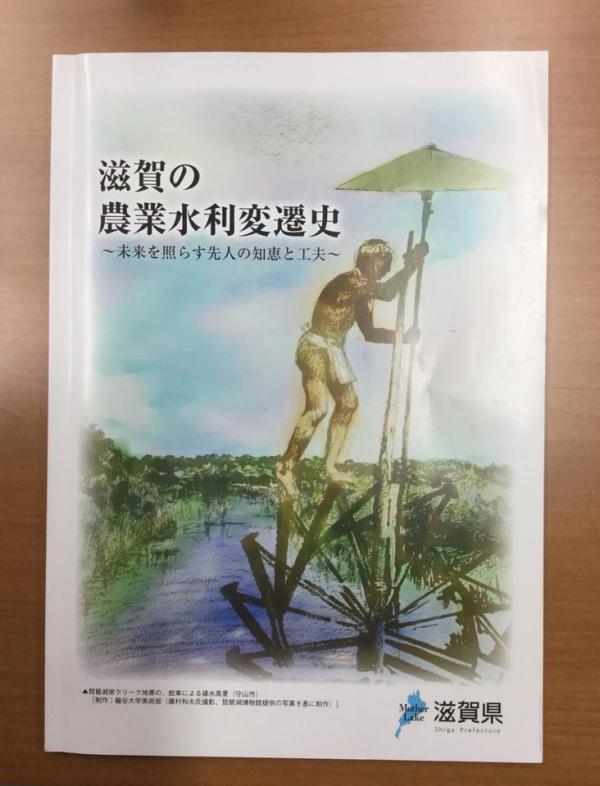
■今週の火曜日、授業が終わったあと、滋賀県庁農政水産部農政課を訪問して、農政課の方達と一緒に取り組んでいる事業に関して、諸々の打ち合わせを行いました。その際、この報告書をいただきました。素晴らしいですね。 龍谷大学農学部の野田公夫先生が中心となってまとめられたものです。インターネットでもご覧いただけます。
■以下は、その目次です。
1滋賀の水利変遷 概要
01社会的背景と水利の変遷
技術の向上と水利
むらの成り立ちと水利
水利の近代化と開発
環境保全と自然との共生02特徴的な滋賀の農業水利
琵琶湖の水位変動と湖辺のかんがい
古来より開発が進んだ河川農業水利
補給水として開発が進められた地下水
Part1 安定した水利のもと古来より発達した農村のむら社会
Part2 安定した水利のもと古来より発達した農村のむら社会
Part1 伝統を誇る持続可能な稲作文化
Part2 伝統を誇る持続可能な稲作文化2 地域毎の水利の変遷
01湖南地域
湖南の水利マップ
祇王井の伝説
Part1 野洲川流域の水利施設
Part2 野洲川流域の水利施設
杣川流域のため池
棚田地域の水利と保全02湖東地域
湖東の水利マップ
湖辺の水郷における半農半漁の生活と田舟の伝承
Part1 古来から続く井堰と現在の新しい形態…愛知川流域
Part2 古来から続く井堰と現在の新しい形態…愛知川流域
大中の湖の干拓と開拓
日野川流域の大規模なポンプによる揚水かんがい
ほ場整備とむらの景観の一大変化…宇曽川流域
地域水利への誇り…犬上川流域03湖北地域
湖北の水利マップ
高時川流域の水利
姉川流域の水利
西野水道の大工事
湖北の農事文化04湖西地域
湖西の水利マップ
安曇川流域の水利施設
鴨川流域の水利事業
いまでも残る条里地割
淡海湖築造の苦労あとがき
水草のこと、世界農業遺産のこと

■今日は、午前中、大津市の皇子山にある大津市公園緑地協会と、堅田の真野浜の「きよみ荘」を訪問しました。両方とも、琵琶湖・南湖の「水草問題」関連での訪問です。民間の力を主体に琵琶湖・南湖の水草問題を解決するための取り組み、少しずつでしかありませんが前進しています。写真は、その真野浜から撮ったものです。普段は対岸や比良山系が美しく見えるわけですが、今日のように湖と空の境目がわからない様な、こういう「水墨画」ような風景も素敵だなと思います。
■午後からは滋賀県庁に移動しました。滋賀県は、現在、世界農業遺産に向けて申請準備を進めています。私は、その申請準備のアドバイザーを務めています。今日は、その申請書の作成をアドバイザーとしてサポートさせていただきました。午後は県庁にこもって仕事をしました。職員の方達とじっくりディスカッションもできました。職員の皆さんは、様々な分野の専門家から、申請に必要な情報や視点に関していろいろヒアリングをされています。そのような、ヒアリングから得られた情報についても考慮しながら、ディスカッションの中で浮かび上がってきた難しい課題を、なんとか乗り越える道筋が見えてきました。安心しました。集中し過ぎて首や背中が凝ってしまいました。結局、今日は「水草問題」と「世界農業遺産」で1日を終えることになりました。両方とも、琵琶湖に関わる事柄です。人生の最後のコーナーで、なかなか愉快です。400mトラックでいえば、300m超えたあたりです。あとは残りは、直線100m。頑張ります。
第1回「生物多様性しが戦略推進専門家会議」

■このホームページのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔初」の下にある青い文字が並ぶメニューバーがあります。このメニューバーのうち、「ABOUT-A」には、私のプロフィールやこれまでの経歴等の基本的な情報が記載されています。その中には「社会的活動」という小タイトルがあり、これまで委員に就任してきた自治体の審議会・委員会のリストが記載されています。そのうちの1つになりますが、2014年1月から2015年3月まで、「滋賀生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」の委員を務めていました。この専門家会議では、滋賀県の生物多様性を推進するための「生物多様性しが戦略」を策定に向けて議論を行ってきました。議論の成果は、「しが戦略」として策定され公表される事になりました。その途中では、県内6ヶ所でタウンミーティングを開催しました。私も、大津会場でファシリテーターを担当しました。この「しが戦略」の詳細については、トップの写真の中にある冊子『自然本来の力を活かす「滋賀のいのちの守り」-生物多様性しが戦略-』をご覧いただきたいと思います。PDFファィルでもお読みいただけます。
自然本来の力を活かす「滋賀のいのちの守り」-生物多様性しが戦略-
■今回開催された「生物多様性しが戦略推進専門家会議」は、この「生物多様性しが戦略」の中間評価に向けて、数値目標(指標)や中間評価の手法について再検討を行う事にありました。いろいろ議論が行われました。ひとつには、生態系サービスのうち調整サービスに関する部分が少ないことが気がかりとの指摘がありました。ダムや堤防だけで治水を行うのではなく、総合治水を行うというのであれば、人が手を入れて水源涵養の機能が上昇した森林を森林整備率等で評価することが必要だという意見です。
■私は、野生の鹿による鹿害の被害について、県内のあちこちで聞いていることから、この点から意見を述べました。鹿が増えすぎて森林や山の植生を破壊しているのです。「しが戦略」では、平成22年を基準年度として、「ニホンジカの生息数」を「しが戦略」策定時から目標年度の平成29年度までに半減することが目指されていました。もちろん、現実はうまくいっていません。また、「ニホンジカの生息数」に加えて、「狩猟免許う所持者の人数」も指標として上がっています。私が指摘したのは、これだけではどれだけ駆除できたのかが見えないので、「社会的努力」の「見える化」が必要だということです。できれば、駆除した鹿肉は廃棄物として処分してしまうのではなく、社会的にも有用な資源として活用されることが望ましいわけですが、そのあたりの実態がどうなっているのかが把握できる数値がありません。指標とはならなくても、参考値として指標を支えるようなデータが必要だと思うわけです。そのような参考値を添えることで、社会の中の生物多様性をめぐるシステムの持つダイナミックな動きを評価することができます。
■評価は、「社会的努力」を後押しするものであってほしいと思います。目標値に到達していないとダメ出しをするためではなく、なぜうまく行かないのかを考える契機にしなければなりませんし、もっと言えば、生物多様性をめぐるシステムの中で、社会的努力をしている人びとの意欲を喚起し、エンパワメントしていくような形で機能するものである必要があります。
■この専門家会議、今年の秋まで3回開催される予定です。
第27回「湖辺ルネッサンス〜大津のヨシ作戦〜」ヨシたいまつ一斉点火


■昨晩のことになりますが、第27回「湖辺(こへん)ルネッサンス~大津のヨシ作戦~」のフィナーレを飾る「ヨシたいまつ一斉点火」に参加してきました。大津市内の以下の4ヶ所で開催されました。堅田学区会場(今堅田三丁目地先・びわ湖大橋プラザ付近湖辺)、雄琴学区会場(雄琴六丁目地先・アクティバ琵琶前湖辺)、膳所学区会場(由美浜地先・大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ)、晴嵐学区会場(松原町及び唐橋町地先・国道1号線瀬田大橋と瀬田唐橋の間の瀬田川右岸(西側)河川敷) 。滋賀県ヨシ群落保全審議会の委員のお1人が、雄琴学区の自治連合会長をされており、その会長さんからお誘いもあったことから、雄琴学区会場の「ヨシたいまつ一斉点火」を見学させていただきくことにしました。会場に到着すると、すでにたくさんの方たちでにぎわっていました。学区内から親子連れで参加されている方が多いように思いました。火を使うことから、消防団の方たちも待機されていました。
■「ヨシたいまつ一斉点火」の4会場のうちで、この雄琴会場がヨシ群落としては一番面積が広いとのことでした。この雄琴学区のヨシ群落では、1月の末、ボランティアの方たちや、企業のCSR活動で参加された社員さんたちが、ヨシ刈りを行いました。昨晩のヨシたいまつは、その時に刈り取ったヨシが使われています。一斉天下の直前、夜空には満月に近い月がのぼっていたこともあり、湖辺に建てられたたくさんのヨシたいまつがうすぼんやりと確認できました。そのたいまつに、雄琴学区の親子の皆さんが一斉に点火すると、ヨシのたいまつはとても勢いよく燃えあがりました。大変、幻想的な風景がそこに生まれました。今年で、27回目。その前からも雄琴学区では、このようなイベントをされているようで、その時代の回数も加えると42回目になるそうです。
■今回初めて見学をして、たくさんの地域の親子が参加される一大イベントであることがわかりました。このようなイベントに参加しながら、ヨシ群落が魚や鳥をはじめとする生き物たちの生息場所であり、ふるさとの原風景でもあることを頭に思いうかべていただけると素晴らしいなあと思いました。さらに、身近にあるヨシ群落のことを普段から感じつつ、暮らしていけるとよいなあと思います。春、夏、秋、冬。四季折々の風景があります。これからもう少し暖かくなると、コイ科魚類が産卵している音が聞こえるかもしれません。ヨシが茂る頃には、鳥の鳴き声も聞こえてくるでしょう。多くの皆さんが、身近なヨシ群落や琵琶湖のことを気にしながら暮らしていくことが、結果としして、ヨシ群落や琵琶湖の環境保全の土台になるのではないかと思います。一般的にもいえる傾向かと思いますが、人びとが身近な環境から関心を失ってしまうと、その環境が破壊されたり、その質が劣化するリスクが高まります。人びとが身近な環境を強く意識することは、ある意味、「抑止力」を生み出すことにもなるのです。地域の皆さんの意識のなかに、このヨシ群落は自分たちが「守り」をして見守っているのだ…という気持ちが涵養されていくことが大切なのだと思うのです。ただ、一般論として「琵琶湖やヨシ群落を大切にしましょう」と言うこととの間には、大きな違いがあるように思います。
第32回「滋賀県ヨシ群落保全審議会」
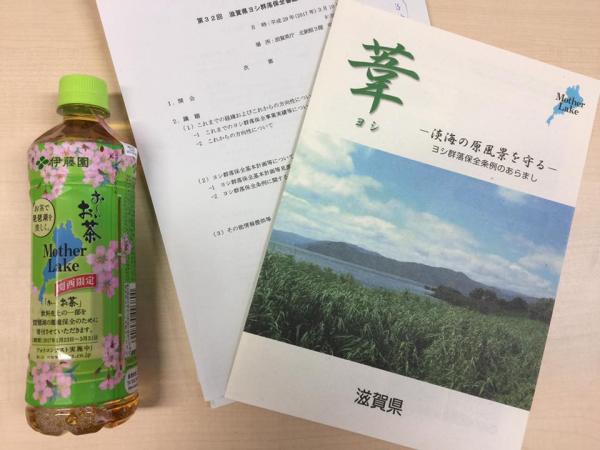
■今日の午前中は、第32回「滋賀県ヨシ群落保全審議会」でした。審議会というと大変固いというイメージがありますが、委員の皆さんのご協力のもと、とても楽しい雰囲気のなかで審議会を進めさせていただいています。審議会の会長ではありますが、委員の皆さんとの議論とその展開にわくわくしています。
■昨年は、審議会以外にも、ワークショップ形式の検討会を開催しました。ヨシ群落を保全する上での課題を抽出しました。現在のヨシ群落保全条例は制定されてから25年ほとが経過しています。そのため、今の時代状況にあった施策、もっとヨシ保全に関わる「人」に焦点をあてる必要があるという認識を、審議会の委員の皆さん、そして事務局の職員の皆さと共有できるようになりました。
■これは、あくまで個人的な意見ですが、これまでのヨシ群落を「守る」「育てる」「活用する」に加えて、ヨシ群落を保全する人びとが「つながる」こと、そのような人びとを社会的に「支える」こと、そしてその活動の様子を社会にたいして「知らせる」ことも必要だと思っています。琵琶湖の周囲には、たくさんの団体がヨシ群落の保全活動に取り組んでいますが、残念なことに、現時点では、ほとんど横のつながりがありません。お互いの活動を紹介しあい、様々な保全に関わる経験や悩みを共有していくために「つながる」ことが大切かと思います。そして、そのような活動を経済的にも社会的にも応援していく「支える」仕組みも必要です。さらに「つながる」と「支える」を育てていくためにも、より広い社会の人びとに知っていただく「知らせる」ことにも取り組まねばなりません。
■そのような「つながる」「支える」「知らせる」ことを強化していくためには、多くの団体が集まることのできるプラットホーム機能、「場づくり」や「関係づくり」が大切だと思っています。今日も、そのようなご意見をいくつかいただきました。行政が、このようなプラットホームを作ろうとするとき、様々な団体に頭を下げてお願いをして、会議に集まっていただく…そのようなパターンが繰り返されてきました。しかし、今回はもっと違った形でプラットホームをつくることができるのではないかと思っています。私が知る限り、ヨシ群落の保全に取り組んでいる方達は、お互いに「つながりたい」とお考だからです。行政から頼まれたから…ではなく、ヨシ群落保全を自分たちの問題として取り組まれているのです。
■これまでのヨシ群落保全条例のなかでは、「守る」「育てる」「活用する」が謳われてきました。これらの「守る」「育てる」「活用する」を縦糸と呼ぶならば、「つながる」「支える」「知らせる」は横糸と呼べるのかもしれません。この縦糸と横糸とが、うまく織り上げられていくなかで、ヨシ群落保全のために、どのような新しい施策や仕組みを考えていけばよいのか、皆さんと力をあわせて考えていきたいと思います。ところで、写真の左の方をご覧ください。伊藤園さんのペットボトルのお茶「お~いお茶」です。このお茶の売上の一部が琵琶湖の環境保全のために寄付されています。伊藤園さん、ありがとうございます。このようなご寄付を有効に活用させていただくためにも、頑張って取り組んでいきたいと思います。
【追記】
■忘れないように追記しておきます。今日の審議会では、前回に続き、科学的なエビデンスにもとづいて、どのようにヨシ群落を多面的に評価していくのか…という点でもいろいろ議論がありました。ヨシ群落の面積だけを指標にするのではなく、もっと多様な指標による評価が必要だという意見です。多面的な評価は、保全活動を行う上での根拠にもなります。もちろん、自然科学的な側面からの評価だけではなく、社会科学的といいますか、社会的な側面からの評価も必要かと思います。地域社会の皆さんが、ヨシ群落の保全に取り組むことの意味もきちんと視野に入れる必要があります。
■出席されたある委員は、琵琶湖博物館の学芸員の指導を受けながら、すでに自主的にヨシ群落の調査を始めたことを紹介してくださいました。また、宇治川でヨシ群落の保全活動についてもご紹介くださいました。また、以下のご指摘、ご意見もいただきました。公道で廃車を放置すれば法律上もすぐに問題なるわけだが、ヨシ原に廃棄された船についてはなかなか社会的に問題にされない。景観上も問題というご指摘。従来のヨシ群落保全条例で言われる「守る」「育てる」「活用する」の「活用する」については、それをヨシ紙等の原料として活用するというだけでなく、例えばエコツーリズム等の対象として、カヌー等のレジャーの場として、ヨシ群落自体が持つ「楽しむ」価値をもっと評価していくべきというご意見。ヨシ群落でのイベントが、地域のつながりを強化し、琵琶湖への関心をより強める機能があるというご指摘。これらのご意見、いずれ議事録になろうかと思いますが、今後の検討会や審議会での議論にきちんと反映できるようにしていきます。