関西学院OB交響楽団のこと
 ■11月4日(月)の振り替え休日の日、「関西学院OB交響楽団演奏会」にいってきました。この演奏会は、関西学院大学交響楽団創部100周年記念であり、OBオーケストラ結成10周年記念でもあります。会場の西宮北口にある兵庫県立芸術文化センターも、今回初めて行きましたが、立派なホールですね。
■11月4日(月)の振り替え休日の日、「関西学院OB交響楽団演奏会」にいってきました。この演奏会は、関西学院大学交響楽団創部100周年記念であり、OBオーケストラ結成10周年記念でもあります。会場の西宮北口にある兵庫県立芸術文化センターも、今回初めて行きましたが、立派なホールですね。
■エルガー「威風堂々第1番」、リスト「前奏曲」、ベートーヴェン「交響曲第5番運命」、チャイコフスキー「交響曲第5番」とプログラムは進みました。一般的なクラシックのコンサートであれば、ありえないプログラムです。しかし、多数のOBOGが出演可能にするためには、このようなコテコテのプログラムでも曲数を増やす必要があったのだと思います。もちろん、会場にいるのは、ほんとんどそOBOGやその関係者ですから、文句が出ることもありません。
■さて、私の主観ではありますが、後になればなるほど、演奏のレベルと質が高まったように思いました。「威風堂々第1番」と「前奏曲」、練習の回数も限られているので仕方がないですね…という感じがしました。特に、「運命」の1〜3楽章のあたりまでは、その思いが強かったな。特に、弦楽器については…。しかし、しだいに尻上がりに調子を上げていきました。
■休憩をはさんで、チャイコフスキーの5番。いや〜、びっくりしました! 指揮者の田中一嘉さんの存在も大きかったとは思いますが、関学らしい迫力のある素敵な熱演になりました。すごく良かった!! 卒業してからも楽器の演奏を続けて市民オケでバリバリ演奏している人もいれば、たまにしか演奏しない人、このOBオーケストラにあわせて楽器を再開した人…それぞれの力量は様々。おそらはく、チャイコフスキーの5番(チャイ5)に演奏レベルの高い人たちが集中していたのでしょう。あるいは、限られた練習のなかでも、比較的、この曲にかける時間が多かったとか…。それでも、みんなで力を合わせて演奏会を成功させようというのは、素敵なことだと思います。この前卒業した若いOBから、その祖父母世代にあたる高齢者のOBまで、これだけの人が集まって演奏会ができるのって…感動しましたよ。
■演奏会のあとは、ロビーで30数年ぶりに、現役時代に一緒に演奏した先輩方にもお会いできました。女性の先輩が、私の名前を覚えてくださっていたのが、とっても嬉しかったりしてね…(^^;;。そのあとは、近い学年の皆さんと集まって呑み会。12人ぐらい集まったかな。これも、楽しかった。話題がつきなかったのです。ああ、また楽器が弾きたくなってきますね〜。そんな余裕はないのですが…。
■このようなすごい演奏会を企画して実現させたOB会の幹事の皆さんには、心から深く感謝したいと思います。まだ、少し余韻にひたっているところがあります。
【追記】■子どもの頃から、バイオリンを半ば強制的に習わされました。両親の青春時代は、戦時中と戦後の混乱の時期であり、「文化」に対するあこがれが大変強かったのだと思います。自分たちは、クラシック音楽に関する関心はあまりなかったのですが、「お稽古事」として子どもにバイオリンを習わせたのですね。いやいやバイオリンをやっていたのですが、大学入学後、学生オーケストラである関西学院交響楽団に入ってからは、真面目にといいますか、一生懸命、音楽に取り組みました。懐かしい思い出です。大学卒業後、私は大学院に進学しましたが、エキストラとして演奏させていただきました。しかし、結婚をして、子供が生まれる頃には楽器を弾くことをやめました。
■当時、バイオリンの調整や弓の毛替え等については、大阪梅田にある宝木宏征さんのf工房というところにお願いをしていました。宝木さんは、私のようなへたくそなアマチュアにもいつも親切に接してくださっていました。あるとき、「脇田さんは、すごいですね〜。研究者をめざしながら、こうやって楽器をやっているんですから。私は、自分が楽器職人を目指しているときは、とてもそんな余裕はありませんでした」と何気なくおっしゃいました。宝木さんは嫌みを言われる方ではなかったので、素直にそう思われたのかもしれません。しかし、その宝木さんの何気なく言われたことが、私にはガンときました。「ほんまに、楽器を楽しんでいるばあいではない。子どもも生まれるというのに」と心の底から思いました。そのときから、楽器を弾くことをやめてしまいました。たまに出して自宅で弾く程度になりました。また、この10年は、ほとんど楽器にはさわってさいません。
■結果として、四半世紀ちょっと楽器を弾いていません。ここ10年は、仕事に集中してきました。OB交響楽団に入って、ステージの上で現役の時と同じように楽器を弾いている先輩・同期・後輩の皆さんをみていると、ちょっと羨ましくもなりますが、それなりのレベルを維持して演奏を続けていく自信がなかなかもてません。いつか楽器を再開するかもしれませんが、それはもう少し先のことかと思います。
■比較的最近になって知り驚いたのですが、宝木さんは2004年にお亡くなりになっていました。お亡くなりになる前に、お話しをしたかった…。現在は、息子さんが工房を継がれているようです。
卒論指導を受ける皆さんへ、脇田のこれから夏期休暇中にかけての予定です。
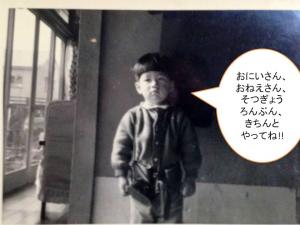 ■面談を希望する人は、以下の脇田の日程を参考に、e-mailで予約をとってください。突然こられても、研究室にはいないことがあります。よろしくお願いいたします。基本的に4年生の卒論面談を念頭においていますが、3年ゼミ生、「大津エンパワネット」履修生の面談についても対応します。なお、今後、あらたに仕事が入り、以下の予定が変更になる可能性があります。
■面談を希望する人は、以下の脇田の日程を参考に、e-mailで予約をとってください。突然こられても、研究室にはいないことがあります。よろしくお願いいたします。基本的に4年生の卒論面談を念頭においていますが、3年ゼミ生、「大津エンパワネット」履修生の面談についても対応します。なお、今後、あらたに仕事が入り、以下の予定が変更になる可能性があります。
■4年ゼミ生の皆さん。9月末には卒論の報告をしていただきます。80%出来上がっている必要があります。もちろん、調査不足、分析不足、そして文章のまずさがこの時点であっても仕方ありません。しかし、卒論の骨格がきちんとゼミできちんと説明できる必要があります。字数でいえば、12,000字程度は必要です。9月以降は、補足調査や分析を深めていきながら、論文の仕上げにはいりますが、11月末には第一次草稿を提出してください。12月は「赤ペン」を入れて数回返却します。冬休みに入るまでには、指導を終えるようにしたいと思います。あとは、各自の責任でしっかり卒論を仕上げて、正月明けには、全員で期限内にきちんと提出できるようにしたいと思います。
————————-
7月15日(月):午前中は大学院生の指導があります。3限オフィスアワー。4限ゼミ。そのあとは、空いています。
7月16日(火):終日、研究にあてる予定です。
7月17日(水):2限授業。午後は会議です。
7月18日(木):2限授業。15時から16時半まで深草キャンパスで「認証評価研修会」です。19時から20時半まで、大津市丸屋町商店街・大津百町館で「まちづくりカフェ」(大津エンパワねっと)です。
7月19日(金):午前中空いています。午後15時まで研究。17時から町家キャンパス龍龍で「大津エンパワねっとを進める会」の会合です。
7月20日(土):午前中、北船路米づくり研究会。午後は『ソシオロジ』編集委員会で、終日京都です。
7月21日(日):オープンキャンパス。「大津エンパワねっと」のチーム「おむすび」のイベント。
7月22日(月):3限オフィスアワー。4限ゼミです。そのあとは、空いています。
7月23日(火):1限から大学院生の指導。11時から12時半まで、大津エンパワねっとの運営打ち合わせ。午後は、17時半から京都で全学研究運営会議。そのあとは、国際シンポジウムの打ち合わせで京都です。
7月24日(水):2限授業。3限大津エンパワねっと運営委員会。そのとは、大学院社会学研究委員会。博士論文受理審査報告。
7月25日(木):大学にいく予定です。
7月26日(金):1・2限、大津エンパワねっと合同授業。
7月27日(土):修士論文中間発表会。
7月28日(日):丸屋町商店街・夜市。
7月29日(月):滋賀県琵琶湖環境科学研究センター評価委員会。
7月30日(火):15時15分から大学院運営委員会。
7月31日(水):2限「地域社会論」試験。3限補助監督。4限補助監督。
————————————————
8月1日(木):大学に行く予定です。
8月2日(金):10時から大津エンパワねっと授業担当者会議。
8月3日(土):私的な用事にあてます。
8月4日(日):韓国からの福祉専攻学生の受け入れ。
8月5日(月):大学に行く予定です。
8月6日(火):終日、学部執行部集中審議。
8月7日(水):14時から16時半まで、滋賀県「マザーレイク21学術フォーラム」。
8月8日(木):大学に行く予定です。
8月9日(金):福井大学教育学部で「環境社会学」集中講義。
8月10日(土):福井大学教育学部で「環境社会学」集中講義。
8月11日(日):福井大学教育学部で「環境社会学」集中講義。
8月12日(月):福井大学教育学部で「環境社会学」集中講義。
8月13日(火):大学には行きません。
8月14日(水):島根県宍道湖で環境調査。
8月15日(木):島根県宍道湖で環境調査。
8月16日(金):島根県宍道湖で環境調査。
8月17日(土):北船路野菜市です。
8月18日(日):個人休暇。仕事を入れません。
8月19日(月):個人休暇。仕事を入れません。
8月20日(火):個人休暇。仕事を入れません。
8月21日(水):個人休暇。仕事を入れません。
8月22日(木):個人休暇。仕事を入れません。
8月23日(金):個人休暇。仕事を入れません。
8月24日(土):個人休暇。仕事を入れません。
8月25日(日):大学にいは行きません。
8月26日(月):大学に行くことが可能です。
8月27日(火):大学に行くことが可能です。
8月28日(水):大学に行くことが可能です。
8月29日(木):大学に行くことが可能です。
8月30日(金):大学に行くことが可能です。
8月31日(土):大学に行くことが可能です。
—————————————————————-
9月1日(日):私的な用事にあてます。
9月2日(月):大津エンパワねっと「報告会」準備期間。大学に行くことが可能です。
9月3日(火):大津エンパワねっと「報告会」準備期間。大学に行くことが可能です。
9月4日(水):大津エンパワねっと「報告会」準備期間。大学に行くことが可能です。
9月5日(木):大津エンパワねっと「報告会」準備期間。大学に行くことが可能です。
9月6日(金):大津エンパワねっと「報告会」準備期間。大学に行くことが可能です。
9月7日(土):午後から大津エンパワねっと「報告会」の予行演習です。
9月8日(日):大津エンパワねっと「報告会」。
9月9日(月):私的な用事にあてます。
9月10日(火):私的な用事にあてます。
9月11日(水):午後から教授会です。
9月12日(木):
9月13日(金):
9月14日(土):
9月15日(日):
9月16日(月):
9月17日(火):午後から大学院運営委員会、大学院委員会、農学部設置委員会。
Kenichi=ケニチ
■私の名前は、健一(けんいち)です。ただし、英語で書くと Kenichi になり、海外の方たちは「ケニチ」と発音します。もう慣れているので、「ケニチ」と呼ばれると反応してしまいます。今日は、パソコンでYouTubeをみていて、たまたま「ケニチ」を発見しました。
■動画に登場されているのは、蛯名健一さんです。もちろん、日本人。アメリカに留学して、様々なダンスを独学で学ばれました。動画は、アメリカの公開オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」に登場されたときのものです。すごいです。まずびっくりするのは、首が落ちるように見えることです。もちろん、眼の錯覚とトリックなのですが、いや、本当に、びっくりです。そのあとの「マトリックス」を題材にしたようなパフォーマンスもすごい。自分の体をここまできちんとコントロールできるだなんて・・・信じられません。こちらの「ケニチ」はすごい!!
武陽人100年のあゆみ
■父の転勤の関係で、5歳から16歳の夏まであいだに、山口県の下関市、福岡県の北九州市小倉区や福岡市、そしてそのあとは広島県の広島市に引っ越すことになりました。引っ越しのたびに、幼稚園や学校を転校することになりました。結局、3つの幼稚園、3つの小学校、そして2つの高校に通うとことになりました。ですから、一応は神戸出身ということになるのですが、少年時代のほとんどは、神戸以外のところで過ごしている…ということになります。
■高校に限定していえば、私は高1の2学期に、広島市内にある広島県立皆実高等学校から神戸市長田区にある兵庫県立兵庫高等学校に転校しました。そして、1977年3月に卒業しました。卒業後、同窓会にきちんと転居先等をお知らせしていなかったこともあり、高校とのつながりはほとんど切れてしまっていました。その母校・兵庫高等学校が創立100周年を迎え、立派な記念式典が開催されたことをfacebookで知りました。上の動画は、そのさいに上映されたもので、兵庫高校の100年の歴史を説明したものです。タイトルに「武陽」とありますが、これは近くを流れる湊川の河原をさします。同窓会の名前は、その地名にちなんで「武陽会」といいます。そして「質素・剛健・自重・自治」の四綱領(しこうりょう)と呼び、校訓として大切にしています。
■この動画「武陽人100年のあゆみ」、お気づきかとは思いますが、コアラが並んでいます。なぜコアラなのか。それは、「校樹」が存在し、ユーカリの樹だからです。ユーカリの葉っぱはコアラの餌ですよね(ちなみに、コアラには「ユカリちゃん」という名前がついています)。並んでいるコアラの頭の上をみると、ユーカリの葉っぱがのっかっています。兵庫高校の校章は、ユーカリの若葉と実をもとにデザインされているからです。「質素・剛健・自重・自治」という四綱領を軸に生徒たちが集う…そのようなイメージにもとづいて校章はデザインされているのです。
 ■動画を拝見すると、兵庫高校は戦前の旧制・第二中学校からの歴史をもつことがわかります。長い歴史をもつせいもあり、全国的にもよく知られる方達が卒業されています。たとえば、小説家の横溝正史、画家の小磯良平、同じく画家の東山魁夷、建築家の清家清、舞台美術家の妹尾河童といった方たちです。私の先輩ということになります。また、第二次世界大戦の沖縄戦当時、沖縄県知事であった島田叡(あきら)さんも先輩のお1人です。島田さんは、1945年1月、第27第沖縄県知事に就任した後、沖縄戦の激戦のなかで消息を絶ったといわれています。高校の敷地には、島田さんのことを偲んだメモリアル「合掌の碑」も建てられています。また、これもfacebookで知ったのですが、OBらが中心となって遺骨の捜索も行われています(右は、神戸新聞記事です。)
■動画を拝見すると、兵庫高校は戦前の旧制・第二中学校からの歴史をもつことがわかります。長い歴史をもつせいもあり、全国的にもよく知られる方達が卒業されています。たとえば、小説家の横溝正史、画家の小磯良平、同じく画家の東山魁夷、建築家の清家清、舞台美術家の妹尾河童といった方たちです。私の先輩ということになります。また、第二次世界大戦の沖縄戦当時、沖縄県知事であった島田叡(あきら)さんも先輩のお1人です。島田さんは、1945年1月、第27第沖縄県知事に就任した後、沖縄戦の激戦のなかで消息を絶ったといわれています。高校の敷地には、島田さんのことを偲んだメモリアル「合掌の碑」も建てられています。また、これもfacebookで知ったのですが、OBらが中心となって遺骨の捜索も行われています(右は、神戸新聞記事です。)
■卒業後は、つながりが切れてしまったと書きました。しかし、卒業後に、母校に行ったことがあるのです。阪神淡路大震災のときのことです。当時、兵庫県教育委員会に勤務していたこともあり、県職員の仕事として被災地・神戸に派遣された。派遣された先が、なんと母校・兵庫高等学校だった。母校は避難場所でした。今でも、晩、図書室で毛布にくるまって眠ったことを思い出します。
父の好きだった蔓薔薇

■老いた母の生活介護のために、週1回、母の家に通っています。「子守り」ならぬ「親守り」です。介護保険で毎日ヘルパーさんが来てくださっているので、とりあえず週1回でなんとかなっています。ご近所の皆さんのお心遣いもにも感謝です。とはいえ、身の回りの世話や買い物に加えて、春になると庭に雑草が生い茂るので、たびたび除草作業が必要になります。これは私がしなければなりません。ひどい庭なんです…。ひどい庭なんですが、この季節は、庭の蔓薔薇が満開になります。
■この蔓薔薇、4年前に亡くなった父が好きでした。ただし、父も含めて両親はこの蔓薔薇や、庭の手入れをしていなかったですね~。庭というものは、丁寧に世話をしてなんぼのものですが、うちの両親は世話をしていなかった。無秩序に樹が植わっています。その剪定と消毒は業者さんにお任せしていますが、庭の除草は私がしなくてはいけません。今日は、その除草作業の日でした。以前は、手作業でやっていたのですが、最近は、家庭用の電動草刈機を使っています。ずいぶん楽になりました。とりあえず、なんとかご近所にご迷惑をおかけしない程度には除草をしました。とはいえ、1ヶ月しないうちに、また庭は雑草でいっぱいになります・・・。仕方ありませんね~。
誕生日

■1970年頃、普通の会社員の定年退職は、55歳だったように思います。55歳で定年というと、退職後の残りの人生はずいぶん長いように思えますが、調べてみると当時の平均寿命は69.31歳でした。今よりも、10歳程短いわけですね(ちなみに1970年で55歳というと、大正4年生まれということになります)。さて、単純には比較できないわけですが、本日、私もとうとうその年齢になりました。昔であれば、今日が退職日ということになります…。そのように考えると、少し感慨深いものがあります(…ような気がする)。とはいえ、私が若い頃の55歳のイメージとは異なり、どう考えても「成熟した…」という感覚はありません。もっとも若い頃は、55歳の男性を勝手にそう見えていただけ…なのかもしれませんね。
■「初老」という言葉を聞いたときに、何歳ぐらいから「初老」というかご存知でしょうか。じつは40歳です。現代社会であれば、40歳といっても、まだ青年の延長線上の気持ちなのではないかと思います。しかし、本来的な意味でいえば、40歳からが初老なのです。昔は、栄養状態が悪く、医療も貧弱、若くして多くの皆さんが病気で亡くなりました。おまけにたびたび飢饉等に苦しめられました。おそらくは死が日常生活のなかに、当たり前のように存在していたのだと思います。そのような時代であれば、40歳が老いの入り口「初老」というのは、なるほどな〜と納得できるわけです。現在、還暦を迎えた方に老人という叱られてしまいます。おそらく「初老」にしても、50歳代後半をイメージする人が多いのではないかと思います。東アジア全般にあった「老の文化」は、どうなってしまったんでしょうね〜…。かつては、老いた人には、老いた人なりの役割と存在感がコミュニティの中に存在していたのですが。
■50歳を超えてからも以前と同じように、あるいは以前よりもさらに仕事に励んできました。体力はあるほうだとは思いますが、それを良いことに健康管理を怠ってきました。いけません。ということで、55歳の誓いです。
・酒量を減らす。
・ランニングに励む。
・良く睡眠を取る。
・プライベートの時間も大切にする。
■この誓いをどこまで守れるのか、私にもよくわかりませんが、少し生活のあり方自体を考え直してみようと思います。
■ところで、トップの写真について説明します。晩に、研究室にいると、お隣の学科の同僚と学生が夕食を誘いにきてくれました。仕事を終えた妻が夕飯の買い物をする前だったので、合流させていただきました。そして、教員2人、学生2人、あわせて4人の皆さんから、誕生日を祝っていただきました。みなさんには、感謝です!家族でのお祝いは、同じく4月生まれの長男と一緒に…かな。連休中、長女と長男、子どもたちが帰省したときになると思います。