50年ぶり

▪️この写真は、小学校4年生の時の集合写真です。当時、私は、福岡県北九州市戸畑区にあるカトリック系の私立の小学校、明治学園小学校に通っていました。といいますか、両親の方針で通わされていた…というのが正しいのかなと思います(特に、両親がカトリックを信仰していたわけではありませんが)。この小学校、元々は現在の九州工業大学の前身である専門学校が、教職員の子弟のために1910年(明治43年)に設立したのが始まりです。第二次世界大戦後は、カナダ系のカトリック修道会に経営が引き継がれました。そのような学校の歴史はともかく、自宅は、小倉区(現在の小倉北区)にあった日本住宅公団が建設した団地でしたから、その団地から1時間以上バスに乗って通学していました。
▪️この写真は1968年の4月に撮ったものです。私「4年2組」でした。集合写真の先生。左が1組の担任のM先生。ベテランの先生ですね、たぶん。次がA校長先生。その次が担任のI先生。山口県のご出身でした。ご健在ならば、今は73歳かな。そして、その隣は3組の先生。お名前は忘れました。私は前から3列目の、右から7番目です。10歳です。じつは、この中に写っている同級生と、もうじき会えることになりました。50年ぶりです。記憶も、もう曖昧なんですが。
▪️母親が暮らしていた家の荷物を整理する時、アルバムや写真を「救出」しました。そのようなアルバムの中の1冊を眺めながら、かすかに覚えている同級生の名前を思い出していきました。その中のお一人。Hくん。ネットで検索すると、たまたま動画を拝見することができたのです。普通、なかなかネットで検索しても手掛かりはなかなかありませんが、彼の場合はお仕事の関係でそのような動画がネット上に存在して、たまたま拝見することができたのです。女性だと名字がご結婚されて変わっている場合が多いですし、まず手がかりはありません。そのようなことはともかく、動画の男性の面影は、私の記憶のなかにある同級生でした。間違いありません。気分が高まり、会いたくなりました。
▪️うまい具合に、人のつながりの中で連絡先もすぐにわかり、メールを送ってみることにしました。すると、驚いたことに、今朝ほど、メールを送ったHくんから返信がありました。仕事の関係で、今は関西におられるようです。彼に、会いに行ってこようと思います。子どもの頃、父親の転勤により私は転校が続きました。昔の友だちとのつながりは、切れてしまっています。そのため、私にはいわゆる「地元」がありません。ただ、還暦を迎えた今年から、チャンスがあれば昔の友だちと再会しようと少しだけではありますが努力?!をしています。その努力が少し実ったのかもしれません。
【追記】▪️関連するエントリーです。「小倉時代」。
真野浜のサンライズ(大津市堅田)
▪️水草の有効利用を目指す市民グループ「水草は宝の山」に参加しています。このグループ、略して「水宝山」の代表・山田英二さんが、facebookに真野浜の日の出の風景を度々アップされています。YouTubeにアップされた動画です。とても素敵な動画なので、このブログでもご紹介したいと思います。コマ落としですので、雲の動き等は早くなっています。早くなっているからでしょうか、いつもとは違う琵琶湖を感じ取ることができます。
生涯学習と地域づくり
▪️学外の、全く関係のない別々ところから、生涯学習に関する問い合わせというか、相談がありました。私は生涯学習の専門家でもなんでもないので、ちょっと弱ったな…というのが本音なのですが、お話しを伺ってみると、「これからの時代の新しい方向性を模索したいので知恵を貸して欲しい」ということのようです。地域社会に、生涯学習の成果を一層活かしていくためには、どうしたら良いのか…というような、それぞれの組織の課題もあるようです。
▪️以前、私が生涯学習に関連する取り組みに関わったのは、岐阜県内の「地域づくり型生涯学習」に関する講演会やワークショップ等でした。講師としての立場なのですが、いろいろ勉強させていただきました。その時の経験は、今もとても役に立っています。とはいえ、いつまでもたっても生涯学習に関しては「素人」でしかありません。
▪️ところで、このような生涯学習ですぐに頭に浮かんでくる世代といえば、企業等を退職された高齢者の方達です。今年、還暦を迎えた私も、そのような高齢者予備軍の1人です。私の場合は、退職は、私立大学ということもあり、まだ8年先のことなのですが、同級生は退職か再雇用の時期を迎えています。みんな、どうしていくのかな。そんな私のことはともかく、少し前の時代には、地域づくりの担い手として前期高齢者の皆さんが期待されていました。実際、私の実感としても、日本の地域社会は元気な前期高齢者の方達が支えているという実感がありました。しかし、少しずつ状況が変わってきました。
▪️今は、高齢者になっても、生きていくために働かねばならない、働く必要があると考える方達が増えてきました。年金制度だって、どうなるのかわかりませんしね。そうなると、地域づくりの担い手って、これからどうなっていくのかなと…私などは少し心細くなります。ただ、そのような変化の中でも、再雇用で勤務しながらも、地域づくりに仲間と取り組もうとされている方達がおられるようです。そういう方達に、いろいろお考えをお聞かせいただきたいなと思います。そのような方達の多くは、「団塊の世代」の後の方達です。世代論的な議論は、あまり生産的でないかもしれませんが、これまでとはまた違った動きが生まれているような気もします。
3回ゼミ生の面談と自己分析セミナー
▪️3回ゼミ生の皆さんへの連絡です。連絡は2つあります。
(1)面談について
▪️ゼミでも伝えましたが、10月の第1週、10/1から10/4までの間で、3回ゼミ生の面談を集中的に行うことにしました。「ゼミ面談強化週間」です。これまでゼミの面談は、ゼミ生の自主性に任せていました。ゼミ生が必要を感じたら随時行っていました。しかしそのようにしていると、卒論への取り組みが先送りになる傾向が強く、ゼミ生自身が自分で自分の首をしめることにもなりかねません。さらには、その矛盾が、卒論提出前の期間に私に向かって「噴出」してきます。ということで、今年度は、定期的に面談を行うことにしました。本当は、こういうのって、よくないんですけどね。
▪️もちろん、空いている時間には、随時面談をしますので、メールで申し込んでください。LINEは使わないでください。メールできちんと丁寧に、面談を申し込んでください。予約を受け付けた段階で、このブログの「2018年度ゼミ面談の記録」に予約状況を追記していきます。確認をしてください。
(2)自己分析セミナーについて
▪️キャリアセンター主催の「自己分析セミナー〜自分を知ることから始めよう〜」を、脇田ゼミでは、10月23日の15:20から開催します。場所は、3号館の315教室になります。セミナーの主旨は以下の通りです。お知らせからの抜き書きです。
キャリアセンタースタッフがファシリテータとなり、個人ワークを通じて、これまでの経験の振り返りを行い、就職活動を行う上で必要となる自身の強みや価値観の再発見・再認識することを目的としています。
自身の強みや価値観などの明確化は応募先選択や働く上での価値観に繋がり、今後の新決定に向けた活動の根幹となります。
義父の米寿の祝い
▪️昨日は、義父の米寿の祝いが奈良の「あやめ館」というお店でおこなわれました。以前暮らしていたマンションのすぐそばにあるお店です。長年連れ添ってこられた義母。義父と義母の2人の娘。その連れ合い2人(そのうちの1人は私です)。そして社会人となってそれぞれの職場で頑張っている2組の娘夫婦の子どもたち、つまり孫が4人。孫の連れ合いも1人。そしてそして1歳半になったひ孫もみんな揃い、11人でお祝いをしました。食事の後は、花束と、お祝いしたみんなからのメッセージを書いた色紙を贈りました。
▪️普段、義父は家族専用のSNSを通して、ひ孫である ひなちゃん の日々の成長や、孫たちの頑張っている様子を楽しみにしているようです。SNSを使って、孫やひ孫の様子を知ることができるように、iPadをプレゼントされているのです。昨日、義父は、ひさしぶりに孫とひ孫全員に会えました。人生の幸せは人それぞれですが、孫やひ孫に囲まれるというのは、そのような幸せの1つなんじゃないでしょうか。大切だと思います。思い起こせば、すでに社会人になった孫4人がまだ3人の頃、みんなで還暦のお祝いをしました。ついこの間のような気がします。あっという間ですね。
▪️還暦の頃、義父は、米寿になる頃のことを想像していたでしょうか。昨日は、そのことを聞きそびれました。私自身は、今還暦ですが、とても米寿まで長生きできる自信はありません。でも、孫のひなちゃんが成人した時に、一緒に飲みに行ける程度には体力と健康を残しておきたいなと思っています。でも、どうなるでしょうね。それは19年後です。これも、あっという間でしょうね。楽しみです。こうやって世代を超えて集まることは、その機会に、人生についていろいろ考え学ぶことになります。大切なことだと思いました。
▪️昨日は、老人ホームに入所している母の見舞いにも行きました。昨日は、老人ホームの「秋祭り」でした。ホームの中では、職員さんたちも着物に着替えるなどして、いろんなゲームや催しを楽しんでおられました。私の母親は、すでに寝たきりの状態ですが、リクライニングの車椅子で居室から出て少し「秋祭り」を楽しんでいたようでした。母は食欲はあるようで、寝たきりの状態ではありますが、身体の方はなんとかなっています。ただ認知的な部分では、どんどん曖昧になってきているような気がします。息子の私と、ひ孫のひなちゃんのことはなんとかわかるようです。
▪️亡くなった父の看病と看取りから始まり、そのあとは母の世話で10年たちました。実際に、ご自宅で介護された方たちのような大変な苦労はありませんでしたが、それでもいろいろありました。こちらも、今となれば、その過程でいろいろ学んできたんじゃないか、これからも学び続けるんじゃないのか、そのように思うわけです。
秋の庭

 ▪️庭に植えてある低木、オトコヨウゾメに赤い実が成っています。オトコヨウゾメは、北海道を除いて、日本中の雑木林に普通に見られる低木です。春には小さなややピンクの白い花がたくさん咲きます。そして秋には赤い実がなります。果実酒にもなるという情報があり、研究してみることにしています。
▪️庭に植えてある低木、オトコヨウゾメに赤い実が成っています。オトコヨウゾメは、北海道を除いて、日本中の雑木林に普通に見られる低木です。春には小さなややピンクの白い花がたくさん咲きます。そして秋には赤い実がなります。果実酒にもなるという情報があり、研究してみることにしています。
◾️このオトコヨウゾメは、庭の大改修の際、庭師さんが庭のデザインを考えて中央に植えることを提案してくださいました。その周りには石で回廊を作られ、草花が植えられています。とはいっても、もともと小さな庭ですので、回廊とは言っても大したことはありません。草木の世話をしやすいようにと、石を並べて作った小さな小さな通路といった感じです。おかけで、毎日の世話がとても楽になりましたし、丁寧に世話ができるようになりました。
◾️2枚目の画像。以前にもこのfbに書きましたが、美しい花と香りを楽しんでいたクチナシなんですが、スズメガの一種であるオオスカシバの幼虫に丸坊主にされてしまいました。左がそのクチナシです。幼虫に歯を食べられるていることに気がついたときは、丸坊主状態だったのです。その手前に、家庭菜園でトマトやシシトウ、それからオクラを植えていたものですが、なかなか気がつくことができませんでした。幼虫に気がついてからは、毎日丁寧に観察して幼虫は自分の手で駆除することにしました。できるだけ、薬は撒きたくないからです。そうやって手で駆除していたせいか、また、美しい若葉が出てきました。頑張って欲しいです。来年もまた花を咲かせてくれると思います。安心しました。

 ▪️ホームセンターで衝動買いした多肉植物も成長しています。お店では、小さな鉢で売られていたのですが、自宅にあった大きな鉢に移し替えて寄せ植え風にしてみました。本当は、もっときちんとデザインをしてかっこよく植えたかったのですが、初めてのこともあり、あまり美しい配置にはなっていません。大きなものを後ろに、小さなものを前にとか、色々工夫ができたはずなんですが…。お恥ずかしい…。
▪️ホームセンターで衝動買いした多肉植物も成長しています。お店では、小さな鉢で売られていたのですが、自宅にあった大きな鉢に移し替えて寄せ植え風にしてみました。本当は、もっときちんとデザインをしてかっこよく植えたかったのですが、初めてのこともあり、あまり美しい配置にはなっていません。大きなものを後ろに、小さなものを前にとか、色々工夫ができたはずなんですが…。お恥ずかしい…。
▪️ただし、元気には育っています。この手の多肉植物は、ほとんど水をやりません。ただし、お日様によく当てるようにします。大した世話はしていないのですが、随分大きくなってきました。気を良くして、やはりホームセンターで売れ残った安売りの小さな多肉植物も衝動買いしてしまいました。1つ、150円ほどの安さでした。まあ、値段のこともありますが、何よりも多肉植物は可愛らしいものですから。多肉植物は、とても個性的な姿をしています。それに、それほど世話も難しくなさそうなので、もう少し種類も増やしてみようと思います。そのうちに、サボテンなんかも衝動買いしてしまうからしれません。

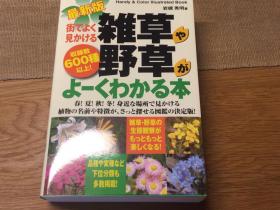
▪️ところで、庭にいわゆる「雑草」が生えてきたとき、私の「審美眼」で、「生かしておく/抜いてしまう」を決めています。これは、「生かしておく」ことにしました。「生かしておく」方になると、「雑草」から「野草」ということになります。随分、勝手な話しですね。「審美眼」と書きましたが、実のところそんな見識があるわけではありません。なんとなく「いいな〜、かわいいな〜」と思ったものですから。
▪️写真の「野草」、家に置いてある図鑑でなんていう草なのか調べてみました。ところが、何度見てもわかりません。そこで、岩手にお暮らしの親切な植物学者、島田直明さんに写真を送り同定していただきました。する「どこにでも生えている、イノコヅチという雑草です」とお返事かすぐに届きました。ありがとうございました。どこにでも生えているらしいのですが、どういうわけか図鑑には載っていません。なぜなんだろう。島田さんのご意見では、あまり目立つ要素がないので、図鑑に載せるべきリストから排除されたのでは…とのことでした。ネットで調べてみると、このイノコヅチという草は食べられるらしいのです。ただし、先ほどの島田さんによれば、湯がいてアク抜きをすると良いみたいです。今年は、もう成長しすぎたので、来年、挑戦してみようと思います。
▪️小さな庭ですから、農薬は使わずに、困った草も虫も自分の手で駆除してきました。そうしながら、自然に生えてくる草を庭造りに活かしていければと思っています。自然な風合いの庭造りを目指しています。鳥、蝶、蛾、バッタ、コオロギ、蜘蛛、ダンゴムシ、ナメクジ、ミミズ、トカゲ…。この小さな庭にたくさんの生き物が暮らしています。そうそう、池の中や睡蓮鉢のヒメダカと、ケースの中で飼っているクサガメもいますね。いろんな生き物を、自分の庭で飼っていると思うと、少し豊かな気持ちにもなります。とはいえ、現在、タマスダレやジューンベリーをムシャクシャと食べてしまう蛾の幼虫たちには、毅然と立ち向かっています。
後期の「大津エンパワねっと」の授業が始まりました!!





▪️昨日から、後期の授業が始まりました。私が担当する授業は今日から。1限に打ち合わせをして、2限は地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の授業を行いました。この「大津エンバワねっと」では、前期に地域で学生たちがお世話になっている方達をお招きして報告会を実施することになっています。ところが、台風で延期になりました。「大津エンパワねっと」の活動は、大学に隣接する瀬田東学区と、中心市街地の中央地区の2箇所になりますが、中央地区については12日に報告会を中央学区市民センターで開催しました。瀬田東学区は来週になります。
▪️今日は、すでに報告会を済ませた中央地区で活動するチーム「しんごうブラザーズ」とチーム「サクらんぼ」から、前期の活動で見えてきた地域の特性や地域課題の特徴と、同時に浮かびあがってきた課題等について報告が行われ、全員で討論を行いました。すでに地域の皆さんから様々なコメントをいただいた上での報告になります。地域の皆さんの鋭いご指摘や、自分たちが活動の中で気がついたこと、専門家の指摘…様々な事柄が学生の皆さんの中で良い具合に発酵してきているように思います。個人的な見解ですが、例年の学生チームのテーマよりもハードルの高いテーマで頑張っています。まだゴールは先のことになりますが、そこに向かう手かがりは得られたのではないでしょうか。瀬田東学区の報告会は来週開催され、そこでの地域の皆さんからのご指摘を踏まえた前期のまとめの報告が行われる予定です。
大学と社会をつなぐ
▪️龍谷大学社会学部に勤務して以来、ずっと大学の地域連携に力を注いできました。地域連携型の教育プログラムの開発と実施だけでなく、カリキュラム外(単位や評価がない)の地域連携の実践にも学生と一緒に取り組んてきました。前者の代表は「大津エンバワねっと」ですし、後者はゼミの有志で取り組んでいた「北船路米づくり研究会」や「おおつまちづくり学生会議」などの活動がそうかと思います。また、行政の委員会や審議会の委員等も、できる限りになりますが就任してきました。そのような行政組織とのつながりや、委員会や審議会での人との出会いが、後の様々な活動に結びついていくことが多々ありました。そうやっているうちに、すっかり私は自他共に「地域連携系の教員」(地域連携を大切にする教員)ということになってきました。おそらく、退職するまでこのような「傾向」が変わることはないのではないかと思います。
▪️ゼミ有志で活動していた「北船路米づくり研究会」では、大津の中心市街地と比良山系・蓬莱さんの麓にある棚田の農村・北船路を結ぶ活動に取り組みました。そのような活動の中で、北船路で生産した酒米を原料に、大津の古い酒蔵(平井商店)で、新しい日本酒の銘柄をプロデュースするプロジェクトがありました。純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」が製造・販売されるようになりました。新しいプロデュースした日本酒は、大津商工会議所による大津の中心市街地の名産品「大津百町百福物語」の一つとしても選定されました。
▪️先日のことになりますが、酒蔵の社長さんから電話がかかってきました。私たちのゼミでプロデュースした日本酒やその取り組みに関心を持った某・国の役所から、ぜひ連絡を取りたいと言ってきている、というのです(現段階では某です…)。メールでやり取りをした後、その役所の方達が大学と連携したい事業の内容に関連しそうな学内の部署とをつなぐことにしました。所属する社会学部教務課の課長さんにも協力していただきました。その結果、学生の皆さんにも有益なちょっとしたイベントが実施できそうになってきました。人と人をつなぐことのから、人の新たな出会いのなかから、素敵な出来事が生まれてきました。こういうことは、しばしばありますが、学生の皆さんにも、ぜひそういうことを何かの機会に実感してもらいたいなあと思っています。餅は餅屋と言います。世の中には、様々な専門性を持った方達がおられます。そういう方達をつないでいく、言い換えれば、関係をデザインすることで社会が素敵になっていく、そういう役割をする人の存在が、ますます重要になってきているように思います。
▪️同様のことは、「地域連携」だけでなく「研究」の分野でも重要になってきているように思います。実際、そのような取り組みを初めています。もっと正確にいえば、「地域連携」と「研究」をつなぐということになります。詳しくはまだ書けませんが、そのうちにこのブログでも報告できるのではないかと思います。ちょっとワクワクする取り組みです。
「地域再生の社会学」
▪️金曜日の3限目には、担当している講義があります。前期は「地域社会論」、後期は「地域再生の社会学」です。前期の「地域社会論」は、例年履修者が100人程度のところに360人を超える登録がありました。履修できるのは、社会学部の全ての学科の2年生以上の学生さんです。もちろん、私の講義に人気があるわけではありません。学生さんたちの話しによれば、、金曜日は授業が少なく履修できる授業があまりないのだそうです。加えて、できるだけ効率的に単位を取得しようと思うと、できるだけコマを詰めた時間割にしたいのだそうです。ということで、積極的な理由からではなく、そのようなある意味「少ない選択肢の中で、この授業でもとっておこうか」という人が多かったのですね。360人いても、例年通り、記述式の試験にしました。もちろん、採点は大変な作業でした。苦労しました。
▪️では、後期の「地域再生の社会学」の履修者はどうなるのだろう…と心配していましたが、大丈夫でした。履修できるのは、前期と同様に社会学部のすべての学科の3年生以上の学生さんです。履修者は、例年と同様に50人程度でした。旧カリキュラムでは「地域社会論I」と「地域社会論II」を担当していましたが、前期が100人程度、後期が50人程度の履修者でしたから、通常に戻ったという感じでしょうか。
▪️ということで、学生の皆さんに、(1)履修動機と(2)扱ってほしい内容について、小さな用紙に書いて提出してもらいました。履修動機については、前期「地域社会論」を履修したので、それにに引き続いて履修したという人が結構な人数になりました。これは、ありがたいことですね。また、授業の中で扱ってほしいことについても、具体的に書いてくれている学生さんがおられました。できるだけ、授業の内容に反映できるように努力しようと思います。
ブルーギルの激減
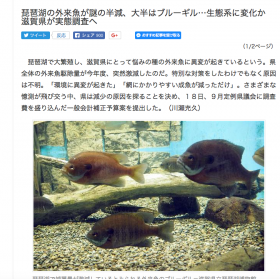 ▪️先日、ショックな報道がありました。ネットのニュース、産経新聞の「琵琶湖の外来魚が謎の半減、大半はブルーギル…生態系に変化か 滋賀県が実態調査へ」です。「問題視されていた外来魚が減るんだから、いいんじゃないの」という意見もあると思いますが、外来魚とはいえ、急に特定の魚種が減少してしまうことの背景に、どのような原因があるのか、大変気になるところです。琵琶湖の生態系に何か変化があるのか、その点も気になります。何かよくないことの予兆ではないことを祈りたいです。
▪️先日、ショックな報道がありました。ネットのニュース、産経新聞の「琵琶湖の外来魚が謎の半減、大半はブルーギル…生態系に変化か 滋賀県が実態調査へ」です。「問題視されていた外来魚が減るんだから、いいんじゃないの」という意見もあると思いますが、外来魚とはいえ、急に特定の魚種が減少してしまうことの背景に、どのような原因があるのか、大変気になるところです。琵琶湖の生態系に何か変化があるのか、その点も気になります。何かよくないことの予兆ではないことを祈りたいです。
▪️いろんな方達のネット上での意見や考えにも注目しています。釣り人の方達の意見が気になります。このような激減の兆候を、もっと早い段階から気づいておられた方が結構おられるようです。南湖の水草の減少とブルーギルなどの産卵床の関係についての指摘もありました。