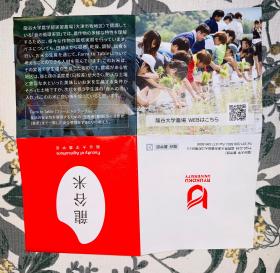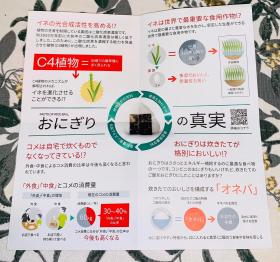龍谷米「つきのあかり」をいただきました。
 ■先日、「龍谷米」を自宅でいただきました。「つきあかり」という銘柄のお米です。瀬田キャンパスの南側に隣接する田上(たなかみ)、その田上の牧地区にある龍谷大学農学部実習農場で生産されたものです。キャンパス内で開催されていた試食と販売のイベントで購入したものです。写真ですが、写真を撮る前にパッケージを破ってしまいました。でも、雰囲気はこんな感じ。説明もきちんとついています。これで2合になります。
■先日、「龍谷米」を自宅でいただきました。「つきあかり」という銘柄のお米です。瀬田キャンパスの南側に隣接する田上(たなかみ)、その田上の牧地区にある龍谷大学農学部実習農場で生産されたものです。キャンパス内で開催されていた試食と販売のイベントで購入したものです。写真ですが、写真を撮る前にパッケージを破ってしまいました。でも、雰囲気はこんな感じ。説明もきちんとついています。これで2合になります。
■「つきあかり」ですが、試食した際に「味が濃いな〜」と思って購入しました。あらかじめ、ネット上の説明を調べて見ました。このような説明がありました。「炊き上がりが艶やかで輝いていたことから名付けられた「つきあかり」は、あの大人気ブランド米『コシヒカリ』にも負けない美味しさを持っているとも言われています」。実際に炊き上げて驚きました。本当に艶やかに輝いていました。しかも、普段いただいているお米よりも粒が大きいです。これはどうしてなのかなあ。もちろんも、味も良いです。近くのスーパー等では、なかなか手に入らない銘柄です。お米は、できるだけ県内、しかも自宅に近いところで生産されたお米をいただきたいと思っています。できれば、農家から直接購入させていただくのが理想です。
ランチにホットドッグ
「龍谷米」の食べ比べ

 ■昨日のことになりますが、龍谷米の食べ比べのイベントに参加しました。農学部の農場で収穫された6種類の米を食べ比べてみました。その上で、「つきあかり」と「にじのきらめき」を2合ずつ購入しました。どの品種のご飯も美味しいのですが、特にこの2つの味が濃いように感じました。でも、どうでしょうね〜。自分の舌に自信がありません。自宅でも食べ比べてみます。農学部の学生と職員さんたちが取り組んでいるイベントです。若い学生の皆さんは、どう感じられたでしょうね〜。
■昨日のことになりますが、龍谷米の食べ比べのイベントに参加しました。農学部の農場で収穫された6種類の米を食べ比べてみました。その上で、「つきあかり」と「にじのきらめき」を2合ずつ購入しました。どの品種のご飯も美味しいのですが、特にこの2つの味が濃いように感じました。でも、どうでしょうね〜。自分の舌に自信がありません。自宅でも食べ比べてみます。農学部の学生と職員さんたちが取り組んでいるイベントです。若い学生の皆さんは、どう感じられたでしょうね〜。
■私が指導しているゼミでは、以前、「北船路米作り研究会」を組織していました。湖西の棚田の農村・北船路の棚田で生産した「龍大米」を販売していました。農学部は「龍谷米」ですが、私たちは「龍大米」です。微妙に名前が違っています。龍大米は、環境こだわり米の「コシヒカリ」を天日干しで乾燥させたものでした。収穫量は、当然のことながら農学部の農場で生産した「龍谷米」の方が多いわけなんですが、「龍大米」の方が「龍谷米」よりも先行しています。農学部が開設される前の話ですから。まあ、食べ比べをしながら、そっと「龍大米」のことを思い出したのでした。
■場所ですが、瀬田キャンパス、Steamコモンズの「Global Lounge & Kitchen)エリアです。ここで、秋に「蜂蜜とジャム」のイベントができたらいいな。農学部の古本先生とのコラボ。1回生の皆さんが、企画から参加・参画します。

農学部・古本強先生の養蜂を見学。







■火曜日の2限は、「社会学入門演習」です。昨日は、農学部の古本 強先生に、瀬田キャンパスに隣接する田上の堂という集落まで連れて行っていただきました。古本先生は、堂で、大学院生と養蜂に取り組んでおられます。その様子を拝見しにいきました。
■たいした距離ではないのですが、オンライン授業のためにパソコンをリュックに入れて担いでいる人もいて、ちょっと大変だったかな。あと、自然がいっぱいが得意でない…せいなのか、ミツバチの巣箱に近づけない人も多数。そのような中、3人の女子学生が刺されないように帽子を被せてもらって、巣箱に近付いてじっくり観察してくれました。
■さて、6月9日に、この堂の養蜂で採取したハチミツのイベントが開催されます。蜂蜜の販売会です。農学部が主催ですが、指導している「社会学入門演習」の有志の学生の皆さんと私も、販売会のお手伝いする予定です。また、ハチミツや身の回りで採れる食べられる植物(たとえばヤマモモやノイチゴとか、庭でも収穫できるジューンベリーとか)を使ったイベントを、古本先生にもご指導いただきながら、秋に開催しようと思っています。いずれのイベントも、瀬田キャンパスにあるSTEAMコモンズ「Global Lounge & Kitchen」で開催することになります。「社会学入門演習」では、秋に開催するイベントの企画をグループに別れて考えてもらおうと思います。
西川さんの慰労会


■昨日は、西川忠雄さんの慰労会でした。西川さんは、滋賀県庁農政水産部長をお務めになり、今年の3月に退職されました。私は、日本農業遺産や世界農業遺産申請のお手伝いをしてきたので、仕事上のつながりもあるのですが、それよりも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、楽しい時間を一緒に過ごさせていただいた飲み仲間といった方が良いかと思います。「利やん」友達です。あのBS-TBS「吉田類の酒場放浪記」にも、2人でカウンターに座っているところが写っています。まあ、そんなこともあり、昨日は西川さんの慰労会だったわけです。であれば、いつもの「利やん」で慰労会ということになるのですが、昨日は、京都の木屋町の小料理屋「喜幸」(きいこ)さんのお世話になりました。当初は、2人だけの慰労会でしたが、現役の部・次長さんもご参加くださいました。
■「喜幸」では美味しい川魚をいただくことができます。店主の浅井喜美代さんが鴨川で自ら獲ってこられた川魚の他、琵琶湖の魚も仕入れておられます。ただ、そのような「喜幸」でもビワマスはなかなか手に入らないとのことで、メニューにはのぼってきていませんでした。しかし、西川さんのご紹介で西浅井漁協から直接入手できるようになったのです。西川さんのおかげで、ビワマスは「喜幸」の定番のメニューにしていただけるようになりました。ということで、昨日の慰労会は「喜幸」での開催となりました。
■写真は、ビワマスの炙りです。炙ることで皮の下にある旨味を上手に引き出しておられます。とても上品な旨味です。昨日は、部・次長のお二人がお手製の鮒寿司を持参されました。鮒寿司、ひさしぶりでした。美味しい料理をいただきながら、京都伏見のお酒を4銘柄ほど温燗にしていただきました。けっこうな量をいただき、何をお話したのか、所々、記憶も危うい感じです…。慰労する側が、飲みすぎてはいけないのですが。大切なことを2つ。
■ひとつは、世界農業遺産関連のことです。もう少し先のことになりますが、国連食糧農業機関(FAO)の現地審査会が行われるので、そのお手伝いを少しさせていただくことになりました。日本農業遺産の時と同様に、微力ながらお役に立てればと思っています。考えてみれば、歴代4人の農政水産部長のもとで、日本農業遺産・世界農業遺産の認定に向けての作業のお手伝いをすることになるので、ちょっと感慨深いものがあります。
■ふたつめ。これは理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の「びわぽいんと」について。世界農業遺産や環境こだわり農業関連で、生産者と消費者をつなぐ仕組みとして「びわぽいんと」が使えるよねという話にもなりました。どう展開させていくのか、またいろいろ相談をさせていただこうと思います。
【追記】■2018年1月1日にBS-TBSで放映された「吉田類の酒場放浪記~あけましておめでとう2時間スペシャル!▼幕末・維新の東海道を歩く」の大津(宿)の酒場として取り上げられたのが「利やん」でした。写真の通り、西川さんと私は隣に並んでいます。

細口のポット

■昨日は帰宅時に、職場の最寄駅JR瀬田駅の近くにある、自家焙煎コーヒー&紅茶のお店「マウンテン瀬田」を訪れました。コロナ禍ということもあり、しばらくお店を閉めておられましたが、今日は開店していることを確認した上でやっと訪問できました。最近コーヒーのことを少しずつ勉強していることから、親切な店主さんにいろいろご教授いただきました。
■今日、ご教授いただいた上で購入したのは、まずは細口のポット。これまでは電気で沸かすケトルを使っていましたが、やはりコーヒーにはこういう細口のものが必要なんだそうです。もちろん、豆も購入しました。以前、こちらのお店でいただいたコスタリカのコーヒー豆です。飲んだ後に、鼻にふっと果物のような香りがするのです。もっとも、自宅でその味や香りが再現できるかどうか。美味しいコーヒーの淹れ方について説明したプリントもいただきました。いろいろ勉強です。お茶と同じようにコーヒーも奥が深いな。
ヨーグルト

■滋賀県大津市に転居し、しばらくしてから、「生活協同組合コープしが 」で買い物をするようになりました。その時から、このコープのヨーグルトを買って、毎朝食べるようになりました。
■大学を卒業して、大学院に進学したあたりから、酒をよく飲むようになりました。腸に良くないです。しかも、元々、ストレスが腸に影響することもあり、ずっとお腹に悩んできました。いつも、「困ったお腹やな…」とため息をつきながら悩んできました。そう、緩いのです…。しかし、このヨーグルをしっかり食べるようになると、少しずつ、お腹の調子が変化してきました。
■毎朝、結構な量を食べます。コープのヨーグルトは、このプラスチックのケースに450g入っていますが、毎朝1/3以上1/2未満程度の量をいただきます。このヨーグルトにやはりコープの「オーツ麦たっぷりのフルーツグラノーラ」というシリアルを加えて、さらにバナナも1本も。そして少しだけ、ジャムを加えます。こんな感じでヨーグルトを食べ続けていると、すっかりお腹の調子も良くなりました。子どもの時のように。おそらく、腸内フローラが改善したのですね。よくわかりませんが、ビフィズス菌はBB-12というやつらしいです。生きて腸まで届くらしいです(ほんまかいな…)。