義父母宅の庭の手入れ
 ■先週の土曜日、親子3人で、奈良に暮らす義父母宅の庭の手入れ(草抜き、落葉除去)に向かいました。息子は大阪に暮らしているのですが、自宅からやってきてくれました。義父母の庭、義理の妹が半分ほど作業をしてくれていたし、午前中は風が吹いて涼しかったので、それほど大変ではありませんでした。そもそも、自分の庭の世話でこういうのは慣れているので、草抜き作業等は苦痛ではないのです。
■先週の土曜日、親子3人で、奈良に暮らす義父母宅の庭の手入れ(草抜き、落葉除去)に向かいました。息子は大阪に暮らしているのですが、自宅からやってきてくれました。義父母の庭、義理の妹が半分ほど作業をしてくれていたし、午前中は風が吹いて涼しかったので、それほど大変ではありませんでした。そもそも、自分の庭の世話でこういうのは慣れているので、草抜き作業等は苦痛ではないのです。
■庭の手入れで義母からお小遣い⁈をいただいたので、昼食は親子3人で韓国料理店に行きました。私は、参鶏湯の定食でした。参鶏湯とは、雛鳥の腹の中に、漢方薬にもなる高麗人参、餅米、ナツメ、ニンニク、クルミなどを入れてじっくり煮込んだ料理です。私自身、夏バテはしていませんでしたが、滋養のある料理で精をつけることができたのかなと思います(まあ、気のせいかもしれませんが)。
■義父母の庭の手入れをしながら、亡くなった母親の生活の介護をしていたころのことを思い出した。あの頃、庭の世話には気合が必要でした。もっとも放置しておくこともできず、ご近所に迷惑をかけないためにやっていたというのが正直なところです。庭がきれいになるのは嬉しかったのですが、あの頃は義務感だけでやっていました。もっとも、滋賀に転居し、自宅で庭の世話をしているうちに、先ほど書いたように庭仕事には慣れてきました。ただし、20年後は果たしてそんなことが言えるのかな…と、ふと思いました。その時、子どもたちは今回のように庭の草抜きをやってくれるのかな…と思いました。そして、今日の息子の作業の様子を見ていると、まあ難しいだろうなと思ったのでした。良い息子なんですけどね。
芋焼酎「薩摩宝山」
 ■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。先日、撮った写真です。常連=お店の維持会員ですので、定期的に「利やん」に通っています。いっとき、お客さんが増えてきたかな〜と思っていたら、第7波に突入したら、ドーンとお客さんが減ってしまいました。まあ、そうなりますね。先日は、私と、「一見さん」らしき方がお一人。
■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。先日、撮った写真です。常連=お店の維持会員ですので、定期的に「利やん」に通っています。いっとき、お客さんが増えてきたかな〜と思っていたら、第7波に突入したら、ドーンとお客さんが減ってしまいました。まあ、そうなりますね。先日は、私と、「一見さん」らしき方がお一人。
■写真は、現在、お店にキープしている芋焼酎「薩摩宝山」です。調べみると、こちらの芋焼酎は「綾紫」(あやむらさき)という、皮も中身も紫のサツマイモを原料に使っているようです。すごく甘い良い香りがします。ちょっとフルーティーな感じです。それほど辛口でもなく、口当たりはとても良い感じです。この「薩摩宝山」、もうじき空になります。新しい一升瓶も、この「薩摩宝山」にしようかなと思っています。
■来週の月曜日は、徳島県からお客さんがやって来られます。地域活性化に取り組む若者です。キャンパスは違うけれど、同窓生でもありますね。私の大学院にもいわゆる「もぐり」で来られていました。懐かしいな〜。月曜日は、ビール、近江酒、そしてこの芋焼酎を楽しみながら、琵琶湖のビワマスをいただこうと思います。
庭の茗荷

■庭の世話をする時間がありません。カメやメダカだけは世話をしないと死んでしまうので、メダカのいる鉢や池には水を足し、水槽代わりに使っているカメのコンテナの水を換えました。カメは気持ちがよさそうでした。もちろん、メダカにもカメにも餌をあげました。そうしていると、収穫できていないプチトマトに気がつきました。熟れすぎて割れてしまっていました。ごめんね。その向こうには茗荷が茂っているのですが、覗いてみると、いつのまにか地面から頭を出しているのです。すでに花を咲かせているものもありました。しまった…。ということで、慌てて、汗びっしょりになりながら収穫しました。こんなにたくさん。薬味だけでなく、練り物(さつま揚げ)と一緒に炒めて、中華風にして食べようと思います。甘酢漬けも良いかもしれません。
鹿の角

■水曜日、仕事が終わった後のことになりますが、首の凝りを解消していただくために、いつもの鍼灸院に向かいました。メニエール病に至るまでにはなりませんが、相変わらず首や肩が凝って辛いのです。もっとも緊張性の頭痛はマシになりました。それはともかく、鍼灸院で治療を終えた後か終える前だったか、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」にいるKohki Kawakitaくんから連絡が入りました。「鹿の角が手に入ったので、あげるよ」との連絡でした。川北くんは、定年退職後、いろんなことにチャレンジしてます。川北くんは以前から農業もやっているのですが(兼業農家)、今度は猟師の資格を取ると言っていました。獣害対策かな。そんなこともあってか?!、どこかで手に入れた鹿の角を持ってきてくれたのです。川北くん、ありがとう。もちろん、「利やん」に行って鹿の角を受け取ることにしました。
■「利やん」に行くと、川北くんの横には、なかちゃん(中川俊典さん)が座っていました。アルミサッシ工事の社長さんです。なかちゃんと会うのは1ヶ月ぶりでした。もう何年も前のことになりますが、なかちゃんとは、ホノルルマラソンのタイムを競った仲なんです。なかちゃんからは、「わしの記録よりもワッキーが早く走ったら芋焼酎1本やる。もしワッキーが遅かったらわしが芋焼酎をもらう」という勝負を挑んでこられたのでした。結果として私が芋焼酎を受け取ることになったのですが、昨日も「あれが、今でも悔しい」と言うのです。しつこいな〜(^^;;。まあ、そんな感じで3人でカウンターに座り、アホな話をして楽しい時間をもつことができました。
■その裏側では、「地域エンパワねっと」でお世話になっている安孫子邦夫さんと、「大津の町家を考える会」の雨森 鼎さんがテーブルで飲んでおられました。お2人は仲良しです。時々、私も仲間に入れていただき3人で呑むこともあります。ということで、もちろんお2人ともお話をさせていただきました。そして、そのお隣のテーブルには、某和菓子の会社の社長さんSさんが。なーんだ、みんな知り合いだ。「利やん」はそういうお店なんです。ノーライフ ノー「利やん」。あくまで個人的な感覚ですが、大学の世界だけで生きていると息が詰まってくるような気持ちになります。この「利やん」のようなお店があり、そこで仲の良いご常連と短時間でも一緒に過ごすことで、気持ちが穏やかになります。まさに、アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグのいう「サード・プレイス」(職場でも家庭でもない第三の場所)なのです。
■さて、鹿の角でしたね。これで何を作りますかね。キーホルダー、チョーカー、ペーパーナイフ、他にもいろいろ。万力と金鋸を買って楽しんでみます。
【追記】■下の写真は、2017年12月21日に撮ったものです。なかちゃんから手渡されている芋焼酎は「晴耕雨読」です。赤いセーターの男性は、当時、すでに龍谷大学社会学部を早期退職されていた原田達先生。左の男性は、お店のご常連の杉浦さん。常連の番付では、横綱級の方です。ちなみに、私は最近は自ら大関級と名乗っています。

原田達先生のこと
 ■昨晩は、ひさしぶりに原田達先生と2人だけでお会いしました。
■昨晩は、ひさしぶりに原田達先生と2人だけでお会いしました。
■原田先生は、私と同じ社会学部社会学科の教員をされていましたが、今からたしか6年前に退職されました。まだ、定年まで3年ほど残しておられたのに、さっさと退職されました。それまで、原田先生には、いろいろと私の話を聞いていただいたり、アドバイスをいただいていたので、退職されたことはとても残念でした。でも、人、それぞれの人生に対する考え方がありますから、仕方がありません。
■今日は、実は、東京からお越しのお客さんと京都で夕食をご一緒させていただくはずだったのですが、その方のご予定が変更になったことから、無理なお願いをすることになりましたが、そのこともきちんとお伝えした上で、原田先生にお付き合いいただきました。原田先生、ありがとうございました。
■原田先生には、昨晩、いろいろ最近の出来事などを聞いていただきました。いろいろ聞いていただきましたが、やはり中心は社会学についてでした。有難かったです。励ましていただいたような気分になりました。酒を呑みながらのことなので、翌朝になると記憶も朧げではありましたが、有難かったと思う気持ちだけはしっかり残っていました。コロナのせいで大学の世界からは、今日のような感じで話をする機会が大幅に減ってしまいました。原田先生には、また、一献傾けるチャンスを頂ければと思っています。
甥の訪問
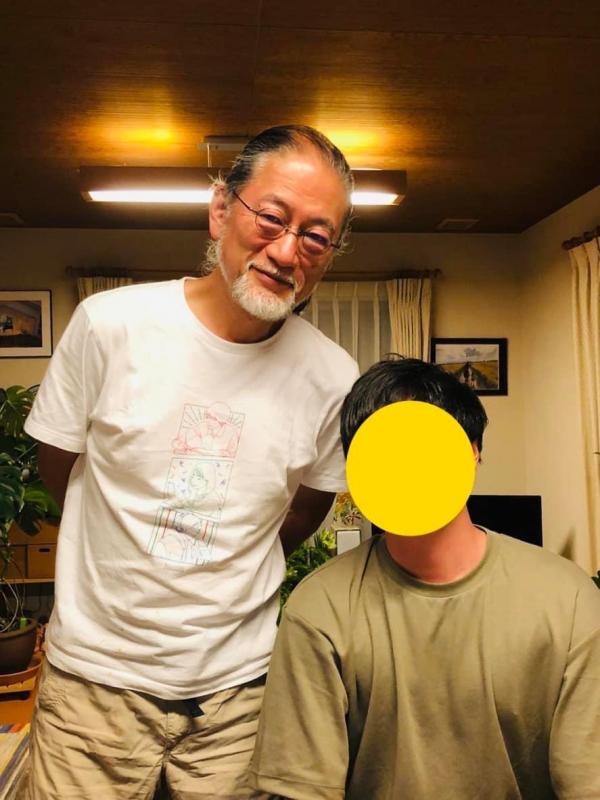
■土曜日の晩は、甥っ子が我が家を訪問してくれました。ある金融機関に勤務しているのですが、この春からは転勤で勤務先がなんと大津になりました。住んでいるのもなんと長等。ご本人にそんなつもりはないでしょうが、伯父さん(私のことですけど…)の縄張りに入り込んできました。
■甥は、中小企業を支える仕事をしています。甥が勤務している金融機関は、中小企業の金融の円滑化を図るために必要な業務を営むことを目的としています。甥自身も、地域の経営者の話を丁寧に聞いて、一緒に頭を悩ませつつ、いろんな人とのコーディネイトもしながら、そうやって支えながら融資していくのだそうです。立派な社会人になりました。頑張って働いているのですね。私は、大学教員で銀行のように融資などできませんが、地域づくりに強い関心を持ってNPO等の活動にも取り組んでいるので、彼の話を聞いていてとても嬉しかったです。
■甥が勤務している金融機関は、全国に支店があって、どこに転勤になるのかわからないのだそうです。次の支店に転勤する前に、大津駅前のいつもに居酒屋「利やん」に一緒に行かなくちゃね。我が家では息子が酒を飲まなくなったし、娘も元々は飲めたのに出産で弱くなってしまいました。彼は、きちんと呑めるので嬉しいです。そう、飲めるではなくて、呑めるです。呼び出しかけます。
エンパワとヤマモモ

 ■ 金曜日2 限は地域連携型プログラム「社会共生実習」のプロジェクト「地域エンパワねっと・大津中央」。
■ 金曜日2 限は地域連携型プログラム「社会共生実習」のプロジェクト「地域エンパワねっと・大津中央」。
■4月から、地域に出て行くために、学生の皆さんはいろいろ勉強をしてきました。自治会の歴史や自治連合会のこと(地域社会学の勉強でもあります)。大津の歴史や現在の概況。先輩たちが「エンパワ」で取り組んだ活動の内容等々、盛りだくさん。先週は、前・中央学区自治連合会会長/現顧問の安孫子邦夫さんにzoomで講義をしていただきました。
■そろそろ、現場に出かけるタイミングになってきました。明日は、2名の学生だけど、まち歩きもします(残りの人たちは来月)。ということで、これまでの勉強で関心を持ったことを、キーワードにして書き出してもらいました。高齢者の問題や、最近増えてきた(マンション建設の結果)子どもたちの問題、中心市街地(old大津)の魅力発信、世代間交流、新住民と旧住民とのコミュニケーション…いろんなキーワードが出てきました。
■これから活動するテーマの前段階のような感じでしょうか。ここから、グループ分けとテーマの絞り込みを行なっていきます。ぜひ、先輩たちが残していった活動の蓄積という資産も利活用しながら、自分たちの取り組みを進めて欲しいと思います。
■授業の後は、こんな感じ。「秋に、農学部の古本先生と一緒に、蜂蜜とジャムのイベントをやるんだけど、2人が企画から参加したいと言ってくれてます(エンパワの学生が)。他の人はどうですか? 考えといて。で、今からジャムの原料になるヤマモモの様子を見にいって、試食してみるんだけど、関心ある人はついてきて」と言ったところ、今日出席していた全員がついてきました。
■現場(場所は秘密…)に到着すると、1人の学生が「これ、知っています。自分が卒業した小学校にありました。私も食べていました」と言ってくれました。慣れた手つきでよく熟した実を取ると、口に入れました。彼女は、九州の出身。彼女は、みんなに熟した実を選んで渡してくれました。恐る恐る口に入れてみていましたが、「甘い」、「すっばい」、「変な香りがする」と色々感想が聞けました。確かに、口に入れて噛んでみると、最初はちょっと薬臭い匂いが鼻を抜けるんですよね。受け止め方には、微妙に違いがありますね。そこが面白い。
■で、ヤマモモには種があるんですが、九州出身の学生は、口からタネをプイッと地面に吐き出しました。ああ、もちろん、木の下の地面にですよ。木の下には、すでに熟して落ちている実もあります。特に、何も問題はないのですが、地面に種を吐き出せない学生もいました。そんなマナー違反はできないというか、気持ちが許さないのでしょうね。きちんと、ゴミ箱に捨てていました。ここも面白いな〜と思いました。状況的に、地面でも問題ないんですけどね。こういう学生が、ヤマモモでジャムを作って食べてくれると嬉しいな。
世界農業遺産の現地調査(4)


■この写真、2016年2月19日の、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」での写真です。世界農業遺産を目指して頑張っていこうと、滋賀県庁職員の皆さんと決起集会を開いたときのものです。あれからコロナ禍もあり6年が経過しました。もうご退職された方、人事異動で世界農業遺産申請作業(その前に日本農業遺産)の仕事から離れた方…いろいろおられます。この時のことを思い出し、写真をひっ張り出してみました。何かちょっと感慨深いものがあります。もし「琵琶湖システム」が世界農業遺産に認定されたら、申請作業に関わった皆さんと喜びを分かち合いたいものです。そして、次のステップに向けて知恵を出し合いたいです。
■知恵を出し合うのも、行政だけではなくて、民間の知恵を大切にする取り組みがたくさん生まれたら良いなあと思います。県庁に何かやってもらうのではなく、世界農業遺産のブランドを民間で上手に適切に使いこなしていくようになればと思います。ええと、これは個人的な意見ですけど。
■1枚目の写真の中央、当時の農政水産部長の安田全男さんです。その少し前のことについても、ここに書いておきます。あくまで、私の個人的な経験ですけど。
■2016年の正月明け頃だったかな…。いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」で、部長の安田さん、そして琵琶湖博物館に私が勤務していた当時の上司で、副知事もされたことのある田口宇一郎さん、このお二人がご機嫌に呑んでおられたところに、私が偶然にやってきて、田口さんに安田さんを紹介されました。安田さんからは「世界農業遺産認定をこれから目指そうと思っている」という話を聞かせてもらい、飲んだ勢いもあってとても話しが盛り上がって、さらに安田さんからは「滋賀県内で唯一農学部のある龍谷大学にも支援してほしい」と言われて、お安い御用とすぐに学長室とつなぎ…という展開の中で、私も世界農業遺産申請のお手伝いをするようになりました。その頃は、すでに庁内で職員の皆さんが申請のための研究や準備を着々と進めておられたと思います。私も、その議論に参加させてもらい、いろいろ意見を述べさせてもらいました。今から思うに、やはり琵琶湖博物館に勤務していた当時の経験がとても役に立ったように思います。
■その後の農政水産部長の高橋滝治郎さんの時代に、東京の農水省までいって日本農業遺産に認定していただくためのプレゼンに同行し、まずは日本農業遺産認定まで辿り着きました。高橋さん、そして他の職員の皆さんたちとは、世界農業遺産の広報を兼ねて100kmウォーキングを4回歩きました。その後の部長、西川忠雄さんの時代は、コロナ感染の時代でした。世界農業遺産に申請したものの、審査がストップしている時代でした。残念でしたが、仕方がありません。そしてこの春からは宇野良彦さんが部長に就任されのですが、FAOが突然審査を再開したのでした。コロナ感染が以前と比較してマシになってきたからでしょう。そして、今回の現地調査が行われたわけです。
■もし、安田さんが直接、龍谷大学に支援の要請に行かれたら、どうだったでしょうね〜…、社会学部にいる私が世界農業遺産に関わることはなかったように思います。そういう意味でも、「利やん」は、安田さんとの出会いを作ってくれたわけです。なんとも、不思議なお店です。
■2枚目の写真。手前のグループ。ひょっとして、佐々木和之くんと近藤紀章くんかな…。2人も知り合いです。君たちいたっけね??
蜂蜜スイーツの差し入れ
 ■火曜日4限(15:15~16:45)は、3回生のゼミ「社会学演習IA」です。今日は、ゼミの開始時に、嬉しいことがありました。うちのゼミは男子ばかりなのですが、そのうちの1人の学生さんが、お菓子を作ってきてくれたのです。
■火曜日4限(15:15~16:45)は、3回生のゼミ「社会学演習IA」です。今日は、ゼミの開始時に、嬉しいことがありました。うちのゼミは男子ばかりなのですが、そのうちの1人の学生さんが、お菓子を作ってきてくれたのです。
■先日、瀬田キャンパスにある「Steamコモンズ」で開催された「Market Place」で蜂蜜が販売され、その蜂蜜を、遊びに来てくれたゼミ生にプレゼントしました。彼はスイーツ作りが趣味とその場で教えてくれたものですから、ぜひ龍大の蜂蜜を使ってスイーツ作って欲しかったのです。まあ、そのようなこともあって、今日は、その龍大の蜂蜜をつかってお菓子を作ってきてくれたのです。非常にしっとりして美味しかったです!! ありがとう。しかもみんなに食べてもらおうと、爪楊枝まで持参してくれていました。やるな〜。
■秋には、農学部の古本先生と先生の研究室のゼミ生のコラボで、社会学部の教員である私や私が指導で関わっている学生とで、「蜂蜜とジャム」のイベントを開催します。その時に、ぜひまた蜂蜜を使ったスイーツを提供もらいたいなあと思っています。また、相談をしてみます。
川北くんのお祝い





■昨日は、午前中から大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行きました。本来、土曜日、「利やん」はお休みなのですが、昨日はお店のご常連である川北くんの「還暦&定年退職」のお祝いのパーティが開催されました。長年に渡り、川北くんとこの「利やん」で交流してきたご常連が集まってきました。思い出になる会にしようと、みんなで餃子を包み、焼いて、そしてお好み焼きも焼いて、楽しい時間を過ごしました。都合がつかず参加できなかった皆様、残念でしたね。また、お店でお会いいたしましょう。昨日は、龍谷大学を64歳で早期退職された原田 達先生もご参加くださいました。ひさしぶりに原田先生ともお会いできました。先生がご退職されてから、もう6年も経ったんですね。時間が経つのは速い、速すぎるな〜。
■「利やん」は、私にとってとても大切な場所、「サードプレイス」です。職場でもある大学の役割からも、家庭における役割からも解放されて、1人の個人としてリラックスできる場所であり、いろんな人のつながりが生まれる大切な場所でもあります。詳しくは、以下の投稿をお読みください。
2015「びわ湖レイクサイドマラソン」/ サードプレイスとしての「利やん」

