日経ビジネス「辺境の地になった日本 生き残る道は世界の“古都” ノンフィクション作家・高野秀行」
辺境の地になった日本。以前、世界的に有名な投資家が「日本は将来、今のヨーロッパのポルトガルのような感じになる」と語っていた。こちらの高野さんも同意見のようだ。うまくいけば辺境の地でも悪くない。今までとは別の「幸せの物差し」を持てれば。https://t.co/rbzKQeqdCa
— 脇田健一 (@wakkyken) March 21, 2022
「国分寺地域通貨ぶんじ」のこと

■時々、このブログで特定非営利活動法人「琵琶故知新」や、「琵琶故知新」でこれから運営していこうと考えている「びわぽいんと」について紹介をしてきました。理事長としての責任の重さをひしひしと感じながら、この「びわぽいんと」を具体的にどのように展開していけば良いのか、そのことについて頭を悩ませています。広い意味で地域づくりの活動に取り組んでこられた方たちに、「びわぽいんと」のことを説明すると、「ああ、地域通貨のようなものですね」と理解してくださいます。よくある地域通貨は、紙幣のようなものを発行して、流通させることで、地域社会の様々な課題を解決したり、活性化させたりしていこうとするわけですが、「びわぽいんと」の場合は、紙幣のようなものではなく、インターネット上で流通させるポイントになります。
■「びわぽいんと」の原理となる仕組みはすでに出来上がっていますが、それをどのようなルールで、どのような具体的な地域社会の活動とつなげながら展開していくのか、今はそのような段階かと思います。ここで乗り越えるべき壁がぐんと高くなりました。ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)だけでは乗り越えられない壁が存在するからです。言い換えればICTを具体的な地域社会というコンテクストの上で、どのようにデザインしていくのかということになります。藁にもすがるような思いで、ヒントになる情報を探しています。先日のことになりますが、滋賀県庁の幹部の方とお話をしたときに教えていただいたことがあります。「皆さんの『びわぽいんと』の話をお聞きして、東京の国分寺市でやっている地域通貨『ぶんじ』のことを連想しました」。ということで、「国分寺地域通貨ぶんじ」について調べてみました。
■「国分寺地域通貨ぶんじ」については、公式サイトがありますから、そちらをご覧いただけばと思います。とても興味深かったのは、この地域通貨が「お金」であると同時に、メッセージカードでもあるということです。地域通貨であるから「お金」の一種であることはわかりますが、メッセージカードとはどういうことなのでしょう。実は、地域通貨「ぶんじ」の裏側には、メッセージを書くことができます。Aさんが、Bさんから何かを買う(物やサービス)時にこの「ぶんじ」を使うわけです。「交換」です。通常、「交換」が成立した時には、AさんとBさんの関係はそれで終了します。「お金」の点だけから考えれば、「交換」が終了した段階で関係が持続する必然性のようなものはありません。しかし、「ぶんじ」は違います。裏側に自分の気持ちをメッセージとして書き込むのです。公式サイトでは、このように説明されています。
金は何かを「手に入れる」ための道具でなく
誰かのやさしさや丁寧な仕事を
「受け取る」ための道具にもなる。そして受け取ってくれる人の存在は
忘れかけていた贈ることのよろこびを、
もう一度思い出させてくれるかもしれない。そして、ぶんじはまた、
次の「贈り手」に向けてめぐっていきます
■「ぶんじ」は、地域通貨です。国が発行している通貨と同様に「交換」されるわけですが、それとともに人をつないでいく、人に思いを伝える「贈与」の側面も持っているのです。そのような「贈与」が人と人とのゆるやかな関係を生み出していくわけです。私が「ぶんじ」に注目するのは、この地域通貨には「贈与」の側面が存在しているからです。公式サイトには、次のように書かれています。「気持ちのこもった仕事に『いいね!』/率先したまちのための汗かきに『ありがとう』/その感謝のメッセージが、働くことのよろこびを思い出させてくれる」。
■この「国分寺地域通貨ぶんじ」については、キーパーソンである影山知明(かげやま・ともあき)のインタビュー記事も参考になります。フコク生命によるインタビュー記事です。この中で、影山さんは、次のように語っておられます。特に、大切だなと思った部分を一つだけ引用させていただきます。
互いに干渉しない、必要以上に立ち入らないという世の風潮もあるように思いますが、うまく関わり、お互いの前向きな重なりをつくれるようになると、1人ではできなかったことが2人だからこそできるということもあるでしょう。それぞれの自由を尊重し合いながらの「他人と共に自由に生きる」道があるのだといいます。
「自分の利益にしか関心がなかったり、自己中心的に考えてしまったりしていると、目の前の一人一人は『利用する(テイク)』対象になってしまいます。そうすると相手も防衛的になり、リターン目当てで関わったりするようになる。こういう関係を続けていくと、奪い奪われで消耗しますから、人と付き合うことが嫌になります。ところが、目の前の一人一人にどうやったら力になれるかと、『支援する(ギブ)』姿勢で関わるようになると、相手もちゃんと返してくれることに気が付く。そしてこうした関わりの方がよっぽど生産的だし、気持ちがよく、長く続くものになります」
■なぜ引用したのかといえば、様々な方たちと連携しようとする中で私自身も強く感じてきたことだからです。地域づくりの活動の中で、研究プロジェクトの中で、大学の組織の中の取り組みの中で…。影山さんが語っておられるのは、「他者を自己の手段や資源にしない関係」のあり方です。とても大切なことかと思います。「他人と共に自由に生きる」、とても素敵な言葉だと思います。さて、私たち「琵琶故知新」の「びわぽいんと」は、よく店舗やスーパーで使われているポイントカードとは違います。そようなポイントカードは、消費者が「自分のため、自分が得をするため」に利用され、そのことで店舗やスーパーも利益をあげることかできるわけです。もちろん、「びわぽいんと」もそのような利用が可能なわけですが、それだけでなく「ぶんじ」と同じく贈与の側面に特徴があります。大津で環境ボランティアで貯めたポイントを、湖北で活動している団体に贈ることができます。その時に、「ぶんじ」のようにメッセージが伴っていると素敵だなと思っています。このあたり、琵琶故知新の理事の皆さんにも、相談をしてみたいと思います。
【追記】 ■「ぶんじ」のキーパーソンである影山知明さんが執筆された『ゆっくり、いそげ ~カフェからはじめる人を手段化しない経済』(大和書房)です。タイトルがいいですね。「人を手段化しない経済」。以下は、この本の紹介文です。
■「ぶんじ」のキーパーソンである影山知明さんが執筆された『ゆっくり、いそげ ~カフェからはじめる人を手段化しない経済』(大和書房)です。タイトルがいいですね。「人を手段化しない経済」。以下は、この本の紹介文です。
働いても働いても幸せが遠のいていくように感じるのはなぜなのか。
金銭換算しにくい価値は失われるしかないのか。
「時間との戦い」は終わることがないのか。
この生きづらさの正体は何なのか。経済を目的にすると、人が手段になる。
JR中央線・乗降客数最下位の西国分寺駅――
そこで全国1位のカフェをつくった著者が挑戦する、
「理想と現実」を両立させる経済の形。
高島市で聞き取り調査
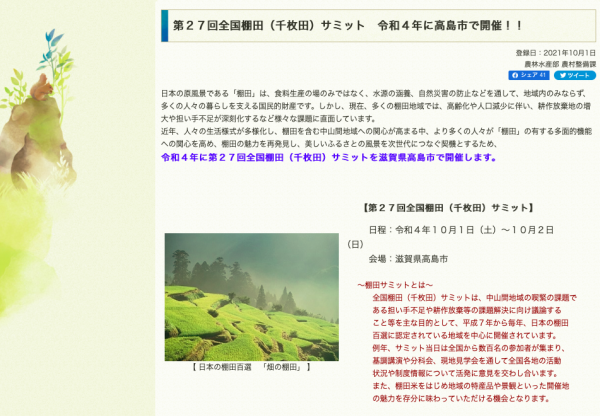
■今年の10月1日〜2日に、滋賀県高島市で「第27回全国棚田(千枚田)サミット」が開催されます。そのことと関連して、龍谷大学の社会学部、農学部、経済学部の7名の教員が研究グループを作って、滋賀県の高島市との協働で高島市棚田地域の調査と、広報用の動画資料の作成(委託事業)に取り組んでいます。また、このサミットの開催についてもサポートさせていただくことになっています。
■さて、今日の朝は、強風と雪でJR湖西線が動いていなかったのですが、昼前からなんとか動き始めました。ということで高島市に移動し、上記の事業の関連で、近江今津に事務所のある「特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島」の職員のSさんに、市役所のお二人の職員の方達と一緒に聞き取り調査を行いました。私が指導している大学院生と学部ゼミ生もオンラインで参加してくれました。
■今回の聞き取り調査では、「NPOとして今後どのように中山間地域の集落を支えていかれるのか」、その辺りのことについてお聞きしました。そうなんですが、だんだん、聞き取りというよりSさんと一緒に「高島市がこうなっていったら素敵だよね〜」という将来の夢について色々語り合うことになりました。大学で教えている社会調査からすると、こういうのはダメなんですけどね。そのことをわかってはいるのですが、最後はSさんや市役所の職員の方達と楽しいディスカッションを行うことに意図的に重点を移していきました。それでよかったと思っています。高島市棚田地域の調査は、昨年から行っています。高島市の中山間地域にある4つの集落でお話を伺ってきました。今月と来月の初旬頃まで、補足的な調査を行う予定になっています。
■滋賀県は、伝都的な琵琶湖漁業、環境こだわり農業、魚のゆりかご水田、水源林保全などからなる「琵琶湖システム」を、世界農業遺産に認定されるようにFAO(国際連合食糧農業機関)に申請をおこなっています。私はこの申請作業をサポートしてきました。そのようなこともあり、高島市の棚田をはじめとする中山間地域の存在は、この「琵琶湖システム」とも深く関係していると思っています。「第27回全国棚田(千枚田)サミット」と、滋賀県による「世界農業遺産」の申請が、うまく連携していけるようになればなあと思っています。とはいえ、「世界農業遺産」の審査、コロナのパンデミックのためになかなか進まないようです。待つしかありませんけど。
生物多様性科学研究センターから

■昨年のことですが、龍谷大学の生物多様性科学研究センターが実施した「100地点環境DNA調査」に参加しました。私は100地点のうち、10地点を「特定非営利活動法人 琵琶故知新」として参加し、採水しました。その分析結果が終了したようです。私のところに、感謝状、私が採水した10地点で判明した生息する魚の種類を示した報告書、そして写真のような記念品のマグネットが送られてきました。この参加型環境DNA調査、どのように発展してくのでしょうね。私は、龍谷大学の一教員として、生物多様性科学研究センターのプロジェクトの末席にいるので、とても気になっています。「流域ガバナンス」の観点から、この参加型環境DNA調査が展開していくことを期待しています。
むらづくりの村人にとっての「意味」
■昨年、高島市朽木椋川を訪問したときのことを、このブログの投稿でも報告いたしました。以下の2つの投稿です。
炭焼きのこと
第18回おっきん!椋川
■椋川を訪問した際に、大変お世話になった高島市市会議員の是永宙さんから、昨日、メッセージが届きました。「令和2年度ふるさとづくり大賞(総務大臣表彰)を受けたことから、昨年『おっきん!椋川』の時に取材を受けました。その時の動画が配信されていますので、良かったらご覧ください」。早速拝見いたしました。皆さんも、まずはご覧いただき、「おっきん!椋川」というイベントのことをご理解いただけるとありがたいです。
■動画の中で、集落のリーダーのお1人であり、このイベントを開催している「結いの里・椋川」会長の井上四郎太夫さんは次のように語っておられます。
最初、これやろうという時、(他所からやってこられたお客さんに)集落の中をあっちに行ってこっちに行ってと買い物に歩かせるのは失礼ではないか。一つの場所にまとめたほうがいいのではないかという意見があったが、お客さんは商品だけが目的ではなく田舎の空気や雰囲気を求めている。
■私も実際に集落の中を歩きましたが、歩くこと自体が気持ちが良いのです。このイベントを楽しみに毎年リピーターとしてやってきてくれる人びとは、おそらく町場や都会に暮らしておられるのでしょうが、そういう方たちには、山里の中を歩いてみること自体が楽しみなのです。「モノ」の購入だけでなく、「モノ」を生み出す背景に存在する文化や環境をも全身で感じとる気持ちになれることが大切なのです。
■ところで、このイベントには、集落外に暮らす子どもや孫の世代の皆さんもお手伝いとして参加されています。このイベントを支えておられるのです。イベントを手伝うことが三世代交流のきっかけになるだけでなく、地域の暮らしの文化を伝えていくことにもつながっているようです。それから、このイベントには、子どもや孫の皆さんだけでなく、滋賀県立大学の学生さんたちも参加されていました。山村の水田で水生昆虫の保全に関する研究をされているようです。これは推測でしかありませんが、自分が研究をしたいということだけでなく、水生昆虫が生息できるような水田を維持できる集落であるためには、こういったイベントに自分たちも参加して応援していくことが大切だ…と考えておられるのかな…ふと、そのように思いました。
■このイベントを企画したのは、この集落に移住してきた是永宙さんです。是永さんは、次のように語っておられます。
もともと村の人も自分たちが作っているものを売りたいというのはずっと前から思っておられて、僕がこっちに来て移住してから一緒に山仕事をしていたんですけど、その時も村の方が「近所で朝市をされている所があるので、あんなことをやりたいんやけどな〜、でもそんな場所もないしできんよな〜と」いうような話をされていて、それなら僕が言い出しっぺになりますのでやりましょうよと。その時は、村の中ではなく国道の入り口の方までモノを持って行って、モノを売るというところから始まりました。
■しかし、集落の中には反発もあったようです。イベントの継続に対する反発です。「なんでこんな面倒なことをするんだ」という地域の人の声が常にあったからです。是永さんは地域の皆さんのやる気を引き出すために試行錯誤されたようです。ちょうど10回目の時に日本で初めて特別警報がでた台風がやってきて椋川も大変な被害を受けました。そのようなこともあり、「今年は『おっきん!椋川』ができるかどうか」と心配されました。そして、開催するかどうかについて集落の会議で相談をしたら、「やったらいいやんか」とあっさり意見が出てきたというのです。あれだけ反発があったにもかかわらずです。是永さんのお話では、外部の方達(おそらくイベントのリピーター)が椋川の被害のことを心配して連絡を取ってこられたというのです。その時は、ちょうどイベントを10年継続してきた時期で、「おっきん!椋川」のことを楽しみに待っている人が多数おられたのです。そのような集落の外からの声が、「なんでこんな面倒なことをするんだ」という反発ではなく、「やったらいいやんか」という前向きな気持ちを生み出したのです。
■ここで重要な事は、「意味」です。災害の被害を心配した集落外の皆さんの声があったことで、「なぜこのイベントを継続しなくてはいけないのか」という問いに対して、集落内の人びとが納得できる「意味」が共有されたのではないかと思うのです。この点が重要かなと思います。イベントを継続することの中で蓄積された、集落の外部の人びととの信頼関係(架橋型社会関係資本)と集落内で強化された連携(結束型社会関係資本)とが、この「意味」を媒介として連関しているところがとても重要かと思います。そのことにより、このようなイベントを継続していくことの「有効性感覚」を集落内で醸成できたのではないかと思います。
■イベントを継続することで蓄積された集落外部との信頼関係や集落内の連携が基盤となって、この集落の中にあった古民家が「おっきん椋川交流館」に生まれる変わることになりました。初めに交流館があって活動が始まる…のではなく(ハコ物作りからではなく)、活動の結果として交流館が生まれていることが大切かと思います。この施設を管理するために組織されたのが「結いの里・椋川」になります。今では、集落の50名に加えて、集落外から20名も参加され、合わせて70名で活動されています。その活動内容も「おっきん!椋川」の開催だけでなく、集落内の草刈りや水路整備までにおよんでいるようです。
■椋川には、昨年の秋にお邪魔してお話を伺わせていただきましたが、コロナ感染が少し収まった段階で、再びお邪魔させていただきたいと思っています。
【追記】■関連する内容のことを、以前、「生物多様性と集落のしあわせ-農村活性化における生物多様性の意味-」(『農村計画学会誌』35巻4号)という特集論考を書きました。その論考の骨子をもとに、椋川の事例について考察してみました。このあたりのことは、来年度、論文化できれば良いなと思っています。
くさつFARMWE’S MARKET





■今日は、草津市に出かけました。廃川になった旧草津川、今は公園に整備されています。その公園を使ったイベント「くさつFARMER’S MARKET」を見学してきました。
■草津市は、私が住んでいる大津市のお隣の自治体ですが、普段、なかなか出かけることはありません。自宅は湖西線沿いにありますしね。もっとも、私が若い頃に勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館の最寄駅はJR草津駅でした。ですから、今から25年程前の草津の中心市街地のことは、それなりに知っているのです。でも、今はその頃とはすっかり街の雰囲気が変わっています。簡単に言ってしまえば、まちづくりが進んでいる、勢いがある、そのような気がします。
■このイベント「くさつFARMER’S MARKET」も、草津市の中心市街地で展開されている様々なまちづくりの取り組みのひとつなのだと思います。このイベントがどのような仕組みで運営されているのか、そういうことにも関心があるのですが、今日は、このイベントに参加している若者グループのお一人のお誘いを受けて出かけることにしました。龍谷大学社会学部の卒業生である尾形 詩織さんのお誘いを受けたのです。
■尾崎さんとは、私が今年度3人の教員で担当している「現場主義入門」という授業に、ゲストスピーカーとしてやってきてくださったことがきっかけで知り合いになりました。写真のグリーンのテントの下にあるような屋台をグループでシェアして、街と人びと、特に若い人びとをつなぐ活動をされています。
今日は、グループの佐藤 鷹政さんがこの手作り屋台を使って「ぎぶみーザぶっく-本と珈琲の物々交換」をテーマにした「さとう珈琲店」を出店されていました。私は、自宅に2冊あった本の1冊を持参し、佐藤さんのおいしいコーヒーと交換してもらいました。もちろん、コーヒー豆の販売や、コーヒーそのものの販売もされています。「くさつFARMER’S MARKET」には、佐藤さんのようなテント、軽トラックの荷台を使ったお店、キッチンカーが並んでいます。公園の周りは、たくさんのマンションが建設されています。ご近所さんたちからすると、日常生活の延長線上に、このようなちょっとした賑わいの場が月に2回開催されることになります。
■でも尾形さんや佐藤さんたちの活動に惹かれるのは、このようなイベントが開催されていないときも、手作りの屋台を使って活動を楽しまれていることにあります。その時、もちろん「販売」はされていません。ただ、この屋台を中心に発信される不思議な魅力が気になって、通りすがりの人たちが、「ここは、何をされているんですか」と立ち寄って行かれるのです。今日も、佐藤さんの「さとう珈琲店」には、様々なな年齢層の方たちが集まってこられていました。お知り合いのようです。無茶苦茶濃くはないけれど、薄くもない。職場も違うし、昔からの知り合いでもない。でも、住んでいるところは比較的近く。お話しを伺いながら、そのような「適度な親しさ」の人たちが、街とつながるネットワークが形成されている…そのようなイメージがふわっと頭の中に浮かんできました。
■よくわかっていませんが、このグループの人たちは、決まった曜日の時間帯(晩)に、暑い夏の日も、寒い冬の日も、晴れの日も、雨の日も、ここに集まってきて街頭の下でお喋りをするのだそうです。立ち話しですね。いろいろ話しを聞いてもらえる、グループのそれぞれの人にとって「大切な場所」になっているようなのです。カフェでもないし、居酒屋でもない。公園の街灯の下に集まってくるのです。繰り返します、よくわかっていないのですが、何か素敵ですよね、絶対に。子どもの時に、あそこに行くと仲良しの誰かがいるんじゃないのかなと思う場所がありましたよね。そうなんです。あの感覚に近いのです。建築家の延藤安弘さんが「まちの縁側」という言葉で表現されていたことにも近いのかな、たぶん。
■尾形さんや佐藤さん以外のグループの皆さんともお話しできました。池田 瞬介さん、そしてご実家が県内にあって、ご実家の農業を継承されているという女性ともお話できました。とっても感動しました。都市と農村との関係の中で、農業の新しい魅力が浮かび上がってくると素敵だなと思いました。年齢をお聞きすると、皆さん、私の子どもよりもお若い方たちばかりです。まちづくりというと、これまではもっと年齢が上の方達がリードされていたように思います。この若いグループの皆さんの活動は、そのようなまちづくりの活動とは少し違っていると思います。それぞれの方達の日常生活の延長線上にあるように思います。そのことが魅力となっているのではないかとも思います。また、遊びに行こうと思います。
■大津の中心市街地にも、とはいっても、大津のばあいはどこが中心市街地か難しいわけですが、それはともかく、若者たちが自主的に楽しみながら何か事を起こすことができるようになるといいなあと思います。
野口・国境の炭焼





■滋賀県高島市マキノ町野口の「国境炭焼きオヤジの会」を訪問しました。午後から炭焼による村づくり活動についてお聞きする予定でしたが、そのことに加えて、午前中は地元のマキノ西小学校4年生の校外学習の様子を見学させていただきました。国境は、高島市マキノ町野口の、3つある集落(小字)の中でも一番北にあります。ちょっと150mほど歩くと福井県に入ります。
■トップの写真は、「国境炭焼きオヤジの会」が作られた炭窯の小屋です。入り口の上には、「夢炭」と書いた看板が掲げてあります。「むーたん」と読みます。たしか、商標登録されているはずです。夢の炭…なかなかロマンチックなネーミングですね。この日は、小学生がやってくるということで、窯の中にライトが照らされていました。私たちも、窯の中に入れていただきました。2段目左の写真は窯の中から撮ったものです。3段目左は、粘土の塊です。炭窯に隙間から空気が入ると炭にならずに灰になってしまいます。そこで、その隙間をこの粘土で塞ぎます。適度な粘りが出るように色々加えてあります。粘土は硬くても柔らかくてもダメなようです。微妙ですね。






■4段目左。左側の割った木材が、右側のような炭になります。重さは1/6に、サイズも少し縮見ます。5段目右、小学生のみなさんが、焼いた炭を適当な大きさにノコギリでカットしています。普通の材木とは切る際の感触が違うので、驚きの声が上がっていました。6段目は、この炭焼窯の近くにある願力寺で、昔の暮らし、特に囲炉裏のある暮らしについて、お話を伺っているところです。いろんな質問が出てきます。予想以上にいろんな知識があります。少し驚きました。

■午後から、願力寺で「国境炭焼きオヤジの会」の活動について、指導している大学院生とともにお話を伺いました。今回は、高島市役所の職員さんも同行された。部屋の真ん中の囲炉裏には、炭が燃えていています。大変温かいです。囲炉裏には五徳が置かれています。五徳に置いた網で餅を焼いていただき、ご馳走になりました。今日も、3時間ほどお話を伺いながら、楽しい時間を過ごすことができました。
■2010年「水源の郷活性化事業補助金」の助成を受けて野口という区の事業として始まった炭焼。最初は、活性化の事業として、どのようなことに取り組むのかを議論されたようです。議論の結果、炭焼をやることになりました。炭焼は、この地域の生業の中心、現金収入の中心でした。この地域のアイデンティティと深く結びついているのです。こんな話も聞くことができました。福井県との県境に位置するこの地域は雪深く、冬の間は炭焼きができません。現金収入が途絶えきます。そこで、炭の問屋から借金をして、雪が溶けて春になってから炭を焼いて、現金ではなく炭で返したというのです。もちろん、そのような経験をされている方は、どうだろう、ご健在ならば100歳前後の方たちでしょうか。
■さて、「国境炭焼オヤジの会」の皆さん、炭を焼くだけでなく、炭を使った石鹸を商品開発して販売もされてきました。近くの道の駅だけでなく、ネットでも販売されたようです。もちろん、炭そのものの販売についても努力されてきました。そうやって盛り上げてきた炭焼きなのですが、活動を始めて10年経過すると、担い手の高齢化や担い手不足等により、炭焼きの活動自体が難しくなってきています。先行きは暗いわけです。しかし、どういうわけだか話は明るく盛り上がります。暗いけど明るい、ここは社会学的にはけっこう大切なポイントかなと思います。
■当初は区の事業として始まった事業ですが、今は野口の有志の個人による活動になっています。加えて、近くの愛知県から在原に移住されてきた方も参加されています。この方はなかなかのアイデアマンのようで、活躍されています。炭窯の煙突にセンサーを設置して、釜の温度を測定したり、窯に原料の薪を運ぶのにも、ローラーコンベアを使ったり、高齢化の中にもいろいろ工夫を提案されているのです。野口の皆さんから期待されています。今日も、リーダーのKさんに、柱を立てて窯全体をブルーシートで覆えるようにすれば、天候に左右されずに炭が焼けると話されていました。しかし、80歳目前のKさんは、「そこまでして、炭を焼きたくないわ」と笑いながら話されていました。このあたり微妙なのですが、大変興味深い点でもあります。
■当初より、野口以外の人たちにもオープンにした活動をされてきました。ただし、炭焼きの作業は、天候や様々な条件に左右されます。作業の段取りが変わるのです。遠く離れたところに住んでいる方、たとえば大津に暮らしておられる方に、急にボランティアで作業をお願いすることもなかなか難しいわけです。結局は、自分たちで作業をすることになります。オープンに活動をする上で、インターネット等での情報発信が大切になるのですが、現在はそこまで手が届いていません。
■高島市には野口の他にも炭焼で活性化に取り組む集落があります。「連携して高島市全体でブランディングしては」という発想も出てくるわけですが、集落によって炭の質が異なるため、それもなかなか難しいとのことでした。炭は工場で生産する工業製品とは異なるのです。もっとも、難しいと言ってばかりでは仕方がありません。なんとか、炭焼を事業化、企業化していきたいとも考えておられます。もう区の事業ではないので、地域外から本気で取り組む若い担い手が来てくれるのならば、技術やノウハウを伝えるという発言がありました。そういう若い担い手が参加してくれるのならば、一緒に頑張るし応援もするという発言もありました。もしそうならば、面白い展開になるのかもしれません。また、「半農半X」ならぬ「半炭焼半X」(炭焼や炭焼に関連する付加価値をつける仕事と、他の仕事(”X”)を組み合わせた働き方)が成立するのならば、実現する可能性もあるのかなと思います。あと、炭焼するには太くなり過ぎた山の広葉樹の利活用をどうするのか。これも大きな課題です。現在、炭にする薪をどうやって調達しているかといえば、別荘地で大きくなりすぎて伐採された樹、炭焼のサイズに割って使っています。山の広葉樹は太くなりすぎて、使えないのです。
■おそらく、こういう現実があることを認識するのならば、地域の支援策もこれまでとは違ったものになってくるのではないかと思います。また、役所の中で部署ごとに縦割りになった支援策をうまく組み合わせていくことも必要だろうと思います。
雲洞谷(うとだに)の炭焼き

 ■高島市朽木の雲洞谷を訪問しました。「うとだに」と読みます。こちらの「まるくもくらぶ」の活動に関して、指導している大学院生とお話を聞かせていただきました。今回は、高島市の中山間地域の活性化について一緒に仕事をしている市役所の職員さんも同行されました。楽しかったです。お話しいただいたのは、「まるくもくらぶ」のリーダーのIさんと、ここに移住してきてIさんと一緒に活動しているFさんです。Fさん一家は、京都からここに転居されました。お2人に、いろいろ細かな質問に丁寧にお答えいただきました。ありがとうございました。
■高島市朽木の雲洞谷を訪問しました。「うとだに」と読みます。こちらの「まるくもくらぶ」の活動に関して、指導している大学院生とお話を聞かせていただきました。今回は、高島市の中山間地域の活性化について一緒に仕事をしている市役所の職員さんも同行されました。楽しかったです。お話しいただいたのは、「まるくもくらぶ」のリーダーのIさんと、ここに移住してきてIさんと一緒に活動しているFさんです。Fさん一家は、京都からここに転居されました。お2人に、いろいろ細かな質問に丁寧にお答えいただきました。ありがとうございました。
■写真は復活した炭焼窯です。炭焼は、かつての生業の柱でした。山での暮らしを象徴する生業なのです。その炭焼きを経験されている方を先生役に、「まるくもくらぶ」では炭焼窯を復活させました。活動されているのは70歳前後の人たちです。年齢は前後しますが、全員幼馴染であり、青年団も消防団も一緒に活動してきた仲間です。彼らは炭焼きの手伝いはしても、自分たちの手で炭窯を作ったり炭を焼いたことはありません。そして、親の世代とは異なり、この山村の中だけで暮らしてきたわけではなく、外の職場に通勤しながらここに住み続けてこられました。車と湖西線を使えば、住み続けることができたのです。ただし、同い年の同級生で雲洞谷に残っているのは、Iさんお1人だけです。
■Iさんが生まれたのは1949年。いわゆる団塊の世代です。Iさんが中学生の頃に、「燃料革命」の影響がこの山村にも届くことになりました。そして雲洞谷の炭焼も1960年代の後半には途絶えることになりました。Iさんの記憶では、炭焼きに必要な広葉樹を伐採した後に、杉の苗をどんどん植えていきました。その頃、政策の後押しもあり広葉樹がどんどん針葉樹に替わっていきました。「拡大造林」です。
■先程、炭焼き経験者を先生役に…と書きました。集落を代表する生業としての炭焼きは途絶えていましたが、その経験者の方だけは、身体が動く間、小さな窯で炭焼きを続けてこられていました。2019年、その方から炭焼きを教えてもらう「勉強会」を開催しました。記録を残して、自分たちでも炭焼きが継続できるようにしたのです。この「勉強会」には、多くの外部の人たちも参加されました。「勉強会」がオープンな形であることが興味深いですね。この村に住み続けるのには、外部の人たちの関わりが重要だとの考えを、活動の当初からお持ちだったのです。雲洞谷のことに関心を持ち、気になる人たち、今流行りの言葉で言えば、関係人口を増やそう、そのような考えのもとで取り組まれているのです。
■「まるくもくらぶ」のロゴは、丸の中に「雲」という漢字を書いて、その後にひらがなで「くらぶ」がついてきます。なんでも、消防団の法被の背中は、この「まる雲」が描かれているそうです。ポイントは、「まる」が完全に閉じておらず、少し切れていて、外部に対して開かれているところにあります。つまり、集落で閉じた活動ではなくて、「外部に開かれた活動ですよ、外部の方達にも参加してもらいたいのですよ」という気持ちが表現されているのです。まあ、このブログには全てを書ききれないわけですが、貴重なお話を聞かせていただくことができました。炭焼き以外にも、栃餅、鯖のへしこ、鯖のなれ寿司の話もおもしろかったですね〜。鯖のなれ寿司は食べたことがありません。食べてみたいな〜。この山深い山村の人たちにとって、琵琶湖の淡水魚よりもひと山越えた若狭の海の魚の方が手に入りやすいし重要だったのでしょう。
■本格的に寒くなる前に、再度、雲洞谷を訪問する予定です。その時は、栃餅の原料である栃の実を実らせる巨木にも逢いに行ってみたいと思います。
炭焼きのこと


■指導している大学院生とともに、高島市朽木で炭焼きと村づくりに関して、少しずつお話しをお聞きしています。昨日の午前中は朽木の椋川(おっきん椋川交流館)で、是永宙さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
■高島市の中山間地域は、高度経済成長期の前半までは、どこの地域でも炭焼きをされていました。いわゆる燃料革命の前までになります。高島市内では、現在確認されているだけで、4つの集落で炭焼きされているか、これから復活させようとされています。いずれの地域も、過疎と高齢化が進行している地域です。かつて炭焼きを生業としてされていたのは、現在の年齢で言えば、80歳代も半ば以上の方達になります。70歳代の方であれば、手伝いはしたけれど、自分が家の中で中心になって炭焼きをしていたわけではありません。ですので、何歳位の方が、いつ頃から炭焼きを復活させようとしたのかにより、微妙に取り組み方や、何のために炭焼きを復活させたのかという理由については違いがあります。
■炭焼きに焦点を当てて聞き取りをしていますが、その背景となる村の暮らしや社会経済の背景、また外部からやっくるIターンの人びとの存在、村づくりの活動、さらには最近の流行りの言葉でいえば、関係人口の拡大といったコンテクストの中で炭焼きの活動を位置付けなければなりません。いつか、もう少し詳しくこのブログでも報告できるかもしれません。
真野浜で理事会





■昨日は、夕方から真野浜(大津市今堅田)にある民宿「きよみ荘」さんで、NPO法人「琵琶故知新」の理事会&懇親会が開催されました。「きよみ荘」は、理事のお一人が経営されている民宿です。昨日は、ひさしぶりにzoomではなく、理事の皆さんと直接お会いして話し合うとことができました。もちろん、zoomでも意見の交換、言葉のやり取りはできるのですが、実際にお会いすると、もっと深いところでお互いの理解が深まり、素敵な交流ができたように感じました。
■この日の理事会の議題は3つありました。1つめは、某財団へ助成金の申請について。結果ですが、残念ながら次点でした。採択に至りませんでした。私たちのNPOで頑張って運営していこうと思っている「びわぽいんと」、その考え方については共感していただき、評価もいただいたようでしたが、助成する側からすれば、「びわぽいんと」が社会に定着していくために、さらに戦略性を高めてほしいということのようです。そうなんです。そのことは、私たち理事たちもよくわかっているんです。頑張らねば…なのです。ということで、議題の2つめが、某大手通信会社との連携事業についてです。具体的なことはまだ書くことができませんが、良い方向で議論が進んでいます。楽しにしています。そして議題の3つめ。「びわぽいんと」の戦略性を高めるための「勉強会」の開催です。勉強会、誰が勉強するのか。はい、私たちNPOの理事が勉強させていただきます。滋賀県内で、環境保全活動に関連して活躍されている皆さんをお呼びして、「びわぽいんと」を鍛えるためのご意見やアドバイスをいただく開催しようと思っています。すでに4人の方達に参加の了解をいただいています。この「勉強会」も楽しみにしています。
■昨日は、このような議題を中心に理事の皆さんとディスカッションを行いました。良いディスカッションができたと思います。そのあとは、民宿「きよみ荘」さんが用意してくださった鍋料理で懇親会を楽しみました。理事の皆さんの中には、滋賀県以外にもお住まいの方もおられます。神戸からお越しの理事は、大津市堅田の酒蔵の日本酒「波乃音」を堪能されていました。その日は「きよみ荘」に宿泊されルことになっておられたので、かなり召し上がったのではないですかね。別の要件のお疲れもあってか、沈没してしまったようです。良い宴会でした。
■写真のことも少し説明しておきます。トップは、真野浜から見た琵琶湖の北湖です。琵琶湖は琵琶湖大橋から南が南湖、北が北湖に区分されます。南湖と北湖とではスケールが全然違います。北湖はワイルドです。写真の真ん中より少し右側に見えるのは沖島です。左から張り出しているように見えるのは、湖西の比良山系です。天気が良ければ、伊吹山まで眺めることができるのですが、今日は雲に隠れているようです。中段左の写真は、対岸の守山市です。真ん中に見えるのは、湖岸にあるマンションです。右の方には、野洲市にある三上山が見えますね。中段右の写真は、左の写真と同じ方向を拡大したものです。遠くに鈴鹿山脈が見えますね。下段は、理事会の様子です。私は、技術的なことはよくわからないのですが、「びわぽいんと」で用いるアプリがバージョンアップしたのでそれを理事の面々で確認しているところです。