2025年最後のご挨拶
▪️2025年大晦日。一年間、皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。いろいろあったわけですが、あっという間の1年でした。これからは、さらに時間が経過していくスピードが増していくのかなと思います。それは仕方のないことだと思います。でも、それでも日々を大切に、楽しい時間、充実した時間を持つことができればと思います。
▪️とはいえ、日々のニュースに接していると、とても暗い気持ち、重苦しい気持ちになってきます。世界各地での戦争、それらの戦争が化学反応のように連鎖して大きな戦争になっていくことが恐ろしいです。そして気候変動です。今年の夏の暑さは異常でした。その気候変動、特に温暖化に起因する様々な気象災害。国内の食糧供給もどうなるのか。さらには、南海トラフのような大地震がいつ襲いかかってくるかわかりません。なかなか明るい未来が見えてきません。
▪️加えて大変個人的なことであり悲しいことなのですが、高校の時の同級生が今月、先日、亡くなりました。突然でした。その方とはクラスメイトだったこともありました。とはいえ、それほど親しくさせていただいたわけでありませんでしたが、それでも亡くなったことをお聞きして、とても悲しい気持ちになりました。これから、こういうことが増えていくのだろうなと思います。すでに同級生は何人も亡くなっています。次は自分の番かもしれないとも思っています。だからこそ、日々を大切に、楽しい時間、充実した時間を持つように努めたいと思います。
▪️シェアしたのは、「びわ湖源流の郷(高島市)の魅力」さんのfacebookへのご投稿です。同級生が亡くなり悲しい気持ちになっていましたが、このような琵琶湖の風景に接すると清々しい気持ちにもなります。皆さま、どうか良い年をお迎えください。
脇田ゼミ1期生の同窓会


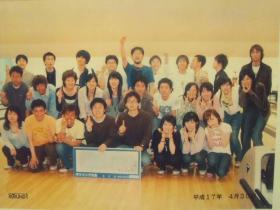
▪️先日の土曜日は脇田ゼミ17期生の皆さんとの同窓会にお呼びいただきましたが、月曜日(12月29日)の晩は、脇田ゼミ1期生の皆さんの同窓会にお呼びいただきました。ありがとうございました。幸せですね。1期生ということで、私が龍谷大学に勤務するようになった最初の学年です。脇田がどんな教員かもわからず、よく私を選んでくれたものです。龍谷大学社会学部の以前は、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。公立大学ですからゼミ生の人数は少なく、多くても6名でした。龍谷大学に異動するとき、私立大学に移っても、公立大学の時と同じ水準の指導を学生の皆さんに行うと自分に誓ったこともあって、結構、厳しく指導していたのではないかと思います。全員にフィールドワーク(調査)を半ば強制していました。それでも、この学年の皆さんはよく頑張りました。1期生は全員で18名ですが、今でもLINEグループで繋がっているのは、そのうちの12名の皆さんです。LINEって大切ですね。手紙や電話でしか連絡が取れない時代だと、同窓会をひらくのもなかなか大変だったんじゃないのかな。どこに住んでいるのかもわからなくなりますからね。
▪️写真ですが、1枚目は一次会です。野菜が美味しい創作料理店。自分のところで野菜を生産して、系列店で使っているのだとか。「囲炉裏酒場 炭棲堂」さんです。たまたまですが、龍大農学部食品栄養学科の1回生のアルバイトさんが働いておられました。2枚目は二次会です。卒業してから20年経過すると、自営業の方以外、転職もいろいろありますね。みなさん、頑張って働いておられます。3枚目はずいぶん昔のもの。1期生と2期生(当時の4回生と3回生)とボーリング大会をした時のものです。懐かしいです。今は無くなった、石山のボーリング場です。写真ではまだ可愛らしさが残っている1期生の皆さん、今は42歳になりました。
▪️昨日の朝になりますが、いつも幹事役を引き受けてくれている方からLINEグループに投稿がありました。来年度で私が定年退職するということで(私のラストイヤーだそうです)、来年も同窓会を開催して、お呼びくださるようです。楽しみです。
脇田ゼミ17期生の同窓会

▪️この前の土曜日(12月27日)は冬期休暇中ですが、研究室に、自宅で仕事をするのに必要な書籍と資料を研究室に取りにきました。そして夕方から京都駅前の居酒屋へ。脇田ゼミ17期生の皆さんの同窓会に呼んでいただきました。ありがとうございます。東京で働いている人も年末や年始は関西に帰省するので、昨年も年末に同窓会を開催されていました。ずっと続くと良いなと思っています。土曜日は、福井県からやってきた人もいました。
▪️卒業したのは、2024年の3月ですが、社会人になってまだ2年に満たないのに、ずいぶん成長されているように感じました。当たり前と言えば当たり前ですが、話している内容からして違っていますからね。社会人の会話でした。そうそう、東京で働いている方は、関西弁を喋らなくなっていました。環境は人を変えますねww。
▪️17期生の皆さんにも、生成AIを仕事で使っているかどうかを聞いてみました。みなさん、ガンガン使っておられました。もうAIを使わないと仕事が成り立たないのでしょうね。
「奇跡のチェロ・アンサンブル 2025」



 ▪️今年も「奇跡のチェロ・アンサンブル」。年末恒例です。今回で4回目でしょうか(ちなみに、カーテンコールの撮影はOKとのことでした)。2人1組でMCを担当されるのですが、岡本侑也さんが興味深いことを話しておられました。岡本さん、現在はエベーヌ四重奏団のチェリストとしても活躍されています。室内楽でもオケでも、チェロは通常は低音部を担当しています。ところが、この「奇跡のチェロ・アンサンブル」では黒い指板のかなり上のほう、駒(コマ)に近い方、ハイポジションで弾くことになります。チェロなのにかなり高い音で演奏することが多々あるわけです。そうすると、ポジションを取るために親指で弦を押さえることになります。そして、親指に普段はできないタコができてしまうのだそうです。そのMCの時の笑いを取る話がとても印象に残ってしまいました。
▪️今年も「奇跡のチェロ・アンサンブル」。年末恒例です。今回で4回目でしょうか(ちなみに、カーテンコールの撮影はOKとのことでした)。2人1組でMCを担当されるのですが、岡本侑也さんが興味深いことを話しておられました。岡本さん、現在はエベーヌ四重奏団のチェリストとしても活躍されています。室内楽でもオケでも、チェロは通常は低音部を担当しています。ところが、この「奇跡のチェロ・アンサンブル」では黒い指板のかなり上のほう、駒(コマ)に近い方、ハイポジションで弾くことになります。チェロなのにかなり高い音で演奏することが多々あるわけです。そうすると、ポジションを取るために親指で弦を押さえることになります。そして、親指に普段はできないタコができてしまうのだそうです。そのMCの時の笑いを取る話がとても印象に残ってしまいました。
▪️この「奇跡のチェロ・アンサンプル」、国内のトップチェリストの集まりですが、小林幸太郎さんは加えて、編曲の担当です。6人のアンサンブルの魅力を最大限引き出すために、さまざまな工夫を凝らしておられます。それも超難易度の。その超難易度のという部分が、この「奇跡のチェロ・アンサンブル」の魅力の「ひとつ」なのでしょう。今回の前半は、6人の方がそれぞれソロを演奏し、残りの5人で伴奏をする構成になっていました。それぞれの方の音の違いがよくわかりました。前半でのそれぞれのソロが記憶に残っているせいでしょうか、後半の合奏で、それぞれの方の音がよく聞こえてきたような気がします。まあ、あくまで気がするですけど。個人的な好みということになりますが、一番お若い上野通明さんの音が一番印象深かったです。素敵です。YouTubeにもたくさん演奏がアップされているようなので、聞いてみることにします。
そもそもタンホイザーとはどのようなオペラなのか

(Tannhäuser and Venus WIKIMEDIA COMMONSより )
▪️先日の龍谷大学吹奏楽部の第52回定期演奏会を楽しんできました。福川伸陽さんの「ホルンと吹奏楽のための協奏曲」の演奏に驚嘆し、メインの「タンホイザー」序曲(ワーグナー)を堪能しました。私自身は、学生時代にオーケストラに所属していましたが、このワーグナーの序曲を弾いたことがありません。3回生のときに歌劇「リエンチ」序曲だけは弾いたことがありますが、有名な「ニュルンベルクのマイスタージンガー」や「ローエングリン」はもちろん、この「タンホイザー」も弾いたことがないのです。
▪️そもそもオペラのなかで演奏される曲ですから、そこにはストーリーがちゃんとあるのですが、そのあたりも不勉強です。この3幕からなる「タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦」についても、よくわかっていませんでした。ということで、あらすじ程度ですが、龍大の定演が終わってから少しだけ勉強しました。序曲の冒頭も第3幕で歌われるコラール「巡礼の歌」なのですね。スコアとともに序曲の演奏を聴くことのできるYouTubeもありました。
▪️トップの絵画は、ドイツの歴史画家オットー・クニレの作品です。オペラの第1幕なんだと思います。ヴァルトブルク城の騎士、タンホイザーは、エリーザベトという純粋な女性への愛を捨てて、愛と美の女神ヴェーヌスが支配する地下の魔法の国「ヴェーヌスベルク」で、長らく快楽と肉欲の日々に溺れていたのですが、その退廃的な生活に嫌気がさして現実世界に戻ってきます。この作品はその時の様子を表現しているのだと思います。タンホイザーは官能的な愛と崇高な精神的な愛の間で苦悩するわけですね。こういうことを理解しながら、龍大吹奏学部の学生の皆さんは演奏していたんでしょうかね。どうやろ。
▪️できれば、一度はオペラをきちんと鑑賞してみたいと思うようになりました。S席だと3万円ぐらいになるようです。ですから、一度は…です。
パソコン関係のメール
▪️「Web版「Gmail」における外部メール受信(POP)機能の終了」だとか、「Microsoft Teamsにおける会議設定方法の統一について」なんていう件名のメールが届いて、「ああ、その件ね」とすぐに理解して対応できるような人であれば問題ないのでしょうが、自分のような場合(知識不足の年寄り)だと理解するのにちょっと時間がかかります。また、正しく理解できているのだろうかと不安にもなります。
▪️ということで、「Web版「Gmail」における外部メール受信(POP)機能の終了」への対応をGoogleのAIモードで調べて、私のような人にもわかるように説明しているサイトを調べてみました。世の中には親切な方達がおられます。そもそも、Googleの設定のどこを確認すれば良いのかもわからなかったので、きちんと説明してくださっていて、とても助かりました。ちなみに、参加しているNPOのメールアカウントを持っているのですが、それは今回終了するPOPという機能を使ってgmailに取り込んでいることがわかりました。大学関係は良いとして、NPOの方は対応を考えないといけません。もうひとつの「Microsoft Teamsにおける会議設定方法の統一について」の方ですが、私自身が会議を設定することはまずないので(会議に呼ばれることはありますが)あまり気にしなくても良いのかな。
▪️こんな感じだと、定年退職した後は、パソコン関係の諸々、世の中にいていけないし大変になっていくんじゃないのかなと心配しています。
阪急大阪梅田駅


▪️龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会を鑑賞するために、JRで京都から大阪に移動しようとしたのですが、電車は高槻駅で止まってしまいました。その先で人身事故があったようです。運転再開まで1時間はかかるということで、JR高槻駅で降りて、阪急高槻市駅まで徒歩で移動し、阪急の特急で大阪梅田駅まで移動しました。結果としてですが、ひさしぶりに阪急大阪梅田駅の、「あの雰囲気」を堪能することができました〜。「あの雰囲気」というのは、阪急最大のターミナル駅が生み出す独特の雰囲気のことです。神戸本線・宝塚本線・京都本線の列車の始発・終着駅です。好きなんです、この雰囲気。以前のことになりますが、独居老人であった母の世話をするために、この大阪梅田駅を毎週のように利用していました。毎回、その雰囲気を楽しんでいました。その母も亡くなり、大阪梅田駅のみならず、阪急自体もほとんど利用することがなくなってしまいました。
龍谷大学吹奏楽部 第52回定期演奏会

▪️昨晩は、大阪福島にあるザ・シンフォニーホールで、龍谷大学吹奏楽部第52回定期演奏会を楽しんできました。
▪️ゲストである福川伸陽さんの「ホルンと吹奏楽のための協奏曲」、すごい演奏でした。自由自在にホルンを吹かれている様子を拝見して驚愕しました。この曲は、福川さんご自身が作曲家の福島弘和に委嘱してうまれた作品です。福川さんは、ある鼎談のなかで以下のように説明されています。
この曲は僕が福島さんに委嘱する形で生まれました。吹奏楽のホルンはもっと注目されていいと思うんですよね。大半が和音担当なので、もっと目立ちたい!と。笑
なので、「ホルンでもこんな素敵なソロができるんだぞ!」っていう、魅力をどうにかして伝えられないかと、そう思ったのがきっかけです。吹奏楽バックでできるコンチェルトもなかなか少ないので。
▪️「俺にしかできない曲」っていうオーダーだったようです。これもすごい話ですよね。龍谷大学吹奏楽部ではなく他のバンドですが、福川さんの演奏をYouTubeで鑑賞することができます。ぜひお聞きいただきたいと思います。
▪️このホルンコンチェルト以外にも、第2部のメインである「タンホイザー」序曲、とても満足しました。オーケストラの作品を吹奏楽用に編曲して演奏するときに、原曲の弦楽器の部分が吹奏楽ではどう演奏されるのかがいつも気になるのですが、龍谷大学吹奏楽部の演奏、ちゃんとしたワーグナーでした。ありがとう。それから、第1部の「カントゥス・ソナーレ」、「ワイルドグース」にも満足しました。特に、「ワイルドグース」は、ケルト文化をテーマに作曲されていることもあり、魅力を感じました。
▪️定演の後は、一緒に定演を楽しんだ息子夫婦と食事をすることができました。遅い時間ですし、短い時間でしたが、ひさしぶりに会って話ができました。そのあと深夜に帰宅して、そして今日は1限の9時15分から授業でした。あああ…。
ヨシ群落保全審議会のこと

▪️12月22日(月)、滋賀県庁で「第41回滋賀県ヨシ群落保全審議会」が開催されました。手元の記録では、2015年9月からこの審議会の会長を務めているようです。規定では、1期3年で3期までということになっているようなのですが、3期を越えて4期会長職を務めることになりました。任期は来年の初め頃までのようですが、実質、昨日が私にとって最後の審議会になりました。委員の皆さんの意見やアイデアが活かされていくような審議ができて本当によかったと思っています。審議会以外にも、ワークショップを委員の皆さんと一緒に開催したり、委員と委員をつないで、新しい事業を生み出すこともできました。まだまだヨシ群落の保全については、やらないといけないことが山積みなのですが、少し新しい時代にふさわしい取り組みにむけて前進できたことで、満足しています。
▪️写真は、近所の公園から見た伊吹山、沖島、琵琶湖大橋です。少し暗くなりすぎていますが、もう少し明るい時間帯だと、伊吹山もよくみえました。写真には写っていませんが、湖東のさらに東側には鈴鹿山脈もよくみえました。琵琶湖の水位、心配ですね。
