ETV特集「カキと森と、ときどき凪」
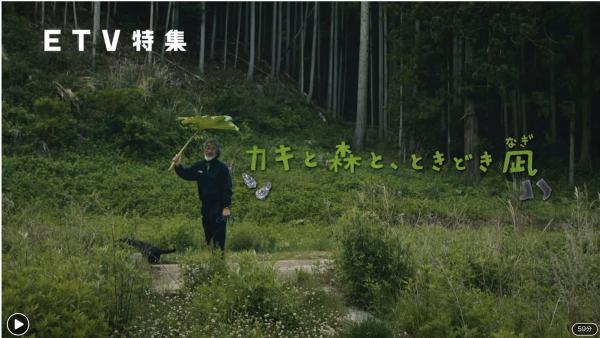
▪️今年の春、畠山重篤さんがお亡くなりになりました。享年81歳。肺血栓塞栓症。体内から運ばれてきた血栓が栓子となって肺動脈が閉塞する病気です。「森は海の恋人」といえば、おわかりになる方も多いでしょう。昨日のETV特集「カキと森と、ときどき凪」は、その畠山重篤さんに焦点をあてたものでした。以下は、番組の概要です。
漁師でありながら山に通い、木を植え続けた“長靴の哲学者”畠山重篤さん。カキを師と仰ぎ、カキのささやきに耳を澄まし、その豊かな知恵を世界中に伝えてきた。4月、畠山さんは81歳で亡くなった。海辺の書斎に残されていた、1つの原稿。公害や東日本大震災、温暖化。母を奪った海を「それでも信じている」と、自然との共生を模索した半世紀。最後に伝えようとしたものとは何か。鏡のような汽水のほとり、14年の記録。
▪️10月11日午後11:59までならば、ネット上で視聴できます。こちらで配信されています。
▪️畠山さんは、気仙沼市の舞根湾で長年にわたり牡蠣養殖業に従事されてきました。高度経済成長期の頃には生活排水が流れ込むことで、牡蠣を養殖している海に赤潮が発生しました。海の環境が劣化していきました。このような海の環境問題をきっかけにして、海の牡蠣の健康な成長に必要な鉄分や栄養塩を供給する山がちゃんとしていなくてはいけないことに気がつかれ、その山を維持するために、仲間の皆さんと一緒に植林活動等の「森づくり」の活動にも取り組んでこられました。だから、「森は海の恋人」です。この畠山さんたちの活動は全国的、そして世界的にも注目されました。畠山さんが執筆された書籍も、多くの皆さんに読まれています。翻訳もされています。
▪️畠山さんには、一度だけお会いしたことがあります。もう20年以上昔のことだと思います。たしか、学会が近くの場所で開催された時かと思います。その学会のエクスカーションで、養殖場を見学させていただいたのでした。そのエクスカーションのことを思い出していると、同時に、この「森は海の恋人」に関連する研究論文のことを思い出しました。「漁業者による植林運動の展開と性格変容一流域保全運動から環境・資源創造運動へ」。帯谷博明さんの論文です。気仙沼湾に流入する大川上流にダム建設が計画されたことに対して、畠山さんたちも、一番下流に位置しているにもかかわらず、建設反対運動に取り組まれました。そのことを事例にとりあげた、社会運動論に関する論文です。今は、阪神地域にある大学で教員をされていますが、当時は東北大学の大学院生でした。なつかしいです。
【追記】▪️番組ではBGMのように男性合唱による讃美歌らしきものが流れています。畠山さん、日本バプテスト同盟気仙沼教会の会員なんですね。そうだったんだと納得しました。