魚見さん(革靴をはいた猫)と「利やん」

▪️昨晩は、「革靴をはいた猫」代表取締役の魚見航大さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお話をお聞かせいただきました。魚見さんに実際にお会いするのは、これが2回目になります。前回お会いした時も、「利やん」でした。前回、この「利やん」を気に入られたようで、今度は魚見さんの方から、「利やん」で呑みましょうとお誘いいただきまた。魚見さんは、障がい者と健常者が一緒に働く靴磨き靴修理の株式会社「革靴をはいた猫」を起業されました。各地にある障がい者就労支援の事業所ではなく、株式会社として起業されたのです。
▪️このあたりのことは、魚見さんにお会いする前から、龍谷大学の広報や、ネットの記事を通して知っていました。龍大の政策学部からはたくさんの皆さんが起業されています。魚見さんもそのような方達のお1人です。自分は何がしたいのかよくわからない、ある意味で、よくいる普通の若者だった魚見さんが、人生の「転轍手」となる女性との出会いがあり、その女性の強い勧めで靴磨きの修行を行い、そして「革靴をはいた猫」を起業された…とってもドラマチックです。困難を抱えた方達に対する魚見さんの眼差しは、とってもフラットです。一緒に働く仲間なんですね。前回お会いした時は、長年一緒に働いてきた方が、別の企業に立ち上げられた新たな部門に雇用されたというお話も聞かせていただきました。素晴らしいです。今回は、滋賀県内で行政と連携して新しい事業を立ち上げるようで、そのお話を少し聞かせていただきました。こちらも素晴らしいです。魚見さんの事業は、様々な企業からも注目されているようです。まだ30歳過ぎの青年です。仕事が楽しくて仕方がないようですね。頑張ってください。
▪️「自分は何をしたいのかよくわからない」、そのような今時の普通の大学生だった魚見さんは、人生の「転轍手」となった女性と出会ったと書きました。その方は、「樹林」のおばちゃんです。。こちらの記事もすごく参考になりました。
「中安商店」さんのライブ
土曜日、大津街中の酒屋さん「中安商店」さんのライブへ。「つぼきーにゃ」さん。ボサノバとかブラジルっぽいライブ。黄緑のブラウスを着たボーカルのつぼめさんと、グレーのセーターのパーカッションやギターのまっさんはご夫婦。ご自宅でも、音楽を楽しんでおられるんだろうな。#大津#中安商店 pic.twitter.com/mKZ9Qmm6Vz
— 脇田健一 (@wakkyken) January 27, 2025
▪️先週の土曜日のことになります。お誘いを受け、大津の街中にある酒屋さん「中安商店」さんのライブへ。「中安商店」さんは、もともと、街中にある普通の酒屋さんでした。ところが、店主さんが音楽好きということもあり、お店をライブハウスに改装されたのです。動画のボーカルの方の後ろ、たくさんのフライヤーが貼ってあるところはお店の入り口になります。そして動画のサックスの方の左側は、コの字型のカウンターがあります。私が動画を撮っている場所には小さなテーブルがあります。ここにやってくるお客さんは、お店の冷蔵庫から飲み物を取り出して、店主さんにお金を払います。つまみは、乾き物か缶詰。いわゆる「角打ち(かくうち)」のスタイルとライブハウスを合体させているといえば良いのでしょうか。
▪️この日は、ほぼ椅子が埋まっていました。ライブをされているのは、「つぼきーにゃ」さんです。ブラジルっぽいライブでした。黄緑のブラウスを着たボーカルのつぼめさんと、グレーのセーターのパーカッションやギターのまっさんはご夫婦。ご自宅でも、こうやって音楽を楽しんでおられるのでしょうね。ライブを楽しんでおられるお客さんたちの中には、別の日には、ここでライブをされるようです。なんというか、音楽好きのアマチュアからセミプロっぽい方達までが、この「中安商店」さんを大切な「場所」、あえていうならば「サードプレイス」にしておられるのですね。また、家庭でもない職場でもない、こういった「サードプレイス」が、けっこうあちこちにあるようなのです。素敵なことだと思います。「中安商店」さんはとても人気があって、かなり先の方までライブの予定が詰まっているようでした。入り口のフライヤーは、ここでライブを行う様々なバンドのものです。
▪️ところで、「中安商店」さん、晩はお店がライブハウスになるのですが、昼間は街中の酒屋さんとして営業されています。そこが、面白いですよね。
3月のような暖かさ…諸々

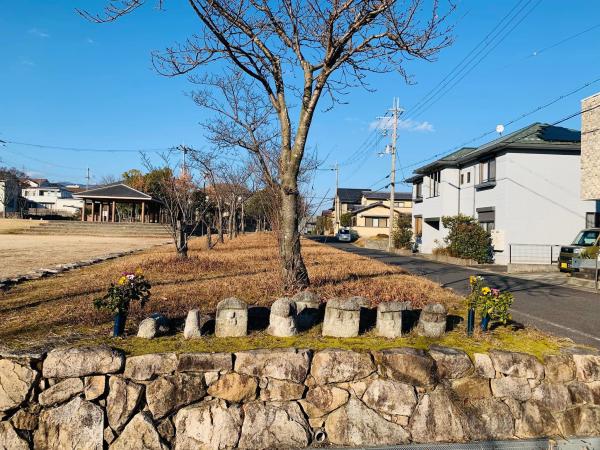
【ウォーキング】
▪️家で仕事をしているとほとんど歩かないことになるので、少しウォーキングをしてきました。いつもの公園から琵琶湖の北湖を眺めると、今日は薄ぼんやり伊吹山が見えました。もっと気温が低ければクリアに見えるのですが、急に3月のような気温になってきて景色はぼやけています。こんなに気温が高いと、琵琶湖の全層循環(琵琶湖の深呼吸)はどうなるのでしょう。心配ですね。
▪️ウォーキングの途中で、公園の端にお地蔵さんや同祖神が祀ってあることに気がつきました。何度もこのあたりは歩いていても、気がついていませんでした。きちんとお花も添えてあります。どなたかが、お世話をされているのでしょうね。もともと、このあたりは里山と農地でした。そこを新興住宅地を造成したのです。これは想像ですが、元々祀っていたものか、工事で見つかったものをここに集めているのではないかと思います。たしか、地蔵盆はやっていませんね。このあたりは小学生以下の年齢の子どもたちがたくさんいるので、よろこぶだろうな。もっとも、私自身は子どもの頃九州にいたので、地蔵盆の経験はありません。先日、「地域エンパワねっと」(社会共生実習)の相談会で、この地蔵盆のことと関連して学生さんと話をすることがありました。この地蔵盆、まちづくりに関連して大切な行事なのではないかと思います。
【鬼門について】
▪️話は変わります。「鬼門」について「あっ」と思ったことがあります。鬼門とは、北東の方角で、鬼が出入りする方角なのだそうですね。災いがやってくる方角なのだそうです。そのためなのか、どうかよくわかりませんが、京都の御所の北東には比叡山延暦寺があります。最澄が鬼門封じのためにこの場所を選んで延暦寺を建立したのか、たまたまなのか。どうなんでしょうね。知識がなくてよくわかりません。
▪️まあ、それはともかくです。地図で京都の御所から北東方面に確かに比叡山延暦寺があります。地図に定規を当てるとよくわかります。で、今日、気がついたのです。御所の北東に延暦寺があって、延暦寺の北東に我が家があることに。京の都の鬼門の方角に暮らしているのです。というか、延暦寺が鬼の侵入を防いでいるとしたら、我が家のあたりは鬼がたくさんいはる場所なのかな。いや、だからどうなんや…って話ではありますし、私が鬼門のことを気にしているわけでもないのですが。
 【イサザ豆】
【イサザ豆】
▪️またまた、話は変わります。先日、沖島で作ったイサザ豆をいただきました。この季節、琵琶湖の固有種であるイサザの漁は最盛期のはずです。このイサザ豆は砂糖を使っているので、持病のため一度にたくさんは食べられませんが、ビール(無糖)のあてとして楽しんでいます。本当は、イサザの吸い物とか味わってみたいのですが、どこにでも売っているわけではありませんので。なかなか難しいです。早めに夕飯の買い物に行き、お相撲初場所を「ビール(無糖)&イサザ豆」で観戦しています。
仰木での農作業、ホウレンソウの収穫


 ▪️今日の午前中は、仰木の畑で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。12月11日の投稿にも書きましたが、もうじき、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。その前に、耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めているのです。今日で5回目でした。これまでの農作業ですが、以下のとおりです。
▪️今日の午前中は、仰木の畑で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。12月11日の投稿にも書きましたが、もうじき、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。その前に、耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めているのです。今日で5回目でした。これまでの農作業ですが、以下のとおりです。
⚫︎10月22日:耕作放棄地の除草作業を行いました。
「農業体験プレイベント」
⚫︎ 11月13日:玉ねぎの苗を植えました。野菜の種も植えました。
仰木の野菜畑で農作業
⚫︎ 12月11日: 葉っぱが伸びてきた小カブと大カブ(聖護院大根)の間引き、ホウレンソウの種まき、それから寒さから守るためにシートで覆いました。
仰木の畑で冬の準備
⚫︎ 12月25日:種から育てた、キャベツとケールの苗を植えました。
仰木の畑でキャベツとケールを植えました。
⚫︎そして今日、1月12日:ニンジン畑の除草作業を行いました。そして、育ったホウレンソウを少し収穫しました。これは、お土産です。
▪️写真について説明しておきます。上段左は、今日、除草作業を行なったニンジン畑です。この写真を撮った時は、まだ手前のところしか除草できていませんが、5人がかりで綺麗にしました。ニンジン畑の右側、黒いマルチシートを被せてある畝が2列並んでいます。左の畝、これはキャベツとケールの畑です。右の畝、タマネギ畑です。両方ともまだ大きな変化は見られませんが、春になるとこれが立派なキャベツやケール、そしてタマネギになるのだそうです。上段右は、今日、収穫したホウレンソウ畑です。下段は、畑から写した比叡山横川中堂方面になります。仰木は比叡山の麓にある集落なのです。
▪️しばらく前に降雪がありましたが、おおかたはもう融けてしまっています。今日の農作業は、ニンジンの畑に生えた雑草を取り除く除草作業です。JAŚ有機の登録はまだしていませんが、認証されるのと同じやり方で野菜を生産しています。今日は保温用のシートを外して、5人の皆さんと一緒にニンジン畑の草を取り除きました。う〜ん、なかなか難しかったですね。根から引き抜かないといけないので、右腕の筋を少し痛めてしまいました。まあ、腱鞘炎にはなっていないとは思いますが…。それから、中腰、あるいはしゃがんで草を抜くので、少々疲れたのですが、まあ、足腰はそれなりにしっかりしているので、大丈夫です。
▪️この畑、もともと水田なので、土の粘り気が強く、雪解けの水で畝と畝の間がぬかるんでいました。畑に足を取られてけっこう大変です。指導してくださっている農家の方のお話によれば、落ち葉等を入れていくと、もう少しサラッとした畑になっていくとのことでした。それと、畝と畝の間のスペースが狭いこともあって、歩きにくいのです。特に、私のように足のサイドが大きい者にとっては辛いところがあります。今日は農家の方ともその話もしました。次にトラクターを使う際には、もう少し畝と畝の間を広げてもらうことにしました。
▪️ニンジン畑ですが、種まきの時期が遅かったので、ニンジン自体はまだあまり成長はしていません。草を抜くときに、気をつけなければニンジンも一緒に引き抜いてしまいそうでした。まだ、そんな感じなんですが、これが立派なニンジンに成長していくのですね。楽しみです。ニンジン畑の除草作業のあとは、成長したホウレンソウを少し収穫しました。この畝の端まで収穫すると相当な量になると思います。今日は、畝の端っこの方を、自宅で消費できる程度をいただいてきました。これは、お土産です。お土産のホウレンソウ、自宅に戻ってから、冷蔵庫のベーコンと炒めてスパゲティにしていただきました。やわらかくてとても美味しかったです。ちなみに、スパゲティといっても、小麦の麺ではなくて豆を原料にした糖質の少ない麺です。糖質、気にしていますから。お土産のホウレンソウはけっこうな量になったので、ホウレンソウのレシピをいろいろ検討しなくてはいけませんね。
3回目の新年会
▪️昨晩は、3回目の新年会でした。場所は大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。お相手してくださったのは、雨森 鼎さんと安孫子邦夫さんです。お2人には、社会学部で長年取り組んできた地域連携型の教育プログラム「大津エンパワねっと」や、その「大津エンパワねっと」の発展系である「社会共生実習」のひとつ「地域エンパワねっと・大津中央」で、大変お世話になってきました。履修した学生さんたちを丁寧にご指導くださいました。ということもあり、お2人とは時々、酒席をご一緒させていただいています。
▪️雨森さんも安孫子さんも後期高齢者、前期高齢者の私からすると人生の大先輩です。前期後期の違いはありますが、そのような高齢者同士の酒席での話題というと、かなりの確率で健康のことになってしまいます。昨晩は、歩くスピードが以前と比較して遅くなっている…ということが話題になりました。100kmウォーキングの大会に出場したりしていますが、自宅近くの坂道で、高校生に追い抜かされることがあります。普通に歩いているつもりなのですが、女子高生にも追い抜かされることもあります。以前は、私が追い抜いていく側だったのですが…。
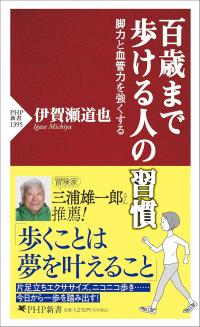 ▪️そのような昨晩の話題が記憶に残っていたものですから、このようなネットの記事が目に止まりました。「人生100年時代でも、健康寿命は非常に短い。延ばすためには、脚力と血管力の両方が必要。歩行速度の低下が、動脈硬化の増加に」という記事です。医師が執筆した新書『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)の内容を要約した記事のようです。ですから、本当は、元々の新書の方を確認しないといけないのでしょうが、記事によれば…
▪️そのような昨晩の話題が記憶に残っていたものですから、このようなネットの記事が目に止まりました。「人生100年時代でも、健康寿命は非常に短い。延ばすためには、脚力と血管力の両方が必要。歩行速度の低下が、動脈硬化の増加に」という記事です。医師が執筆した新書『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)の内容を要約した記事のようです。ですから、本当は、元々の新書の方を確認しないといけないのでしょうが、記事によれば…
・健康寿命は、「食事を自分でとれる」「トイレが自分で使える」「お風呂に自分で入れる」など、日常生活ができる期間と言い換えることができる。
・歩かないと、年をとると歩けないことに直結する。
・普段から脚力を鍛えて、生活のなかでつまずいたり転倒したりすることを防ぐことが大切。
・そのような脚力と血管力(=血管年齢:おもに血管の柔軟性や弾力性を示す指標)は深く関係している。
・血管年齢が高い場合には、脚力が弱い=太ももの筋面積が小さい。
・歩行速度の低下が、とくに下肢の動脈硬化の増加と関連している。
▪️なるほどと思う記事でした。このネットの記事の内容は、この新書の序章を要約したもののようですね。amazonで少し目次を眺めてみましたが、おもしろそうです。役にも立ちそうです。ということ『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)を読んでみようと思います。以下は、amazonでのこの新書の紹介です。
「人生100年時代」には、介護が不要な状態を保つ「健康寿命」を延ばすことが人生を楽しむ鍵になる。それには自分でしっかり歩けることが肝要だ。
抗加齢医学研究に長年携わってきた著者は、歩くための力には「脚力」と「血管力」があるという。本書は、百歳まで歩ける人になるために、脚力と血管力を鍛えるエクササイズや、ウォーキング事例を紹介する。
脚力を鍛えるためには、「かかと上げ下げエクササイズ」「片足立ちエクササイズ」「ゆるジャンプ」「座ろうかなスクワット」などがおすすめ。
血管力については、ヒハツ、シナモン、ルイボス茶などを摂って毛細血管を強くすること、ニンニク、ナッツなどを摂ったり、ウォーキングや軽いサイクリング、エアロビクスなどの有酸素運動をしたりして大血管を強くすること、などを推奨している。
ウォーキングについては、著者が考案した「ニコニコ歩き」のほか、「インターバル速歩」「パワーウォーキング」「俳句ウォーキング」などを解説している。
日々の心がけ一つで、いつまでも歩ける人になれる。
学生時代の部活の同窓会


 ▪️今晩は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の、私の前後の学年の方達のうち、滋賀県に居住されていか勤務されている方達が集まりました。というわけで、「関西学院交響楽団OB・OG会滋賀支部」(勝手に立ち上げましたが…)の「総会」です。今回は、卒業後、ずっとお会いしていなかった方も参加してくださいました。ということは、40年ぶりの再会ですかね。
▪️今晩は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の、私の前後の学年の方達のうち、滋賀県に居住されていか勤務されている方達が集まりました。というわけで、「関西学院交響楽団OB・OG会滋賀支部」(勝手に立ち上げましたが…)の「総会」です。今回は、卒業後、ずっとお会いしていなかった方も参加してくださいました。ということは、40年ぶりの再会ですかね。
▪️今日は、OB・OG会ですから当然なのですが、昔話に花を咲かせました。びっくりしたのは、参加された方の恋愛話でした。当時、オーケストラの活動を一緒にしていたのですが、ぜんぜーんそいうことを知らなかったからです。いろいろありますね。今日参加された皆さん、全員、還暦越えの皆さんです。一番下の方が、61歳。また、この飲み会を持ちたいと思っています。右の白黒写真は、今は還暦を超えた面々が現役の学生だった時のものです。前列、左から3人目は、私です。4回生の時は、コンサートマスターを務めていたので、偉そうに真ん中に座っています。私の右側は、学生指揮者です。4回生の後ろで交響楽団の団旗を持っている後輩も、昨日の宴会に参加されました。
▪️学生時代のつながり、この年になると大変ありがたいなと思います。まあ、ありがたいと思えること自体が幸せなことなのだと思います。そうそう、写真は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。たまには別の店にしようかなと思いましたが、結局、「利やん」になりました。
弁当と昆布の佃煮
 ▪️今日も大学に行くことになったので、冷蔵庫にあるもので弁当を作りました。一応、血糖値のことを考えています。ピーマンの炒めもの、チクワの蒲焼、白いのは小蕪を炊いたん、プチトマト。ご飯は、ロウカット玄米に黒胡麻とふりかけをまぶしたもね、ウインナーと冷凍食品のミンチカツとミニハンバーグ。
▪️今日も大学に行くことになったので、冷蔵庫にあるもので弁当を作りました。一応、血糖値のことを考えています。ピーマンの炒めもの、チクワの蒲焼、白いのは小蕪を炊いたん、プチトマト。ご飯は、ロウカット玄米に黒胡麻とふりかけをまぶしたもね、ウインナーと冷凍食品のミンチカツとミニハンバーグ。
▪️出勤までに時間があったので、冷蔵庫に置いてあった出汁昆布(鍋で使いました)と冷凍庫に入れてあった山椒で、佃煮も作りました。スーパーで買った安い出汁昆布で、お店で売っているような立派な厚みのある昆布ではないし、砂糖ではなく血糖値を考えて人工甘味料のパルスイートを使っているので、見た目はイマイチかもしれませんが、味はなかなかのものでした。ご飯のお供と言いたいところですが、私は白米は食べられないので、酒の肴かな。
▪️今日は、留年されている学生さんの相談に乗ることになっています。学生さんの方から相談したいとの連絡をくれたので、ホッとしています。無事に卒業してほしいです。


おうみ会


▪️昨日は大学に行く日でした。朝、「血糖値をあげない弁当を」作って、月1回のクリニックへ。昨日も医師と看護師さんにきちんと血糖値をコントロールしていることを褒めてもらいました。この歳になって褒めてもらえることって、滅多にありません。この月1回の診療ぐらいかな。HbA1cは5.3、血糖値、中性脂肪、肝機能全て問題なしでした。安心しました。ちなみに「血糖値を上げない弁当」っこんな感じです。小さな2段重ねの弁当箱。ひとつはブロッコリー、プチトマト、小松菜のお浸し、シメジの炒め物。もうひとつは、炒り卵(卵1個)、冷凍食品の弁当用のソース豚カツとハンバーグ。小さいやつです。それから、玄米。玄米は、茶碗で言えば1/3程度です。これでも不満に思わないようになりました。
▪️来年度、勤務している社会学部は瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転します。問題は引っ越しです。昨日は、オンラインですが、引越しの説明会がありました。担当部署の方、それから実際引越しを行う業者さんが資料に基づき丁寧に説明してくださいました。書籍の類は、業者さんが全て梱包してくれるし、引越し作業にあたって事前にヒアリングがあることもわかり少し安心しました。しかし、2004年から20年にわたって使用してきた研究室には、書籍以外にもたくさんのものが溜まっています。いらない書類は廃棄するとして、大量の資料があります。これは、ファイルに綴じてあるのですが、これを梱包しなくてはいけません。あと、自宅に持って帰らないといけないものも多数あります。さらに、廃棄、売却等で書籍もできれば少し減らしておきたいと思います。ざっと研究室を見回してみましたが、これからの作業に少し心が萎えてしまいました。
▪️説明会の後は、大学院社会学研究科の研究科長選挙。今年度は特別研究員ですが、学長選挙も含めて選挙はきちんと投票しました。そして、そのあとは社会学部の懇親会「おうみ会」の忘年会でした。場所は、琵琶湖プリンスホテルの最上階38階の「トップオブオオツ バンケットルーム」です。もうすでに真っ暗でしたが、美しい月が昇ってきました。たた、できれば昼間、ここから琵琶湖を眺めみたかったですね。今年度は同僚の皆さんにリアルにはほとんど会うことがなかったのですが、昨日は久しぶりに食事をしながらおしゃべりを楽しむことができました。
▪️「おうみ会」の後は、大津駅前まで同僚の津島昌弘さんと一緒に移動し、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で2人だけ二次会を持ちました。30分くらいかな。私の方がずっと年上なのですが、還暦を超えたという点では一緒です。年齢が年齢だけに、健康管理の話になってしまいます。写真、シャッターのタイミングが悪く、とんでもない柄の悪い目つきになっているので「自主規制」しました。
第79回毎日甲子園ボウルを観戦しました。



▪️昨日は、良い天気でした。朝は、暮らしている住宅地の自治会の一斉清掃の日でした。公園の樹木のものすごい量の枯葉が住宅地内の道路にまで風で飛ばされてきて、当該のエリアの皆さんはお困りだったので、小一時間ほどその落ち葉の除去作業に取り組みました。そのあとは、餅つき大会があったのですが、私は西宮に向かいました。第79回毎日甲子園ボウルを観戦するためです。
▪️大変残念なことですが、母校の関西学院大学ファイターズは、アメリカンフットボール全日本大学選手権準決勝で法政大学に敗れたため、決勝戦であるこの「甲子園ボウル」に出場することができませんでした。それでも、今年の「甲子園ボウル」の立命館大学パンサーズ(関西1位)と法政大学オレンジ(関東1位)の試合を観戦したかったのです。昨年の「甲子園ボウル」では、関西学院大学ファイターズが大差で法政大学を破り優勝しました。母校の優勝は嬉しかったわけですが、試合内容はいまいちだったように思います。ワンサイドゲームでした。しかし、今年の「甲子園ボウル」は違いました。肉体的にも能力的にもずば抜けた両校の選手の皆さんが活躍されていました。立命館が最後は逃げ切りましたが、とても盛り上がる試合内容だったと思います。素晴らしかったと思います。
▪️結果ですが、立命館大学が法政大学を45ー35で破り、9年ぶり9度目の優勝を飾りました。立命館大学の関係者の皆さん、おめでとうございます。優勝したのは立命館大学ですが、法政大学も相当頑張っていました。その様子は、この投稿に貼り付けたハイライトシーンでご確認ください。試合の冒頭、立命館大学の山嵜(RB)選手が、強力なオフェンスラインに守られながら、法政大学のディフエンスを潜り抜けて独走し、タッチダウンしたシーンが印象に強く残ることになりました。立命館大学を法政大学が追いかける試合展開で、一時は3点さまで詰め寄りましたが、最後はまた立命館大学に突き放される形になりました。試合を楽しませてもらいましたが、来年の「甲子園ボウル」では、また関西学院大学が出場してほしいです。来年も「甲子園ボウル」を観戦します。そして、校歌「空の翼」を歌います。
 ▪️昨日は職場で作っている母校の同窓会「龍谷大学新月会」の会員で、経済学部の教員である工藤和也先生と法学部教務課に勤務されている平國祐樹さんと一緒に観戦しました。工藤先生は、大変アメリカンフットボールにお詳しく、先生の解説を聞かせて頂きながら観戦することができました。贅沢ですね。試合後は、工藤先生はご帰宅されましたが、平國さんと私は、梅田の居酒屋に向かい、やはり関学の同窓生で龍谷大学を退職された増田滋さんと3人でプチ同窓会を持ちました。楽しい一日でした。
▪️昨日は職場で作っている母校の同窓会「龍谷大学新月会」の会員で、経済学部の教員である工藤和也先生と法学部教務課に勤務されている平國祐樹さんと一緒に観戦しました。工藤先生は、大変アメリカンフットボールにお詳しく、先生の解説を聞かせて頂きながら観戦することができました。贅沢ですね。試合後は、工藤先生はご帰宅されましたが、平國さんと私は、梅田の居酒屋に向かい、やはり関学の同窓生で龍谷大学を退職された増田滋さんと3人でプチ同窓会を持ちました。楽しい一日でした。
▪️甲子園球場の外では、記念品の物販が行われていました。私は、マグカップを買わせていただきました。自宅では、BSで放映された昨日の試合を録画していましたので、このマグカップでコーヒーをいただきながら、録画を見て、いろいろ「復習」してみることにします。
豊かな暮らし

▪️理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、大津市の仰木で耕作放棄地を農地に復活させ、農家と近隣の地域住民とが協働して有機野菜の栽培に挑戦するプロジェクトに取り組んでいます。一昨日の午前中は農作業の日でした。作業のひとつは、カブを間引くことです。これは小蕪ですが、密集しているとカブの根である、あの白いところが大きくならないのだそうです。ということで間引くのですが、間引いた間引菜はお土産としていただきました。
▪️今日の昼食は、この間引菜をお浸しにして、そして味噌汁も作りました。茹で上がった間引菜、何も味付けをせずにそのまま食べましたが、柔らかくて、優しい味がしっかりあって、とても美味しかったです。「豊かな暮らし」って、こういうことなんだなと思います。この間引菜以外に、シュンギクもいただきました。晩は湯豆腐にして、シュンギクをいただこうと思います。