第2回「ナカマチのひみつきち」


▪️昨日は、「地域エンパワねっと」(龍谷大学社会学部社会共生実習)の学生さんたちが主催した「ナカマチのひみつきち」の第2回目のイベントが、大津市中心市街地のナカマチ商店街にあるナカマチスタジオで開催されました。ナカマチ商店街は、丸屋町商店街、菱屋町商店街、長等商店街の3つの商店街が連なった商店街です。ナカマチスタジオは、その中の菱屋町商店街にあります。平和堂のフレンドマートの前です。今回も前回と同様に、最近この地域に転入されてきた若い親子で絵本を楽しんでいただきながら、「商店街とのつながりや、若い親子同士のつながりが生まれるきっかけになったらいいな」、そのような思いから企画されています。
▪️今回も、たくさんの親子がお越しくださいました。ありがとうございました。私は、通り過ぎりのお爺さんのような感じで、会場にいるだけですが、学生さんたちは頑張っていました。小さなお子さんが選んだ絵本を読んであげたり(読み聞かせ)、紙コップ+輪ゴム+ペットボトルのキャップを使った工作も手伝ってあげたり。スタジオはガラス張りなので、商店街を歩く方たちが、スタジオの中の楽しそうな雰囲気を気にしておられるのが良いなあと思いました。なかには、「楽しそうやね〜」とそばによって見学される方や、スタジオ内でお子さんと一緒に工作をされているお母さんの様子をご覧になって、「お母さんが楽しそうやわ〜」とおっしゃる方もおられました。
▪️私は、基本、通りすがりのお爺さんなんですが、このナカマチスタジオが取り組んでおられる事業に関心をお持ちの方たちと、知り合い、じっくりお話をすることができました。これから、何かコラボできたらいいなと思います。そのようなコラボも含めて、このナカマチスタジオや商店街そのものが、様々な方達が交流できる場所になっていったら素晴らしいなと思っています。そうそう、今日は、映像作家の中島省三さんにひさしぶりにお会いすることができました。ナカマチスタジオの中にある「Oi Caffe」にコーヒーを飲みにこられた時に、偶然お会いしました。私が琵琶湖博物館の開設準備室に勤務している時からのお付き合いですから、知り合ってから35年ぐらいになりますかね。いろいろ、懐かしい話をすることができました。ありがとうございました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」だけでなく、同じ中心市街地にあるこの商店街も私にとっては、人とのつながりを生み出す「場所」なのだなと思います。自分の人生にとって、とても大切な「場所」なのだと思います。
▪️昨日は、来年度の社会学部のパンフレットの取材がありました。「地域エンパワねっと」を履修している1人の学生さんに焦点をあてて取材をされていました。左側の写真、カメラマンの方がスタジオ内にレンズを向けて写真を撮っておられるところです。また、京都新聞の取材もありました。本日の京都新聞の滋賀版で記事になりました。みなさん、ありがとうございました。

2025年度社会共生実習「活動報告会」




 ▪️今日は、社会学部の2025年度社会共生実習「活動報告会」の日でした。昼休みと3講時の時間を使って実施しました。今年度のプロジェクトは全部で5つでした。そのうちの1つは前期で終了したこともあり、今日はポスターを掲示(テーブルの上に)しただけでしたが、他の4プロジェクトは、前半に口頭での各プロジェクト発表(3分)と、後半にポスター発表(13分)を行いました。
▪️今日は、社会学部の2025年度社会共生実習「活動報告会」の日でした。昼休みと3講時の時間を使って実施しました。今年度のプロジェクトは全部で5つでした。そのうちの1つは前期で終了したこともあり、今日はポスターを掲示(テーブルの上に)しただけでしたが、他の4プロジェクトは、前半に口頭での各プロジェクト発表(3分)と、後半にポスター発表(13分)を行いました。
▪️ポスター発表では、参加者は4つのプロジェクトを順番に回りました。まず、受講生から3分間の説明を受けた後、参加者の皆さんに質問やコメントをしていただきました。また、ポストイットカードに書いてポスターに貼り付けていただきました。
▪️今日は、学外から19人の方達がご参加くださいました。京都市役所、大津市役所、それから京都信用金庫からもご参加くださいました。これまでもこういった報告会を開催してきました。ただ、昨年の春に社会学部が深草キャンパスという参加しやすい便利な場所に移転したせいかもしれませんが、今日はいつもよりもたくさんの方達が参加してくださったように思います。加えて、龍谷大学附属平安高校の高校3年生で来春から社会学部に入学することがきまっている生徒さんたちも参加してくださいました。ありがとうございました。最後に講評を3人の方にお願いしました。平安高校の先生、本学教育企画部の課長さん、そして政策学部の井上芳恵先生のお3人です。平安高校の先生からは大切なご提案もいただきました。来年の報告会に役立てていきます。高校生の皆さんがもっと積極的に参加できる工夫をしてまいります。
▪️さきほども書きましたが、社会学部は昨年の春に深草キャンパスに移転しました。社会科学系の学部がこのキャンパスに集まったのです。できれば、学部の垣根を越えてさまざまな交流がうまれてほしいと思っていますし、異なる学びをしている(学部が異なる)学生さんたちが、力をあわせて地域課題に取り組むような、PBL的、CBL的な実習がこのキャンパスから生まれてきてほしいと思います。今日の山川課長や井上先生からの講評でも、同様のご意見をいただくことができました。そのような取り組みが生まれてから定年退職したかったのですが、私にはもうそれだけの時間がありません。私よりもお若い、同じような「志」をお持ちの教職員の方達に、ぜひ大学を導いていただきたいと思います。
他者の他者性
▪️今日は、2回生対象の社会学基礎ゼミナールで「杉岡先生を偲ぶ」というタイトルの高田文英先生(文学部・真宗学科)の講演録を読みました。『りゅうこくブックス 今ここの苦によりそう』138(龍谷大学宗教部)に収録されています。杉岡孝紀先生は、実践真宗学研究科で「宗教実践演習」を担当予定だったようですが、病気でお亡くなりになり、そのあとを高田先生が代わって担当されました。シラバスに書かれたテーマは「真宗他者論」でした。杉岡先生がお亡くなりになったので、履修予定者の院生のみなさんはそういうことであればと、他の先生の演習に変更されたのですが、お1人だけ「真宗他者論」を学びたいということで、高田先生はその院生の方と2人で演習をされたようです。贅沢な話ですね。
▪️この講演録、2回生のゼミ生の皆さんにも大変前向きに受け止めてもらえました。ゼミのテキストのひとつとして利用させていただいたわけですが、よかったなと思っています。
▪️高田先生は、杉岡先生の問題意識について、このように書いておられます。真宗学においては「他者との関係」ということが見過ごされてきたのではないかという問題意識です。もちろん、浄土真宗は阿弥陀如来との直接的な一対一の関係が根本ですが、親鸞聖人は「あらゆる諸仏や菩薩たち、天の神や地の神など」も信仰の中に位置づけられているし、異なる考えの信仰や、それを信仰する人々との関係性についても、考えを巡らしていたというのです。知りませんでした。杉岡先生は、阿弥陀如来と私という関係性が信仰の中心であっても、「それが全てのように捉えることで、その他の私たちを取り巻く様々な存在との関係というものが捨象されがちになっているのでないか」とお考えだったのです。
他者は私が決して理解することのできない存在である。その理解できないという事実を無視して、勝手に自分のなかで理解したつもりになるのならば、それは相手の独自性を抹殺することであり、それは暴力に他ならない。
▪️杉岡先生は、「他者は私が決して理解することのできない存在」と捉えておられました。それを「他者の他者性」と概念化されていました。フランスの哲学者エマニュエル・レヴィナスの他者論の思想からも学びとられていました。「他者の他者性を廃棄することは暴力になつながる…」、高田先生は杉岡先生のこの指摘をご自身の経験のなかで反芻されています。「『私は相手のことが分かっている』という思いが相手を傷つけ、相手の声を抹殺していく、そうしたことにも繋がってしまう」わけです。
▪️でも、それではどうすればよいのか、すぐにそのような指摘が出てきそうです。高田先生は以下のように話されています。
決して他者を理解することはできないという認識は、一見否定的で、あまり生産的なことではないように思ってしまいます。しかし、心のどこかでこの他者の他者性に思いをいたすことが、逆説的ですが、相手の思いを受け止めていく可能性を開いていく。とくに宗教信仰は一面において、独善的な排他主義に陥りやす危険性を孕んでいる。浄土真宗はそこを省みながら、具体的な事柄に対応していかねばならない。杉岡先生はそういうことをおっしゃっているのであろうと、私は理解しております。
▪️ここで大切なことは、「他者の他者性」という自分の物差しでは捉えきれないものをもっているということを常に前提として、相手の思いを受け止めていく…ことなのでしょうが、これはとても困難なことなのだろうなと思います。高田先生は、杉岡先生のお考えは、「他者の他者性ということを認識し、そこに耳を傾けること」だと述べておられます。
▪️もうひとつこういう大切なことも指摘されています。
他者の他者性を対象化するということ、それは裏返して言えば、私自身の愚かさを対象化するといてことでもあろうと思いますが、それは、自分は分かっていると自己完結してしまう在り方ではなく、他者の声を聞き続けるという、外に開かれた在り方を志向するものと言えます。
▪️龍谷大学の行動哲学は、「自省利他」です。他者のために何かを行うことは「利他」ですが、前半の「自省」の部分に、このか「他者の他者性」が深く関わっているのだと思うわけです。それがなければ、「利他」は暴力になってしまう危険性を孕んでいます。また、この「他者の他者性」という概念を根本におくと、様々なディシプリンの間に対話が生まれてくるような気もします。社会学部が移転した深草キャンパスで、そのような動きが生まれてくると素敵だなと思っています。
脇田ゼミ1期生の同窓会


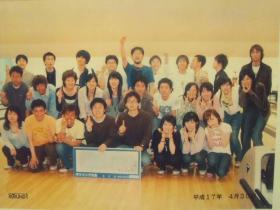
▪️先日の土曜日は脇田ゼミ17期生の皆さんとの同窓会にお呼びいただきましたが、月曜日(12月29日)の晩は、脇田ゼミ1期生の皆さんの同窓会にお呼びいただきました。ありがとうございました。幸せですね。1期生ということで、私が龍谷大学に勤務するようになった最初の学年です。脇田がどんな教員かもわからず、よく私を選んでくれたものです。龍谷大学社会学部の以前は、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。公立大学ですからゼミ生の人数は少なく、多くても6名でした。龍谷大学に異動するとき、私立大学に移っても、公立大学の時と同じ水準の指導を学生の皆さんに行うと自分に誓ったこともあって、結構、厳しく指導していたのではないかと思います。全員にフィールドワーク(調査)を半ば強制していました。それでも、この学年の皆さんはよく頑張りました。1期生は全員で18名ですが、今でもLINEグループで繋がっているのは、そのうちの12名の皆さんです。LINEって大切ですね。手紙や電話でしか連絡が取れない時代だと、同窓会をひらくのもなかなか大変だったんじゃないのかな。どこに住んでいるのかもわからなくなりますからね。
▪️写真ですが、1枚目は一次会です。野菜が美味しい創作料理店。自分のところで野菜を生産して、系列店で使っているのだとか。「囲炉裏酒場 炭棲堂」さんです。たまたまですが、龍大農学部食品栄養学科の1回生のアルバイトさんが働いておられました。2枚目は二次会です。卒業してから20年経過すると、自営業の方以外、転職もいろいろありますね。みなさん、頑張って働いておられます。3枚目はずいぶん昔のもの。1期生と2期生(当時の4回生と3回生)とボーリング大会をした時のものです。懐かしいです。今は無くなった、石山のボーリング場です。写真ではまだ可愛らしさが残っている1期生の皆さん、今は42歳になりました。
▪️昨日の朝になりますが、いつも幹事役を引き受けてくれている方からLINEグループに投稿がありました。来年度で私が定年退職するということで(私のラストイヤーだそうです)、来年も同窓会を開催して、お呼びくださるようです。楽しみです。
脇田ゼミ17期生の同窓会

▪️この前の土曜日(12月27日)は冬期休暇中ですが、研究室に、自宅で仕事をするのに必要な書籍と資料を研究室に取りにきました。そして夕方から京都駅前の居酒屋へ。脇田ゼミ17期生の皆さんの同窓会に呼んでいただきました。ありがとうございます。東京で働いている人も年末や年始は関西に帰省するので、昨年も年末に同窓会を開催されていました。ずっと続くと良いなと思っています。土曜日は、福井県からやってきた人もいました。
▪️卒業したのは、2024年の3月ですが、社会人になってまだ2年に満たないのに、ずいぶん成長されているように感じました。当たり前と言えば当たり前ですが、話している内容からして違っていますからね。社会人の会話でした。そうそう、東京で働いている方は、関西弁を喋らなくなっていました。環境は人を変えますねww。
▪️17期生の皆さんにも、生成AIを仕事で使っているかどうかを聞いてみました。みなさん、ガンガン使っておられました。もうAIを使わないと仕事が成り立たないのでしょうね。
「ナカマチのひみつきち えほんとこうさくを楽しもう!」
卒業生との同窓会


▪️あっという間に1年が過ぎてしまいました。年末は、脇田ゼミの出身者の皆さんが、同窓会を開催されるそうで、幸せなことにその同窓会にお呼びいただいています。ありがたいことですね。まず、27日に2024年春に卒業された17期生の皆さんの同窓会が、そして29日には2006年3月に卒業された1期生の皆さんの同窓会が開かれます。楽しみにしています。
▪️2枚の集合写真、両方とも卒業式の時のものです。この写真の中に私も写っています。左の写真、一番後ろの列の真ん中あたり。顔は丸いです。今よりも10kgほど体重が思いはずです。髪の毛はたくさんあるし、色も黒いし。髭も真っ黒です。まだ40代ですね。右の写真は、2024年3月ですから、比較的最近です。こちらも一番後ろの列の真ん中あたり。時の経過を感じます。1期生の皆さんは、40歳を超えて社会の中堅として活躍されています。一方、17期生の皆さんは社会人になって仕事をきちんとこなせるようになってきた頃でしょうかね。どのようなお話をお聞かせいただけるのか、楽しみです。
実習報告会
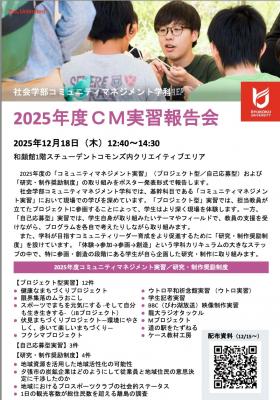


▪️上段左の画像は、本日18日に開催された「2025年度CM実習報告会」のチラシです。2回生以上が履修する旧カリキュラムの実習なのですが、旧カリキュラムの時代は3学科体制(今は1学科体制)で、その3つの学科のうちのコミュニティマネジメント学科の実習になります。私は、旧カリキュラムでは社会学科なので、この実習を担当することはありませんが、今日は見学させていただきました。ありがとうございました。
▪️上段右のこちらも実習の活動報告会のチラシになります。こちらは、旧カリキュラムで3学科合同で運営している「社会共生実習」の活動報告会です。ややこしいですね。旧カリキュラムでは、3つの学科がそれぞれの実習を運営していましたので、話がややこしくなります。開催は、来月の1月9日です。当日、私は司会進行を担当します。学外からもご参加いただけます。指導している「ナカマチのひみつきち」のグループも発表します。下段は、その「ナカマチのひみつきち」のグループがInstagramにアップした画像です。今月開催した1回目は、絵本と紙芝居のイベントでしたが、来月の2回目は絵本と工作のイベントになります。楽しい会になると思います。
▪️「社会共生実習」の活動報告会については、社会学部以外の教職員の皆さんに講評していただく予定です。おひとりは、すでに決定しています。政策学部の井上芳恵先生です。井上先生も、伏見区の商店街の活性化に関して学生さんたちと一緒に実習に取り組まれています。「ナカマチのひみつきち」にも、わざわざ見学に来てくださいました。ありがとうございました。
▪️今年の4月から社会学部が滋賀県大津市の瀬田キャンパスから京都市伏見区の深草キャンパスに移転しましたが、それは社会科学系学部を深草に集約し、キャンパスの活性化と多様な学びの拠点化を目指すためです。ということなのですが、実際には、学部の垣根を越えての交流が進んでいるとはいえません。じっと待っていても、交流は進みませんので、それぞれの教職員や学生が各自の立ち位置から交流を進めていく必要があると考えています。というわけで、今回は、政策学部の教員である井上先生に活動報告会を見学し、最後に講評していただくことにしました。
まちなかメンタルヘルス2025 大津編 (秋田大学地域心身医療学公開講座)
◾️ひとつ前の投稿に関連した投稿です。ナカマチスタジオで、学生さんたちの活動を見学していたら、そこにやってこられていた秋田大学大学院医学系研究科(医学専攻等)医学専攻・社会環境医学系・地域心身医療学講座の助教のロザリン・ヨン先生から、突然、インタビューを受けることになりました。それが、すぐにYouTubeにアップされていました。びっくり。
「ナカマチのひみつきちで えほんじかん を楽しもう!」



◾️このまえの土曜日、12月13日に、龍谷大学社会学部社会共生実習「地域エンパワねっと」を履修している学生さんたちが、大津市の中心市街地にあるナカマチ商店街で「ナカマチのひみつきちで えほんじかん を楽しもう!」というイベントを開催するので、その様子を見学してきました。場所は、ナカマチ商店街のなかの菱屋町商店街にある「ナカマチスタジオ」です。写真には出せませんが、この場所のスペースにちょうど良い数のご家族が来てくださいました。ありがとうございました。
◾️午前中、同時開催の湖太郎さんによる「怪談文学紙芝居」に、NHKの取材が入りました。来週の木曜日の18時半からのローカルニュースで放送されるようです。大学の学長室広報がプレスリリースしてくださったおかげで、中日新聞の取材もありました。こちらは、学生さんたちが開催したイベントがメインの取材です。中日新聞は、このような小さな街中の出来事にも取材に来てくださいます。いつも、ありがとうございます。
◾️2021年に「地域エンパワねっと」で開催したイベント「あつまれ!みんなで作る絵本館」の取り組みを継承しています。以前は、大津市の町家サテライトオフィスで開催しましたが、今回は、中心市街地の商店街にあるまちづくりの拠点です。中心市街地にどんどん建設されているマンション、そこに転入されてくる若いご家族の皆さんと商店街をつなぐきっかけを作ろう、子どもの時から商店街に親しめるチャンスを作ろうと頑張って準備を進めてきました。お世話になったキーパーソンの方が、「のべ20〜30人ほどの来場者を迎えながら、その場その場で工夫されている姿がとても印象的でした。初めてのことばかりで大変だったと思いますが、楽しそうに取り組む様子が微笑ましく、こちらも元気をもらいました」とコメントをくださいました。私のめから見ても、学生諸君、頑張って、張り切って取り組んでいたと思います。
◾️このイベントは、来月は確実に開催されます。そのあとも、すくなくとも1年間は続けてほしいと思っています。
