琵琶湖低層の無酸素状態について
▪️新聞各紙でも報道されていますが、滋賀県が、琵琶湖の北湖の低層で無酸素状態が確認されたことを発表しました。原因はいくつか考えられるようですが、そのうちのひとつが、表層水温の高さです。水温が高いと比重が軽くなり、底の方の重い水と混じりにくくなるので酸素が供給されにくい…ということのようです。
昨年度と同様今年度も、表層水温が高く水温躍層が強固に形成され、6月以降に強風の日が少なく底層付近の水の混合が弱いことも、底層DOが大きく低下している要因と考えられる。
▪️ただ、なぜ表層水温が高いのかについて、滋賀県の発表にはその理由が書かれていませんが、常識的に考えて猛暑日が続いたことが原因かと思います。ということは気候変動と結びついてくることになります。無酸素状態になることで心配されることは、底泥の中の重金属やりんが酸素と切れてしまい、溶け出してくることにあるようですが、水質から見る限り今のところそういう影響はみられないとのことです。でも、安心はできません。
底層DOが低下することで影響を受けやすいとされる水質項目には、重金属類(マンガン等)や栄養塩類(りん等)がある。
底層DOの低下がみられる7月中旬以降からこれまでの間に、これらの水質項目の濃度に特に影響は見られていない。
▪️かつて琵琶湖の富栄養化問題の時は、下水道等という技術的解決手法、法的規制、加えて社会運動(たとえば石けん運動)等によって社会的にコントロールしようとしてきました。富栄養化の原因は、琵琶湖の周りの地域社会の中にあったからです。しかし、琵琶湖の無酸素状態が発生する原因のひとつが気候変動にあるのならば、それは地球規模のメカニズムの中で生じているということになります。どうやって対処していったらよいのか…と戸惑うことになります。滋賀県民だけが頑張っても、無酸素状態は改善されません。
▪️温暖化ガスの排出が地球温暖化を生み出し、その結果、北極域の昇温により偏西風は蛇行をするようになり、偏西風の蛇行は、移動性高気圧、台風、低気圧などの動きに作用して、それらを長く同じ地域に留まらせるようになり、また温暖化によって派生する大量の水蒸気は台風を成長させ…いろんな要因が繋がっていくことの中で、さらに琵琶湖低層の無酸素状態が水質と生物に悪影響を及ぼすという心配事にも繋がっていくのではないかと思うのです。低層の無酸素状態という自然の側からの「サイン」を、私たちはどう受け止めたら良いのでしょうか。
▪️話は少し変わります。滋賀県が定めたマザーレイクゴールズ(MLGs)は、多くの皆さんの議論の中かから生まれた13のゴールです。「Goal 7」は「びわ湖のためにも 温室効果ガスの排出を減らそう」です。「日常生活や事業活動から排出される温室効果ガスを減らす取組が広がり、琵琶湖の全層循環未完了などの異変の進行が抑えられる」からです。これは、無酸素状態、水質や生物への悪影響と直接的に結びついています。ただし、ここが大切なことなのかなと思いますが、「Goal 7」は、他の12のゴールとも直接的にそして間接的に連関しあっています。そして、最後の「Goal 13」は「つながりあって目標を達成しよう」です。「年代や性別、所属、経験、価値観などが異なる人同士、また異なる地域に住まう人同士がつながり、琵琶湖や流域の現状、これからについて対話を積み重ね、その成果を共有できる機会が十分に提供される」ことを目指そうというのです。
▪️私は、前期高齢者の老人ですが、気候変動を生み出してしまったことに対して責任のある世代です。若者の皆さんからは、もっと批判されて良いように思います。私は老人ですから、そのうちに死んでしまいますが、若者(孫の2人はそこに含まれます)の皆さんは、その後も気候変動が厳しくなる状況の中で生きていかなければなりません。将来においてより大きな被害を受ける可能性があるわけです。気候変動のことで怒っている若者のことがニュースに登場します。ただし、そのようなニュースは海外のものです。日本の若者ももっと怒って良いと思います。
▪️若者たちは、化石燃料の使用など温暖化ガスを排出する社会の仕組み自体を変えないと主張しています。システムチェンジというようですね。でも、そのようなグローバルに拡大している仕組みを変えることはできるのか。3.5%の人びとが声を上げると世の中は変わっていくという説があります。書籍にもなっています。ハーバード大学のエリカ・チェノウェス著『市民的抵抗 非暴力が社会を変える』(白水社刊)という本です。この本に関連した解説はこちらです。
▪️日本の人口は1億2488万5175人(2024年1月1日現在)の3.5%とは、4,370,981人。滋賀県の人口は1,401,134人(2024年9月1日現在)の3.5%は49,040人。これらの人びとを、どうような方法でつないでいけば良いのでしょうか。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、その方法を探っています。話が、琵琶湖低層の無酸素状態の話から大きく脱線してしまいました。すみません。
▪️滋賀県が発表した資料ですが、こちらもご覧いただきたいと思います。
若者気候訴訟

▪️「若者気候訴訟」の公式サイトです。
▪️以下は、「若者気候訴訟」が訴訟を起こした理由です。こちらからの転載です。実際にサイトをご覧になってみてください。
温暖化や気象災害の激甚化など、気候変動の悪影響が世界各地で頻発する中、IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)などの最新の科学によれば、2020年に生まれた子どもたちは1950年生まれの世代の4~7倍、気候変動の悪影響を受けると予測されています。
またIPCCは、CO2の累積排出量と平均気温の上昇が比例関係にあること、地球の平均気温の上昇を産業革命前から1.5℃に止めることが極めて重要であることなどを報告しています。そして、気温上昇を1.5℃に抑えるには、世界全体でCO2排出量を、2019年比で、2030年までに48%、2035年までに65%削減し、2050年にはカーボンニュートラルを実現していく必要があることも示しています。さらにIPCCは、この10年で行う対策が、数千年先まで影響を与えると警告しています。
そこで国際社会は、気温上昇を1.5℃に抑えることを決意し(COP26グラスゴー気候合意)、脱化石燃料・再生可能エネルギーの時代へと移行していくことを確認しました(COP 28)。実現には、火力発電など大規模排出事業者の取組が不可欠です。しかし、現状では1.5℃に抑えることができないどころか、3℃も上昇してしまうことが懸念されています。とくに日本はG7国のなかで唯一、石炭火力の廃止年を示していません。逆に、「ゼロエミッション火力」と称して火力発電での水素・アンモニア混焼、CCSを公的資金で支援し、また、電気料金に転嫁させ、再生可能エネルギーの導入も遅れています。
近年、世界で国や企業に対する気候訴訟が提起され、勝訴判決も現れています。誰もが、安定した気候のもと健康的に暮らす権利を持っています。気候変動によってこのような人権が侵害されることに対して、法律の力で、政府や企業に十分な気候変動対策をとることを求める訴訟、それが気候訴訟です。
そこで、日本に住む16人の若者たちが日本の主な火力発電事業者10社(日本のCO2排出量の約3割を排出)に対し、少なくとも、IPCCが示す水準まで排出を削減することを裁判所に求めました。それがこの訴訟です。また、この訴訟を通して、気候変動対策の重要性・緊急性が広く日本社会に共有され、理解と共感が広がることもめざします。
▪️「若者気候訴訟」のことは、多くのメディアで取り上げられているようです。
【特別編】みんなのBIWAKO会議/COP3|第458回(2024年9月6日)
▪️「みんなのBIWAKO会議/COP3」が開催されました。以下は概要です。
琵琶湖版のSDGs「マザーレイクゴールズ(MLGs)」が策定されて3年。
MLGsに関わる人々が集い、MLGsのゴール達成状況を確認しあい、今後に向けて学びあう「MLGsみんなのBIWAKO会議/COP3」を開催します。
今年度は、web配信の情報番組「びわモニ」とコラボレーション。
“ミスターびわ湖”の愛称で親しまれている川本勇さんが司会を務めます。
琵琶湖を愛する多様な人々が一堂に会する貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。
▪️「みんなのBIWAKO会議/COP3」の第1分科会「MLGsの可能性~できそうなこといろいろ考えてみよう~」には、理事長をしている「特定非営利活動法人琵琶故知新」の理事のお1人である秋國寛さんが、琵琶故知新で進めている「デジタルマップ」について説明されます。第一分科会の開始時間は動画の「01:42:33」からです。秋國さんの「デジタルマップ」の説明は、「02:12」あたりからになります。動画の中では、この「デジタルマップ」をご覧いただくためのQRコードも出てきます。そこから「デジタルマップ」をご覧いただくことができます。こちらからアクセスすることもできます。7月1日の「びわ湖の日」に公開されました。現在はβ版です。多くの皆さんから寄せられた情報をこのデジタルマップの上で表現していく予定になっています。
▪️私どもの「デジタルマップ」の取り組みは、2024年度「未来ファンドおうみ」から助成を受けています。
大崎博子さんのこと
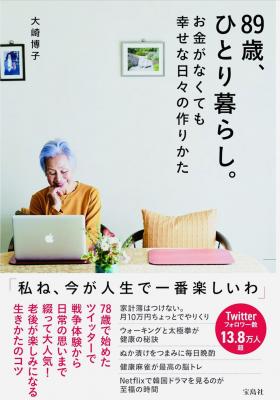 ▪️朝、ネットで「孤独死した91歳母、娘が語る美しい最期 “おひとり様シニア”の日常にSNS反響 「理想の逝き方」を考える #令和の親」という記事を読みました。記事に登場されるのは大崎博子さんです。東京の団地でお一人暮らしをされていた大崎さんは、90歳を過ぎても、ウォーキング、太極拳、麻雀、韓国ドラマを楽しみ、決して無理はせずに楽しく暮らしておられました。お酒も毎日のように楽しまれていました。記事では「孤独死」という言葉を使っていますが、これは孤独死なのかなあ。よくわかりません。孤独死の定義次第ではありますが…。ご家族が海外で離れてお住まいでも、こうやって最期を迎えられること、私個人はとても素晴らしいことだと思います。
▪️朝、ネットで「孤独死した91歳母、娘が語る美しい最期 “おひとり様シニア”の日常にSNS反響 「理想の逝き方」を考える #令和の親」という記事を読みました。記事に登場されるのは大崎博子さんです。東京の団地でお一人暮らしをされていた大崎さんは、90歳を過ぎても、ウォーキング、太極拳、麻雀、韓国ドラマを楽しみ、決して無理はせずに楽しく暮らしておられました。お酒も毎日のように楽しまれていました。記事では「孤独死」という言葉を使っていますが、これは孤独死なのかなあ。よくわかりません。孤独死の定義次第ではありますが…。ご家族が海外で離れてお住まいでも、こうやって最期を迎えられること、私個人はとても素晴らしいことだと思います。
▪️娘さんともインターネットのビデオ通話で毎日のように話をして、ご家族やまわりのご友人ご近所さんとはLINEでもつながっておられました。きちんとエンディングノート等も準備をされていました。ご近所の皆さんのさりげない気遣いや見守りも大切ですね。私は大崎さんのご著書も拝読していましたし、ほぼ毎日大崎さんのXへの投稿も拝見していました。Xでは、20万人を超えるフォロワーがおられました。私もそのようなフォロワーの1人です。大崎さんは2冊の書籍も出版されていました。そのうちの1冊は拝読させていただきました。『89歳ひとり暮らし。お金がなくても幸せな日々の作りかた』です。大崎さん以外にも、何人かの高齢者のひとり暮らしの女性が書籍を出版されています。でも、男性はいないのです。ここは大切なポイントかもしれまん。
▪️さて、大崎さんが亡くなられたこと、娘さんが大崎さんのXにポストされたことで知ることになりました。Xへの投稿がないので心配していたのですが、驚きました。大崎さんは娘さんにXのパスワード等を教えておられたのですね。しかも、亡くなったことをフォロワーに伝えて欲しいとお願いもされていました。でも、どうやって最期を迎えられたのかはわかりませんでした。そのあたりのこと、記事に以下のように説明されていました。
「『今日はめずらしく電話に出ないな、出かけているのかしら?』と思っていたところ、母の近所に住む友人から、私宛にLINEが届いたんです。何かあったときのために、ご近所さんや母の友人数名とLINEを交換していました。
連絡をくれたのは、お向かいのマンションに住む方で、日本時間の7月23日20時頃です。『今日は珍しくXに1度もツイートがないし、夜になっても部屋に灯りがつかないの。心配だから家を訪ねてもいい?』という内容でした。
母は団地の上の階に住む別のお友だちに合鍵を渡していたので、その方に鍵を開けてもらって、その後念のため警察が来て確認、という順序でした。」
お2人は自宅のなかで最期を迎えときのために、すぐに発見してもらい、家族に連絡がいくよう準備していました。
▪️大崎さんは、細かな何重ものセーフティーネットの中で最期を迎えられたことがわかります。遠いイギリスで暮らしておられる娘さんとはインターネットのビデオ電話で毎日のようにお話をされていました。そのイギリスに暮らしておられる娘さんと、ご近所の大崎さんのお友達とはLINEでつながっていました。もちろん、部屋の灯りが点灯しないことに気がつくさりげないご近所の皆さんの気遣いも大切です。大崎さんの同世代のお友達はすでに亡くなっておられていますから、お友達とはいっても20歳ほどお若い方達のようです。そういった「細かな何重ものセーフティーネット」を、大崎さんご自身が時間をかけて築いてこられたのでしょう。
▪️ところで、大崎博子さんは、突然亡くなられました。身体が弱って衰弱しておられた様子は窺えません。「Xに投稿されていた夕飯の手料理の残りは冷蔵庫にしまわれていました。部屋の中は掃除も整理整頓もされていて、きれいに保たれていました」とのことですから、最後まできちんと暮らしておられたのです。これから先の予定もカレンダーに記入されていたといいます。誰もがご自身の最期の瞬間がやってくるのかはわからないけれど、「細かな何重ものセーフティーネット」を築き、早め早めに終活を進めてこれたことは本当に素晴らしいと思います。見習わなくてはと思います。とはいえ、娘さんをはじめとしてご遺族の皆さんには、大崎さんが亡くなったことを受け止めるためには少し時間が必要なようですね。突然でしたからね。
“観測史上最も暑い夏” 気温がこれ以上あがったら、どうなる?猛暑日増で複合災害や健康被害の可能性も…【news23】
▪️ネットで「“観測史上最も暑い夏” 気温がこれ以上あがったら、どうなる?猛暑日増で複合災害や健康被害の可能性も…【news23】」という記事を読みました。調べてみると、動画もありました。これらは、短期間でネット上から消えていくように思います。少しメモを残しておこうと思います。
▪️気候変動・温暖化がリアルに実感できるようになってきました。でも、まだ「茹でガエル」状況から抜け出せていないようにも思います。「茹でガエル」とは、危険が迫っているけれど変化がゆるやかなため気がつかないまま、気づいたときにはすでに手遅れになってしまっている…という意味です。この記事の最後の部分では、ドイツの例が紹介されていました。ドイツでは、2021年の歴史的な洪水以降、経済エネルギー省が経済気候保護省になったのだだとか。最初の一歩ということのようです。気候変動は果たして抑制できるのでしょうか。すでにティッピングポイントを超えたのではという説もあります。ティッピングポイントとは、温室効果ガスの排出が続き大気中の濃度が限界値を越えると、後戻りできない劇的な気候変動が起こる、その臨海点のことです。実際、地球上では、グリーンランドの氷床融解をはじめ、永久凍土の融解、南極氷床の融解、アマゾン森林破壊等、といった現象が発生しています。
▪️気候変動にブレーキをかけることはもはやできないのか。いや、まだ頑張れば大丈夫なのか。もしできないとすれば、どのような適応の対策をしたらよいのか。記事にはありませんが、気候変動は農業生産に大きな影響を与えることは確かで、食料自給率の低い日本の場合は、食糧難を経験することになるやもしれません。それでなくても、農業従事者は高齢化しており、耕作放棄地も増加している現状を考えると、こういった気候変動が日本の農業に打撃を与える可能性を無視はできないのではないかと思います。以下は、メモです。専門家の予想は、かなり深刻です。「最悪のシナリオ」をさらりと語っておられますが、これが具体的にどのような恐ろしい状況なのかを専門家以外にも理解できるように具体的に示す必要もあるように思います。
・「(今世紀末の)年平均気温は20世紀末と比べて+4.5℃ということが予想されています」
・「たとえば7月の気温があれだけ暑くて、(月の)平均気温は(平年より)2℃高いぐらい。4℃上がるというのは、ものすごいことですね」
・「極端な暑さの確率が上がってくると、他の自然災害と一緒に起こる確率がすごく高くなる。極端に強い台風が来たすぐ後に熱波が来るとか」
・「熱中症の死者は30年を平均して300人ぐらい。“熱疲労”で亡くなっている方は3000人ぐらい」
・「暑くなって体温が上がる以前に、他の臓器に影響が出て亡くなってしまうことがあります。例えば、呼吸器とか循環器です。気温と疾患の関係をとると、明らかに気温が上昇したらそういう疾患の死亡が増えている」
・今回の台風10号について、気候変動によって最大風速が7.5%も増した可能性があるということです。
・今回の台風10号クラスの台風の発生頻度は、気候変動がなかった地球での場合は10年間で4.5回ですが、気候変動の影響があると5.7回に増えるという可能性を指摘しています。
・母国のドイツでも災害が増えています。例えば、2021年に歴史的な洪水があって、それを機に不安が広がり始めました。その後、選挙がありましたが、選挙にも影響が出ました。
・ドイツには昔、経済エネルギー省がありましたが、編成して、今は経済気候保護省になっています。なので、何か経済的なことをやろうとすると、必ず1回は気候のことも考えないといけないという新しいルールになっているので、最初の一歩かなという感じです。
▪️私はに2人の孫がいます。その孫たちが後期高齢者になる頃、地球はどうなってしまっているのか…とよく想像することがあります。私は21世紀の中頃には当然この世にいません。しかし、孫たちは21世紀末を生きなければなりません。
NHK「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 復活 〜サイモン&ガーファンクルとセントラルパーク〜」
▪️サイモン&ガーファンクルは、私の年齢よりも少し年上の皆さんが夢中になっていたデュオグループではないかと思います。有名な「明日に架ける橋」が発表された1970年、私は、まだ小学校6年生でした。おそらく1970年前後に20歳前後の皆さんが夢中になったのではないでしょうか。wikipediaではありますが、そこには、次のような説明がありました。
1970年発表のアルバム『明日に架ける橋 (Bridge Over Troubled Water)』の制作中に、ポールとアートの音楽に対する意見の違いが表面化した。『明日に架ける橋』は、全世界で売上が1,000万枚を超える大ヒットとなり、グラミー賞の最優秀レコード賞・最優秀アルバム賞を受賞したものの、このアルバムを最後に2人はそれぞれのソロ活動に入った。
▪️1981年9月19日、サイモン&ガーファンクルは、ニューヨークのセントラル・パークで再結成チャリティコンサートを開いて53万人もの観衆を動員しました。先日NHKの「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 復活 〜サイモン&ガーファンクルとセントラルパーク〜」では、このコンサートを契機に、荒廃したセントラルバークを再生復活させる取り組みが始まったことを知りました。
セントラルパークはニューヨーク市の財政危機から荒廃、治安も悪化し、窮地に陥っていた。セントラルパークを救うため二人を同じステージに立たせるプランが浮上。復活と再生をかけた二つの物語。
▪️このセントラルパークは、かつては荒れ果てて、誰も近づかなかった場所だったようです。しかし、寄付も集まり、このコンサートをきっかけに、自分たちの公園として大切にしてきたいという気持ちも育まれたようですね。素敵なことです。一般論として、人びとの関心が薄れるとその環境は劣化していく傾向があります。逆に、人びとが関心を再び向けると環境が改善していくこともあるのです。自分のことしか考えなかったけれど、このコンサートをきっかけとして自分たちの大切な公園なんだという意識が涵養されていたわけっです。これは公共性にも関わることだと思います。素敵な事例を知りました。
▪️セントラルパークの再生について、こちらの記事に少し詳しく説明してあります。「公園が変わる! 街が変わる!第9回 米国NY市のユニークな公民連携による公園管理(その1)」という記事です。公民連携の中で公園を維持管理する仕組みを立ち上げてこられたようです。
龍谷ミュージアム秋季特別展「眷属」

▪️9月21日から11月24日まで、龍谷ミュージアムで秋季特別展「眷属」が開催されます。以下は、公式サイトから転載。
眷属(けんぞく)とは、仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格のことです。仏教美術では主尊のまわりを囲むようにあらわされ、仏法を守護したり、主尊を信仰する者に利益を与えたりする役割を担っています。
龍谷ミュージアムで昨年度開催した特集展示「眷属―ほとけにしたがう仲間たち―」が、この秋、特別展としてパワーアップし、各地から約80件の作品が集います。
仏教美術における名脇役ともいえる眷属の個性豊かな姿をご覧ください。
▪️龍谷大学の学生の皆さん、瀬田キャンパスの皆さんも、ぜひ足を運んでみてください。観覧料は無料です。
伊吹山の鹿の食害と貴重植物の保護活動
▪️長らく、公益財団法人平和堂財団「夏原グラント」の選考委員をしています。もう10年目になります。毎年、夏原グラントが助成をしている環境保全団体の活動からは、多くのことを学ばせていただいています。今年度から助成を受ける「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の高橋滝治郎さんのFacebookへの投稿です。鹿に貴重な植物が食べられないように、地域住民の手でできることをしようと、これまでの化繊のネットではなくて、もっと頑丈な鉄柵で囲むことに取り組んでおられます。助成には上限がありますが、上限いっぱいまで鉄柵を購入する費用に当てられていたと思います。すごく、シンプルで分かりやすく、評価も高い申請でした。こうやって、鉄柵で囲んだエリアを増やしていかれるのだと思います。
▪️伊吹山は、今、鹿の食害で大変な状況になっています。やっと自治体も県境を超えて連携しながら動き始めました。食害の結果として、雨が山肌を抉り、深い谷のようなものがいくつも生まれています。山が崩壊していくかのようです。すでに土砂災害も発生していることから、至急に、土木的な対策を講じる必要があるでしょう。加えて、鹿の捕獲ですね。高橋さんたちは、投稿の冒頭に「深刻な状況だけどわれわれができることを着実に進めます」と書いておられます。力強いお言葉です。
「滋賀・岐阜の3市町 伊吹山再生へ連携協定」というニュース
▪️滋賀県米原市の伊吹地区は7月1日と7月25日の両日、二度に渡り土石流が発生ました。5軒の住宅に土砂が流れ込み大変な状況になりました。このような土石流が発生した原因は、シカによる食害です。上の動画では、「現在600頭あまりが生息していますが、山林などの植物を食べることで土砂がむき出しになり、土や水が流れやすくなって土石流災害が起きたとみられています」と説明しています。
▪️この土石流に関連して、7月27日の「【土石流 発生の瞬間】土砂崩れ原因はシカの「食害」か シカが植物を食べ尽くし土がむき出しに 今月2度目の「緊急安全確保」発令 現場の伊吹山では昨年から3回目の土砂災害〈カンテレNEWS〉」という投稿を行いました。その中で、この地域にお住まいの知人の方のお話として、以下のように書きました。
当初は、生態系に関わる課題として問題提起してきたのだそうです。ところが、「その時はまさか6〜8合目の裸地化が山麓の人家にまで被害を及ぼすとまで想像力が働かなかった」そうです。実際、この方は、シカを防ぐネット等を使って希少植物をシカの食害から守る活動をされてきたのですが、今や防災の問題になってきています。「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」とおっしゃっておられました。大変大切なご指摘だと思います。これはもう地元の地域の力だけではなんともなりません。知人は、「国、県、市、関係団体が連携して喫緊の取組と中長期の取組を総合的、順応的に、そして強力に推し進めてほしい」と強く求めておられました。
▪️当初は、シカの食害により「伊吹山の高いところが裸地化する」、「貴重な植物が消えてしまう」ことを心配されていました。当初は、生態系の問題、あるいは稀少生物の保護問題として捉えておられたのですが、そのような裸地化は降った雨水の速度を遅くすることができず、同時に、地面に染み込む猶予もないままに、雨が土砂と一緒にどんどん流されていくことになったのです。山肌は少しずつ削られていき、少しずつ深い谷間ができてしまいました。その谷間を土砂と雨水は流れていくようになったのです。そしてそのような土砂は麓の集落にまで流れ込むようになってしまったのです。
▪️この動画で、米原市の平尾道雄市長は「(伊吹山が)かつての水を貯える豊かな山林ではなく、まさに水を流す川のように変わってしまった。山の機能が失われることを、私たちは“伊吹山ショック”というふうにとらえています」と言っています。この「伊吹山ショック」というのは大袈裟な表現のように思う方もおられるかもしれませんが、これまで伊吹山の状況を深刻に捉えていなかったということなのかなと思います。少しずつ、困った状況が進行しているのに気が付いていなかった、突然、土砂災害という形で気がついた…そういう意味でのショックなのだと思います。知人が、「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」と語ったことと重ね合わせても、そういうふうに理解できように思います。
▪️10日前のことになりますが、「滋賀・岐阜の3市町 伊吹山再生へ連携協定」というNHKのニュースをネットで視聴しました。もっと早い段階でこういった県境を超えた自治体同士の連携をやっていればなあ…と思うのですが、今の段階で言っても仕方がありませんね。米原市長が「滋賀県と岐阜県が一体となって伊吹山の再生に取り組むスタートラインに立つことができた。専門家の意見を聞きながら、シカをどう効果的に捕獲していくか検討していきたい」といっておられます。検討の先にある実施まで急いでいただきたいなあ思います。今まで、米原市だけで駆除しても岐阜県側からどんどんシカは入ってくるだろう、どうするのかなと思っていましたが、今回は岐阜県の関ケ原町、それに揖斐川町との連携協定です。でも、どうやってシカを捕獲するのでしょうね。
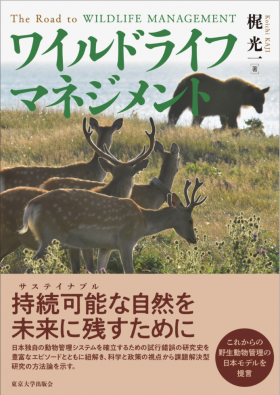 【追記】この問題に関しては、様々な分野の専門家が必要とされるはずです。特にシカの管理に関しては、東京農工大学名誉教授の梶光一先生のご研究などは、この問題の役に立つのではないかと思います。『ワイルドライフマネジメント』等が参考になるのかなと思います。私は伊吹山から離れたところに住んでいますし、関係者でもないし部外者なのですが、個人的には、梶先生のような方にいろいろご助言ご指導いただきたなと思うのです。
【追記】この問題に関しては、様々な分野の専門家が必要とされるはずです。特にシカの管理に関しては、東京農工大学名誉教授の梶光一先生のご研究などは、この問題の役に立つのではないかと思います。『ワイルドライフマネジメント』等が参考になるのかなと思います。私は伊吹山から離れたところに住んでいますし、関係者でもないし部外者なのですが、個人的には、梶先生のような方にいろいろご助言ご指導いただきたなと思うのです。