「地域エンパワねっとⅡ」8期生スタート!!
ありがたい


▪︎今時の若い方たちは、仕事とプライベートをきちんと分けて、職場の上司や先輩、そして仲間と「呑み」に行くことが減ってきているという話しをよく聞きます。私は「昭和のおじさん」だからでしょうか。そのような感覚がよくわかりません。職場のなかにも、地域のなかにも、楽しく時間を過ごすことのできる方たちがたくさんいます。昨日は、職場の方と仕事上のことで懇談をした後、「ちょっと行きますか」と大学の近くの中華屋へ。今日は、大学の地域連携でお世話になっている昔からの知り合いの方から、昼間に「ちょっとどうですか」とお誘いがあり、大津の街中での地域の皆さんとの会議が終わったあと、夕方から大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。自分のまわりに広がるたくさんの知り合いの方たちとのネットワークを、有難いことだと、いつも思っています。
総合地球環境学研究所で「魚のゆりかご水田」研究の会議

▪︎朝一番に自宅を出て、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所にやってきました。このエントリーは、地球研で書いています。「魚のゆりかご水田」プロジェクトの「超学際的研究」*を進めるためのミーテイングです。滋賀県の水産試験場の研究者、淡水魚のゲノム解析を得意としている研究者も参加して、プロジェクトリーダーの奥田さんの進行のもとで会議を行いました。まだ具体的にお話しをすることかできませんが、「ニゴロブナが孵化した水田に回帰してくる」(母田回帰)という習性を科学的に明らかにしていくことを軸に、そのようなニゴロブナの習性と、琵琶湖沿岸地域の農村の活性化の活動である「魚のゆりかご水田」プロジェクトとをどのように結びつけていくのか、また、どのように研究として進めていくのか、そのばあいの研究の枠組みはどうして構築するのか…、そのあたりのことについて議論をしました。なかなか、楽しい会議でした。一般の方たちにも関心をもってもらえるようなテーマなので、わかりやすい新書にでもなればなあと思っています。
▪︎今日は、午前中が総合地球環境学研究所での会議、午後からは深草キャンパスに戻ります。研究部の仕事と会議がはいっています。龍谷大学の第5期長期計画の「目玉」といってもよい「世界仏教文化研究センター」の立ち上げに関わる仕事です。学長室広報の皆さんと連携しながら、作業を進めています。研究部の仕事と会議が終わったあとは、情報メディアセンターの次長さんとミーティングをもつ予定です。龍谷大学の研究をもっと社会的にアピールしていくための作戦会議です。ということで、今日も頑張ります。
*「超学際的研究」 : ▪︎私たちのプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会―生態システムの健全性」は、総合地球環境学研究所のプロジェクトです。総合地球環境学研究所では、現在「Future Earth」という国際協働研究の枠組みに参加しています。この「Future Earth」では、「持続可能な地球環境に向けての国際協働研究イニシアティブ」であり、国際科学会議(ICSU)などの学術コミュニティ、研究資金提供団体や政策決定者などが協働して地球環境を包括的に理解し、地球規模の課題の解決に資する研究を総合的に推進することをめざしています。私たちの研究プロジェクトも、この「Future Earth」の方向性と連動しながら、「超学際的研究」のスタイルを堅持しつつ、プロジェクトを進めています。この「超学際的研究」についてですが、以前のエントリーにも書きました。再度、総合地球環境学研究所での説明を以下に引用しておきます
Future Earthは、人間活動による地球 環境への影響評価に加えて、自然科学 と人文・社会科学との文理融合の学際的(interdisciplinary)研究、及び、研究者と他のステークホルダー(行政、産業界、 NGO/NPO、メディア、市民など)との超学際的(transdisciplinary)な連携(協働)を通じて、持続可能な社会へむけた転換を目指すところにその特色があります。とくに、研究者コミュ ニティ以外のステークホルダーとの協働は、研究の立案の段階から成果の普及に至るまで組み込まれ、これまでの 科学プロジェクトとは大きく異なる研究設計となっています。
ゼミOGからの連絡
▪︎化粧品会社で働いているゼミの卒業生から連絡が入りました。OGです。彼女が、ビューティーサークルという美容教室の講師をしているときの写真が、facebookに投稿されたので、少しコメントをしました。そうすると、ひさしぶりということもあって、コメント欄でもりあがりました。「ちゃらんぽらんだった私も講師してます!頑張ってます!就活メイクレッスンも承ってます」と営業もきちんとしてきました。せっかくなので、大学の知り合いの女子学生たちにLINEで連絡をしたところ、全員がぜひ美容教室で「就活メイクレッスン」を受講してみたいと連絡をしてきました。そのことを彼女に伝えたところ、母校でぜひ美容教室を開催させてほしいとのことでした。
▪︎彼女は、2011年の春に卒業しました。自分で「ちゃらんぽらんだった私も講師してます!頑張ってます!」と自覚しているようですが、ちょっといいにくいのですが、たしかにその通りでした。私の彼女に関する記憶は、クロックスをはいて、ジャージをはいて…化粧っ気もまったく無しというものです。そして、同時に、とても明るい性格だったように記憶もしています。その彼女から「化粧品会社に就職する」と聞かされたときは、少々、びっくりしました。化粧品等にあまり関心があるようには見えなかったからです。facebookには、彼女の通勤時の姿の写真も載っていましたが、学生時代とはまったく違う雰囲気です。
▪︎美容教室ですが、いろいろ彼女の会社側の要望や、大学で開催するばあいは大学側の条件など、調整しないといけないことは多々あると思いますが、うまくいくとよいなと思っています。
ゼミOBからの連絡
 ▪︎昨日、昨年の春に卒業したゼミのOBからLINEで近況報告がありました。じつは、そのOBからは、今年の4月に「今の会社なんですがけど、もうじき辞めようと思っています」という連絡が入っていました。原因は過労だったようです。ちょうど、私の誕生日だっかな…。こういう連絡を唐突にもらうと、ゼミの教員としては落ち込みますよね〜。
▪︎昨日、昨年の春に卒業したゼミのOBからLINEで近況報告がありました。じつは、そのOBからは、今年の4月に「今の会社なんですがけど、もうじき辞めようと思っています」という連絡が入っていました。原因は過労だったようです。ちょうど、私の誕生日だっかな…。こういう連絡を唐突にもらうと、ゼミの教員としては落ち込みますよね〜。
▪︎ところが、です。そのOBが、こんどは会社から成績優秀につき表彰されたというのです。その連絡が、昨日LINEに届いたのです。彼は営業職です。なにか仕事のコツを得たようです。彼自身は、「覚醒しています(笑)」といっていました。彼が言うに、社歴最短で役職クラス級の営業成績を上げたようなのです。私にはよくわかりませんが、目標の7.0ポイントを大幅に上回る15.02ポイントの営業成績をあげることができるようになったらしいのです(私には、1ポイントの持つ意味や価値がわかりませんが…)。その証拠の写真、「表彰状」を撮った写真もわざわざ送ってくれました。
▪︎今も新人にかわりはないのですが、ここ数ケ月で、仕事のどこに力を入れて、どこは抜いてもよいのか…そのあたりのコツをつかんだようですね。力をぬくというのは語弊がありますね、無駄な力が抜けるようになったという方が正しい表現かもしれません。あとは、実績を積むことで自分に自信がついてきたといっていました。こういうのって、大切なことですよね~。彼のいうところの「覚醒」ってどういう経験なんでしょうね。後輩の人たちにも説明してほしいなあと思います。
平和堂財団夏原グラント「2014年度活動報告書」
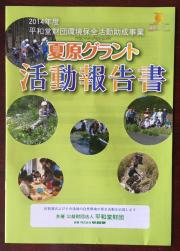 ■現在、公益財団法人平和堂財団 「環境保全活動助成事業夏原グラント選考委員」を務めています。以前のエントリーにも書きましたが、簡単にこの「夏原グラント」について説明をしておきます。平和堂は、滋賀県を中心に近畿地方・北陸地方・東海地方で総合スーパーとスーパーマーケットを展開していますが、平和堂財団はその企業により設立された財団です。公式サイトによれば、株式会社平和堂の創業者である故夏原平次郎さんが、平和堂をここまでに育てていただいた地域に感謝し、そのご恩に報いるため、私財を寄付し平成元年3月に設立したものなのだそうです。平成23年(2012年)からは、環境保全活動に対する助成も行っておられます。それが「夏原グラント」です。
■現在、公益財団法人平和堂財団 「環境保全活動助成事業夏原グラント選考委員」を務めています。以前のエントリーにも書きましたが、簡単にこの「夏原グラント」について説明をしておきます。平和堂は、滋賀県を中心に近畿地方・北陸地方・東海地方で総合スーパーとスーパーマーケットを展開していますが、平和堂財団はその企業により設立された財団です。公式サイトによれば、株式会社平和堂の創業者である故夏原平次郎さんが、平和堂をここまでに育てていただいた地域に感謝し、そのご恩に報いるため、私財を寄付し平成元年3月に設立したものなのだそうです。平成23年(2012年)からは、環境保全活動に対する助成も行っておられます。それが「夏原グラント」です。
■送っていただいた報告書からは、じつに様々な地域の皆さんが、様々な環境保全活動に取り組まれていることがわかります。このような点としての活動がつながり線となり、そしていつかは面となって、広がりを生み出すことになるれば…と思っています。
今シーズンの龍大「SEAHORSE」
▪︎今年の龍大アメリカンフットボールチーム「SEAHORSE」のことについて。第1節は、8月29日(土)に「EXPO FLASH FIELD」で開催されました。関西大学戦です。結果は、「関西大学27-0龍谷大学」、実力の差を見せつけられた感じでしょうか。第2節は、9月12日(土)に第1節と同じく「EXPO FLASH FIELD」で開催され、「龍谷大学31-8 近畿大学」で近大に勝利しました。動画は、ネットで配信されたrtvの動画です。昨年は、QBがゼミ生だったので、いろいろ話しを聞くことができましたが、今年は…。第3節は、9月26日に神戸の王子スタジアムでの関西学院大戦になります。昨年、「SEAHORSE」は、Division1(1部リーグ)8チーム中6位でした。今年は、関学・立命館・関大の壁がかなり高いわけことはわかっていますが、なんとかそれらのチームに次ぐ4位を確保してほしいなと思います。
meijiの「カルミン」

▪︎昨日、母のために買い物に出かけたとき、スーパーでmeijiの「カルミン」をみつけました。「カルミン」は、1921年から製造販売されているお菓子です。硬い言い方をすると、炭酸カルシウムが配合された白色のミント錠菓…ということになるようです。この「カルミン」、私のような年代の人たちにとっては、懐かしいお菓子です。遠足やピクニックのお供といえば、この「カルミン」でした。
▪︎じつは、このお菓子、今年度末で生産が中止されます。ロングセラーではありますが、さすがに時代にあわなくなってきたのか、売れ行きがかなり低迷しているようです。このことがニュースになるや、あちこちで「カルミン」が飛ぶように売れていると聞いています。きっと大人の方たちが「大人買い」しておられるのでしょう。昨日、スーパーでみたときも、棚におかれた「カルミン」の数は、左右の他のお菓子に比べてかなり数が少ない状況でした。
▪︎買ったあと、一粒食べてみました。以前食べたのは…、記憶がありません。おそらく30年以上は経過していると思います。炭酸カルシウムが配合されているので、スーッとするのかなと思っていましたが、かなり穏やかな感じでした。現在、他社の人気のある商品、たとえば「FRISK」なんかだと、かなり強いミントの刺激があります。また、その清涼感も長持ちします。このような味の違いにも、時代の移り変わりを感じます。
▪︎私のような年代の人たちにとってみれば、「カルミン」以外では、中野の「都こんぶ」も懐かしいものです。しかし、「都こんぶ」は現在でも現役です。あと「ボンタンアメ」とか…。こうやって昔を懐かしむことが多くなるって、自分自身がけっこう歳をとり、人生そのものがどんどんセピア色になり、歴史家している…ということなのでしょうね。
カマキリ


▪︎母が先週の金曜日から1週間程、体調を悪くして入院していました。昨日、土曜日、なんとか退院することができしまた。妹と一緒に介助をして、自宅に連れ帰りました。退院にあたっては、病院のメディカルソーシャルワーカーやケアマネージャーの皆さんにお世話になりました。ありがとうございました。介護保険のおかげで、母の生活は、なんとかなっているというのが実情です。ヘルパーさんによる生活のサポート、本当にありがたいです。もし、これを自分一人でやることになったら、とてもではありませんが無理です。
▪︎母は急に入院することになりました。この手配もケアマネージャーさんがやってくださいました。あわてていたものですから、母の入院にあたって冷蔵庫の中をきちんと処理していませんでした。ということで、妹がその傷んだ食料品の処理をして、私の方は、近所のスーパーに買い物に出かけました。スーバーの駐車場で、ふと左のミラーをみると、どこからやってきたのか1匹のカマキリがしがみついているではありませんか。そばに寄って写真を撮ってみました。何か、秋を感じました。
【追記】▪︎このカマキリですが、「ハラビロカマキリ♀」なのだそうです。昆虫に詳しい方が教えてくださいました。カマキリにも、いろいろ種類があるんですね。
村上春樹『職業としての小説家』
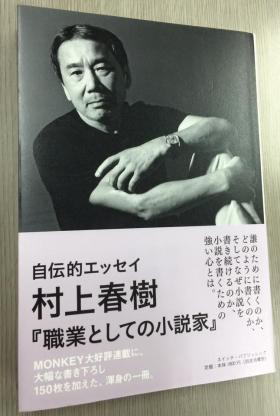 ■村上春樹のエッセイ集『職業としての小説家』が手元に届きました。じっくり、一気に読みたいところですが、電車の中で読むことになりそうです。
■村上春樹のエッセイ集『職業としての小説家』が手元に届きました。じっくり、一気に読みたいところですが、電車の中で読むことになりそうです。
■ところで、このエッセイ集、ニュースを通しても話題になりました。紀伊国屋書店が、初版10万部のうちの9万部を買い切ったからです。全国66にある紀伊国屋の店舗や自社ネットで販売し、残りにいては、他の書店に卸すと聞いています。ネット販売が浸透し、全国で書店が減少しています。2000年に21,495あった全国の書店は、2005年には17,839、2010年には15,314、2014年の5月1日現在では13,943と、漸次減少してきています。書籍や雑誌の売り上げも減少しているようです。書籍の売り上げのピークは1996年でしたが、2013年には約31%減少しています。雑誌の売り上げのピークは97年でしたが、2013年には差書籍を上回る45.5%の減少となっています。書店が減っていくことと、書籍の売り上げが減少していくことは相関しているのではないかと思います。
▪︎そのようなこともあり、紀伊国屋は全国の書店を活性化するために、今回のような思い切った販売を行ったのでした。私自身は…、職業のせいもありますが、たくさんの書籍を購入する方だと思うのですが、そのほとんどはamazonを使っています。思いついたときに、簡単に本を注文できるので、こういうことになってしまっているのですが、結果として、街から書店が消えていくことに加担していた…ということにもなります。
■さて、このエッセイの内容ですが、以下の通りです。どのエッセイも、面白そうなタイトルですが、特に、「フィジカルな営み」とか、「物語」、「河合隼雄」というところが気になります。私自身は、村上春樹と河合隼雄の対談である『村上春樹、河合隼雄に会いにいく 』は非常に興味深く読みました。村上春樹は、河合隼雄のユング派心理学の考え方から、いろんなヒントを得ているように思います。村上が語る「デタッチメントからアタッチメント」という創作上の転換とも深く関係していると思います。言い方を換えると、村上春樹が自身の実践に関して語ったことを、河合隼雄が深いところでしっかりと受け止めた…という感じなんじゃないのかな~と思っています。
第一回 小説家は寛容な人種なのか
第二回 小説家になった頃
第三回 文学賞について
第四回 オリジナリティーについて
第五回 さて、何を書けばいいのか?
第六回 時間を味方につける──長編小説を書くこと
第七回 どこまでも個人的でフィジカルな営み
第八回 学校について
第九回 どんな人物を登場させようか?
第十回 誰のために書くのか?
第十一回 海外へ出て行く。新しいフロンティア
第十二回 物語があるところ・河合隼雄先生の思い出
あとがき


