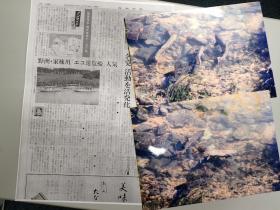小佐治での生き物調査


▪︎総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のフィールドのひとつである、滋賀県甲賀市小佐治にいってきました。小佐治では、今年度、滋賀県庁農林水産部や滋賀県立琵琶湖博物館の支援で、集落の環境保全部会の皆様が「豊かな生きものを育む水田づくり」のブロジェクトに取り組むなかで、定期的に水田の生き物調査を実施されています。また、地域の子どもたちと水田の生き物の観察会も開催されています。昨年の夏から、私たち地球研のプロジェクトでも、この小佐治の活動に参加させていだたいています。


▪︎今回は、冬なので、どれほどの生き物がみつかるのかな…と心配していましたが、夏と比較すると生き物の影は薄いですが、トンボの幼虫であるヤゴ、ゲンゴロウ、マツモムシ等の水性昆虫、そしてメダカ、ドジョウ等の魚たちが多数確認できました。それから、私は初めて見ましたが、アカガエルの卵も多数確認することができました。アカガエルは、早春に卵を産みます。水田周辺の森林に生息しています。そして、春先に冬眠を一時中断して繁殖のため池や沼などに産卵するようです。この小佐治では、土質が細かく水田が割れてしまわないように、水を張ってある水田が多く、田んぼのなかにもアカガエルが産卵にやってきます。


▪︎左は水田の水たまりに産卵されたアカガエルの卵です。そばに寄ってみると、右のような感じです。なんといいますか、こんな飲み物がありましたよね。なんといったかな…。バジルシードという飲み物かな。それから、タピオカ…って感じもしますね。もちろん、これらの卵は、観察したあとは、必ず水田に返しています。午前中の観察会のあとは、地球研の私たちのプロジェクトのコラボレーションの内容に関して、地元の環境保全部会の皆さんと話し合いを行いました。なんとか、見通しがたってほっとしました。詳しくは、またいずれご説明することになろうかと思いますが、生き物のにぎわい作り(生物多様性の保全)の活動と営農やコミュニティビジネスとの関係、流域の水質や栄養循環との関係、コミュニティ形成等との関係について研究上の関心をもちつつ、小佐治の皆さんとの連携していく予定です。
総合地球環境学研究所にて



▪︎「総合地球環境学研究所」のことについては、このブログで何度もエントリーしてきましたが、参加している地球研のプロジエクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」が、4月より、いよいよフルリサーチの段階に進みます。地球研では、以下のような仕組みになっています。
地球研では、既存の学問分野で区分せず、「研究プロジェクト方式」によって総合的な研究を展開しています。
研究プロジェクトはIS(インキュベーション研究 Incubation Study)、FS(予備研究 Feasibility Study)、PR(プレリサーチ Pre-Research)、FR(フルリサーチ Full Research)という段階を経て、研究内容を練り上げていきます。
国内外の研究者などで構成される「研究プロジェクト評価委員会(PEC)」による評価を各対象年度に実施し、評価結果を研究内容の改善につなげています。研究の進捗状況や今後の計画について発表し、相互の批評とコメントを受け研究内容を深める「研究プロジェクト発表会」を年に1回開催しています。
CR(終了プロジェクト Completed Research)は、社会への成果発信や次世代の研究プロジェクト立ち上げなど、さらなる展開を図っています。
▪︎「段階を経て、研究内容を練り上げ」、「研究プロジェクト評価委員会(PEC)」による評価を毎年受けることが、義務付けられています。これがこの研究所の特徴なのですが、フルリサーチの段階に進むまでには、たくさんのプロジェクトが評価を獲得できずに脱落していきます。プロジェクトが取りやめになります。非常に厳しい評価制度になっています。私たちは、なんとかフルリサーチまで進むことができましたが、フルリサーチを進んだ後も、毎年厳しい評価を受け続けなければなりません。今日も、実は、その評価委員会が開催されています。リーダーの奥田昇さんが頑張っているはずです。数日前、プロジェクトのコアメンバーの皆さんが集まって「研究プロジェクト評価委員会(PEC)」の評価を受けるための「作戦会議」を開催しました。会議のあとは、その翌日に滋賀県の甲賀市の農村で行う調査の準備をしなければなりませんでした(まだ、本格的な調査の前段階あたりなのですが、農村のリーダーの皆さんと相談をしながら、少しずつ前進しています)。そうやっているうちにすっかり晩になってしまいました。写真は、その時のものです。
▪︎黒いシルエットの建物は、地球研です。丘の斜面に建設された不思議な形をした建物です。帰りは、畏友でもある京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さんと一緒でした。谷内さんとは、長年にわたり流域管理に関する研究プロジェクトを一緒に取り組んできました。いずれも、文理融合を基盤にした学際的な流域管理に関する研究プロジェクトです。今回の地球研のプロジエクトのばあいは、さらに地域住民の皆さんや行政の皆さんとも協働・共創(Co-design/co-production)しながら進める「超学際研究(trans-disciplinary)」的研究になります。
▪︎この日、谷内さんとは、叡山電鉄で京都の街中まで出かけて、夕食を一緒にとりました。谷内さんは、「IPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)」の報告書作成のメンバーです。昨年の10月にはオランダで第1回目の会議が開催され、来月はアルゼンチンで第2回目の会議が開催されるそうです。谷内さんからは、そのようなIPBESの動向や、環境科学分野の国際的な動向などをいろいろ教えてもらいながら、これからのプロジェクトの方向性に関して意見交換をしました。総合地球環境学研究所は、「Future Earth」のアジアの拠点になっています。「Future Earth」とは、持続可能な社会への転換のためには、科学者と社会の様々なステークホルダーとが超学際的連携・協働を行うための国際的な枠組みです。詳しくは、このパンフレットをお読みいただきたいと思いますが、私たちはこのような国際的な動向を視野にいれながらプロジェクトに取り組んでいます。
甲賀市の大原財産区を訪ねる





 ■総合地球環境学研究所のプロジェクトで、甲賀市にある大原財産区の事務所を訪問しました。いろいろお話しをお聞かせいただいたあとは、大原ダムを見学しました。農業用のダムです。下流には、私たちのプロジェクトで調査を進めている小佐治という集落があります。古琵琶湖の湖底だったところが隆起してできた丘陵地帯に、降雨によりいくつもの谷筋が生まれました。いつの時代かはわかりませんが、小佐治の皆さんは、この谷筋に水田を作り農業をしてきました。いわゆる八津田です。そして、後背地の丘陵の森林の中にため池を作り、そのため池の水から灌漑していました。大きなため池が5つ、小さなため池は無数にあったと言います。水不足の時のために、小さな無数のため池に水を貯めてリスクを分散させていたのです。しかし、大原ダムができてからは、そのような灌漑に伴う苦労は無くなりました。無数にあった小さなため池は放棄されることになりました。生物多様性の観点からは、そのような無数にある小さなため池には意味があったと思うのですが…。このことについては、またこのブログの中で書くことにしたいと思います。
■総合地球環境学研究所のプロジェクトで、甲賀市にある大原財産区の事務所を訪問しました。いろいろお話しをお聞かせいただいたあとは、大原ダムを見学しました。農業用のダムです。下流には、私たちのプロジェクトで調査を進めている小佐治という集落があります。古琵琶湖の湖底だったところが隆起してできた丘陵地帯に、降雨によりいくつもの谷筋が生まれました。いつの時代かはわかりませんが、小佐治の皆さんは、この谷筋に水田を作り農業をしてきました。いわゆる八津田です。そして、後背地の丘陵の森林の中にため池を作り、そのため池の水から灌漑していました。大きなため池が5つ、小さなため池は無数にあったと言います。水不足の時のために、小さな無数のため池に水を貯めてリスクを分散させていたのです。しかし、大原ダムができてからは、そのような灌漑に伴う苦労は無くなりました。無数にあった小さなため池は放棄されることになりました。生物多様性の観点からは、そのような無数にある小さなため池には意味があったと思うのですが…。このことについては、またこのブログの中で書くことにしたいと思います。
Know your food, change the world. | Hiroyuki Takahashi | TEDxTohoku
▪︎「都会人に欠けている”共感力”とは? 食べ物付きの月刊誌『東北食べる通信』が伝えたいこと」。高橋博之さん。彼の強い思いが伝わってきます。
私たちが毎日食べているお米。これを作っている生産者が困っているんですから、決して他人事ではいられないはずです。だけれども、どうしてこうも他人事になってしまうのでしょうか。
それは、困っている農家の具体的な顔が思い浮かばないからだと思います。もしも顔が思い浮かぶ農家が知り合いにいたら、決して他人事ではいられないのではないでしょうか。その相手との関係性が「共感力」を育むのです。
消費者と生産者が大きな流通システムで分断されてしまったこの国で、私たち消費者が得られる食べ物の情報は、値段、見た目、食味、カロリーなど、全て消費領域の話です。もちろん食べ物を選ぶ上でこれらの情報も大事なわけですが、決定的に欠けている情報があります。それが食べ物の裏側にいる、血の通った人間の存在です。……
甲賀市の小佐治を訪問

▪︎先週の水曜日(2月11日)、総合地球環境学研究所の奥田昇さんと一緒に、滋賀県甲賀市の小佐治集落にある「甲賀もちふる里館」を訪れました。奥田さんがリーダー、私がコアメンバーの1人として取り組んでいるプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」について相談をするためです。小佐治集落からは、環境保全部会の皆さん、小佐治集落の区長さんがご出席くださいました。小佐治集落は、滋賀県庁や滋賀県立琵琶湖博物館の支援のもと、「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策」のための事業に取り組んでいます。そのような関係もあり、この日は、滋賀県庁農林水産部農村振興課の職員や琵琶湖博物館の学芸員の方たちもご参加くださいました。
 ▪︎小佐治では、水田の内部に水田内水路を設けて、年間を通じて生き物が生息できる場所を提供しています。生き物が生息できるということは、安心・安全な農産物を生産している水田でもあるということの証明にもなります。現在、そのような水田では、メダカが繁殖して藻のなかで越冬していることが確認されています。小佐治も含めた甲賀市の農村地域の水田は、「ズリンコ」と土地の人びとが呼ぶ古琵琶湖層群の粘土でできています。きめが細かいため、水田から水を抜くことが難しい土質なのです。この湿田に苦労されてきました。小佐治では、そのような性質をもつ水田の内側に水路をつくり、塩ビのパイプ等を設置し、生き物の生息場所をつくってきたのです。その効果は生き物だけでなく、作付け面積が減るものの水田内の水位調整が容易になり湿田が解消することにもなりました。右の写真は、そのズリンコです。ズリンコのなかにあるのは、淡水貝の化石です。ここがかつて琵琶湖の底であったことがご理解いただけるとおもいます。
▪︎小佐治では、水田の内部に水田内水路を設けて、年間を通じて生き物が生息できる場所を提供しています。生き物が生息できるということは、安心・安全な農産物を生産している水田でもあるということの証明にもなります。現在、そのような水田では、メダカが繁殖して藻のなかで越冬していることが確認されています。小佐治も含めた甲賀市の農村地域の水田は、「ズリンコ」と土地の人びとが呼ぶ古琵琶湖層群の粘土でできています。きめが細かいため、水田から水を抜くことが難しい土質なのです。この湿田に苦労されてきました。小佐治では、そのような性質をもつ水田の内側に水路をつくり、塩ビのパイプ等を設置し、生き物の生息場所をつくってきたのです。その効果は生き物だけでなく、作付け面積が減るものの水田内の水位調整が容易になり湿田が解消することにもなりました。右の写真は、そのズリンコです。ズリンコのなかにあるのは、淡水貝の化石です。ここがかつて琵琶湖の底であったことがご理解いただけるとおもいます。
 ▪︎このような小佐治の生き物を賑わいを育む取り組みは、村の活性化にもつながっています。メダカが繁殖した水田で生産した米は、「めだかのいる田んぼの米」(メダカ米)として販売されています。販売されているのは、集落のなかに設けられた農村レストラン&直売所の「甲賀もちふる里館」です。さきほど「ズリンコ」について説明しました。たしかに「ズリンコ」は農作業が大変です。しかし、この粘土のなかにはケイ酸カリやマグネシウムが豊富に含まれており、稲やもち米が強く育つのです。小佐治では、そのような地域の環境特性を活かして、村づくりの活動にも取り組んでおられるのです。
▪︎このような小佐治の生き物を賑わいを育む取り組みは、村の活性化にもつながっています。メダカが繁殖した水田で生産した米は、「めだかのいる田んぼの米」(メダカ米)として販売されています。販売されているのは、集落のなかに設けられた農村レストラン&直売所の「甲賀もちふる里館」です。さきほど「ズリンコ」について説明しました。たしかに「ズリンコ」は農作業が大変です。しかし、この粘土のなかにはケイ酸カリやマグネシウムが豊富に含まれており、稲やもち米が強く育つのです。小佐治では、そのような地域の環境特性を活かして、村づくりの活動にも取り組んでおられるのです。
▪︎さて、私たちの総合地球環境学研究所のプロジェクトでは、この小佐治の生き物のにぎわいづくりを通した村づくりの活動を、プロジェクトの研究調査を進めることのなかで応援させていただければと思っています。少しずつ相談を進めてきました。具体的な計画の詰めはこれからということになりますが、いよいよこの春から「超学際(トランスディシプリナリティ) 」的取り組みが始まります。
「限界集落株式会社」
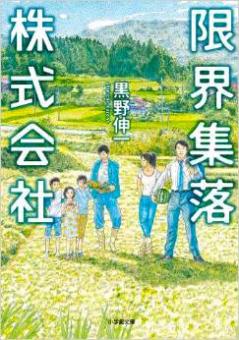
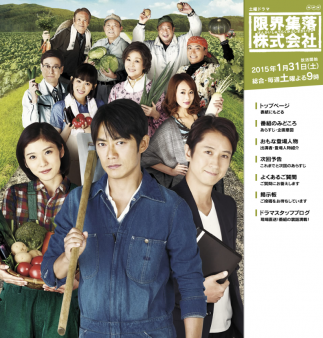
▪︎黒野伸一さんの『限界集落株式会社』が、NHKのドラマになるようです。主演は、反町隆史さん。カッコいいですね〜。このドラマのホームページで、制作統括をされた落合将さんが、次のように語っておられます。
NHKの現代ドラマ、久しぶりの農業ものです。農業を撮影するのは困難を極めます。作物の状態が、限られたスケジュールに合うのか、台風などの襲来によっては撮影用の畑が壊滅します。それでも、その困難な素材に正面から取り組んだのは、いま劇的に日本の農業をめぐる世界が変わってきているからです。ドラマをつくるにあたって、いろいろ取材をされていることがわかります。
日本の農村はいまや「限界集落」どころではなく「地方消滅」の危機を迎えています。そのなかで、地方唯一の産業「農業」を通じて、一矢を報いていく小さなチームを描くときに、バブルの時代に描かれたのんびりした空気の流れる「村おこし」を描くことはもはやできませんでした。シビアな時代に、どういまある力を使って、仲間たちと立ち向かっていくのか、難しい題材を描く際に、あとおししてくれたのは、実際に農業法人をたちあげて、新しい農業の形を模索する若者たちの姿でした。農業未経験者の彼らは、都会ではなく、農村に夢を求めて、アイターンしてきます。旧来の世襲制度が崩れ始め、地方の農村が変わり行く中で、私たちの目には彼らが「開拓者」のように見えました。そういったたくさんの取材先の方々たちの力を借りながら、この挑戦的な企画はなりたちました。出来上がったドラマもまた、素晴らしい出演者の皆さんの力を借りた、現代の「開拓者たち」のドラマに仕上がったと思います。
▪︎黒野さんの本自体は、研究室に置いてあるのですが(本のタイトルに惹かれて…)、まだ読めていません。原作とドラマは少し違っているようですが、まずは明日31日(土)から始まるドラマを視ることにしたいと思います。小説自体の評価は様々なようですが、大切なことは、ここからどういうメッセージを受け取るかでしょうかね。このような限界集落のようなテーマと関連する新書を紹介したことがあります。1月7日のエントリー「『農山村は消滅しない』(小田切徳美・岩波新書)」です。こちらの方、ぜひご覧いただければと思います。新書の著者である小田切徳美さんの講演の動画も貼り付けてあります。
【追記】▪︎さきほど、ゼミ生が研究室に相談にやってきました。ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」の活動に関して、ある財団に活動助成を申請するのですが、その申請書類をチェックしてほしいとやってきたのです。ちょっと雑談もしました。お父様が、時々、このブログを読んでくださっているとのこと。ありがとうございます。お父さん、娘さんは頑張って大学で勉強してはりますよ!!
『農山村は消滅しない』(小田切徳美・岩波新書)
 ▪︎ネットでこういうニュースを読みました。NHKのニュースです。一部を引用します。
▪︎ネットでこういうニュースを読みました。NHKのニュースです。一部を引用します。
住民の半数以上を高齢者が占め、存続が危ぶまれているいわゆる「限界集落」は国の調査で全国400か所以上に上り、中でも東北地方は50か所と中国・四国地方に次いで人口減少が深刻な過疎地が多く、集落維持のコストが課題となっています。
このため国土交通省は、集落を維持する場合と中心部に移しコンパクトな街づくりを進める場合のコストを比較し、実際の集落をモデルに検証することになりました。
▪︎国交省は、限界集落を維持するための、社会的費用がかかりすぎる…といいたいのでしょうね。「集落の維持にかかる道路や上下水道の費用やバスやゴミ収集車などのコストと、集落の移転に伴う費用を比較し移転でどれだけ節約できるのかを分析する」のだそうです。人口が集中している地域に住んでもらいたい、移転の費用を出すから、いまいるところを諦めて、町の方に暮らしてくれ…ということなのかもしれません。東北地方整備局の方は、「限界集落の問題は、住民の合意形成が難しくなかなか解決に向かわないが、『コスト』を見える形にすることで、集落再編を進める貴重なデータにしたい」とも話しておられます。
▪︎このようなコストだけが突出するような形での調査には違和感があります。単純に、集落維持に必要なコストと移転の費用を天稟にかけて判断することに違和感があります。限界集落の移転の話しは、その地域の歴史や状況、そして当事者の方たちの考え方を大切にしながらでないと進みません。コストの見える化だけの話しではないでしょう。移転するにしても、その移転先は、集落にとって馴染みのある地域なのか、それとも縁もゆかりもない地域なのかで、かなり違った話しになります。また、何代にもわたって暮らしてきたその土地の持つ意味、土地の「場所性」の問題についても、きちんと視野にいれないといけません。さらには、近くの町場に息子世代が暮らしているのかどうかといったことも、移転の問題にとっては重要になるでしょう。どのような地域を対象にした調査なのか、どのようなデータが収集されるのか、そのあたりもすごく気になります。特定の地域の事情が強く反映しているにもかかわらず、データだけが一人歩きしてしうことが怖いと思います。なんとか生き残ろうと頑張って村づくりに取り組んでいる地域がありますが、そのような地域にも、冷水をかけてしまうことにはならないのか…と心配しています。
▪︎この小田切徳美さんの『農山村は消滅しない』(岩波新書)は、このような政策的動向が既成事実化していく状況を批判的にとらえています。新書の帯には、「地方消滅論が見落とした農山村の可能性」と書いてあります。以下は、この新書の内容です。
増田レポートによるショックが地方を覆っている。地方はこのままいけば、消滅するのか? 否。どこよりも先に過疎化、超高齢化と切実に向き合ってきた農山村。311以降、社会のあり方を問い田園に向かう若者の動きとも合流し、この難問を突破しつつある。多くの事例を、現場をとことん歩いて回る研究者が丁寧に報告、レポートが意図した狙いを喝破する。
▪︎今は、時間的余裕がありませんが、近いうちに読んでみようと思います。
【追記】▪︎日本記者クラブで、小田切さんが講演されています。その講演がYouTubeにアップされています。
ビワマスのこと
■「つながり再生モデル構築事業」(滋賀県琵琶湖環境部環境政策課)の関係で、野洲市にある家棟川の支流に調査にいってきました。先日、地元の「NPO法人家棟川流域観光船」の方たちとの協議のなかで、この支流にビワマスが産卵をするために遡上しているというお話しを、写真とともに伺っていたからです(写真下段右)。地元の皆さんの観察によれば、琵琶湖からやってきたビワマスたちは、家棟川の支流に入り上流に昇ろうとするのですが、河川の構造物が邪魔をして遡上できないようだというのです。また、大きな礫が河床にあって、産卵に適した砂利がないということもご指摘されていました。ということで、ビワマスが遡上し産卵できるようにするために、関係者が集まって現地を調査することになりました。
■この日の調査は、地元からは、「NPO法人家棟川流域観光船」の代表である北出さんと、野洲市環境基本計画の策定に市民として参加された方達3名の皆さんがご参加くださいました。研究者では、「つながり再生モデル構築事業」のモデル地域選定委員会でご一緒した、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤さんが、今回の調査をアレンジしてくださいました。佐藤さん、ありがとうございました。そして、河川に魚道をどのように設置すればよいのかという技術的な点から、同じく選定委員会でご一緒した徳島大学の浜野龍夫先生(生物資源増殖学、地域生物応用学)もご参加くださいました。浜野さんは、ご自身で「私は、便利な水辺のおっちゃんなんですわ」とおっしゃいます。全国各地の河川の魚道設置に積極的にアドバイスし、それぞれの河川にあった魚道を提案をされてきたたくさんの実績をお持ちなのです。その他、行政からは、滋賀県琵琶湖政策課・流域政策局・南部土木事務所から4名の職員の皆さんが、野洲市からは環境課の皆さんが2名、そしてなんと驚いたことに、野洲市長の山仲さんもお忙しいなかご参加くださいました。
■調査は、冷たい雨が降るなかで実施されました。写真をご覧ください。地元の皆さんが困っておられるのは、トップの写真にあるような仮設の「落差工*」をビワマスが超えることができない…ということです。この落差工の手前までは、河川がすでに整備済みで、矢板をうってあるところから上流は未整備のままになっており、その整備の時期も未定なのだそうです。数十年間は整備される予定がない(必要性がない)とのことでした。ということで、現在の「落差工」の状況を確認し計測するために、浜野先生と佐藤さん、そして地元の市民のお1人が川のなかに胴長を着用して入っていかれました。あまり役に立たない環境社会学者の私は、橋の上から見学…。浜野先生からは、写真の中断左のような支流のさらに支流については、ビワマスが遡上しないような工夫をして、落差工に魚道を設置すれば、ビワマスは遡上させることができるというご意見をお聞かせいただけました。工事費もおそらくは600万円程度で済むとのことでした。浜野先生の言われる魚道とは、私たちが通常考える魚道とは異なります。河川の横に階段状の魚道がよく設置してありますが、日本の河川の魚達に不向きなものなのだそうです。こちらをご覧いただくと、浜野先生がご指導されている魚道がどのようなものであるのか、わかります。また、工事費が安く済むのかもわかります。
■こうやって、冷たい雨のなかで立場の異なる人たちが一緒に行動すること、言い換えれば、身体を使って「場を共有することは」とても大切なことだと思います。私たちは、調査のあとは、野洲市の図書館の一室を借りて協議を継続しました。異なる視点から、どうやって魚道を設置していくのか、知恵を出し合いました。生息調査を継続していく。工事費をどうやって捻出するのか。魚道の設置工事には市民参加で行う必要があること。野洲市全体の市民活動・まちづくりの文脈(環境再生型地域づくり)を背景にして、ビワマスの遡上・産卵や魚道設置を位置づける必要があることなど…いろいろ意見が出ました。意見を出すだけでなく、目標に向かってロードマップを作成していくことなども、全員で共有することになりました。
▪︎ところで、ビワマスってご存知でしょうか。ビワマスは、琵琶湖の固有種です。琵琶湖にしか生息していません。ビワマスは、琵琶湖の周囲の河川で生まれた仔魚は、琵琶湖の深いとろこにいって4〜5年かけて40〜50cm前後まで成長します。そして産卵期になると、生まれた河川に遡上していくのです。この産卵期のビワマス、大雨のときに黒く群れをなして河川を遡上することから、アメノウオともよばれています。しかし、そのような群れをなして遡上することは、この野洲市のあたりではあまり見られなくなってきました。河川改修などによる生息環境の悪化などで、生息数が年々減少しているからです。現在は環境省のレッドリストに準絶滅危惧種(NT)として指定されています。 今回、家棟川支流でこの準絶滅危惧種のビワマスの産卵が確認されたことから、家棟川をはじめとする身近な河川にもっと多くの皆さんの関心が向かっていけばよいなあと思っています。そして、流域管理を柱にした、環境再生型のまちづくりが展開していけばよいなと思っています。
*落差工:洪水防止や農業用水確保のために、急勾配の河川の勾配を緩やかにする構造物のことです。落差を河川のなかに設置して、階段状の段差をつけて流れを緩やかにします。そのことで流速を調整するのです。
地球研「奥田プロジェクト」

■昨日のお仕事。1つ前のエントリーにも書いたように、総合地球環境学研究所でのミーティングでした。「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」。奥田昇さんをリーダーとするプロジェクトのミーティングです。機能は、リーダーの奥田さん、そして副リーダーの谷内茂雄さん(京都大学生態学研究センター)、そして私の3名のミーティングです。いろいろ事務的なこともやらねばなりません。とりあえず、地球研で3時間半ほどミーティングと事務作業を行いました。
■写真は、研究所内にある奥田プロジェクトの場所です。地球研にはプロジェクトごとの部屋がありません。大きなスペースを簡単に仕切ってあるだけです。プロジェクト間のコミュニケーションを活発にしていくため、このような建物のデザインになっているようです。私も、来年度からは定期的にこちらに出かけてプロジェクトの仕事を進めたいと思っています。まだ机が空いていますが、これから順番に埋まっていく予定です。ポスドクの方たちなど、これから順番に雇用されていきますので。現在は、まだリーダーの奥田さんと事務的な仕事を担当される方が2名。広さのわりには人が少ないのです。まあ、そのうちに、賑やかになってくるではないかと思います。
コアメンバー会議
 ■昨日は、京都大学生態学研究センターで、研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のコアメンバー会議が開催されました。生態学研究センターから総合地球環境学研究所に異動したリーダーの奥田さん、センターの谷内さん大薗さん、滋賀県立大学の伴さんと、プロジェクトの進捗状況を相互に確認し、これからの研究先駆略等について議論を行いました。いろいろ難題が山積なのですが、とにかく前進しなくてはいけません。
■昨日は、京都大学生態学研究センターで、研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のコアメンバー会議が開催されました。生態学研究センターから総合地球環境学研究所に異動したリーダーの奥田さん、センターの谷内さん大薗さん、滋賀県立大学の伴さんと、プロジェクトの進捗状況を相互に確認し、これからの研究先駆略等について議論を行いました。いろいろ難題が山積なのですが、とにかく前進しなくてはいけません。
■総合地球環境学研究所の研究プロジェクトのシステムは、以下のようになっています。地球研のサイトからの引用です。
地球研では、既存の学問分野で区分せず、「研究プロジェクト方式」によって総合的な研究を展開しています。
研究プロジェクトはIS(インキュベーション研究 Incubation Study/個別連携プロジェクトのみに設定)、FS(予備研究 Feasibility Study)、PR(プレリサーチ Pre-Research)、FR(フルリサーチ Full Research)という段階を経て、研究内容を練り上げていきます。
国内外の研究者などで構成される「研究プロジェクト評価委員会(PEC)」による評価を各対象年度に実施し、評価結果を研究内容の改善につなげています。研究の進捗状況や今後の計画について発表し、相互の批評とコメントを受け研究内容を深める「研究プロジェクト発表会」を年に1回開催しています。
CR(終了プロジェクト Completed Research)は、社会への成果発信や次世代の研究プロジェクト立ち上げなど、さらなる展開を図っています。
■もうじき、上記の説明にある「研究プロジェクト発表会」が開催されます。この「研究プロジェクト発表会」の評価により、「FS(予備研究 Feasibility Study)」の段階から「PR(プレリサーチ Pre-Research)」に進むことができます。関門があるのです。私たちの研究プロジェクトは、昨年、この関門をなんとか突破することができました。来年からは「FR(フルリサーチ Full Research)」に進みます。関門を突破できなかった「FS(予備研究 Feasibility Study)」の段階にある研究プロジェクトはやり直し、または中止になります。最後まで到達するのはなかなか厳しいのです。今年は、この関門がさらに厳しくなっているようです。ただし、「PR(プレリサーチ Pre-Research)」に進んだからといっても「研究プロジェクト発表会」や「研究プロジェクト評価委員会(PEC)」の厳しい評価を受けなければなりません。11月26日から28日にかけて、今年の「研究プロジェクト発表会」が開催されます。