秋の琵琶湖





■火曜日は、大学では報恩講の行事があり、授業は全学休講でした。ということで、普段は、まだ働いている時間に家にいることができました。せっかくなので、近所を少しだけ散歩してみることにしました。近くの丘陵地にある公園からは、手前から、琵琶湖大橋、沖島、伊吹山を遠くに眺めることができます。まだ、伊吹山は少し霞んで見えましたが、これから気温が下がり空気が澄んでくると、雪の伊吹山を眺めることができます。この伊吹山、お近くにお住まいの知人にお聞きしたが、麓から頂上まで3時間半もあれば登れるようですね。積雪の前に、案内して登ってこようかなと思っています。
■散歩をしながら、よそのお宅の外に飛び出している花や実を観察しました。
流域治水の真空地帯

■火曜日は、1講時から授業があります。朝、多くの学生の皆さんと一緒に、JR瀬田駅から瀬田キャンパスに向かっていると、LINEで家族からメッセージが届きました。どうしたろだろうとスマホを見てみると、今朝の新聞記事でした。記事は、8月上旬に氾濫した高時川に関連するものでした。このブログでは、高時川に関連して、過去にこのような投稿をしてきました。
「被害引き受けた農地の苦悩」という記事
高時川の氾濫に関してご教示いただきました。
流域治水に関連して
高時川氾濫の動画
高時川の氾濫に関連して-「遊水池」の受苦-
■8月上旬の高時川の氾濫で、被害を受けられた農家である横田圭弘さんとも少しやりとりをさせていただきましたが、溢れた水を受け入れた後、農地は大変なことになっています。今は、稲の収穫をされていますが、圃場に流入した漂流物を手で取り除いても、どうしても全ては取り除くことができません。しょっちゅうコンバインに漂流物が挟まって作業が進まず、たびたびコンバインや乾燥機等が故障しているとのことでした。今のところ、この費用は、被害農家である横田さんの農園が負担しなければなりません。以下は、9月24日の横田さんのfacebookへの投稿です。
■さて、今朝の記事の内容を見てみましょう。記事では、農業保険制度のうち収入保険制度の算定方法について解説してあります。記事を引用します。
過去5年平均収入を基準にして、被害に遭った年の収入が90%を下回ると下回った額の最大9割が補填される仕組みですが、横田さんは数年前の台風でも大きな被害を受けました。過去の5年のうち毎年のように被災した場合は、基準となる平均収入が低くなるため、補填額の算定は厳しくなます。従業員を雇って運営する法人の経営では楽ではありません。
■横田さんは、自分の農地が「霞堤」として機能するように治水計画上で位置付けているのであれば、被害にあうリスクが高いわけだから、どうして他の地域と同じ扱いで算定されなければならないのか、おかしいのではないかというわけです。本当にその通りだと思います。算定方法は、被害を受けた農地の実態に即したものではないということになります。農家を補償する制度としては単純すぎるようにも思います。
■記事では、県が田畑に治水機能を期待しているのなら、その機能を果たした時の補償はないのかとの疑問から、滋賀県庁の流域治水政策室に質問されたようですが、以下のような回答のようです。
「霞堤」は県流域治水基本方針に記載はあるが、流域治水条例への明記はなく、知見も深まっていない。治水機能を果たす農地があることは認識しているが、それにより下流への影響の検証はできない。
湖北圏域河川整備計画は2016年に策定しており、高時川上流は整備実施区間には位置付けられている。そのなかでも、霞堤の扱いは広域への影響を考慮する必要がある。測量やシミュレーションをしながら、慎重に進めているところ。
■率直に言えば、「いかにも行政組織らしく慎重な回答だな」と思います。私なりにこの行政組織の回答を言い換えれば、「霞堤」が治水機能を果たしているかもしれないし、そのことはわかってはいるけれど、きちんと科学的に評価できていないので、本当に下流の被害を軽減しているのかといえば、よくわからない。たがら、すぐには対応できない、どうすれば良いのか今は考えがあるわけではないし、何かできるわけでもない…ということのように聞こえます。直接的には言ってはいないにしろ、結果として、「被害農家には、ご自身で負担していただくしかない…」と言っているのに等しい内容かと思います。被害農家の横田さんにはそのように聞こえていると思います。記事では農政課にもお尋ねになっています。農政課は「『農業保険制度は全国一律の仕組みで、現状、県独自に別途助成することは困難であると考えている」と回答されています。行政は、何の法的・制度的な根拠もなく、簡単に、被害農家に寄り添うような、あるいは期待を持たせるような発言はできないのでしょう。そのことも理解はできます。でも、流域治水の制度の真空地帯に横田さんは置き去りにされたままになります。
■記事には、次のようなことも書かれていました。日本農業新聞の記事のようです。
農水省が自民党農林合同会議に23年度農林予算概算要求の重点事項を示した際に、自民党側から収入保険について、毎年のように被災した場合に基準収入が低く計算され、補填額が減ってしまうとの課題提起がありました。農水省側は問題は認識しているとし、何らかの対応を検討する考えを示唆したとのことです。
■これから気候変動がさらに進んでいきます。豪雨による被害が頻発するでしょう。そのような被害に対応できるように、さまざまな救済制度を修正していく必要があるように思います。そのような被害発生後の救済制度の修正も含めて、国土強靭化なのではないでしょうか。土木技術だけの話ではないはずです。
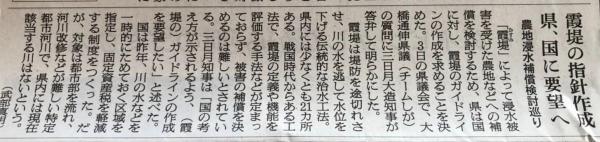
■以上の堀江さんの記事の下の方に、「霞堤の指針作成県、国に要望 農地浸水補償検討巡り」という記事が掲載されていました。県議会で、三日月滋賀県知事が以下のような答弁をされています。「霞堤の定義や機能を評価する手法などが定まっておらず、被害の補償を決めるのは難しいとされている。三日月知事は『国の考え方が示されるよう、(霞堤の)ガイドラインの作成を要望したい』と述べた」。県が国に下駄を預けるかのような答弁のようにも聞こえますが、「国がまずは基準(ガイドライン)を作ってくれないと、県としても動きようがない」ということなのでしょう。このような要望の結果として、国はどう対応していくのか継続して注目したいとは思いますが、このような中で、横田さんの被害の苦しみは、そのままということになってしまうのでしょうか。すでに起こったこととして、救済の対象にはならないということになるのでしょうか。
第27回全国棚田(千枚田)サミット(2)

■この写真は、昨日開催された第27回全国棚田(千枚田)サミットの第2分科会の様子を、参議院議員の嘉田由紀子さんが写真に撮ってくださったものです。滋賀県庁の農政水産部の部長さんや次長さんもお越し下さいました。ありがとうございました。第2分科会ですが、パネリストの皆さんからは、「とても楽しかった」、「もっと話しがしたかったです」という感想をいただきました。集落を超えて、志を持った方たちが集まって、ヒントを出し合い、愚痴をこぼしあい、支え合える場ができたら素敵だと思います。ぜひ、そういう集会が定期的にできたら良いなあと思っています。


「全国棚田(千枚田)サミット)の2日目は、朝から3つに分かれてエクスコーションを実施されました。私は、全国各地の棚田からお越しの皆さんと一緒に、高島市の一番南にある鵜川を訪問するエクスカーションにしました。琵琶湖に面する棚田です。一般には、棚田自身が生み出す風景に評価が集まりますが、鵜川の棚田は、棚田からの琵琶湖の風景が素晴らしいと思います。棚田、JR湖西線、琵琶湖、沖島、湖東…それらが重なる風景に感動します。集落では、この棚田を保全するために、様々な活動に取り組んでおられます。詳しくは、以下をご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/…/nousonshinkou/317821.html
http://www.ukawama-to.com/tanada-2.html
https://smout.jp/plans/5779


■本日の正午に、2日にわたって開催された「第27回 全国棚田(千枚田)サミット」が閉会しました。閉会式典では、まずは分科会のコーディネーターを担当された、龍谷大学社会学部の坂本清彦先生(第1分科会)、経済学部の西川芳昭先生(第3分科会)とともに、私も第2分科会の報告を行いました。最後は、特別分科会のコーディネーターをおつめになった中島峰広先生が報告をされました。
■第2分科会からは、およそ以下のような報告をさせていただきました。テーマは、市役所の事務局の方で決められたものです。
第2分科会のテーマは「棚田に根付く”価値”を繋げる〜地域産業の振興と次世代への継承〜」です。高度経済成長期の燃料革命により、地域の大切な副業であった炭焼きは途絶えることになりました。ところが、高齢化や過疎がすすむ中山間地域の集落や地域の中から、炭焼きをもう一度復活させて活性化につなげていこうという動きが出てきました。今日、お越しの皆さんは、そのような炭焼きに関わって来られた皆さんです。
パネリストは全員で5名の皆さんになりますが、地元の方は1名で、残りの4名の皆様は外から移住された方達です。それぞれの皆さんにお話いただいたことから浮かび上がってくることは、次のようなことでした。移住がスムースに進んでいるところでは、地元の側に、移住者の皆さんを受け入れ支える人たち、見守る人たちがきちんといるということです。また、移住者の人たちも、地元の暮らしの仕組み、習慣、文化、そして技術に対する尊敬の気持ちを持ち、地元の人たちに謙虚な気持ちで接しておられるのです。この地元の人たちの内からの支えと、移住者の外からの力がうまく調和してハーモニーを醸し出されてくることが大切だということです。また、地元の皆さんは、”地元の様々な事情”という「制約」の中で暮らしておられて、自由に発言や行動ができないことがあるわけですが、移住者の皆さんはそのような「制約」から相対的に自由なことから、移住者だからこそできることを地元の皆さんから期待されているというお話もありました。
ただし、こういった内(地元)と移住者(外)とをつなぐことを、個々人や集落の力だけに頼ることには限界があるという指摘もありました。内と外とを繋ぐシステムが必要だというわけです。これは、「人」だけの話ではなく、炭焼きで生産された炭、炭の原料となる落葉広葉樹の木材という地域の中で生み出された”価値”を、外でそれらを求めている人たち(潜在的な需要)と繋いでいくような仕組みも必要との指摘もありました。
高島市の中山間地域に限ったことではありませんが、高齢化と過疎化が加速を増して進んできています。しかし、逆に、そのようなピンチはチャンス。危機意識を共有することで、新しい地域の持続可能性を高めるための新しいアイデアが生み出されるのではないでしょうか。
■分科会会の報告の後は、「サミット共同宣言」、「次期開催地挨拶」、そして「協議会旗引き継ぎ」と続きました。来年度は、和歌山県那智勝浦町で開催されます。長年にわたってIターンの方たちを受け入れてきた那智勝浦町には、那智勝浦町ならではの魅力や棚田地域の課題を克服するための工夫や仕組みがあるのではないかと思います。そのことについてぜひ知りたいなと思いました。
■もうひとつ、「棚田(千枚田)サミット」は今回で27回目。約ひと世代にわたって全国各地の棚田地域で開催されてきました。その間に、どのような議論が行われてきたのか、どのような知見が蓄積してきたのか、棚田をめぐる人びとの関心はどのように推移してきたのか、そのようなことについても知りたいなと思いました。
■さて、今回、高島市での開催にあたっては、全国の皆様をお迎えするために、地域の皆様、市役所の職員の皆様は、大変なご努力で開催に向けての準備をされてこられました。お疲れ様でした。また、いろいろお世話になりました。2日とも天候も良く、無事に閉会できて本当によかったです。
百瀬川の隧道(滋賀県高島市マキノ町)
■お世話になっている高島市在住の谷口良一さんが、facebookにマキノ町にある百瀬川の隧道のことを投稿されていました。百瀬川は天井川の下を通る隧道(トンネル)がその役目を終えて解体されるという話題です。その前にこの百瀬川と百瀬川が形成した扇状地のことについて少し確認しておきましょう。私は知らなかったのですが、この百瀬川によって地理学や地理学教育の分野では、大変有名なんだそうです。自分でも少し調べてみました。こちらの「日本の地形千景+α」[/rul]では次のように解説されています。
百瀬川」は,滋賀県西北部と福井県若狭地方に跨がっている「野坂山地」から流れ出しています。山地と平地の境界には「琵琶湖西岸断層」が走っており,その特徴は「西側隆起の逆断層」です。従って,野坂山地側が隆起する度に,河川の「下刻侵食」が激しくなると共に,平地には巨大な「扇状地」が発達します。
百瀬川の強大な侵食力によって,平地には広大な「扇状地」が形成されました。大量に運ばれてくる土砂により,「自然堤防」が高くなって「天井川」となってしまいました。このため,県道287号は「百瀬川」の下をトンネルで抜けています。
【百瀬川扇状地に関して解説しているサイト】
[url=http://www.eonet.ne.jp/~otto/outline-content.html]百瀬川扇状地-扇状地のあらまし
百瀬川扇状地-天井川と治水
120.扇状地 扇端集落のわき水 百瀬川扇状地
コンターサークル地図の旅-百瀬川扇状地
第27回全国棚田(千枚田)サミット2022in高島市
 ■来月、10月1・2日の両日、高島市で「第27回全国棚田(千枚田)サミット2022in高島市」が開催されます。テーマは、「棚田をつなぐ人のかけ橋~びわ湖を育む清流の輪~」。1日目の午後は分科会が開催されます。私は、第2分科会「棚田に根付く”価値”を繋げる~地域産業の振興と次世代への継承~」のコーディネーターを務めます。このテーマにある地域産業とは、高度経済成長期に入った頃まで続いていた炭焼きのことです。この炭焼きをどう継承していくのか、落葉広葉樹の森をどう活かしていくのか、後継者はどうするのか、外部の人びととの関係(移住者、関係人口等)はどのように関わることができるのか…この辺りのことをご報告いただく予定です。充実したディスカッションになるようにコーディネーターとして努力いたします。
■来月、10月1・2日の両日、高島市で「第27回全国棚田(千枚田)サミット2022in高島市」が開催されます。テーマは、「棚田をつなぐ人のかけ橋~びわ湖を育む清流の輪~」。1日目の午後は分科会が開催されます。私は、第2分科会「棚田に根付く”価値”を繋げる~地域産業の振興と次世代への継承~」のコーディネーターを務めます。このテーマにある地域産業とは、高度経済成長期に入った頃まで続いていた炭焼きのことです。この炭焼きをどう継承していくのか、落葉広葉樹の森をどう活かしていくのか、後継者はどうするのか、外部の人びととの関係(移住者、関係人口等)はどのように関わることができるのか…この辺りのことをご報告いただく予定です。充実したディスカッションになるようにコーディネーターとして努力いたします。
■実は、昨晩、この第2分科会でご報告いただく皆様と事前の打ち合わせをいたしました。私は、吹奏楽部の演奏旅行と重なってしまったため、演奏旅行先の名古屋から急いで自宅に戻り、オンラインで参加させいただきました。分科会で報告いただく皆様には夜や遅くからの会議になりご迷惑をおかけしてしまいました。すみませんでした。打ち合わにご出席いただいた皆様は、昨年、高島市の委託研究でヒアリングをさせて頂いたこともあり、スムースに話が進みました。当日が楽しみです。
■今日の午前中は、滋賀県の「ヨシ群落保全審議会」でした。ヨシ群落の保全も、面積を増やしていく時代から、すなわち「量」を問題にする時代から、ヨシ群落多くのステークホルダーの皆さんと、どのように維持していくのか、活用していくのか、すなわち「質」を問題する時代に移行しています。明日は、そのような新しい時代の問題について話し合うことになりそうです。こちらもこれからの展開が楽しみです。
■さて、今日はこの「ヨシ群落保全審議会」の後、演奏旅行中の龍谷大学吹奏楽部に合流し、岐阜県羽島市で開催されるコンサートで演奏を聴かせていただくはずだったのですが、残念ながらコンサートは中止になりました。演奏旅行中の部員の中から、新型コロナウイルの陽性者が出たからです。このことは、すでにfacebookやTwitterで広く広報するとともに、コンサートを予約していただいた皆様には、部員が分担して中止になったお詫びの連絡をしました。以上のことをまずはこの拙ブログでもお知らせしておこうと思います。
2022年度 集中講義「びわ湖・滋賀学」

■来週月曜日から金曜日まで、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の先生方と「びわ湖・滋賀学」の集中講義の授業を行います。私自身は、コーデイネーターで授業を担当しません。裏方の仕事です。
■琵琶湖博物館は、「湖と人間」をテーマとする博物館です。滋賀県草津市の琵琶湖に突き出した烏丸半島にあります。6年の歳月をかけて展示をリニューアルを行い、一昨年の10月にグランドオープンしました。この集中講義では、8月29日〜8月31日の3日間をオンライン講義で、9月1日〜2日の2日間は琵琶湖博物館の展示を用いて講義を行う予定になっています。
■講義のねらいは、滋賀県の特徴について、「琵琶湖」と人の関わりという視点から理解を深めることにあります。この地域で暮らしてきた人々の産業(農林水産業が中心です)や日常の文化のありかたを見つめ直し、それらと琵琶湖集水域という環境との密接な関わりについて学びます。
具体的なトピックとしては、琵琶湖の自然と生い立ち、自然と暮らしの歴史、暮らしとつながる自然、水の生き物と暮らしを取り上げ、琵琶湖博物館の新しい調査研究の成果をまじえて講義していただく予定になっています。具体的には、こんな感じです。
【オンライン授業 8月29日・30日・31日】
1.オリエンテーション
2.琵琶湖の魚と水田利用魚類
3.琵琶湖・河川の漁業
4.魚のゆりかご水田・滋賀の水田農業
5.近江のふなずし
6.琵琶湖の漁具・人々の暮らし
7.水辺の暮らし・森の暮らし
8.気候変動と人の利用による植生変遷
9.琵琶湖の固有魚の進化【展示による授業 9月1日・2日】
10.A展示室見学・課題学習
11.B展示室見学・課題学習
12.C展示室見学・課題学習
13.水族展示室見学・課題学習
14.企画展示見学・課題学習
15.まとめと課題レポート作成
■ひょっとすると、「これ、世界農業遺産に認定された琵琶湖システムの内容とちゃうの?」とお気づきの方がおられるかもしれませんね。琵琶湖博物館の学芸員の先生方が、特に世界農業遺産を意識しているというわけではないのですが、そうなんです、内容はかなり重なっています。というか、世界農業遺産の琵琶湖システムも、琵琶湖博物館も、共にこの滋賀県固有の地学・地理、生態、生業、文化、社会…そのような要素が40万年の歴史の中で順番につながり構造化されてきたシステムに焦点を合わせているからです。まあ、琵琶湖博物館の方がちょっと先輩ではありますが。
■このような内容だと、学生さん以外にも、一般の皆さんの中にも、講義を受けてみたいという方がおられるかもしれませんね。その気になれば、龍谷大学のREC等でも同様の市民向けの講義ができるはずです。まあ、その辺りは将来の可能性ということにしておきます。とはいえ、大学の学外連携部門の担当者の職員さんからは、ぜひ進めたいとのご意見も頂いています。私がこの授業を担当しているわけではないのですが、今後の展開が楽しみになってきました。
■最後になりますが、この「びわ湖・滋賀学」を履修した皆さんが、この集中講義をきっかけに、実際の琵琶湖・滋賀県のフィールドへと足を運んでくださることを期待しています。滋賀県に暮らしてみたい、滋賀県で働いてみたい、滋賀県に移住したい、何度も滋賀県に来てみたい、そのような若者が増えたらいいなあと妄想しています。(トップの写真は、昨年の「びわ湖・滋賀学」で琵琶湖博物館を訪問した際、近くの湖岸が撮影したものです。)
琵琶湖の水草問題が

■最近、水草の大量繁茂の話題がすーっと消えてしまったかのようです。もちろん、きちんと、滋賀県が、適切、計画的に、刈り取って除去しているせいかと思います。ある研究者は、もはや水草は琵琶湖の重要な環境問題ではなくなっているという見解をお持ちのように記憶していますが、そうなのかもしれません。社会的な費用はかかっていることに変わりはないと思いますが、とりあえず水草繁茂はコントロールできているからです。水草の刈り取りが、現在、どのように行われているのかについては、滋賀県の「水草の刈取り・除去予定」をご覧ください。
■私たちが立ち上げたNPO法人「琵琶故知新」、当初は浜に漂着する水草をなんとか有効利用できないか…というところから始まりました。そのような水草がゴミ処理場で焼却処分されているのを、昔のように、土壌改良剤=水草堆肥として再利用・有効利用できないだろうか、というのが私たちNPOの出発点だったのです。ところが、浜に漂着する水草自体が、ここ数年相当量減少しているのです。嬉しいような、ちょっと空振りみたいになってしまって困っているような…。
■それはともかく、一昨日のことです。近所を車で運転しているとこんなトラックが走っていました。助手席の妻にとってもらいました。刈り取った水草らしきものを大量に積んでおられたからです。初めて拝見しました。こんな感じなんだ〜とちょっと興奮しました。こんな様子を見て興奮するのは、私ぐらいでしょうかね(^^;;。この水草、確か近江八幡市だったと思いますが、休耕田に野積みにして自然発酵させて、数年後に水草堆肥として無料配布されていたと思います。
■ところで、水草で空振りした私たちのNPO法人「琵琶故知新」では、今、食物残渣を地域社会で循環させていくための仕組みができないかということを、地域の様々な方達(事業者の方達を含みます)と相談を始めました。高い社会的な志しを持たれた事業者の皆さんとお話しできるようになり、少し前進している実感があります。「食物残渣→堆肥化→農業→直売所→消費者・観光業者→食物残差→堆肥化…」という循環をできるだけ太くしていくためには、どうしたら良いのか、どのような仕組みが必要なのか、いろいろ検討しています。
■こういうSDGsにもつながる地域課題を少しでも解決していきたいのですが、頭が痛いことが多々あります。社会の制度や法律が、根本のところで、大量生産・大量消費型の一方通行に適応した形になっていることです。この一方通行を、どれだけ循環型に切り替えていくことができるのか。とても大切なことだと思っていまするのですが…。大量生産・大量消費=安い・便利・簡単…ということから、地域循環=大切だ・おもしろい・やりがいがある・かっこいい…という方向に少しずつ替わっていったらよいなあと思っています
今日のTV番組「新移住時代」「流転!足利義満が愛した秘宝」
 ■本日、個人的にはですが、興味深い番組が放送されます。「地域再生・地域づくり」、「琵琶湖」に関連しています。
■本日、個人的にはですが、興味深い番組が放送されます。「地域再生・地域づくり」、「琵琶湖」に関連しています。
■ひとつめは、見逃してしまい視たかった番組「クローズアップ現代」の「移住新時代 過疎地域にチャンスあり」です。関西では、今日の夕方に再放送するようです。NHKBS1で17時半からです。
今、都市から過疎地へ移住する若者が増えている。最新の国勢調査によると過疎市町村の半数近くで20代後半から30代の転入者が転出者を超えた。リモートワークを活用し転職せずに移住したり、町の支援策を使って資金150万でパン屋を開業したり、農業で売り上げ1千万を目指す若者が現れたりと、新たなトレンドが。チャンスの少ない都市を脱し、人手の足りない過疎地で暮らし始める若者たち。可能性と価値観の変化を見つめる。
■昨年度に引き続き、今年度も滋賀県高島市で受託研究に取り組むことになっています。取り組むテーマは、関係人口、人口、移住者、移住者の定着過程と受け入れの仕組み等々です。参考になる部分があるかもしれません。期待しています。
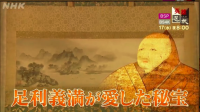 ■もうひとつの番組は、今晩20時からBSプレミアムで放送される「英雄たちの選択」です。今晩は、「流転!足利義満が愛した秘宝」です。滋賀の「近江八景」は、中国の「瀟湘八景」に倣ったもの。その「瀟湘八景」が、足利義満、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった時の権力者に深く関係していたことを知りませんでした。「瀟湘八景」については、京都国立博物館の解説をお読みください。
■もうひとつの番組は、今晩20時からBSプレミアムで放送される「英雄たちの選択」です。今晩は、「流転!足利義満が愛した秘宝」です。滋賀の「近江八景」は、中国の「瀟湘八景」に倣ったもの。その「瀟湘八景」が、足利義満、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった時の権力者に深く関係していたことを知りませんでした。「瀟湘八景」については、京都国立博物館の解説をお読みください。
今回の番組の主人公は、歴史上の人物ではなく、水墨画の最高傑作といわれる「瀟湘(しょうしょう)八景図」。室町将軍足利義満が愛した秘宝の数奇な運命をたどる。
絵巻は、その後切断され、流転していく。信長や秀吉、家康といった天下人の手に渡り、茶道の大名物(おおめいぶつ)として珍重された。江戸期にはいると、将軍吉宗が、江戸ルネサンスの文化の象徴として、各藩に分散しているこの絵巻を一堂に集めようとした。絵巻の流転の歴史から見えてくるのは、一枚の絵巻に託された権力者の飽くなき欲望とそれに振り回された悲喜こもごもの物語である。
■「近江八景」のもとになった「瀟湘八景」、現在の中国ではどのような状況になっているのでしょうね。状況というのは、実際の景観がどのようなものなのか、加えて、「瀟湘八景」のひとつであることをそこに暮らしている人たちがどのように捉えているのか…ということです。気になってネット上で調べてみましたが、まあわかりませんね。
朽木の河原仏
■2011年の春に卒業した坂本昂弘くんのルーツは、現在の高島市朽木にあります。その坂本くんの叔父様である坂本Kyojiさんがfacebookに投稿されました。お名前がローマ字になっているのは、漢字を存じ上げないからです。すみません。今度、お会いしたらお聞きしておきます。坂本くんや坂本家のことについては、こちらをお読みいただければと思います。スマホやタブレットでは、おそらくご覧いただけないかと思います。坂本さんは公開されておられますので、リンクを貼り付けておきます。
■坂本家は今も朽木にある先祖伝来のお宅を大切に維持されて、お盆の行事もなさっておられます。そのようなお盆の行事のひとつがこの河原仏です。こうやって、各家の男たちが川辺で精霊送りのための河原仏を作ることになっているのです。雨が降ったら、石を積んだだけの河原仏は流されていくことになります。
■以下は、「朽木古屋の六斎念仏踊り 滋賀県選択無形民俗文化財」というタイトルのついた動画です。この動画には、以下の説明が付けられています。この動画の最後に、河原仏を作っている様子をご覧いただけます。
「滋賀県高島市、朽木古屋地区にて受け継がれてきた念仏踊り。かつては集落のそれぞれの家を廻って踊られていたものの、過疎化によって2012年を境に途絶えた。2016年、途絶えていたこの芸能を、武田力、タカハシ’タカカーン’セイジなど7名のアーティストが習い、地元の高齢者とともに復活させた。
翌15日朝には河原に六地蔵を設える「河原仏」という儀式が行われる。」
