夏休みの自由研究(その2)






▪️夏休みの自由研究(その2)です。翌日、宿泊したホテルが「えちぜん鉄道」福井駅の真横にあったものですから、駅に入場券で入り、恐竜列車を拝見してきました。残念ながら、この列車は予約して乗ることができません。この後の、歴史の自由研究(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の観覧と一乗谷朝倉氏遺跡の見学)もやらねばならず、仕方なく見学のみです。親子連れが興奮されていました。私、前期高齢者ですが、小さな皆さんが羨ましかったな〜。
▪️こちらの電車、静岡鉄道から譲渡された車両なのだです。鉄道関連の企業にお勤めの知人からご教示いただきました。もともとは通勤電車なのですが、そうは見えませんよね。その知人も「かなり思い切って改造していますね」と言っておられました。できれば、次回は、孫たちと一緒にこの電車に乗ることができればなあと思っています。
夏休みの自由研究(その1)






 ▪️夏期休暇らしいことが全くできていないので、せめてもと8月23日〜24日、1泊2日で福井県に旅行に出かけました。普段、近所でしか車の運転をしない私からすると、けっこうなドライブです。あまりドライブ自体があまり好きでないのです。住んでいる大津市の湖西から福井県の敦賀へ、敦賀からは北陸自動車道に乗り途中から中部横断道で勝山市まで。なんとか辿りつくことができました。
▪️夏期休暇らしいことが全くできていないので、せめてもと8月23日〜24日、1泊2日で福井県に旅行に出かけました。普段、近所でしか車の運転をしない私からすると、けっこうなドライブです。あまりドライブ自体があまり好きでないのです。住んでいる大津市の湖西から福井県の敦賀へ、敦賀からは北陸自動車道に乗り途中から中部横断道で勝山市まで。なんとか辿りつくことができました。
▪️とはいえ、いつもとは違う楽しみもありました。敦賀に入ると、しだいにローカル放送局のラジオ番組(中波)が聞こえてきました。普段、大阪の番組を聞いているのですが、内容がかなり違っていました。たびたび、「♪茶碗のマークの よーしむらのおかきっ」というCMが流れていました。おそらくは、これは福井県内でないと聞けないCMでしょうね。番組では、地域特産の農産物であるナスやイチジクの生産状況のニュースだとか、新米の出荷だとか、農業関係の内容が多いことに驚きました。素敵だな〜と思いました。これはドライブ中のラジオの話ですが、窓から見える風景にも滋賀との違いを感じました。農家の屋根の形態が異なるので、集落の印象も違ってくるのです。中部横断道に入ると、山の間に挟まれた勝山盆地の山裾を走ることになります。そこからは、迫力がある風景が見えてきました。もちろん、運転に集中しているので、脇見運転をするわけにもゆかず、ちらりと見るだけでしたが。
▪️さて、勝山市に向かったのは、あの有名な福井県立恐竜博物館の展示を観覧するためでした。博物館の中は、夏休みということで、お子さんを連れた家族の皆さんがいっぱい楽しんでおられました。どうしてもあの映画『ジュラシックパーク』を連想してしまいます。博物館側もおそらく意識されているのではないでしょうか。じっくり観覧しようと思うと半日は絶対に時間が必要かと思いますが、その半分程度の時間で勉強してきました。いろいろ勝手な思い込みを修正することにもなりました。これは誰しもがご存知の常識になっていることだと思いますが、恐竜が進化して鳥になっているわけです。冬場、我が家の庭にやってくるかわいらしいメジロも、恐竜の「末裔」なんですよね。




 ▪️展示のストーリーは、恐竜を中心とした進化のドラマが中心になっていますが、地球科学や生命進化の話もあります。最後の方は、哺乳類や人類も登場します。その中でも、個人的な一番の推しは、やはり地元でみつかった恐竜の化石でしょうか。福井県の発掘調査で発見された新種の恐竜5種と他の動植物化石が展示されています。ちなみに、勝山市は、「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク」に認定されています。福井県の北東部に位置する勝山市全域をエリアとするジオパークです。詳しくは、こちらをご覧いただきたいと思います。
▪️展示のストーリーは、恐竜を中心とした進化のドラマが中心になっていますが、地球科学や生命進化の話もあります。最後の方は、哺乳類や人類も登場します。その中でも、個人的な一番の推しは、やはり地元でみつかった恐竜の化石でしょうか。福井県の発掘調査で発見された新種の恐竜5種と他の動植物化石が展示されています。ちなみに、勝山市は、「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク」に認定されています。福井県の北東部に位置する勝山市全域をエリアとするジオパークです。詳しくは、こちらをご覧いただきたいと思います。
▪️福井県立恐竜博物館は、親子連れでテーマパーク的に楽しむことができます。小さなお子さんも楽しめると思います。しかし、大人の夏休みの自由研究としては、事前学習をしっかりして、展示からもっと深く学ぶことが大切なのかなと思いました。今回は、お土産に図録をきちんと買い求めました。自宅でしっかり学習し、またこちらの博物館を再訪して学びを深めたいと思います。そうそう、博物館に行く前に、福井県の名物であるおろし蕎麦で腹ごしらえをしました。奮発して、天ぷらがついているものにしました(血糖値のこと心配ですが…)。食べてから、おろし蕎麦の大盛りにすればよかったかなとちょっと後悔しました。でも、美味しかったですよ。
加藤剛先生を囲んで


▪️今日も大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。今宵は12年前にご退職された加藤剛先生を囲んで、「ビワマス」の夕べ。そうです。また琵琶湖の固有亜種ビワマスの料理を楽しみました。ご参加くださったのは、加藤先生以外では、同僚の津島昌弘さんと工藤保則さんです。飲みながら、くだらない話もしながらも、先生の学問的ご関心を中心とした話で盛り上がることができしました。脳みそが興奮しました。楽しかった。
▪️加藤先生は、京都大学の研究所に勤務された後、龍谷大学に勤務されました。そして2011年に定年退職されました。個人的には、龍大に勤務されていた時に、親しくお付き合いいただきました。また、大学の課題に取り組む際に、お力をくださり支えてくださいました。本当に感謝しかありません。また、加藤先生と呑む機会を持たせていただければと思います。
『聴かずぎらいのための吹奏楽入門 』と有吉佐和子『複合汚染』
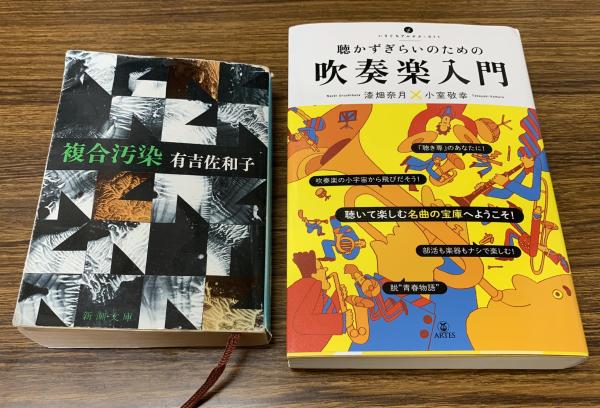
▪️今日、リュックの中に弁当や水筒と一緒に入れてきた本です。ただいるだけの部長だけど、もっと深く吹奏楽を楽しめたらとの思いから購入しました。『聴かずぎらいのための吹奏楽入門 』。おそらくコンクールで多くの学校が演奏してきた50曲の解説が、漆畑奈月さんと小室敬さちさんのお二人の対談の形式で、丁寧に行われています。今は、YouTubeでいろんな演奏を簡単に知ることができるので、重ねて読むとわかりやすいのかもしれませんね。本の情報は、こちらからどうぞ。漆原奈月さんの情報は、こちらです。
▪️もう一冊は、有吉佐和子さんの(1931年- 1984年)『複合汚染』。有吉さんは、1984年に53歳で亡くなっておられるのですね。この本は、1975年に出版されました。私の年代以上、あるいは近い人は、この『複合汚染』について、それなりにご存じなのではないでしょうか。これから来年度にかけて取り組む仕事に必要かなと判断し再読しています。この本が出版された頃の社会状況も含めて理解したいからです。時代の文脈のようなものを再確認したいのです。さまざまな公害や環境問題に関係する市民運動にも影響を与えたのではないかと思います。
▪️この有吉佐和子さんについては、朝日新聞で環境社会学者の友澤悠季さんが解説を書いておられました。たまたま彼女とは、学会に関わることでオンラインで会議をすることがあったのですが、その会議の後に、解説を書いておられることに気がつきました。私が手元に持っているこの『複合汚染』は新潮文庫ですが、1995年に出版されたものです。この段階で四十刷。もう、紙は茶色くなっています。字が小さい…。
関西吹奏楽コンクール金賞、全国大会へ。
本日、第73回関西吹奏楽コンクールにおいて、当部は金賞を受賞し、関西代表として全日本吹奏楽コンクールへの推薦をいただきました。
ご声援をくださった皆さま、本当にありがとうございました。
全国大会に向け精進して参りますので、今度とも龍谷大学吹奏楽部の応援をよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/1R2W1vb1Gx— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 19, 2023
▪️昨日、守山市の守山市民ホールで開催された「関西吹奏楽コンクール・大学の部」で、龍谷大学吹奏楽部は金賞を受賞するとともに、関西代表として宇都宮で開催される全日本吹奏楽コンクールに推薦をいただき出場することになりました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。全日本吹奏楽コンクールは、10月28日(土)に宇都宮市文化会館で開催されます。
2019年の関西吹奏楽コンクール

▪️龍谷大学吹奏楽部の部長に就任した年の関西吹奏楽コンクールで金賞を受賞した時の写真です。2019年です。
▪️吹奏楽のことについて何も知らない私は、若い頃からずっと吹奏楽に関わってきた知人から、いろいろ話を聞かせてもらっていました。そして、「もし、関西代表に選ばれなかったら、部員の中に全国大会を経験した人がいなくなるわけで、これは大変なことになるな」、そう思って心配していました。結果、この年、青森で開催された全国大会に3年ぶりに出場することができました。審査結果を会場で聞きましたが、その時の感動を今でもありありと思い出すことができます。私の横では、副部長が涙を流して喜んでおられました。
▪️2020年度の全国大会はコロナ禍により中止になりましたが、2021年度(高松)、2022年度(北九州)と、連続して全国大会に出場し金賞を受賞することができました。学生の皆さんの日々の懸命な努力、監督とコーチそして学外の先生方の丁寧で的確な指導、大学からの支援、この3つがうまく噛みあっているからなのかなと思っています。
▪️昨年度まで関西の代表枠は1校だけでしたが、今年度からは2校になりました。もちろん、代表枠が2校になったからといって、油断できるはずもありません。ライバル校の吹奏楽部の皆さんも、「今年こそは全国大会に行くぞ!!」と相当頑張ってこられていると思います。龍谷大学吹奏楽部は、明日も大学の練習場で最後の練習に取り組み、夕方から開催されるコンクールに出場します。大学の部に出場するのは、龍谷大学、立命館大学、関西大学、滋賀県立大学、近畿大学、京都産業大学、関西学院大学、神戸学院大学の8大学です。龍谷大学は一番最初に演奏します。圧倒的な演奏で、全国大会に進んでもらいたいと思います。
4年ぶりの合宿
▪️吹奏楽部の合宿が高島市の近江白浜で行われました。ということで、部員の皆さんや指導者の皆さんと合流するために、昨日、湖西線で移動しようとしたのですが、近江舞子で止まってしまいました。近江今津のあたりで落雷による信号トラブルが発生したのです。敦賀に行く人は、山科まで戻り琵琶湖線で移動してほしいとアナウンスがありました。私は安曇川まで行く予定だったんですが…。運転再開はかなり遅れるようでした。仕方がないので、近江舞子駅からタクシーに乗って、合宿場所の白浜荘までなんとかたどり着くことができました。


▪️ところが、運転手さん機械の操作を間違ったようで、運賃が500円と出てきました。そんなアホな安すぎる。まあ、納得できる金額を払って下車させてもらいました。いやいや、いろいろありますね。私のせいじゃないのに。さて、合宿は、コンクールのメンバーと、夕照コンサートのメンバーにわかれて練習しています。こちらは夕照コンサートの練習です。サマーコンサートでご指導いただいている金山徹先生にご指導いただいています。先生、ありがとうございます。


▪️合宿は本日の午前中までということで、昨日の夕食はBBQでした。そのあとは、花火大会です。盛り上がっていますね。現在の部員の皆さん、コロナ禍のために 、1回生から4回生まで、全員が合宿の経験がないのです。これ、初めての合宿なんです。楽しそうでしょう‼︎ やっと、以前の学生さんであれば当たり前のようにやっていた経験を、やっとすることができたわけです。本当に良かったと思います。こうやって多くの部員が楽しんでいる間にも、コツコツと練習をしている部員さんがおられました。一生懸命マリンバの練習をされていました。指導してくださる先生から宿題が出ているそうです。同じ楽器の部員の皆さんの演奏レベルが高いので、自分も頑張らなければならない、そう言っておられました。素敵ですね。素敵だと思います。

▪️本日は合宿の最終日でした。これは吹奏楽コンクールに出場するメンバーの練習風景です。合宿場所から少し離れたところにあるホールをお借りして練習をしました。監督やコーチ以外にも、3人の学外指導者の先生方にお越しいただき、最終の細かな調整が進められました。明日は、いよいよ関西吹奏楽コンクールです。
高齢者の交流

▪️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。地域連携型の教育プロジェクトである社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部)で、ずっとお世話になってきた雨森鼎さんと安孫邦夫さんとの呑み会でした。楽しい時間を過ごさせていただきました。じつは雨森さんと安孫子さんは、「地域エンパワねっと」を通して仲良しになられたんですよ。「エンパワねっと」の学生を指導していただく中で、知り合いになり、意気投合されたというわけです。お二人は、たびたび一緒に呑んでおられます。こういうのって、素敵だな〜と思います。今宵は、後期高齢者のお2人から、前期高齢者になったばかりの私をお誘いいただきました。ありがとうございました。これからは、高齢者同士の、特に男性の高齢者同士のこういう交流の機会を増やしていかねばならないと思っています。
