世界農業遺産の「琵琶湖システム」と「魚のゆりかご水田」
▪️滋賀県では、琵琶湖の湖岸に接する水田で、盛んに「魚のゆりかご水田」の取り組みが行われています。そのなかでも、特にこの動画の「須原せせらぎの郷」の取り組みがよく知られています。この「魚のゆりかご水田」は、国連の国連食糧農業機関(FAO)の「世界農業遺産」として認定された「琵琶湖システム」の中核にある取り組みです。正確には、「琵琶湖システム」は、「森・里・湖に育まれる、農業と漁業が織りなす琵琶湖システム」です。後半の「農業と漁業が織りなす」の方の中核に「魚のゆりかご水田」は位置付けられることになります。
▪️しかし同時に考えないといけないことがあります。前半の「森・里・湖に育まれる」の部分です。「魚のゆりかご水田」が可能になるのは、もちろん地元の農家をはじめとする関係者の皆さんの努力にあります。それはもちろんなんですが、そのような「魚のゆりかご水田」が可能になるのは、その背景にあるれ「森・里・湖」での様々な活動があるからなのです。「森・里・湖」で環境や生物多様性を守るために地道に活動されている方達の存在を忘れてはいけないと思っています。また、そのような方達の活動にもっと光が当たっていく必要があるとも思っています。産業としての林業、落葉紅葉樹の森林の保全、里山の保全、環境こだわり農業、ヨシ群落の保全、身近水路や小河川の保全…、全てが「琵琶湖システム」に包摂される取り組みなのです。これらの多種多様な人が関わる活動がつながりあって「琵琶湖システム」はできています。そのようなことは普段は意識しないのですが、少しお互いに意識し合うだけで、何か変化が起こるはずです。
安曇川河辺林内の竹林の整備

▪️今日は、特定非営利活動法人「コミュニティねっとわーく高島」さんが取り組まれている「安曇川の河辺林をみんなの森に」の活動の日でした。滋賀県の湖西地域を流れる安曇川沿いの、綾羽工業さんの敷地内にある河辺林を、市民の手で整備して素敵な森にしていこうという活動です。今は人の手が入らず、荒れ果ててしまい、鵜の巨大なコロニーになってしまっています。これをなんとかしようというわけです。
▪️広大な河辺林のうち、竹が枯れているエリアがあるのですが、まずその枯れた竹をノコギリで切り出して、森の中に入っていける通路を作っていくことになっています。切り出した竹は活用します。枝については切り取って、竹チップにします。そうやって人が手を加えながら、生き物の調査も進めていくようです。5年ほどの期間をかけて整備していく予定になっています。少しずつ、参加される皆さんの想いのこもった素敵な森に変わっていくことを楽しみにしています。
▪️こちらの河辺林には車で行くのですが、秋の行楽シーズンということもあり、渋滞に巻き込まれてしまいました。ということで遅刻してしまいました。また、午後から家族が車を使うということもあり、作業は1時間ほどしかできませんでした。残念。良い汗をかかせていただきましたが、最後まで頑張ったみなさんにちょっと申し訳ない気持ちです。電車と徒歩だと1時半ほどで行けるので、これからは車はやめるかもしれません。最寄の駅は湖西線の新旭駅です。新旭駅から綾羽工業さんまでは2kmほどです。天候が良ければ気持ちよく歩けそうです。
 ▪️ところで綾羽という名前を聞いて、滋賀県民でなくても、高校野球を愛しておられる方であれば、今年の夏の高校野球に出場した綾羽高校を思い出すでしょう。その綾羽高校を設立したのが綾羽工業さんです。綾羽工業さんは繊維会社なので、高度経済成長期の頃は、九州等から集団就職でたくさんの女工さんたちがやってきて、この工場で働いておられました。そして、働きながら勉強して高卒の資格を得たわけです。写真は元々は分校だった建物なのだそうです。今は使用されていません。このようなことを綾羽工業さんの敷地内を歩きながら、社員さんからいろいろ説明していただきました。今はどのような繊維製品を製造されているのですかとお尋ねしたところ、タイヤを強くする繊維であるとか、それから鉄道の枕木も製造されているとのこと。びっくりしていると、「ぜひ、ホームページをご覧ください」ということで、確認しました。合成木材エースウッドスリーパー(AWS)というようです。ガラス繊維強化硬質発砲ウレタンを主原料とする新素材なんだそうです。
▪️ところで綾羽という名前を聞いて、滋賀県民でなくても、高校野球を愛しておられる方であれば、今年の夏の高校野球に出場した綾羽高校を思い出すでしょう。その綾羽高校を設立したのが綾羽工業さんです。綾羽工業さんは繊維会社なので、高度経済成長期の頃は、九州等から集団就職でたくさんの女工さんたちがやってきて、この工場で働いておられました。そして、働きながら勉強して高卒の資格を得たわけです。写真は元々は分校だった建物なのだそうです。今は使用されていません。このようなことを綾羽工業さんの敷地内を歩きながら、社員さんからいろいろ説明していただきました。今はどのような繊維製品を製造されているのですかとお尋ねしたところ、タイヤを強くする繊維であるとか、それから鉄道の枕木も製造されているとのこと。びっくりしていると、「ぜひ、ホームページをご覧ください」ということで、確認しました。合成木材エースウッドスリーパー(AWS)というようです。ガラス繊維強化硬質発砲ウレタンを主原料とする新素材なんだそうです。
公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」
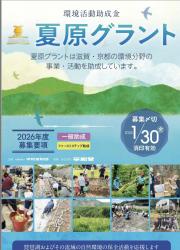 ▪️公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」。2026年度の応募受付期間は、2025年12月1日(月)から2026年1月30日(金)までです。郵送のみの受付、当日消印有効です。「夏原グラント」では、地域で頑張って取り組まれているたくさんの環境活動団体を応援してきました。助成金は、団体の皆さんが使いやすい仕組みになっています。ぜひ、会場での説明会・相談会、オンラインでの相談会に気軽にご参加いただければと思います。選考委員長からのお願いです。詳しくは、こちらをご覧ください。
▪️公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」。2026年度の応募受付期間は、2025年12月1日(月)から2026年1月30日(金)までです。郵送のみの受付、当日消印有効です。「夏原グラント」では、地域で頑張って取り組まれているたくさんの環境活動団体を応援してきました。助成金は、団体の皆さんが使いやすい仕組みになっています。ぜひ、会場での説明会・相談会、オンラインでの相談会に気軽にご参加いただければと思います。選考委員長からのお願いです。詳しくは、こちらをご覧ください。
▪️この「夏原グラント」には、2014年から選考委員に就任しました。選考委員長であった仁連孝昭先生がご退任になられたことから、役不足ですが、今年の4月から選考委員長に就任いたしました。10年以上この「夏原グラント」の選考委員を務めさせていただき、いろいろ思うことがあります。助成をさせていただく団体間に、協働や連帯の契機が生まれてきてほしいなあということです。今年の夏に、夏原グラントでは市民環境講座を開催しました。選考委員から毎年2人の委員が講師となって講座を受け持つことになっています。今年は、私の番でした。講演のタイトルは「助成団体間の連帯を深めていくために」にさせていただきました。「夏原グラント」自体も、次のステップに進み、発展していってほしいという思いがあるのです。
「地方創生のファクターX寛容と幸福の地方論」
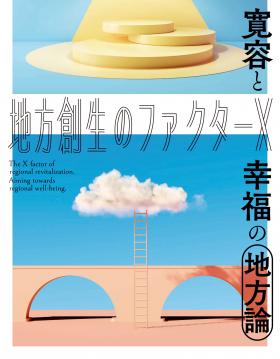 ▪️朝日新聞の「連載 8がけ社会」の記事に関する情報が、朝、メールで届きました。さっそく拝見すると、「「仕事がないから故郷に戻らない」は本当か 全国調査で見えた答え」という興味深い報告書のことがニュースになっていました。「LIFULL HOME’S 総研」による「地方創生のファクターX 寛容と幸福の地方論」という報告書をもとにした記事でした。大学に行き、授業のあと、大学の図書館にある朝日新聞のデータベースで記事の全体を読んでみました。
▪️朝日新聞の「連載 8がけ社会」の記事に関する情報が、朝、メールで届きました。さっそく拝見すると、「「仕事がないから故郷に戻らない」は本当か 全国調査で見えた答え」という興味深い報告書のことがニュースになっていました。「LIFULL HOME’S 総研」による「地方創生のファクターX 寛容と幸福の地方論」という報告書をもとにした記事でした。大学に行き、授業のあと、大学の図書館にある朝日新聞のデータベースで記事の全体を読んでみました。
▪️地方からの若者転出に関して、地方には仕事がないからということが理由にあげられますが、「LIFULL HOME’S 総研」の島原万丈さんたちは、県民所得も低いなど経済関連の指標はいずれも高くなくても、Uターンする割合が高いのは、なぜなのかを探っておられます。経済指標だけでは説明できない状況を、さまざまなデータを分析することで、Uターン意向を左右する要因を探られました。その結果、浮かび上がってきたのが「寛容」です。
▪️「寛容」とはなにか。島原さんは、次のように説明されています。
言い換えれば他の可能性を認めるということ。「こうでなければいけない」と決めつけない。物事の解釈に幅を持ち、そうじゃない可能性を考える。その「余白」が大事なんです。
例えば、女性はこうじゃなきゃいけないとか、若者はこうなんだって決めるから社会が不寛容になってくる。そういうことが嫌で故郷に戻らない人は多かった。今だって地方で自分たちのライフスタイルにモヤモヤしている人たちはいる。だから報告書を出したとき、「寛容性」という言葉にしたことで納得する人がたくさんいました。
▪️この「寛容性」に関わる話ですが、「東北地方の若い女性が東京に転出するのは、女性たちが生まれ育ってきた地域が、個々人の生き方に関して上の世代の価値観を押し付けてくるから」ということをXで読んだことがあります。そのことと、島原さんたちが指摘する「寛容性」の問題は重なっていると思います。「地方創生のファクターX 寛容と幸福の地方論」の概要ですが、以下の通りです。
地方創生をテーマにした今回の調査研究では、47都道府県の在住者へのアンケート調査を実施し、各都道府県の「寛容性」の気風を測定しました。同時に東京圏に住む各道府県出身の若者の意識調査も実施し、分析の結果、各地域の「寛容性」と地域からの人口流出意向・東京圏からのUターン意向の間に密接な関係があることが分かり、地域の「寛容性」がこれまでの地方創生政策が見落としていたファクターXであるという結論に至りました。地方創生の重要な指標として「寛容性」に注目することを提案します。
また、近年さまざまなシーンで注目度が高く、今後の地方創生議論の中でも不可欠になると思われる「幸福度(Wellbeing)」の実態についても都道府県別に把握し、今後の議論の材料として発表いたします。 2021.09.15
▪️報告書のなかでは、「問題は若者の転出が多いことではなく、外の世界で新しい技術や知識を学んだ優秀な若者が戻って来ないことにある。あるいは、生まれ故郷にこだわらず自分の能力を発揮する場所を探している若者が、その地域を選んでくれないということにある」という指摘がなされていました。大切なご指摘かと思います。この報告書のテーマともかかわることで、卒業論文を執筆しようと考えている学生さん2人に、さっそくこの新聞記事と報告書のことをメールでお知らせしました。
小さな自然再生 ビワマス魚道を設置して地域を盛り上げよう!!
▪️滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんによるFacebookへの投稿です。本当に残念、この事業が開催されるのは木曜日なんですね。土日でないと参加できません。定年退職したら、こういう活動にも参加できるのかなと思います。どんな感じになるのでしょうね。楽しみです。ただし、75歳になったら運転免許を返納する予定なので、時間は限られています。しかも、健康に生きていることを前提にしています。
▪️こういった様々な環境に関わる市民活動で、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が発行するデジタルポイント、「びわぽいんと」が、いつか使われるようになって欲しいと思っています。ポイントの「贈与」を通じて、活動間のつながりや連帯がネットワーク化していくことを夢見ています。
安曇川河辺林で竹林整備




▪️昨日は、朝から車で高島市の新旭町にある綾羽工業株式会社に向かいました。綾羽さんが所有されている安曇川の河辺林の中にある竹林を、市民の手で整備していく活動に参加するためです。高島市の竹林ですが、長浜、米原、東近江からも参加されてました。主催は、「たかしま市民協働交流センター」です。この交流センターの職員である坂下靖子さんには、これまでも龍谷大学の学生さんたちの指導で大変お世話になってきました。そのようなつながりの中で、「この竹林整備の活動に参加しませんか」とお誘いいただいたのです。今回で2回目の参加になります。前回は、関心のありそうな人に呼びかけて、集まった方達で、こんな竹林にしたいね、こんなことしたいねと、ワークショップを行いました。
▪️昨日は、あいにくの雨でした。整備作業はできませんでしたが、室内で講師の方から「竹林整備時における安全について」と「竹の種類とその特性」について学びました。すごく情報量の多い濃い講義でした。講師は「里山実験室HareMori」を主催されている山本綾美さんです。講義の冒頭、山本さんは、このような話をされました。竹に関して最近は「竹害」がよく話題になります。でも、竹はかつて重要な資源でした。筍を味わうこともそうですが、重要な建築資材でしたし、身の回りの籠などの道具を作る際にも大切な材料になりました。以前は、竹林に「出口」(様々な竹の利用)があったのですが、今はそれが無くなってしまった結果、竹林には手が入らず、迷惑な植物になってしまったわけです。竹そのものが迷惑な存在なのではなく、人間の社会のあり方が変化してしまったことの結果、「有用」な植物から「迷惑」な植物になってしまったわけです。
▪️3段目の写真・左ですが、黄色いのは、ポイズンリムーバーです。竹林整備の際に、蜂に刺されたりした際の応急処置に使います。これで毒を吸い出すのです。黄緑のものは、ダニに食いつかれた際に使用するダニトリスティックです。両方とも使わないことが一番望ましいわけですが、今回の竹林作業には用意しておいた方が良いかと思いました。オオスズメバチは、土の中に巣をつくります。気をつけないといけまん。ダニも怖いですね。ダニが服と身体の隙間に入ってきても何も感じないのだそうです。で、ふと気がつくと柔らかい皮膚のところに変なイボのようなものができているなと思ってよく見ると、それがダニだったということがあるのだそうです。マムシもいますしね。講義の最初から、ちょっとビビってくる内容でした。私はよく蚊に刺される体質なのですが、これも気をつけなくてはいけません。「太巻き」の蚊取り線香で対応します。11月に入ると蚊もいなくなるらしいですが…。
▪️3段目の写真・右。竹の皮です。プラスチックが出てくる前までは、肉屋さんで肉を買うと竹の皮に包んでくれました。今は、竹の皮風のプラスチック製の皮に包んでくれるだけですけど、昔は本物の竹の川でした。昔は、竹林をお持ちのお宅ではねこの竹の皮も黴ないようにきれいに保存しておかれたようです。業者さんが買い付けに来られていたという話も、昨日、お聞きしました。竹林が整備されたら、この竹の皮も有効利用できたらいいなと思います。



▪️講義の後は、雨の中、綾羽工業の敷地にある竹林の状況を見学して、現地でも山本さんからご指導いただきました。竹林整備にあたって、知っておかなくてはいけないことが山ほどありました。昨日の講義だけでは、老人の頭の中にはきちんと整理されて入ってきません。これから、少しずつ勉強していきます。これからの竹林整備、まずは枯れた竹林の整備から始めることになっています。花が咲いて枯れた竹林です。どのような竹林にしていくのかで、整備のやり方は違ってくるとのことです。もし、竹林を残していくのであれば、4段目右の写真で、講師の山本さんが説明されているササのような葉を残さなくてはいけません。このササのような葉は、根から伸びてきているものです。これを刈ってしまうと、竹林は再生しません。竹に関する知識を一通り身につけられたら、いいなと思っています。それから、整備が順調に進捗したら、竹林の「出口」(活用法)をたくさん見つけられたらいいなと思っています。
▪️昨日は雨が降っているせいもありますが、とても肌寒い日でした。帰宅時の車では、ヒーターをつけました。これから秋が深まっていくのでしょうね。
最近の「仰木地域共生協議会」のこと
理事長をつとめる特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、現在、1000年の歴史をもつ農村・仰木の皆様や、その仰木に隣接する新興住宅地・仰木の里の関係者の皆様と共に、農水省の補助金(農村RMO)をいただきながら「仰木地域共生協議会」を立ち上げました。生産者(農家)と消費者(住宅地住民)が連携・協力しながら、仰木の農業を持続可能にし、耕作放棄地を有機農業を行う農地に再生していくことを目指します。この協議会の運営につきましては、NTT西日本滋賀支店からもご協力とご支援をいただいています。
先日のことになりますが、9月21日~23日、仰木の棚田で生産された新米が、仰木の里の皆様に販売されました。その時のことが、「仰木地域共生協議会」のブログで報告されています。米価の高騰のなか、農家の側も消費者の側も満足できる金額で予約販売されました。確保した1.5トンの枠を超える事前申し込みがあったので、抽選のうえで300名ほどの方にお届けすることができました。現在、協議会では将来ビジョンを作成中ですが、今後、さらに様々な取り組みを開始して、両地域の皆さんの交流が深まっていくことを期待しています。
中学校の「部活動の地域移行」
▪️大学吹奏楽部の部長をしていましたし、今は近江八幡市教育委員会の点検・評価委員を務めていることもあり、中学校の部活動、特に吹奏楽部の「地域移行」のことが気になっています。いろいろ調べていたからでしょう、Googleが「地域移行」に関連する記事を探してきて見せてくれるようになっています。
▪️「部活動の地域移行」とは、「学校の部活動を地域が主体となって運営するクラブ活動に移行する取り組み」のことです。文科省の方針です。部活動の顧問されている先生たちの激務、大変ですよね。教員も、ワークライフバランスをきちんと考えていく時代になっています。ということでの、文科省の方針です。ただ、それぞれの地域には地域固有の事情や条件があり、全国一律にというわけにはなかなかいかないのかなと思います。「地域移行」するにしても、それぞれの自治体で工夫を重ねて、段階を踏まえないとうまく行きません。でも、地域移行できずに、廃部になっていく吹奏楽部もたくさんあるでしょうね。吹奏楽部の活動を
維持するためには、指導者の問題に加えて、経済的な問題も非常に重いのです。
▪️地域に移行すると、学校や教育委員会ではなく、基本、保護者が経済的な負担をしなくてはいけません。楽器の購入、メンテナンス、コンクールへの参加に伴う輸送代、バスの借り上げ…。もちろん、自治体からの補助金もあるとは思いますが、経済的な負担の多くは保護者になります。そうすると、負担できる保護者と、それは絶対に無理という保護者がおられるのではないか思います。子ども:「吹奏楽部に入りたいのだけど、これだけの年間の負担がいるんだって」、保護者:「そうなんか、ごめんね。我が家ではとても無理やわ」。そういう家庭もきっと出てくると思います。そうなると、中学校の部活動においても「体験格差」が生じることになるのではないかと思います。
▪️とはいえ、記事の最後の部分、大切かなと思います。
「これまでは、学校が部活をやってくれて当たり前だったし、そこに先生に払う講師料などがあったわけでもなく、ある程度専門的なことも教えてもらえて“当然”みたいな感じでいた」
「むしろ今後は、私たち地域側が意識を変えて『協力していく』という体制を作らないといけない…」地域それぞれにの課題から、部活動の『地域展開』がスムーズに行かないケースもありそうですが、学校や保護者だけではなく『地域の子どもたちは地域で育てる』という意識の広がりこそが、子どもの活動場所を狭めないための第一歩となりそうです。
▪️「地域の子どもたちは地域で育てる」というのは、「自治の精神」を涵養していくということなのでしょう。自治って、まちづくりと言い換えてもいいかもしれません。「まちづくりは人づくり」とも言いますからね。こうやって、地域の大人に指導をしてもらいながら、また応援してもらいながら、部活動に取り組んだ経験が、子どもたちにとって意味のある経験になってほしいと思います。そして、将来、こういう「地域移行」による「アウトカム」が地域にとってもプラスになってほしいと思います。
▪️付け加えることになりますが、こういう記事もありました。
カンテレNEWSで報道された「革靴をはいた猫」
▪️「革靴を履いた猫」を経営している魚見航大さんから、この動画のことを教えていただきました。ありがとうございました。魚見さんは、この会社を学生の時に起業されました。ちなみに、龍谷大学の政策学部を卒業されています。こちらの会社では、様々な困難を抱えた方達を社員に迎えておられます。そして、それぞれの社員の方達が成長というのかな、元気になっていかれているんですよね。とっても素敵なことだなと思います。以下は、この動画の概要です。
京都市中京区にあるちょっと変わった「靴磨き」店。
その名も「革靴をはいた猫」 通称“革猫”。【革靴をはいた猫・代表】「障害のある方だとか、引きこもりの経験がある方がお客様の目の前で靴を磨いたり、修理したりしてお客様に喜んでもらいながら職人自身も成長していくというコンセプトで会社を立ち上げました」
誰もがチャレンジできる優しい店を目指しています。
そんな”革猫”の新メンバー・木村昇平さん(37)は元警察官。
働き盛りのときに発達障害が発覚し休職。どうやって生きていこうか、悩んだときに出会ったのが「靴磨き」でした。
▪️昨日のことになりますが、魚見さんと少しだけネット上でやり取りしました。魚見さんは、「皆さんに伝わる形で発信できる機会をいただけてよかったです!」と感じておられるようです。大学の後期のことになりますが、魚見さんの「革靴を履いた猫」を、1回生の「基礎ゼミナールB」の学生の皆さんと一緒に訪問する予定になっています。ちなみに、魚見さんとは飲み友達でもあります!!
