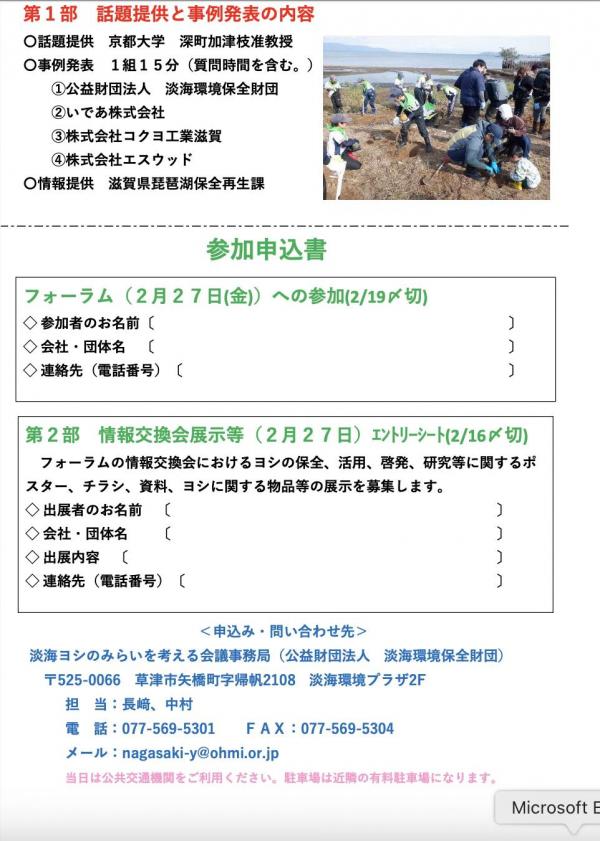世界農業遺産の「琵琶湖システム」と「魚のゆりかご水田」
▪️滋賀県では、琵琶湖の湖岸に接する水田で、盛んに「魚のゆりかご水田」の取り組みが行われています。そのなかでも、特にこの動画の「須原せせらぎの郷」の取り組みがよく知られています。この「魚のゆりかご水田」は、国連の国連食糧農業機関(FAO)の「世界農業遺産」として認定された「琵琶湖システム」の中核にある取り組みです。正確には、「琵琶湖システム」は、「森・里・湖に育まれる、農業と漁業が織りなす琵琶湖システム」です。後半の「農業と漁業が織りなす」の方の中核に「魚のゆりかご水田」は位置付けられることになります。
▪️しかし同時に考えないといけないことがあります。前半の「森・里・湖に育まれる」の部分です。「魚のゆりかご水田」が可能になるのは、もちろん地元の農家をはじめとする関係者の皆さんの努力にあります。それはもちろんなんですが、そのような「魚のゆりかご水田」が可能になるのは、その背景にあるれ「森・里・湖」での様々な活動があるからなのです。「森・里・湖」で環境や生物多様性を守るために地道に活動されている方達の存在を忘れてはいけないと思っています。また、そのような方達の活動にもっと光が当たっていく必要があるとも思っています。産業としての林業、落葉紅葉樹の森林の保全、里山の保全、環境こだわり農業、ヨシ群落の保全、身近水路や小河川の保全…、全てが「琵琶湖システム」に包摂される取り組みなのです。これらの多種多様な人が関わる活動がつながりあって「琵琶湖システム」はできています。そのようなことは普段は意識しないのですが、少しお互いに意識し合うだけで、何か変化が起こるはずです。
「淡海ヨシみらいフォーラム ~ヨシ群落の保全とネイチャーポジティブ~」
ウエルダイング
▪️小学校のときのクラスメイトと、昨年の正月にメールでやりとりをしたあと、連絡がありませんでした。今日、年賀状をいただいてわかったのですが、脳出血で倒れて半年間入院をされていたことを知りました。驚きました。どうりで連絡が取れないわけです。今はリハビリの結果、身の回りのことは自分でできるようになられたようです。頑張ってリハビリに励まれています。昨年末は、高校のときの同級生が亡くなりました。いろいろ同級生のことが続くと、いつ自分もそうなるのかなと考えることになります。
▪️今日は、同僚とひさしぶりに立ち話をすることができました。私からは、昨日投稿した杉岡孝紀先生の「他者の他者性」についてお話しをしたら、同僚からはウェルダイング(死への旅路)ということを教えていただきました。ウェルビーイングはよく聞きますが、ウェルダイングです。書籍も出版されているようです。『ウェルダイング(死への旅路)の臨床社会学 生老病死と宗教』(櫻井 義秀/横山 聖美 編, 法藏館)です。以下のような内容です。
人生の終わりを、どう迎えるのか?高齢多死社会を迎えた日本において、「よく生き、よく死ぬ」ことを支えるケアの実践と宗教の役割を、看護学、宗教学、社会学、社会福祉学の専門家が臨床社会学の視点から描き出す。
▪️私個人としては、このウェルダイングを可能にする社会的な仕組みが必要だと思っています。肉体の苦しみを緩和する医療や看護、生活の質、QOLを支える福祉、そしてスピリチュアルを支える広い意味での宗教、これら3つがうまくつながったセーフティーネットが必要だと思っています。できれば、それぞれの方達が生きている地域社会に、です。こういった臨床社会学的研究が当事者研究であってもほしいわけです。ただ、どうすればよいのでしょうね。人間は、生まれたときからすでに死への旅路は始まっているわけです。しかし、そのことを深く体験できるときには、言い換えればこれから死んでいくのだなとの深い自覚が生まれたときには、すでに自分では動けないわけですから、ケアの仕組みを共助のなかで作っていくことはできません。
▪️昨日投稿では、龍谷大学の行動原理である「自省利他」についてふれました。前半の「自省」のなかで重要な位置を占めるのが「他者の他者性」なのではないか思いました。その「他者の他者性」の自覚なくしては、「利他」は暴力的なものになってしまいますから。そして今日は「ウェルダイング」についても教えてもらいました。「他者の他者性」を自覚したとき「ウェルタイング」を支えるケアとはどのようなものになるのだろう。よかれと思って実践したケアが、死への旅路にある人を苦しませてしまうことはないのか。気になります。「他者の他者性」にしろ、この「ウェルダイング」にしろ、いろんな専門分野の研究者が議論できるテーマだと思います。また、龍谷大学のような仏教系の大学ならではのテーマなんじゃないのかなとも思っています。
ヨシ群落保全審議会のこと

▪️12月22日(月)、滋賀県庁で「第41回滋賀県ヨシ群落保全審議会」が開催されました。手元の記録では、2015年9月からこの審議会の会長を務めているようです。規定では、1期3年で3期までということになっているようなのですが、3期を越えて4期会長職を務めることになりました。任期は来年の初め頃までのようですが、実質、昨日が私にとって最後の審議会になりました。委員の皆さんの意見やアイデアが活かされていくような審議ができて本当によかったと思っています。審議会以外にも、ワークショップを委員の皆さんと一緒に開催したり、委員と委員をつないで、新しい事業を生み出すこともできました。まだまだヨシ群落の保全については、やらないといけないことが山積みなのですが、少し新しい時代にふさわしい取り組みにむけて前進できたことで、満足しています。
▪️写真は、近所の公園から見た伊吹山、沖島、琵琶湖大橋です。少し暗くなりすぎていますが、もう少し明るい時間帯だと、伊吹山もよくみえました。写真には写っていませんが、湖東のさらに東側には鈴鹿山脈もよくみえました。琵琶湖の水位、心配ですね。
琵琶湖の水位
▪️このブログのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」です。このタイトルとは関係ない、大学スポーツの投稿ばかいりが続きました。なんですが、これは琵琶湖に関するものです。琵琶湖の水位についての報道です。
「愛土農園」で農作業



 ▪️今日は、朝10時から暮らしている新興住宅地に隣接する農村、仰木に出かけました。国の「農村型地域運営組織(農村RMO:Region Management Organization)」に採択された「仰木地域共生協議会」の活動の一環で農作業に取り組みました。あいにく、今日の参加者は少なく2人だけでした。私と同じく新興住宅地にお住まいのSさんです。
▪️今日は、朝10時から暮らしている新興住宅地に隣接する農村、仰木に出かけました。国の「農村型地域運営組織(農村RMO:Region Management Organization)」に採択された「仰木地域共生協議会」の活動の一環で農作業に取り組みました。あいにく、今日の参加者は少なく2人だけでした。私と同じく新興住宅地にお住まいのSさんです。
▪️今日の農作業は、タマネギの苗を植えることでした。協議会の会長さんからご指導をいただき、頑張って大量の苗を植えていきました。針金を縛るシノという道具がありますが、あのシノをマルチシートに空いている穴に突き刺して、少し穴を開けてそこに苗を植えていきます。簡単なことなんですが、なかなかコツをつかめませんでした。苗を3/2ほど植えた頃にやっと早く植えることができるようになりました。残りは別の仲間が明日植えてくださることになっています。タマネギの苗って、なんだか頼りない感じなんですが、これがだんだんしっかりしてきて、来春には美味しい玉ねぎが土の中にできる予定です。苗を植えた後は、ひとつひとつの苗にジョウロで水を与えました。頑張って美味しいタマネギになってねと願いを込めて水をやりました。
▪️この畑には名前がついています。「愛土農園」(あいどのうえん)といいます。このあたりの字名が「合土(あいど)」だったので、合を愛にかえて名称にしたというご説明を受けました。「集えるみんなが同じ土に触れ、種や名前を植え付け、収穫を心待ちする”交流農園”」なんです。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も「仰木地域共生協議会」に参加していますが、こういった農作業に取り組む方達の交流が促進していくように、スマートフォンのアプリを開発して提供していくことになっています。今日は、しゃがんでタマネギの苗を植えていたものですから、少し腰を痛めてしまいました。
『家で幸せに看取られるための55のヒント』
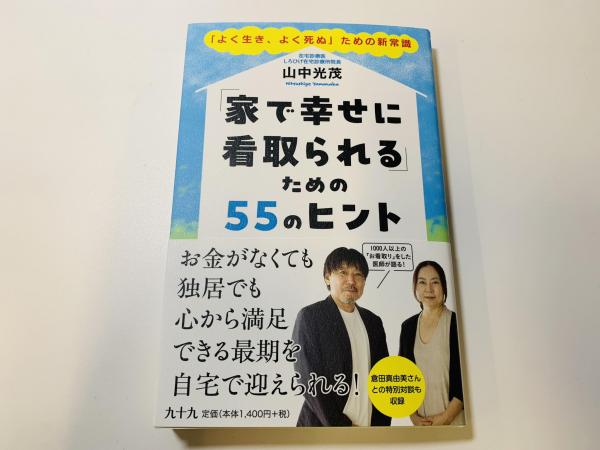
▪️定年退職1年前には研究室の断捨離。定年退職後は自宅の断捨離に励まねばなりません。できるだけ身軽になって、終活に励みたいと思います。そして、この本のタイトル通りになりたいと思います。ということで、まずは勉強させてもらいます。ただ、残念ながら、スピリチュアルな側面については、この本では触れていませんね。私は、スピリチュアルも大切だと思っているのです。浄土真宗では「後生の一大事」というそうですが、「死後の自分はどこに行くのか」という問題のことです。「死んだらそれまでなんだから、関係ないよ」と思われるかもしれませんね。私は、そう思いませんが。
▪️有名な精神科医の中井久夫さん、そして評論家の加藤周一さんは、人生の最期でカトリックの洗礼を受けられました。また、社会学者の吉田民人さんも仏教に相当傾倒されました。そういえば、学部生の時に農村社会学の講義をしてくださった余田博通先生も、病床でだったと思いますが、プロテスタントの洗礼を受けられたのではなかったかな。中井久夫さんは、洗礼を受けられた理由を尋ねられた時「べんりでしょ」とお答えになったとか。「死後の自分はどこに行くのか」という問題にイメージを与えてくれるという意味で便利なのでしょうか。私には詳しいことはわかりません。ただ、みなさん、自分の最期には、スピリチュアルな支えが必要だと判断されたのではないかと思います。想像ですけど。
▪️以前、在宅診療医の方とお話ししたことがあります。その時に、「お迎え」現象の話が出ました。亡くなる直前になると、すでに亡くなっている人があの世から迎えに来てくれるかのように感知する現象を、「お迎え」というようです。その医師のお話しでは、「お迎え」があった方達は、苦しまずに安らかに亡くなっていったと言っておられました。そして、それは何故なんだろうと私にも聞かれたのです。その時は、龍谷大学に勤務していたかもしれないけれど、まだ仏教のことをあまり勉強していませんでした。今だと、近代主義的・合理主義的な人でも、最期の最期は、自分が消えていくことに強い不安を覚えるのではと考えています。人間は弱い存在です。それが、「後生の一大事」なのかな。スピリチュアル的な面で明確なイメージをもつことは、「後生の一大事」を通過していくことを容易にするのではないのか、そのように思うのです。中井さんが「べんりでしょ」と言ったのは、そういうことなんじゃないのかな。どうやろ。
『斜め論』
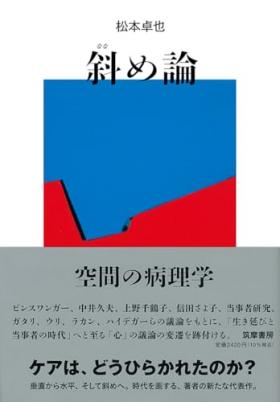 ▪️『斜め論 空間の病理学』の書評。何か困り事を抱えた人びと(他者)に、自分の側から関わっていく(他者へのケア)ときの姿勢。中井久夫さんのいう「ちょっとした垂直性」が気になりました。以前、環境社会学会の編集委員長をしているときに、学会誌『環境社会学研究』で「市民調査」という特集を組みました。その特集の中の蔵治光一郎さんの論文で、一般の市民による「市民活動」(環境調査)を、専門性からズレていて質問されてもちょっと自信がないぐらいの人が手伝うとうまくいって(市民は楽しみを優先している)、バッチリ専門性のある人が手伝うとうまくいかない(科学的な精度を求める)…随分前のことなので記憶が曖昧ですが、そのような話が論文の中に出てきました。きちんと確認していないんですけど。この「斜め論」、「ちょっとした垂直性」というのは、私の研究や実践の文脈では、そういうふうなことに重ね合わせて理解することになります。筆者には「違うよ」って言われるかもしれないな…。もっとも、この本の中に出てくる信田さよ子さんのお話のような迫力は、自分には全くありません。以下は、書評の中の一部。
▪️『斜め論 空間の病理学』の書評。何か困り事を抱えた人びと(他者)に、自分の側から関わっていく(他者へのケア)ときの姿勢。中井久夫さんのいう「ちょっとした垂直性」が気になりました。以前、環境社会学会の編集委員長をしているときに、学会誌『環境社会学研究』で「市民調査」という特集を組みました。その特集の中の蔵治光一郎さんの論文で、一般の市民による「市民活動」(環境調査)を、専門性からズレていて質問されてもちょっと自信がないぐらいの人が手伝うとうまくいって(市民は楽しみを優先している)、バッチリ専門性のある人が手伝うとうまくいかない(科学的な精度を求める)…随分前のことなので記憶が曖昧ですが、そのような話が論文の中に出てきました。きちんと確認していないんですけど。この「斜め論」、「ちょっとした垂直性」というのは、私の研究や実践の文脈では、そういうふうなことに重ね合わせて理解することになります。筆者には「違うよ」って言われるかもしれないな…。もっとも、この本の中に出てくる信田さよ子さんのお話のような迫力は、自分には全くありません。以下は、書評の中の一部。
しかし、臨床的な意味での治癒は、むしろ水平方向において、つまり他者との横のつながりの回復などによって起こるのではないか。このことは、中井久夫が統合失調症患者がその急性期から「共人間的世界(身近な他者との関係)」の再構築において回復に向かうとしたことにも通ずる。ただし中井は、治療者が権威的ではないやり方で患者を導くこと、つまり「ちょっとした垂直性」の必要性に触れていた、と著者は指摘する。
そう、水平方向はケアにおいて重要な意味を持つが、そこには平準化(横並びに埋没させること)に陥る危険も潜んでいる。垂直方向の批判から水平方向の全面賛美に向かうのではなく、「斜め」を目指すこと。ここに、ラ・ボルド病院の実践において垂直と水平の次元を乗り越えようとしたガタリの「斜め横断性」の概念が重ねられる。
安曇川河辺林内の竹林の整備

▪️今日は、特定非営利活動法人「コミュニティねっとわーく高島」さんが取り組まれている「安曇川の河辺林をみんなの森に」の活動の日でした。滋賀県の湖西地域を流れる安曇川沿いの、綾羽工業さんの敷地内にある河辺林を、市民の手で整備して素敵な森にしていこうという活動です。今は人の手が入らず、荒れ果ててしまい、鵜の巨大なコロニーになってしまっています。これをなんとかしようというわけです。
▪️広大な河辺林のうち、竹が枯れているエリアがあるのですが、まずその枯れた竹をノコギリで切り出して、森の中に入っていける通路を作っていくことになっています。切り出した竹は活用します。枝については切り取って、竹チップにします。そうやって人が手を加えながら、生き物の調査も進めていくようです。5年ほどの期間をかけて整備していく予定になっています。少しずつ、参加される皆さんの想いのこもった素敵な森に変わっていくことを楽しみにしています。
▪️こちらの河辺林には車で行くのですが、秋の行楽シーズンということもあり、渋滞に巻き込まれてしまいました。ということで遅刻してしまいました。また、午後から家族が車を使うということもあり、作業は1時間ほどしかできませんでした。残念。良い汗をかかせていただきましたが、最後まで頑張ったみなさんにちょっと申し訳ない気持ちです。電車と徒歩だと1時半ほどで行けるので、これからは車はやめるかもしれません。最寄の駅は湖西線の新旭駅です。新旭駅から綾羽工業さんまでは2kmほどです。天候が良ければ気持ちよく歩けそうです。
 ▪️ところで綾羽という名前を聞いて、滋賀県民でなくても、高校野球を愛しておられる方であれば、今年の夏の高校野球に出場した綾羽高校を思い出すでしょう。その綾羽高校を設立したのが綾羽工業さんです。綾羽工業さんは繊維会社なので、高度経済成長期の頃は、九州等から集団就職でたくさんの女工さんたちがやってきて、この工場で働いておられました。そして、働きながら勉強して高卒の資格を得たわけです。写真は元々は分校だった建物なのだそうです。今は使用されていません。このようなことを綾羽工業さんの敷地内を歩きながら、社員さんからいろいろ説明していただきました。今はどのような繊維製品を製造されているのですかとお尋ねしたところ、タイヤを強くする繊維であるとか、それから鉄道の枕木も製造されているとのこと。びっくりしていると、「ぜひ、ホームページをご覧ください」ということで、確認しました。合成木材エースウッドスリーパー(AWS)というようです。ガラス繊維強化硬質発砲ウレタンを主原料とする新素材なんだそうです。
▪️ところで綾羽という名前を聞いて、滋賀県民でなくても、高校野球を愛しておられる方であれば、今年の夏の高校野球に出場した綾羽高校を思い出すでしょう。その綾羽高校を設立したのが綾羽工業さんです。綾羽工業さんは繊維会社なので、高度経済成長期の頃は、九州等から集団就職でたくさんの女工さんたちがやってきて、この工場で働いておられました。そして、働きながら勉強して高卒の資格を得たわけです。写真は元々は分校だった建物なのだそうです。今は使用されていません。このようなことを綾羽工業さんの敷地内を歩きながら、社員さんからいろいろ説明していただきました。今はどのような繊維製品を製造されているのですかとお尋ねしたところ、タイヤを強くする繊維であるとか、それから鉄道の枕木も製造されているとのこと。びっくりしていると、「ぜひ、ホームページをご覧ください」ということで、確認しました。合成木材エースウッドスリーパー(AWS)というようです。ガラス繊維強化硬質発砲ウレタンを主原料とする新素材なんだそうです。