真の方法は、探究されるべき物事の性質に従う。(折々のことば)
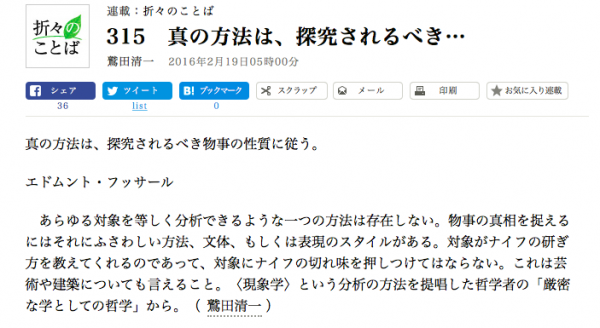
■朝日新聞の1面に掲載されている哲学者・鷲田清一さんの「折々のことば」、楽しみにしています。私の場合は、ネットで拝見することの方が多いと思います。ネットでは、過去のものも拝見することができるからです。新聞で読むことができなかった(忘れていた)ものも、読むことができます。昨日の「折々のことば」は、「細く 長く 曲がることなく いつも くすくす くすぶって あまねく 広く 世の中へ 松栄堂」でした。これは、京都のお香の老舗、その創業家に伝わる家訓です。こんな時代だからこそ…、この家訓は心に染み入ります。この「折々のことば」、新聞でも読みましたが、ネットでもじっくり味わいました。その時、ふと過去のものも目に入りました。哲学者フッサールの「ことば」でした。
■「真の方法は、探究されるべき物事の性質に従う」。鷲田先生は、次のように解説されています。
あらゆる対象を等しく分析できるような一つの方法は存在しない。物事の真相を捉えるにはそれにふさわしい方法、文体、もしくは表現のスタイルがある。対象がナイフの研ぎ方を教えてくれるのであって、対象にナイフの切れ味を押しつけてはならない。これは芸術や建築についても言えること。〈現象学〉という分析の方法を提唱した哲学者の「厳密な学としての哲学」から。(鷲田清一)
■「対象がナイフの研ぎ方を教えてくれるのであって、対象にナイフの切れ味を押しつけてはならない」という鷲田先生のわかりやすい比喩的な説明にグッときました。私は、流域の環境問題について、他の分野の研究者と一緒にプロジェクト研究を進めています。流域に限りませんが、環境問題は非常にたくさんの要因が、相互に連関を持ちながら構造化されていくことによって発生します。流域の環境問題を考える場合も、調査や研究を通して知ろうとする「対象」は専門分野によって異なります。私が参加している研究プロジェクトでは、多く分野の研究者がメンバーとなっていますが、それぞれのメンバーは、自分の専門分野という枠組みを通して流域のある一部分を「対象」にしているにしか過ぎません。その「対象」に応じて方法を選択しなければなりません。自分の方法や考え方が他の「対象」についても有効かといえば、そうではありません。自分の専門分野から一刀両断的に全体像を把握できた「つもり」になることはできても、それは自己満足でしかありません。それぞれの専門分野のコミュニティ内部では通用しても、そのコミュニティの外に出たとたんに、特に環境問題の現場に出て行った時には、使い物にならないことが明らかになります。相手にされません。仮に、意味のある批判はできたとしても、「それでは、どうしたらよいの?」と聞かれたとき、その先に進むことができません。問題点を指摘し批判しても、「今・ここ」から解決に向けての「具体的な道筋」を見つけることができません(その意思もない、「解決論」がない…)。
■「心地よいコミュニティ」の外に出ていく必要があります。では、他の分野の研究者、行政の職員の皆さん、地域の住民の皆さん、企業の関係者…自分とは異なる多様な人びととともに、流域の環境問題を解決していくためには、どのような社会的な仕組みを育んでいけばよいのでしょうか。その辺りが、私の関心になります。鷲田先生が取り上げられた「真の方法は、探究されるべき物事の性質に従う」というフッサールのことばに反応したのは、このようなことをいつも考えているからなのです。もっとも、フッサール自身、どのような意図でこう言っているのか、「厳密な学としての哲学」を自分自身できちんと読んでみなければなりませんね。
■私自身が、社会学の勉強を始めた若い頃、アルフレッド・シュッツや彼の弟子にあたるピーター・L・バーガーやトーマス・ルックマンの現象学的社会学に関する研究は、特に若い世代に人気がありました。私もそのようなある種のブームの中で、現象学的社会学の文献を読みましたが、シュッツが影響を受けたフッサールまでには遡ってきちんと読込むようなことはやっていません。若い時に、もっときちんと「古典」と呼ばれる文献を勉強しておけばよかったと思います。反省。
【関連エントリー】いい専門家とは