びわ湖大津経済新聞の取材
 ■龍谷大学REC棟で合資会社ドットラボを経営され、「 滋賀咲くブログ」の運営もされている松崎和弘さんが、私の研究室にやってこられました。今回は、同じく経営されている「びわ湖大津経済新聞」の編集長としてやってこられました。私がゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の活動や、社会学部が取り組んでいる「大津エンパワねっと」にご関心をお持ちとのことで、今回はこの2つを中心に取材をしていただきました。松崎さん、ありがとうございました。
■龍谷大学REC棟で合資会社ドットラボを経営され、「 滋賀咲くブログ」の運営もされている松崎和弘さんが、私の研究室にやってこられました。今回は、同じく経営されている「びわ湖大津経済新聞」の編集長としてやってこられました。私がゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の活動や、社会学部が取り組んでいる「大津エンパワねっと」にご関心をお持ちとのことで、今回はこの2つを中心に取材をしていただきました。松崎さん、ありがとうございました。
■私の方からは、それぞれの活動や取り組みの目的や理念、その過程での教育のあり方等についてお話しをさせていただきました。「北船路米づくり研究会」、そして「大津エンパワねっと」の具体的な活動内容については、このホームページの右欄にあるカテゴリーをクリックして、ブログのエントリーをご覧いただければと思います。近いうちに、「びわ湖大津経済新聞」に、今日お話しさせていただいた内容が記事になるかもしれませんね。松崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。
雑誌『Meets Regional』の取材
 ■雑誌『Meets Regional』の取材を受けました。関西の大学教員の研究や活動や趣味等について紹介する「ミーツアカデミー」というコーナーに掲載されるとのこと。10月1日発売の号の予定です。もし、きちんと掲載されたら、またこのホームページでもご紹介します。写真は、ライターのOさんと、編集部のTさん。
■雑誌『Meets Regional』の取材を受けました。関西の大学教員の研究や活動や趣味等について紹介する「ミーツアカデミー」というコーナーに掲載されるとのこと。10月1日発売の号の予定です。もし、きちんと掲載されたら、またこのホームページでもご紹介します。写真は、ライターのOさんと、編集部のTさん。
■いろいろお話しをさせていただきました。研究のこと、「北船路米づくり研究会」や「大津エンパワねっと」のことなど。さらには、この雑誌らしくよく行く店をお聞きになったので、もちろん大津駅前の居酒屋「利やん」のことについても「熱く」語りました。でも、掲載されるのは1ページの記事です。かなり話しを圧縮してまとめてくださるのでしょう。楽しみだな。
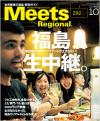 ■こんな雑誌です。これは、10月号。いただきました。掲載されるのは、11月号のようです。京阪神エルマガジンが出している雑誌です。ところで、私の取材とは関係ないのですが、ぜひ『Meets Regional』でも「大津を取り上げてほしい!!」と伝えておきました。いつでも、取材先を紹介するんですけどね〜。「そうや、大津にいかんと!」という特集とか〜♪
■こんな雑誌です。これは、10月号。いただきました。掲載されるのは、11月号のようです。京阪神エルマガジンが出している雑誌です。ところで、私の取材とは関係ないのですが、ぜひ『Meets Regional』でも「大津を取り上げてほしい!!」と伝えておきました。いつでも、取材先を紹介するんですけどね〜。「そうや、大津にいかんと!」という特集とか〜♪
子どもマチナカ発見隊(大津エンパワねっと)

 ■今日は、龍谷大学社会学部「大津エンパワねっと」のチーム・きりんが、「子どもマチナカ発見隊」のイベントに取り組みました。大津市役所都市計画部都市再生課とのコラボです。今年で3年め(おそらく・・・)。夏休みの定番行事となっています。
■今日は、龍谷大学社会学部「大津エンパワねっと」のチーム・きりんが、「子どもマチナカ発見隊」のイベントに取り組みました。大津市役所都市計画部都市再生課とのコラボです。今年で3年め(おそらく・・・)。夏休みの定番行事となっています。
■今回のイベントには、大津市内各地から20名の子どもたち(小学1年生~6年生)が参加しました。残念ながら私は参加できませんでしたが(町家キャンパス龍龍に駐在のため…)、子どもたちは、大津祭曳山展示資料館・大津百町館を見学し、町家がたくさん残る中心市街地のまち歩きを行いました。また、長等商店街の老舗の漬物店「八百与」さんで、漬物の体験も行いました。普段、スーパーマーケットで買い物をしている子どもたちには、新鮮な経験だったのではないかと思います。
■商店街での体験学習の後は、龍谷大学町家キャンパス「龍龍」に移動して、駐車場を会場に素麺流しで昼食。これもこのイベントの定番メニューになっています。毎年、竹の樋から素麺があふれて大騒ぎになるのですが、今年はあまりやんちゃな子どもたちもいなかったせいでしょうか、無事に(?!)素麺流しを終えることができました。昼食後は、工作の時間。町家キャンパス「龍龍」のなかで団扇づくりを行いました。障子紙を色水で上手に染めて、団扇の骨にはり、オリジナルの素敵な団扇ができあがりました。そして、おやつは、これまた定番のスイカ割りです。その合間には、きちんと今日のまち歩きの「ふりかえり」の時間も設けられていました。学生たちが紙芝居風のパワーポイントを作成しましたが、子どもたちのパワーに圧倒させれてしまい、予想外の展開に…。この点については触れないことにしましょう(^^;。
■ところで、市職員の方たちから、「今年の学生のみなさんは、しっかりされていますね~」との評価をいただきました。もちろん過去の学生たちも頑張ってはいるですが、それに加えて今年の学生たちは、中心市街地で行われているイベント「100円商店街」に参加し、商店主のみなさんとの交渉や話し合いのなかで、結果として、かなり鍛えらることになったのではないかと思うのです。チームとして責任をもって仕事をやり遂げる。チーム内できちんと仕事を分担する。チーム内のそれぞのメンバーの持ち味や能力を活かし合いあう。一緒にこのイベントを行う市職員のみなさんとの連絡・相談を怠らない…。社会に出れば当たり前のように必要になってくる「力」を、在学中に、この「大津エンパワねっと」から獲得できたのだとすれば、担当教員としてはこれ程うれしいことはありません。
【写真1段目】左:エネルギーがありまっている子どもたち。中:ふりかえりの時間。おとなしそうですが…。右:最初はこんな感じで、なかなか大変でした。
【写真2段目】左:町家キャンパス「龍龍」の玄関に、小さな靴がたくさんならびました。右:2階の窓から外をのぞく!
【写真3段目】左:すいか割り。中:予算の関係から1玉のスイカをわけてみんなでおやつに。右:ということで、1人分はこの程度ですが、美味しいスイカだったようです。
【写真4段目】左:学生たちが作成した、本日のシオリ。マチナカ・ゴレンジャーです。右:チーム・きりん=マチナカゴレンジャーの面々。ポーズに注目。
【追記】■チーム・きりんのN君が、地元のテレビ局BBCのニュースに登場したとか…。情報が入ってきました〜♪
エフエム滋賀で「大津エンパワねっと」のことを話しました
 ■今日は朝9時過ぎから、大津市にスタジオのある「エフエム滋賀」の「平和堂 MY DAILY LIFE」という番組にゲストとして出演し、「大津エンパワねっと」についてお話しをさせていただきました。お相手してくださったパーソナリティは、木谷美帆さんです。
■今日は朝9時過ぎから、大津市にスタジオのある「エフエム滋賀」の「平和堂 MY DAILY LIFE」という番組にゲストとして出演し、「大津エンパワねっと」についてお話しをさせていただきました。お相手してくださったパーソナリティは、木谷美帆さんです。
■「大津エンパワねっと」では、現在4期生が、7チームに分かれて地域の皆さんと一緒に活動をしています。そのなかでも、今回番組で注目していただいたのは、チーム・どんぐりが、中心市街地の丸屋町商店街にある大津百町館で毎月1回開催している「まちづくりカフェ」のことでした。本来であれば、学生たちも一緒に出演してもらいたかったのですが、すでに夏期休暇のスケジュールがいっぱいのようで、私だけが番組でお話しをさせていただくことになりました。
■お話しさせていただいた内容は、「大津エンパワねっと」の取り組みの目的や概要、「まちづくりカフェ」のこと、「まちづくりカフェ」を学生たちが始めたきっかけ、「大津エンパワネット」全体のカリキュラム、街の皆さんの声…といったところでしょうか。30分の番組なので、少しいろいろ話しを盛り込みすぎたかもしれません。
■CM等が流れているあいだには、木谷さんと少しおしゃべりもさせていただきました。木谷さんも、走っておられるのです。私が毎年出場している「びわ湖レイクサイドマラソン」にも第2・3回に出場されたとか(15kmの部に出場されているようですが、タイムは私などよりも10分も速い!!)。木谷さんのホームページを拝見すると、フルマラソンも走っておられます。すばらしい!!
■今回は、「大津エンパワねっと」に関する情報発信の場を与えていただき、「エフエム滋賀」さんと木谷美帆さんには心から感謝です!! こんどは、「エンパワ」の学生たちを出演させていただければと思っています。
「平和堂マイデイリーライフ★」(エフエム滋賀)のブログ
木谷美帆さんのホームページ
【追記1】■番組の始まる前やCM等が流れているあいだ、木谷さんとは、マラソン以外のことでもお話しをさせていただきました。「社会人になってからわかること…」(Saturday, July 28, 2012)に書いたことと重なるのですが、「学生のうちから、こんな経験ができるなんて、いいな〜」と盛んにおっしゃっておられました。大学には、先生-学生の関係や生徒同士の関係はありますが、それ以外の関係がありません。街のなかに、ごく普通にある、年上の皆さん(いわゆる、街のおじさん・おばさん)、そして年齢の下の人たち(街の子どもら)との関係です。木谷さんは、そのような関係を通して、学生が成長していく…ということに大変納得されていました。実社会で働くようになれば、老若男女を問わず、様々な方たちと関係をもたざるをえません。「エンバワ」に懸命に取り組むと、結果として、実社会で必要とされる総合的な力がついてくように思うのです。
【追記2】■気がつきましたが、テーブルの上に「大津エンパワねっと」の資料が見えてますね!! ところで、今日の出来事について、facebookを通じてですが、ゼミのOGから連絡が入りました。「すごーい!朝友達からわっきー先生がラジオにでてる、てメールきましたよ(*^_^*)」。その他にも、facebookを通じて、いくつか感想をいただきました。なんだか、嬉しかったな〜。
中央学区からの連絡
 ■先月の27日のエントリー江州音頭の練習にも書きましたが、8月3日、琵琶湖湖岸の渚公園で「びわ湖夏まつり」のプログラムのひとつ「江州音頭総おどり」(コンテスト)が開催されました。大津市の各種団体の連(グループ)が参加するなか、私は、「大津エンパワねっと」で学生たちがお世話になっている中央学区自治連合会の連に参加させていただきました。自治連の方から、「大津エンパワねっとの学生や先生たちも参加してほしい」との要請があったからです。もっとも、学生たちの参加はなく、残念ながら私だけになりました。
■先月の27日のエントリー江州音頭の練習にも書きましたが、8月3日、琵琶湖湖岸の渚公園で「びわ湖夏まつり」のプログラムのひとつ「江州音頭総おどり」(コンテスト)が開催されました。大津市の各種団体の連(グループ)が参加するなか、私は、「大津エンパワねっと」で学生たちがお世話になっている中央学区自治連合会の連に参加させていただきました。自治連の方から、「大津エンパワねっとの学生や先生たちも参加してほしい」との要請があったからです。もっとも、学生たちの参加はなく、残念ながら私だけになりました。
■今日、中央学区の市民センター(学区公民館)職員のKさんが、「大津エンパワねっと」事務局経由で、コンテストの結果の連絡とともに、当日の写真もメール添付で送ってくださいました。結果ですが、「ベスト部門・ベストスマイル賞」に選ばれ、賞金とトロフィーを獲得されたようです。これは嬉しいお話しですね。やっと江州音頭の振り付けを覚えたばかり、しかもふだん浴衣など着たこともない私が、地元の女性に帯を締めていただき、俄か仕立の参加。心配しましたが、なんとか皆さんの足をひっぱらずにすんだようです。右の写真の茶色の浴衣が私です。もちろん、自治連から貸していただいたものです。
 ■中央学区自治連合会の会長さんや、参加の団体役員の皆さんには、「大津エンパワねっと」の学生たちが大変お世話になています。最近は、この教育プログラムの運営についても、「もっと 、オリエンテーションを短くして、早めに地元に入って話しをいろいろ聞いてもらったほうがよいのでは」、「エンパワを修了した先輩やOB・OGの体験談を、後輩に知らせてはどうだろうか」といったようなアドバイスをいただいています。大変ありがたいことだと思っています。
■中央学区自治連合会の会長さんや、参加の団体役員の皆さんには、「大津エンパワねっと」の学生たちが大変お世話になています。最近は、この教育プログラムの運営についても、「もっと 、オリエンテーションを短くして、早めに地元に入って話しをいろいろ聞いてもらったほうがよいのでは」、「エンパワを修了した先輩やOB・OGの体験談を、後輩に知らせてはどうだろうか」といったようなアドバイスをいただいています。大変ありがたいことだと思っています。
■2008年から「大津エンパワねっと」が始まった頃は、「このエンパワという授業で大学側は何をしたいのか」という質問をたびたび受けました。というのも、通常の大学の授業では、教員が具体的な授業の目的を決め、それを学生に学習させ、最後に評価を行う…というパターンが多いわけですが、この「エンパワ」では、その目的はあらかじめ設定されていないからです。このように書くと誤解があるかもしれませんが、学生たちが地元に入って「地域づくり」の活動に取り組むにしても、その課題は学生たちが地元の皆さんの活動に受け入れていただきながら、学生の目線で「発見」していくものだと考えているからです。そのような課題(あるいは、地域の隠れた魅力を伸ばしていく)を、地域の皆さんと協働しながら「解決」し、その成果を「共有」する。そのような「発見」・「解決」・「共有」というプロセスを大切にしていこう…というのが、この「大津エンパワねっと」の特徴なのです。最近では、地元の皆さんにも、この「大津エンパワねっと」の特徴をよくご理解いただけるようになりました。そして、さきほど書いたように、アドバイスや注文までいただけるようになってきました。
■地域と大学の関係づくり。「大津エンパワねっと」のように、いったんうまく出来上がった関係ではあっても、日頃から、お互いの関係を「磨き合う」ことが必要なように思っています。ちょっとしたことなのですが、江州音頭に参加させていただく…そんなことさえも、結果として、お互いの関係を「磨き合う」ことにつながっているように思うのです。
生涯学習課の来学
■今朝も、朝のジョギング=朝ランで5km走ってきました。体は(特に、下半身の筋肉は)、どことなく疲れているわけですが、朝ランは脳を活性化します。朝から気持ちが高揚し、今日も元気に仕事に取り組んでいます。さて、今日は、滋賀県教育委員会生涯学習課の職員の方が3名、社会学部の「大津エンパワねっと」のヒアリングのために来学されました。「大津エンパワねっと」は、別のエントリーにも書きましたが、社会学部がある瀬田キャンバスに隣接する「瀬田東学区(小学校区)」と大津市の中心市街地にある中央学区を中心とした「中央地区」の2カ所で、学生たちが地域の皆さんと協働しながら地域の課題解決や魅力を伸ばしていく活動に取り組んでいます。活動が大津市であるということもあり、これまでは大津市役所さん(特に、都市計画部都市再生課)には、大変お世話になってきました。
■今日は、滋賀県教育委員会の生涯学習課の皆さんです。じつは、今年の春、広い意味での「地域づくり」に関連する滋賀県庁の部署に、「大津エンパワねっと」の活動報告書や関連資料をお送りしたのですが、それらの報告書や資料をお読みいただき、「大津エンパワねっと」にご関心をお持ちいただいたことが、今回の来学につながったようです。ヒアリングということもあり、基本的には、「大津エンパワねっと」の概要や取り組みのポイント、また地域との連携のあり方等についてお話しをさせていだいたのですが、生涯学習課が、今後どのような事業展開をしていきたいのかという点についてもお話しを聞かせていただきました。
■生涯学習というと、公民館のような施設での「座学」というイメージが強いわけですが、私自身は、それだけではないと思っています。少し、説明させてください。現在、企業を退職された方、あるいはこれから退職されようとしている方たち(男性が多いわけですが)が、地域社会のなかに再度、自分と社会との「つながり」をもてるような仕組みが地域社会のなかに必要とされています(中高年男性の地域デビュー)。また、地域社会のなかには、大学も含めた様々な学校、広い意味で地域づくりに関わる様々な団体、それから地域にねづいて活動をしている自治会関連の団体、これらが有機的な「つながり」を構築していくことも必要だと考えています。そのような様々な「つながり」、地域社会のなかで孤立した個人、そして「島状」になって分散する小さなネットワークをつなぎながら、さらに社会関係資本(Social Capital)を蓄積しネットワークを重層的に築いていくこと、そのためにはコーディネートする「人材」や「社会的な仕組み」が必要です。
■私は、前者の「人材」を、「呼びかけ屋さん」「つなぎ屋さん」と読んでいます。そのような「呼びかけ屋さん」や「つなぎ屋さん」は地域づくりの表舞台に出るというよりも、舞台裏で活躍する人びとです。「呼びかけ屋さん」や「つなぎ屋さん」は、自分が表舞台に立って、自分が思い描いた「青写真」を、周りの人びとをリードしながら実現していく…そのようなタイプの人ではありません。また、なんらかのカリスマ性のもとで、人びとを魅了し、人びとをまとめるようなタイプの人でもありません(一昔前のリーダーシップ像とは、そのようなものでしたが)。むしろ、様々な潜在的な力や資源をお持ちの個人や団体が、それぞれの「持ち味」を活かしあう「相補的な関係」が生まれる「場」や「チャンス」をつくっていくような人こそが求められているのかなと思っています。そのような意味で、ディレクターではなく、表舞台には出ない影のプロデューサーである必要があります。「影の」という点が重要です。
■そのような「場」や「チャンス」が一定程度、ゆるやかに制度化されていったときに、さきほどの(後者の)「社会的な仕組み」が生まれていくことになります。そのような「社会的仕組み」のなかでは、特定の個人や団体が、他の個人や団体=「他者」を自らの目的のために「手段」として使うような状況(あるいは、そのように見えてしまう状況)に陥らないことが必要です。お互いの「持ち味」を活かしあえる関係が必要なのです。「他者」を「承認」し「評価」しあうこと、と言い換えてもよいかもしれません。これまでも、よく「win-winの関係」ということが言われてきました。しかし、そのような「win-winの関係」が、単に功利主義的(自分にとって都合がよい、自分が得をする…)な関係のままでは、「社会的仕組み」には持続性が生まれません。「他者」を「承認」し「評価」しあうこと、「私(あるいは、私たちの団体)は、あなたの(あるいは、あなたたちのような団体)の存在があって、さらに光輝くことができる」という、他者への「リスペクト」が伴う関係であってほしいと思います。さらには、「他者」の様子をそれとなく伺いながら、お互いに、さりげなく「支援」を申し出ることができる関係であってほしいとも思います。少し難しい言葉になりますが、他者を自らの「エージェント」にしない、他者に自らの「ミッション」を押し付けない関係(「エージェント」化と「ミッション」化の回避)、そして他者を「包摂」しながらも同時に「排除」するような抑圧性を孕まない工夫が必要なのです。
■影のプロデューサーである「呼びかけ屋さん」や「つなぎ屋さん」が生まれるような土壌づくり、そして「他者」を「承認」し「評価」しあうことのできる「社会的仕組みづくり」、この両方をどのように地域社会のなかに根付かせていくのか、そのあたりのことが現在の地域社会の課題になっているように思います。そして、そのような取り組みこそが、これからの時代の、広い意味での「生涯学習」ではないかとも思うのです。生涯学習課の皆さんとは、「大津エンパワねっと」の事以外にも、このようなお話しをさせていただきました。せっかく「ご縁」が生まれたのですから、これからは生涯学習課の皆さんとも、なにか新しい取り組みができればと考えています。
社会人になってからわかること…
■ひとつの前のエントリーにも書きましたが、「大津エンパワねっと」(龍谷大学社会学部・地域密着型教育プログラム)では、大学に隣接する「瀬田東学区(小学校区)」と大津市の中心市街地にある中央学区を中心とした「中央地区」の2カ所で、学生たちが地域の皆さんと協働しながら地域の課題解決や魅力を伸ばしていく活動に取り組んでいます。この「大津エンパワねっと」を地域に受け入れていただき円滑に取り組みが進むように、月1回、地元の皆さんとの連絡調整会議として「大津エンパワねっとを進める会」を両地区で開催しています。昨日(7/26・金)は、大津市の中心市街地にある町家キャンパス「龍龍」(ろんろん)で、「大津エンパワねっとを進める会 中央」が開催されました。この「進める会 中央」には、毎回、中央学区自治連合会の役員の皆さん、大津祭やまちづくり団体の皆さんが委員として出席してくださっています。昨日からは、大津市社会福祉協議会の職員(ソーシャルワーカー)Mさんも参加してくださることになりました。
■会議が終了したあと、Mさんと少しお話しをすることができました。Mさんは、龍谷大学社会学部で社会福祉を学んだ後、市社協で職員をされていますが、「こんなプログラムが、自分達の学生時代にもあって欲しかったです。大津エンパワねっとは、私が卒業した後に誕生したんですよ。地域の中に入って、地域の人と関係をもちながら、地域づくりの活動をするって、すごい力がつくと思うんですよね〜。でも、それが良くわかるのは社会人になってからかもしれませんね」と、笑いながら話されていました。そうなんです。普通、経験や体験したことの意味は、学生の立場を離れて(卒業して)、しばらくしないとわからないのですね。私のゼミの卒業生たちは、「どうして自分たちの時には、エンパワがなかったんですか」とよく言いいます。また、「どうして自分たちの時には、北船路米づくり研究会のような活動をしてくれなかったんですか」とも言いいます。しかし、それは「社会人になってからわかること」なのかもしれません。
■卒業論文の場合はどうでしょうか。最初、嫌々渋々、仕方なしに取り組んでいた学生でも、フィールドでの調査と大学で学んだ社会学とがつながり、フィールドから意味のある「発見」をした学生は、卒業後も、その経験を大切にしています。自分の卒業論文も大切に保管しています。「その時」にはよくわからない、卒論での経験や体験の意味。それは時間差をともなって、社会人になってから実感されていくのです。できれば、卒業生の皆さんには、そのような自分の「変化」を、現役学生の前で語ってもらいたいと思っています。
チームどんぐりの「まちづくりカフェ」
 ■「大津エンパワねっと」(龍谷大学社会学部・地域密着型教育プログラム)では、大学に隣接する「瀬田東学区(小学校区)」と大津市の中心市街地にある中央学区を中心とした「中央地区」の2カ所で、学生たちが地域の皆さんと協働しながら地域の課題解決や魅力を伸ばしていく活動に取り組んでいます。写真は、「中央地区」で活動するチーム「どんぐり」。女子学生4人組のチームです。彼女たちは、現在、中心市街地にある丸屋町商店街の大津百町館をお借りして、毎月1回、「まちづくりカフェ」を開催しています。
■「大津エンパワねっと」(龍谷大学社会学部・地域密着型教育プログラム)では、大学に隣接する「瀬田東学区(小学校区)」と大津市の中心市街地にある中央学区を中心とした「中央地区」の2カ所で、学生たちが地域の皆さんと協働しながら地域の課題解決や魅力を伸ばしていく活動に取り組んでいます。写真は、「中央地区」で活動するチーム「どんぐり」。女子学生4人組のチームです。彼女たちは、現在、中心市街地にある丸屋町商店街の大津百町館をお借りして、毎月1回、「まちづくりカフェ」を開催しています。
■大津市の中心市街地は、他の地方都市と同様に、いわゆる「空洞化」の問題を抱えています。そのような状況をなんとかしようと、様々な団体が活動を行ってきました。チーム「どんぐり」の出発点は、そのような様々な団体の皆さんにお話しをお聞きしながら、「これだけたくさんの団体が活動しているのだが、いまひとつお互いの”つながり”が薄いのでは…、もっと”つながれ”ば中心市街地はさらに盛り上がっていくのでは…」という問題意識にあります。そこで、もっと気軽に街や地域のことについて”おしゃべり”をしながら、お互いの活動の内容や考え方を知ることのできる社会的な「場」=「まちづくりカフェ」をつくるこにしたのでした。
■この「まちづくりカフェ」では、地域のことに関心をもち活動している皆さんをゲストとしてお招きし、話題提供をしていただき、参加者とともに”おしゃべり”を楽しみながら、結果として(ここが大切なのですが…)街中の人びとの”つながり”が太くなり、そのような”つながり”が拡大していくことを目指しています。言い換えれば、楽しい時間を共有すること(アウトプット)で、社会科学で近年、人口に膾炙している「社会関係資本」を地域社会のなかに蓄積していくこと(アウトカム)を目指している…といってもよいのかもしれません。島状に地域社会のなかに分散した人びとの小さなネットワークを”つないでいく”、個々の団体のネットワークを”つないで”拡げていく試みであります。
■今日は、夏期休暇中に開催する第5回の「まちづくりカフェ」に向けて、これまでの反省点と改善点を洗い出し、これから「まちカフェ」の活動をどのように発展させていくのか…といった点について、私も参加し、話し合いを行いました。街中の皆さんからも、「こういう試みは、地元の人間ではできない。学生の皆さんだからこそ…の活動だと思う」との評価もいただいています。夏期休暇に入りますが、さらに頑張って取り組んでいってもらえればと思っています。
江州音頭の練習
 ■毎年8月の初め、大津市では、琵琶湖湖畔の広場で「びわ湖大津夏まつり」が開催されます。この「びわ湖大津夏まつり」のなかでは、プログラムのひとつとして、大津市の各種団体の連(グループ)が参加する「江州音頭総おどり」(コンテスト)が行われています。龍谷大学社会学部「大津エンパワねっと」でお世話になっている中央学区自治連合会の皆さんは、地元自治会ということから、この「江州音頭総おどり」に連を組んで毎年参加されています。昨晩は、その中央学区自治連合会の連の練習日でした。自治連の方から、「大津エンパワねっとの学生や先生たちも参加してほしい」との要請があり、参加することにしたのです。もっとも、学生の参加はゼロ。「おじさん1人」(私)の参加になってしまいました。
■毎年8月の初め、大津市では、琵琶湖湖畔の広場で「びわ湖大津夏まつり」が開催されます。この「びわ湖大津夏まつり」のなかでは、プログラムのひとつとして、大津市の各種団体の連(グループ)が参加する「江州音頭総おどり」(コンテスト)が行われています。龍谷大学社会学部「大津エンパワねっと」でお世話になっている中央学区自治連合会の皆さんは、地元自治会ということから、この「江州音頭総おどり」に連を組んで毎年参加されています。昨晩は、その中央学区自治連合会の連の練習日でした。自治連の方から、「大津エンパワねっとの学生や先生たちも参加してほしい」との要請があり、参加することにしたのです。もっとも、学生の参加はゼロ。「おじさん1人」(私)の参加になってしまいました。
■この「江州音頭」、単純な所作の踊りのように見えて、皆でそろって美しく踊ることはなかなか難しい。個人的な感想かもしれませんが、体重の移動を滑らかにし、手の伸びがまっすぐそろっていなければ、連としての統一感はなかなか生まれません。冷房の効いた部屋ではありましたが、1時間半ほどの練習で、普段、お世話になっている中央学区自治連の皆さんと一緒に汗を流しました。「大津エンパワねっと」の活動そのものではありませんが、こういった普段のお付き合いが大切なのだと思います。もっとも、私自身、ちょっと気合いが入っています。本番の8月3日、浴衣や帯は自治連からお借りしますが、草履は自分のものを用意しています。マイ草履で参加です(というのも、私の大足にあうサイズがなかったものですから…)。
○「びわ湖大津夏まつり2012」









