夏期休暇の課題・卒論までのスケジュール・来室

▪️夏期休暇が近づいてきました。ということで、水曜4限の「社会学演習IA」では、夏休みの期間に卒業論文の執筆に資する書籍を2冊選んで、その書評を書いてもらうことになっています。丁寧にノートを取りながら精読して、要約を作成し、その要約をもとに書評を書いてもらいます。書評の書き方を説明した資料も配布してあります。今日は、選んだ2冊の書籍を、ひとりひとり発表してもらいました。すでに、具体的なテーマやフィールドまでだいたい決まっている人もいましたが、多くのみなさんは、まだぼやっとテーマが決まった段階でしょうか。私が指導しているゼミですので、私の研究関心に近いてテーマの人が多いわけですが、J-POPの歌詞分析や、K-POPのファン行動の分析をしたいという人まで様々です。
▪️また、卒論を提出して卒業するまでのスケジュールも確認しました。あくまで目安ですけども。期間は、2025年の4月から2027年の1月まで、各自の卒論に向けての研究と、ゼミでの発表や討論、それから各自の就職活動についても書き込めるようにして、それを表で一覧できるようにしたものです。全員で22名。きちんと「完走」してほしいです。私が卒論を指導する最後の学生になりますしね。
▪️夕方、研究室で仕事をしていると、農学部の 古本 強さんが研究室にやってこられました。古本さんは、農学部の開学準備をする段階、農学系学部設置委員会や農学部設置委員会の頃からお付き合いいただいています。素敵な先生です。ということで、記念撮影。古本さんは少林寺拳法部の部長さんをされています。コロナ禍で部員が激減した時からご自身も少林寺拳法を習い始め、部の再興にご努力されてきました。現在は2段なんですって。すごいですね。今日は、深草の体育館で練習がある日で、私の研究室は体育館に隣接しているものですから、ついでに立ち寄ってくださったのです。それから、それから。古本さんは、学生さんたちと一緒に「養蜂」の活動もされています(本業は、植物の光合成のメカニズムの研究だったと思いますが)。ということで、古本さんとは、大津の街中で、ハチミツを使ったサイエンスカフェのようなイベントを開催する予定です。秋になるかな。楽しみです。
自宅で仕事のあと「利やん」へ


▪️昨日は夕方まで自宅でしっかり仕事をしていました。やり残している仕事もありますが、とりあえず頑張ったので、夕方から大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へでかけました。今日は社会共生実習「地域エンパワねっと」でお世話になっている雨森鼎さんと安孫子邦夫さんと、お2人との呑み会を約束していたからです。
▪️雨森さん安孫子さんとは、年に何回か「利やん」でご一緒しています。だいたい、雨森さんが声をかけてくださいます。昨晩も、いつものように、いろいろお話ができましたが、昨日は、それぞれのライフヒストリーを語り合うような感じでした。私も、それなりにライフヒストリーを語れる年齢になりました。私は67歳ですが、一昔前(平均寿命が短い頃)だと、民俗学での聞き取り調査でいう「古老」の類に突入しているのかもしれません。それはともかく、ご縁のある方達のライフヒストリーをお互いに聞き合えるような集まりがあったらいいね〜という話にもなりました。お2人は私よりも一回り以上年上、後期高齢者です。そして、人生の大先輩です。よく存じあげているお2人のお話でも、昨晩は、びっくりするようなことがたくさんありました。やはり、戦争という出来事が、大きく影響を及ぼしているように思いました。
『風来坊 01<創刊号> 宮本常一 × X ジェネレーターのためのシン・ミヤモト学』
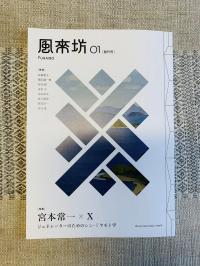
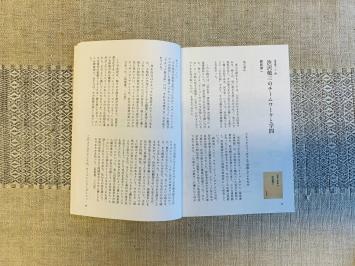
▪️週1回、埼玉県から日帰りで2コマの授業をするために深草キャンバスまで通っておられる 原尻 淳一さんが、一昨日の夕方、研究室までお越しくださいました。原尻さんはとてもユニークな教育をされていて、自分も学生だったら教わりたいな~と思うような授業をされます。時々、授業の様子(板書書)をfacebookにもアップされていますが、とてもシステマティックで、学生さんたちもよく理解できるのではないかと思います。
▪️今回、原尻さんは、わざわざ研究室までお越しくださり、写真のような冊子を届けてくださいました。ありがとうございました。『風来坊 01創刊号』です。創刊号の特集は「宮本常一 × X」です。あの民俗学者の宮本常一。なぜ「× X」(かけるX)は後段のところで説明します。サブタイトルには「ジェネレーターのためのシン・ミヤモト学」とあります。原尻さんは、私が宮本常一に強い関心をもっていることをご存知だからでしょう、お届けくださったのではないかと思います。少し説明します。
▪️創刊号のあとがきを、執筆者のお一人である市川力さんが執筆されています。そこには、こういうことが書いてありました。
宮本常一の研究者でも、民俗学者や郷土史家でもないけれど、宮本常一の著作に強く惹かれた仲間の皆さんが、お互いに「宮本常一のどこに惹かれるるのか」という話になり、それぞれが著作集の1冊を選んで語り合ったそうです。そうするとそれぞれの「常一性」が浮かび上がってきて面白いので、冊子にまとめることにされたのだそうです。
▪️このあたりが、「× X」の部分です。宮本常一を、それぞれがなぜ惹かれるという自分の問題関心とクロスさせておられるわけです。素敵じゃないですか。原尻さんが選ばれた著作集は第50巻の「渋沢敬三」です。「渋沢敬三のチームワークと学問」。文章のなかには、渋沢がアチックミュージアムをどのように運営していたのか、どのように人と接していたのか、そして彼の学問観はどのようなものだったのか、原尻さんの思いをクロスさせながら丁寧に解説されていました。そうか、渋沢敬三は「サーバントリーダーシップ」の人だったのか。宮本常一はそのような渋沢のもとで成長したんですね。今回、拝読させていただき、渋沢敬三が昭和38年、1963年に68歳で東京虎ノ門共済病院で亡くなられたことを知りました。死因は、糖尿病・萎縮腎なのだそうです。ちょっとドキッとします、はい。私は、67歳できちんとコントロールしてはいますが糖尿病だからです。
▪️発行者は、原尻さんも参加されている一般社団法人「みつかる・わかる」。発行書は、横浜にある「珈琲と図書室」さん。みなさん、楽しんでおられますね。すばらしいというか、羨ましいというか。いいな~と思います。こうやって同じ問題関心の方達が集まって交流するって、素敵なことだと思うんですよね。
巣立ち雛


▪️朝、小雨が降る中、メダカとクサガメの世話をしていると、庭でヒヨドリが大きな声で鳴いていました。何か怒っているようにも聞こえました。というのも、庭のジューンベリーの熟した実をヒヨドリに食べられないように、ネットを被せたからです。大きな声で鳴いているのは、そのことに強く抗議をしているのかもと思ったのですが、もちろん違っていました。庭の法面に植えてあるヤマモミジ、今、緑の葉が美しく茂っているのですが、その茂みの中に雛がいたのです。そして、その雛に親鳥がせっせと餌を運んでいたのです。
▪️最初は、巣から雛が落ちたのかな、うちのヤマモミジに避難しているのかな、などと想像しましたが、調べてみると違っていました。「巣立ち雛」というのだそうです。GoogleのAIが教えてくれるところによれば、ヒヨドリの雛は生後約10日ほどで巣立つのですが、その巣立ち後も親鳥に付いて数十日間は餌をもらうのだそうです。ということで、まだ十分に飛べないのですね。巣から落ちたわけではなくて。カラスやトンビに狙われないように、しばらくは、我が家のヤマモミジをシェルターにして、無事に、成長して欲しいです。いつもは図々しいヒヨドリはあまり好きではなく、もっと小さな小鳥を愛でてきたのですが、今日はヒヨドリを応援したい気持ちになりました。
▪️夕方になりました。我が家のヤマモミジに避難している?!ヒヨドリの巣立ち雛。嘴が黄色いですね。人間で言えば、お尻が青いって感じ。兄弟姉妹関係はどうなんだろう。時々、親鳥が餌を運んできますが、夕方になり親鳥の姿が見えなくなりました。2羽だけで心細いでしょうね(知らんけど…)。ネコなんかに襲われないことを祈ります。時々いるんですよ、うろついている猫。明日の朝まで無事にいてほしいです。明日になると、また両親がやって来てくれることを信じています。急に、ヒヨドリの味方になってしまいました。
▪️冬、庭にみかんを針金に刺してシマトネリコの枝にぶら下げています。メジロだったら、そのぶら下がったみかんにとまってみかんを食べることができます。ヒヨドリは大きいので、とまることができません。ホバリングして、必死に食べようとします。そうやって、メジロを愛でるために、ヒヨドリには意地悪をしていたのです。しかし、今日は応援しています。人間のその時の感情や都合の身勝手な話であることはわかっているのですが。
▪️まあ、そういうことで今日は日暮で終わりかなと思っていたら、雛たちが枝に止まったまま羽をバタバタさせ始めました。その時は、親鳥たちもやってきていました。「頑張って、羽、バタバタさせなさい」と言ったのかどうか。そのあたりはよくわかりませんが、ヤマモミジの枝に隠れてじっとしていたのに、飛び立ったのです。遠くまでは飛べないのですが、その様子を親鳥たちが見守っている感じでした。
▪️右の写真ですが、ヤマモミジから庭の別のところにあるシマトネリコに飛んで移動した雛鳥です。もう1匹の雛鳥は、隣の家の方に飛んで行きました。感心したのは、ヒヨドリの両親が雛鳥に声をかけながら(そういうふに感じられました)、雛鳥たちをきちんと見守っていたことです。これは、勝手な推測ですが、「独り立ちできるように声をかけて見守っている」のではないのかなと、そういうふうに感じました。
花に癒され出勤と素敵な報告






▪️今日は日曜日ですが、出勤しました。引越しで取られた時間を取り戻そうと頑張っています。ということで、朝、少しだけ、庭の花を眺めて癒されました。上段左、ヒカゲツツジ。上段右、イカリソウ。冬の間に、昨年の枯れた葉を刈り取っていませんでした。春を迎え、慌てて枯れ葉を取り除いたら、一緒に花芽も少し刈り取ってしまったみたい…残念です。中段左、ヒメツルニチニチソウ。中段右、ヒマラヤユキノシタ。下段、スミレ。正確な品種、わかりません。栽培品種です。野生の小さな小さなスミレも、もうじき庭で咲き始めるはずです。
▪️こんなふうに書くと、庭が花でいっぱい…みたいな感じではありますが、そうではありません。ところどころで可愛らしい花を咲かせてくれています。でも、本当は庭中に花が咲いて欲しいです。特に、春は。まあ、それは定年退職後の楽しみにしておくことにします。それから、室内ですが、コーヒーの木を観葉植物として育てています。下段右、実がなったのですが、それが赤く熟してきました。どうしましょうかね。
▪️新しい研究室は、なかなか快適です。引っ越しも終わったし、仕事のペースをあげます集中していきます。大学の図書館にない書籍を滋賀県立図書館で探して借り出したりしています。『油脂石鹸洗剤工業史-最近10年の歩み-』(1981年)。なかなか興味深いですね。滋賀県立図書館には、また近々行かねばなりません。
▪️そんな中、素敵な報告がありました。私は2004年から龍谷大学社会学部で勤務しています。昨日は、最初のゼミの卒業生、脇田ゼミ1期生から連絡がありました。その卒業生は、卒業後すぐに結婚されました。この学年とは、過去に2〜3回、同窓会を開催したように記憶しています。今回の連絡の中身は、お子さんが、この春から龍谷大学に入学されるということでした。そのお子さんが、まだ赤ちゃんだった時に、私は抱っこしているのです。なんだか、感慨深いものがあります。時間が経つのは、本当にはやいです。
▪️ もう少し、今日のことを書いておきます。今日は研究室に入る時、私の研究室の前にある共用の洗い場の横の備え付けの大きなテーブルで、1人の学生さんが勉強されていました。お尋ねすると、法学部の学生さんとのこと。新しい校舎に、勉強するのに良い場所を見つけてられたようです。ここは、コンセントがあるのです。日曜日だと、人があまりいませんしね。私が帰宅する時も、まだ勉強をされていました。頑張っておられます。
▪️帰りは冷たい風が吹く中、JRの稲荷駅まで歩きました。駅のプラットホームで電車を待っていると、吹奏楽部の部員さんが向こうからやってこられました。コントラバスの主席奏者、4回生の方です。今まで瀬田キャンパスで練習だったとのこと。これから、京都駅の近くでアルバイトをして、晩遅く、遠くのご自宅まで帰宅されるのだそうです。慣れているとはいえ、大変ですね。
▪️勉強にしろ、課外活動にしろ、頑張っている学生さんと話ができて嬉しかったです。元気をいただきました。
魚見さん(革靴をはいた猫)と「利やん」

▪️昨晩は、「革靴をはいた猫」代表取締役の魚見航大さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお話をお聞かせいただきました。魚見さんに実際にお会いするのは、これが2回目になります。前回お会いした時も、「利やん」でした。前回、この「利やん」を気に入られたようで、今度は魚見さんの方から、「利やん」で呑みましょうとお誘いいただきまた。魚見さんは、障がい者と健常者が一緒に働く靴磨き靴修理の株式会社「革靴をはいた猫」を起業されました。各地にある障がい者就労支援の事業所ではなく、株式会社として起業されたのです。
▪️このあたりのことは、魚見さんにお会いする前から、龍谷大学の広報や、ネットの記事を通して知っていました。龍大の政策学部からはたくさんの皆さんが起業されています。魚見さんもそのような方達のお1人です。自分は何がしたいのかよくわからない、ある意味で、よくいる普通の若者だった魚見さんが、人生の「転轍手」となる女性との出会いがあり、その女性の強い勧めで靴磨きの修行を行い、そして「革靴をはいた猫」を起業された…とってもドラマチックです。困難を抱えた方達に対する魚見さんの眼差しは、とってもフラットです。一緒に働く仲間なんですね。前回お会いした時は、長年一緒に働いてきた方が、別の企業に立ち上げられた新たな部門に雇用されたというお話も聞かせていただきました。素晴らしいです。今回は、滋賀県内で行政と連携して新しい事業を立ち上げるようで、そのお話を少し聞かせていただきました。こちらも素晴らしいです。魚見さんの事業は、様々な企業からも注目されているようです。まだ30歳過ぎの青年です。仕事が楽しくて仕方がないようですね。頑張ってください。
▪️「自分は何をしたいのかよくわからない」、そのような今時の普通の大学生だった魚見さんは、人生の「転轍手」となった女性と出会ったと書きました。その方は、「樹林」のおばちゃんです。。こちらの記事もすごく参考になりました。